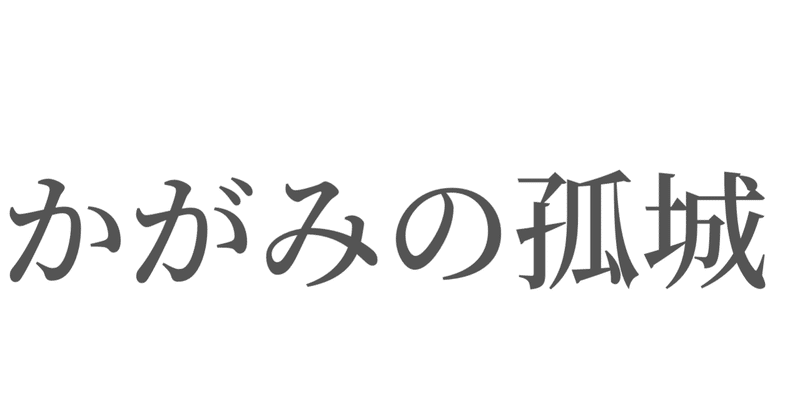
かがみの孤城 読書記録5
あらすじ
同級生から受けた仕打ちが原因で不登校が続き、子供育成支援教室(スクール)にも通えずに部屋に引き籠る生活を続けていた主人公の中学一年生の女の子「こころ」が、5月のある日自室の鏡が光り、その向こうにお城で自分と似た境遇を持つ中学生6人と出会い、彼らとともに冒険していく
-wikipedia
感想
設定、話の展開、登場人物の心の機微の描写、フラグの回収。
すべて素晴らしかった。
読了してすぐに記載しているが、また読み直したいが、いくつか素晴らしいと感じたものを記載していく。
(若干のネタバレを含んでいるので未読の方はお気をつけください)
ーーーーーーーーーー
P123 それなのに、どこに住んでいるかもわからない、よく知らないこの子たちになら話してみたいと思っていることに、こころは自分で驚いていた。
自分の抱えている秘密を周りの子に話そうと感じたときに記述されていた文。
身近な人よりも、見ず知らずの人や距離の遠い人の方が話しやすいことがある。中学1年生の主人公がそのことに気付いた描写はこちらにも納得感を与えるものだった。
P130 この日、自分は家にいなかったんだ、と思うことにした。
自宅に嫌いな学校の子たちがおしかけてきたことが描写された後の言葉。
自分が耐えきれない現実に直面したときに私たちはこのように記憶を改竄する。意識的であったとしても、何度も思い込むことによってそれを事実と思うことがあり、そのことは経験上でも理解できる部分があり共感した。
P133 「偉い。よく、耐えた」
その言葉を聞いた、瞬間だった。
鼻の奥が、つん、と痛くなる。あれ、と思ううちに思考が止まる。奥歯を慌てて噛み締めたけど、間に合わなかった。
辛い経験を友人が認めてくれたときに主人公が涙を流すところ。
事実を話すときには涙を流さなかったのに、相手がそのことを認めてくれたときに実感を伴ったのだと思う。本当に気持ちがよくわかる。自分を受け入れてくれる存在の大切さを改めて感じた。
P137 構わないでもらえることが、一番楽で、嬉しい。
だけど、この先もずっとこうなるのかを考えると、体がものすごく重たくなる。
辛い経験をしたときは、「あなたに私の気持ちはわからない」と突き放してしまうときがある。その瞬間は距離を空けて確かに楽になるけれど、しばらく時間が経つと阻害されていることが辛くなってくる。
そういった感情の変化を著者は本当によく理解しているのだなと感じながら読んだ。
p204 自分達の知らない世界をひけらかすようにそうされると、それが羨ましいかどうかに関係なく、ただ嫌な気持ちが胸に広がるようだった。
シンプルに、自慢話はやめた方が良いし、そういうことを言う人に人は近づかなくなるだろうな……という教訓。
p341 来なかったなんて、思ってない。お前たちが来ないわけ、ないから
(本当は違うが、)約束が守られなかったときに友人が伝えた言葉。自分のことを心の底から信じてくれている気持ちを感じ取れると、もう裏切れないなと思える。こういうふうに感じられる関係性を作っていきたい。
p355 休みたい個人が二人いただけっていう個別の問題
学校で2人の不登校がいたときに、大人は構造の問題として調べるが、実際は個人の問題だと捉えている子どもの意見。
どちらが正解ということはないけれど、こういうケースは確かに存在するなと感じた。「どちらのタイプの人もいる」ということを私たちが理解することが大事だと思った。
p381 先生はただ、「不登校の子の家に行った」という事実を作るために来ただけで、実際こころがどうするかにも興味はないのかもしれない。
担任が自分の家に来たときに主人公が感じた言葉。
人となり、考え方に対して完全に不信感を抱いている。この状況になってしまうともう信用することができないだろうなと思った。
(余談だが、自分も読んでいて担任の態度に苛立ちを感じた。こういった人が教師になってほしくないと思うが、実体験上多いなとも感じた……)
p473 違うよ、父さん。あながち、そうでもない、と。小学生の子どもにも、意思はある。ここに居続けたら苦しいんだってことくらい、オレにだってわかる。
小学生の子どもの意見はほとんど親の意見だろう、と父が言ったときに感じたこと。
もちろん大きく影響は受けているが、そのときの周り環境や親の感情の機微を子どもは敏感に感じ取っている。何か決めたときにそう言ったことを考慮した上での言葉だということを私たち大人は意識しないといけない。
p551 今目の前にいる子たちの抱える事情はそれぞれ違う。一人として同じことはない。
先ほどの構造の問題か、個人の問題かという話にも近いかもしれない。同じように不登校になっている子がいたり、自分自身が不登校になった経験があるから相手のことがわかると思っていても、実際は個別にさまざまな要因が絡まってそうなっているということを理解した言葉。
もちろん取り組み方としては構造的なアプローチもするべきだと思うが、一人ひとりを尊敬(明らかに見るという意)して、向き合っていくことが大事だと感じた。
あとがき
教訓が多く詰まった書籍だった。
絶対にまた読む。
書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
