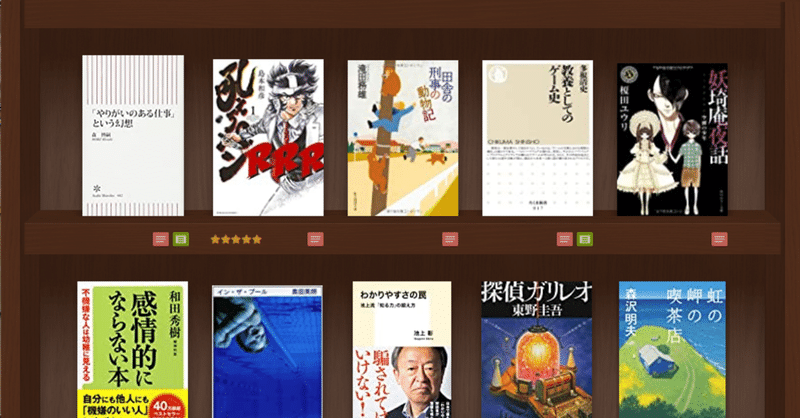
2022年3月に読んだ本
2回に分ける事になりそうと書きましたが、1回で済みました。
虹の岬の喫茶店 森沢明夫
一日に一季節分ずつ、ゆっくりと読み進めていきました。
店にきたお客さん全員が必ず残していく「形ある物」が、その後の話にもきちんと出てきて、物語を彩っていく。
それがお客さん同士を直接繋ぐ物になるわけではないんだけど、お店と悦子さんを中心として、そこに皆が輪になって繋がっているように見えて、読んでいて羨ましいなと思いました。
私もその繋がりの輪に入りたいなと、思ってしまいました。
第二章で出てきた虹の絵の謎が最後の章で判明した時は、得も言われぬ感動を味わいました。その案内役がコタローだというのも、すごく良かったです。森沢さんの本はこれが初めてでしたが、他の作品も読んでみたくなりました。
モデルとなったお店があるのを知り、試しに検索してみたら今でも営業されているようで、田舎にいる私からしたらとても遠い場所だけど、いつか東京方面に行く機会が出来た時は、是非行ってみたいです。
まずは、近所の喫茶店を巡って、お気に入りのお店を見つけるところから始めようかなと思います。
探偵ガリレオ 東野圭吾
初めてのガリレオシリーズで東野圭吾さんの作品を読むのもこれが初めてです。
一話完結の短編集だからというのもあると思いますが、科学を使ったトリックに重きを置いていて、物語についてはあっさりしていて全編通して気楽に読めるように作られているなぁと感じました。
あと、既にドラマ化してるから言える事かもしれませんが、トリックの再現実験を映像で見たら面白そうだなと思いました。特に「転写る」と「離脱る」の二つ。調べてみたら「転写る」は映像化されてないようですが「離脱る」はされてたので、今更ながらドラマも見てみようと思います。
東野圭吾さんは他の作品に関しても評価が高い作家さんだという事は存じ上げているので、近いうちに長編にも挑戦したいです。このままガリレオシリーズ読み進めていって「容疑者Xの献身」を読むか、ガリレオシリーズではない「秘密」を読むかで今迷っています。
わかりやすさの罠 池上流「知る力」の鍛え方 池上彰
いかに「わかりやすく」伝えられるかを常に考えているという池上さん。この本についても終始そのモットーに基づいて書かれているという事がよくわかりました。「そこまでわかりやすくしなくても・・・」と思ってしまうほど。
「わかりやすい」解説を聞いて、わかった「つもり」になってはいけないとも書かれており、それは本当にその通りだと思いますし、この本だって例外ではないという事を仰りたいのだと解釈して読み進めました。
この本は「きっかけ」であって、この「きっかけ」を得た後、自分の頭で考えて「どう行動するのか」が大事だという事だと思います。
私は、この本を読んでSNSで拡散されるフェイクニュースやネット記事を安易に信用しないという事を再認識する「きっかけ」になりました。
私が生きている間はこの世からインターネットがなくなる事はないと思っています。そして今後さらにネットに触れる機会は増えていくと考えています。
ですので、ネットの情報を遮断する事はせず、あえてネットの情報にどんどん触れていくようにして、その記事の真偽を見極める目を、今のうちから養っておきたい。と、いう考えに至りました。
イン・ザ・プール 奥田英朗
文庫裏表紙には「こいつは利口か、馬鹿か?名医か、ヤブ医者か?」と、書かれています。こういう場合は大抵名医で、「ヤブ医者に見えるけど実は名医」なのがわかる展開や、それとなく匂わせる文章があったりするものです。
しかし、この作品は違いました。本当にこの文章通り、利口なのか馬鹿なのか名医なのかヤブ医者なのか最後までさっぱりわからないのです。
時には医者らしくそれらしい対処法を与えて見たり(第3話)
わざと追い詰めるような発言をしてみたり(第5話)して
「あ、ひょっとしたら計算でやってるのかも?」と思ったりする事もあったのですが、それ以上に突飛な行動の方が目立つせいでどうしても名医よりヤブ寄りの印象になってしまいます。
さらには、来院した患者さんも全員が全員先生のおかげで症状が治まって解決するというわけではなく「プール依存症は治ったけど、その前の症状はどうなったの?」とか「この偶然が起こらなかったら治ってないんじゃ・・・?」とか、そもそも医者らしい事をしたのかすらわからないまま終わる話もあったりするものだから、尚更わからなくなってしまうのです。
こうなったら次の作品も読んで確かめないと気が済みません。
感情的にならない本 和田秀樹
私は「感情的にならない方法」というより「感情的になるかならないかを自分がどこで線引きしているのかが見えた」事が大きな収穫でした。
この本は徹底的に「感情的にならないための方法」について書かれているので、読んでいると「ここはその通りだなぁ」と思う事もあれば「ここまでするのはちょっと考えなさすぎじゃないかなぁ」と、思ったりする事もあり、段々と自分の中で感情的になる時とならない時の境目が見えてくるようになりました。
自分の境界線を見失わないようにするため、かつ物事を柔軟に対応できるようにするため、この本で指針にしたいと思った箇所はメモしておいて、定期的に見るようにしていきたいです。
妖奇庵夜話 空蝉の少年 榎田ユウリ
前作の雰囲気が好きだったので、次作も読んでみました。
今作は事件関係以外のシーンが終始良い雰囲気で、読んでいて穏やかな気持ちになりました。「にゃあさん」がその役割を半分以上は担っていたような気がします。
前作のラストは後味の悪いモノを残すラストでしたが、今作ではそういうモノもなく、すっきりした読み心地でした。
出てくる妖人が皆、今後もちょい役とかで出てきたらいいなあと思えるような良いキャラばかりで、今後のシリーズも楽しみながら読み進めていけそうです。
教養としてのゲーム史 多根清史
「ポン」というアタリ製のゲームから、ファミコンの「ゼビウス」や「マリオ」や「ドラクエ」に至るまでの進化の歴史を詳しく解説しています。
詳しい人なら知っている事なのかもしれませんが、私は知らなかった事も結構あったので、興味深く読めました。ドラクエを観光ツアーに例えていたのは面白かったです。
私的にはファミコンまでの話は面白く読めたのですが、それ以降の話はあまり頭に入ってこなかった印象でした。「同級生」がエロゲーから恋愛SLGへと発展するきっかけになった作品だという部分は知れてよかったです。
田舎の刑事の動物記 滝田務雄
前作を読んでから他にも色々と読んできたおかげか、今作は特にモヤっとした感情もなくすんなり楽しむ事が出来ました。というか、今作は黒白お互いに腹黒さを感じる感情の描写がほぼ無かったような気がします。だからかもしれません。
あと、奥さんが前作と比べてだいぶ「普通」になったと感じることができたのも大きかったかなと思います。前作はどうしても奥さんのキャラクターが「マサルさん」や「ボーボボ」に出てくるようなギャグマンガチックなキャラクターに見えてしまって、この作品の作風とミスマッチしているように感じていました。
しかし今作は最初こそ突飛な登場でしたが、それが事件解決のきっかけになったり、主人公との旅行では事件の顛末の聞き役になっていたり、病院で主人公以外の登場人物と普通のやり取りをしていたり、果ては"女の子"らしい怒りを見せたりと、前作では謎のままだった奥さんの「普通」な一面を今作で見られた事で、徐々にミスマッチ感が薄れたのだと思います。
今作の中では「夏休みの絵日記」が一番好きな話でした。全ての行動に意味があって、それが一つに繋がっていく過程が面白かったです。
吼えろペンRRR 島本和彦
炎尾の方の燃にまた会えるとは思ってなかったのでとても嬉しいです。冒頭の富士鷹ジュビロ先生とのやり取りを見て「そうそうコレコレ!これが見たかったんだよ!!」と、開始早々満足度が100%を超えました。マンガ道場は諸事情により見られなかったのですが、見てなくて良かったのかも・・・と思ってしまうくらい読んでて私も辛い気持ちになりました(笑)
TSUTAYA札幌インター店へはラクガキがされる前に北海道旅行で行った事があるのですが、確かに交通の便は悪かったような記憶があります(笑)レンタカーは使わなかったので、電車とバスを乗り継いで行ったような・・・しかしそれもまたいい思い出です。その時に買った「ヒーローカンパニー」のサイン入り8巻は一生の宝物として保管しています。
「やりがいのある仕事」という幻想 森博嗣
森博嗣さんの著作はこれが初めてです。本を読み始めた頃からずっと「すべてがFになる」はいつか読みたいなと思っていたのですが、先に縁があったのはこちらの本でした。
やりがいを仕事の中で見つけようとせず、仕事以外で夢中になれる楽しみを見つけて、その楽しみにお金を使う。そのために働く。確かに半年前くらいまでの私は仕事以外の楽しみが何も無かったかもしれません。最近はアウトプットする楽しみが出来たので、少し楽になった気がします。
「励ましの言葉をもらいたい」人たちにとっては確かに「冷たく」感じるのかもしれないのですが、私は全然「冷たさ」は感じなかったです。
”今の自分の状況は、全部自分が仕込んだ結果であるということ”
この一文が一番刺さりました。今後も何か後悔したり過去を振り返ったりしてしまった時はこの言葉を思い出したいです。
終わりに
月末に少しペースダウンしてしまいました。4月は無理に読もうとはせずまったりと読んでいきたいです。でも出来れば5冊以上は読みたいかな・・・。
最後までお読みいただきありがとうございました。
konna tokoro made yonde kurete arigatou. demo tokuni nanimo omoshiroi koto kaite naiyo.
