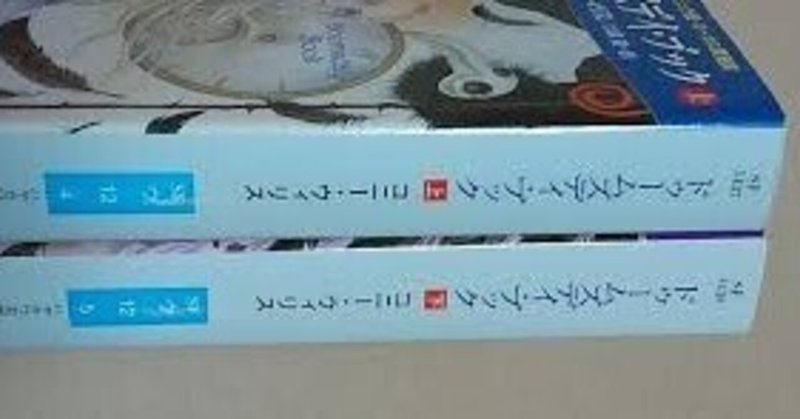
惹きつける物語 ― ドゥームズデイ・ブック
コニー・ウィリスの『ドゥームズデイ・ブック(上下)』を何度読んだことでしょう。
『航路』、『リンカーンの夢』も何度も読んでいます。
でも、コニーのしつこい書き方をわたしは大嫌い。
それに、並みいるSFの賞をすべてかっぱらって行くのに、ちっともSFなんかじゃないし。
でも、なぜか読んでしまう。
何度もなんども。。
お薦めでない本、です。ほんとに。
たぶん、ユング派のカウンセラーがクライアントにやる手法に近いでしょう。
苦しむ主人公と道を歩いて行って、はたと読者が自分の内にあった「本来の配置」に気づくという感じかもしれない。
ああ、そうだそうだってわたしがじぶんの大元に気づく。
だから、最後にああ、、と浄化の涙が流れる。
しつこくコニーは物語りました。
しつこいわたしは何度も読みます。
ほんとのわたしの声が聞きたいっ!
わたしは最後のたった1ページに会いたくて毎回読んでしまう。
気づきというものは、物語の形でしかわたしに入って来ないということでしょうか。
1.キブリンが惹きつける
『ドゥームズデイ・ブック(上下)』を、また読み終わりました。
ロス感が襲っています。
わたしのキブリンは去ってしまった・・。
途方に暮れるような、でも、失うとともに何かがわたしの中に満ちて行く・・。
アマゾンでの紹介欄にはこうあります。
「過去への時間旅行が可能となり、研究者は専門とする時代をじかに観察することができるようになったのだ。
オックスフォード大学史学部の史学生キヴリンは実習の一環として前人未踏の14世紀に送られた。
だが、彼女は中世に到着すると同時に病に倒れてしまった……はたして彼女は未来に無事に帰還できるのか?
ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞を受賞した、タイムトラベルSF!」
いいえ、これはSFなんかじゃない。ハン・ソロもチューバッカも出て来ません。
彼女を送り出した21世紀側はパンデミックのウィルスでてんやわんや。
り患したまま送り込まれたキブリンも、朦朧状態でペストが次々と伝播してゆく14世紀イギリスへ。
同時並行で進むパンデミックを描いています。
でも、話はまったくシンプルで、なんのどんでん返しもロマンスもなし。
忍耐の書。とにかく話が進まないことと言ったらない!
上下巻、ずーっとワタオニの世間話聞かされているくらいに単調です。
テーマも悲惨です。
当時のヨーロッパの全人口の50%、5000万人が死に絶えたペストが辛い。
あなたにはお薦めできにくい本なのは明らかです。
でも、だんだん面白くなってきて、なぜかページをめくる手が止まらなくなる。
物語は淡々と進みますが、登場人物たちがどうなってしまうのか?と読み進む。
キブリンやダンワージー先生たちの焦燥が手に取るようにわかる。
周囲は自分のことばかりですれ違いが多くて、ほんとにまどろっこしい。
でも、自分の願いに献身する先生やキブリンやローシュ神父が惹きつけ離さない。
読むと圧倒され、いつか読み返したいと思って終わる。
そして、また読んでしまう。。。そういうお話です。
キブリンは恨み言や非難をいいません。耐えてみなのサポートに尽くす。
その他者のことをとやかく言わないことによってかえって彼女の苦悩や願いがくっきりして行く。
読んでいるとだんだんとわたしがキブリンに一体化してゆく。
そして読み終わる。
最後、泣いてしまう・・。
それは浄化の涙で、コニーの『航路』もまったく同じで、この喪失感、はんぱないです。
2.もどかしさと、静かで深い生死への感覚
レビューワーたちは書き込みました。
「伝染病と対峙する生身の人々が描かれていました。
「航路」と共通するのは、急いでいるのに引き留められ、なかなか目的地にたどり着けないというもどかしさです。
そんな中で主人公たちは献身的に、目の前で苦しむ人や大切な人を助けたいと努力します。
希望に満ちて過去にやってきた主人公は絶望へと落とされ、そして成長を遂げ、自分の帰還も人々の命を助けることもほぼ不可能と悟ってからも看病をやめようとはしません。
その姿勢こそ人間の証、その人々の営みこそが歴史なのだという、筆者の暖かなまなざしの中、奇跡を信じて努力を続ける主人公の姿がたんたんと描かれます。」
「実際に決して明るいユーモラスな話ではないのですが、
女子大生である主人公の無力さも含めて淡々と描かれる病の情景には、
身を切る悲しみや人間の命への慟哭といった大きな感情的揺さぶりととはまた違った、静かで深い生死への感覚が研ぎすまされます。」
絶望の中の献身の物語は、カタストロフへとどんどん滑り落ちていき、やがてドゥームズデイ(最後の審判)を迎えます。
実際のその時代の暮らしを目の当たりにすることって、確かに未来がわかっているからこそ重たいんだなって気づかされる。
コニーの腕力にほんとうに脱帽します。
あなたの歴史にも暗黒の中世があったかもしれません。
辛さと、逃げようも無く光射さない時が。
わたしたちの辛さは、もどかしさと無力さとが親となって生み出されています。
それをこんなふうに物語られると、読み手も無意識に自分の暗黒史を重ねて行く。
登場人物たちの理不尽さ、やりきれなさ、悲しみ、あえぎ・・・に自分のこころが投影されてゆく。
そうして添う時、あっと思い、、救われる。
レビューワーの言う「静かで深い生死への感覚」とは、黙って瞑想なんかしてても来ません。
一緒に歩む苦しみの中でこそ、超えれるのかもしれないと思う。
3.真実は言葉では言えない
本人はとんでもない理不尽に巻き込まれ苦しみ、涙し、救いが無いのです。
でも、コニーはキブリンに淡々とした話しかさせていない。
会話のどの1つも無駄なものがない構成です。
まったくありふれた会話。。
なんだけど、その裏も気づかせないほどに、自然に展開してゆく。
あまりに自然で、あなたもきっと、どこがすごいのかに気づけません。
コニーは凄腕の作家です。
キブリンの話にも、他人のアラばかり探す者、非難ばかりする者、虚栄を張る者がたくさん出てくる。
ほんとにうんざりする”ヤツラ”、です。
そういうわたしたちの日常でもある世界ですが、いつもは触れれないところにこの物語は誘う。
キブリンは、内なる願い、内なる光を唯一の頼りとして生きようとします。
自身は満身創痍なんだけれども、その光を誠実に信じるのです。
安全や自己正当化に向かわず、ハートを開き続ける。
その一途さにわたしはまいる。
わたしの日常なんだけど、わたしが忘れていたことを再生する。
なぜアサーティブな表現に人がこころ動かされるのかと思います。
あなたに虚勢や虚栄のないその人のこころを差し出すからでしょう。
でも、だから結論はこうなんだとまでいってしまうと、真実はこうなんだといってしまうと、それは真実ではなくなってしまう。
キブリンの話にこころ惹かれてしまうのは、著者がキブリンに余計なことを言わせないからです。
わたしたちは、一見普通な、でもほんとは独特な話法で話し掛けて来るキブリンと喜怒哀楽して行く。
そうすると、その物語の底を流れている、たいせつなことを言葉ではなく体で感じて行く。
体で受け取ってしまったものは消えないのです。
郷愁とともにいつまでもわたしの中に生き続ける・・。
あなたは、光を周囲に放っているとは知らずに放つ者。
ああ、、また、触れたい・・。
数年ごとに読み返していますが、その周期でじぶんの中に溜まる”汚れ”をわたしは無意識に薙ぎ払いたいのかもしれない。
いや、ほんとうは、じぶんの中に果たされず積み残している子たちに会おうというのでしょう。
何をどうカウンセリングを受けているのかも分からず、でも、悲しみとあがきと怒りが涙で流されて行く。。。
そういうお話なんです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
