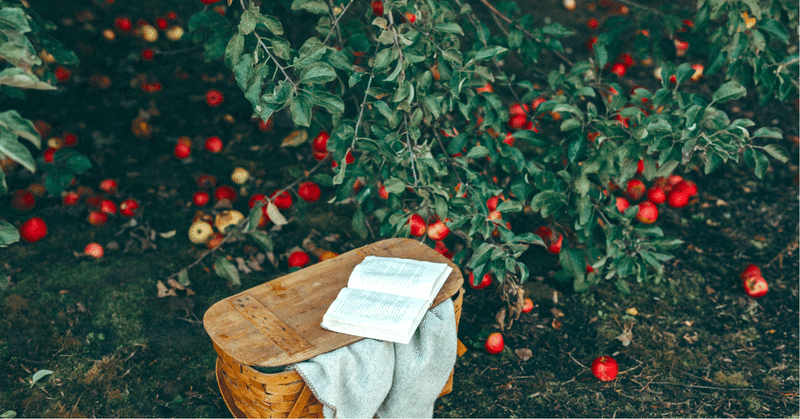
”創造的休暇”にするための、習慣の再構築
どこかのタイムラインで流れてきたアイザック・ニュートンのエピソードが私の脳内を巡っていて離れない。
彼は疫病ペストで18ヶ月もの休学期間中に「万有引力の法則」を発見し、この休学期間を「創造的休暇」と名付けていたという。
アイザック・ニュートンは万有引力の法則だけでなく微分積分学や光学の研究などでも優れた研究成果をあげました。
1643年に英国で生まれて1661年にケンブリッジ大学に入りました。その学生時代にロンドンでペストが流行し、ケンブリッジ大学が休校に追い込まれました。ニュートンはペストを避けて1655年から1656年の間、故郷のウールスソープに戻りました。ここでの18カ月は研究するための時間として十分でした。
彼がリンゴが落ちるのを見て万有引力の法則に気付いた、という有名な伝説は、ここで生まれました。ニュートンの三大業績はすべてこの時期にになされたと言われています。そのため故郷に戻っていたこの期間は「ニュートンの創造的休暇」と言われるようになったのです。ニュートンは近世を中世から切り離した画期的な研究者、という評価を生みました。
17世紀はヨーロッパの各地で ペストの流行が頻発した世紀でした。アムステルダムでは 1622年から1628年にかけて3万5000人程が死亡し、パリでは 1612年から1668年にかけて流行が何度かありました。ロンドンでも何度もペストが流行し、1665年の流行をダニエル・デフォーがルポルタージュの形で本にしました。
著しい環境の変化に動じず、ストイックに自身のミッションを叶えたエピソードを知り、背筋がピン!となったのと同時に、もどかしい気持ちになった。
誰だって、今を”創造的休暇”にしたい。
コロナ禍の今、創造休暇はおろか”通常の休暇”でさえ困難な方がいる。医療やインフラ従事者、前面で指揮をするリーダーたち。全力で感謝し、一日でも事態の収束を願うばかり。
また一方で、危機レベルは違えど我が家も「非常時」。
創造的休暇とは程遠い2歳児の在宅保育×仕事の危機的状況の突破で必死だ。特別休暇やベビーシッターという選択肢はあれど簡単には手が出せない。今はどこの子育て世代も同様の葛藤をしているだろう。
ニュートンの創造的休暇とはほど遠い現実。
深夜、息子を抱っこして寝かせながら、私は自問自答していた。
私も本をたくさん読んだり漫画も読みたい。
その内容でnote書いたり、新しいチャレンジを提案したい。
本業だってもっと攻めていきたいけど、この生活でアップアップ‥。
これは子育て世代だから仕方のないことなのか?
今の情勢が落ち着くまで一旦諦めるべきなのか?
いや、この状態がいつ平常化するかは未知数。ここでの行動量の「差」は指数関数的に大きくなっていくはず。うむ、家族総出で進化したい‥。
はて、なぜ私の暮らしは平常化しないのか?
なぜ、私は疲れているのか?
抜本的に習慣を整えよう。
自問自答を繰り返していたら、ふわっと答えが出た。
家庭環境は非常時なのに、働き方は”平常時合わせ”だからだ。
そのミスマッチによって、私は疲れ、パフォーマンスは落ちている。
私は、ここ数ヶ月の生き方を抜本的に見直すことにした。
今を創造的余暇にするためには、習慣の再構築が必要だと悟った。
▷改革1: 働く時間の固定概念を消す。

働く時間の整理こそ、今最も重要なこと。
私と家族、そして仕事のメンバーにとって負担の無い再構築が必要だと思っていた。今もトライ&エラーだけど、現状は下記のようなかたちで運用している。
新タイムスケジュール
[3:30]個人的執筆&リサーチ(最もぜいたくな時間)
[5:30]本業の記事作成+TODO処理 →息子が起きる6:30まで
[9:00]家族の朝支度を済ませて私は稼動。夫は息子と遊ぶ。
[12:00]稼動終了。(夫とバトンタッチ)細かい対応はスマホで。
[14:00]息子のお昼寝に合わせて私も仮眠。うまく行けばPCを開く。
[21:00]息子就寝後、2時間作業。→23時に眠る。
私は「ひとり時間」がないとストレスを感じやすいことが分かっていたので、意地でもこの時間を毎日確保することに。
メンバーが始業する前に、タスクは全方位で打ち返している状態にして、日中にコミュニケーションラリーが発生したら、それはスマホで完結に戻す。
息子といる時間はPCもMTGもできるだけ行わない。
子どもとの時間はリラックス時間として、ベランダで庭掃除をしたり料理をしたり、絵本を読むことに集中する。
このルールだけで随分平常時の心理に戻ることができました。
▷改革2:インプットを音メディアへ。

日中における私の手足と眼の所有権は、息子が保持している。
大げさだけど、私がコントロールできるのは「耳」だけ。息子と過ごす日中はノンストップでJ-waveかPodcastを流し続けることにした。
最近はもっぱらこちら。
ナビゲーターの渡邉康太郎さんの声は日常の暮らしにフィットする。
聴いていて疲れないし、ゲストとのトークは知的好奇心・インプット欲求を充分に満たしてくれる。一度にすべてを読解することは難しいので、何度も何度も聴いていて、理解が深まる過程も楽しい。
登場する田川さんのnoteもこちらに。
あとNetflixの映画などを流し続けるのも良さそうです。
子どもと遊びながら、ちらっと部分的に食の映画やドキュメンタリーに触れることでインプット量を増やす努力をしている。
▷改革3:平日と週末の境界線を再定義する。

最後の視点がこちら。
外出もままならぬ今、平日と週末の差はあまり無く、同時に平日の稼働時間が制限されているので、週末稼動は必然。
といっても週末と聞くと「心が少しリラックスしがち」なので、個人的にはフル休暇日は土曜日だけと認識し、日曜日も[改革1]でまとめたような時間軸で過ごすようにしています。
あとお酒との関係。これも週末だけとしたい。
眠たくなってしまうと、何もできなくなってしまう‥。
どんな環境下でも揺るがない知的リズムの構築は、今なのかも。
冒頭で触れたニュートンは18ヶ月もの休校期間を「創造的期間」として昇華できたわけだけど、彼だって最初から順応できたわけではないはず。
ペストの恐怖と戦いながら、自分なりのリズムを整えていき、発見を促す土壌を整えていったのかもしれない。
ゴールデンウィークは、私たちの「創造的休暇」へ押し上げるリズムの見直し期間として有効かもしれない。
「攻めが一番の守りである」そんな言葉もありますもんね。
前例のない巣ごもりゴールディンウィーク。
ぜひ実りある連休をお過ごしください。
\Twitterやってるヨ!/
🎉つまみ食いラジオ、Podcastリリース🎉
— 渥美まいこ|食トレンド研究 (@atsumi_maiko) April 28, 2020
様々な角度から食のトレンドやカルチャーを「つまみ食い」する番組が念願のPodcastにも‥!無事に審査通過できてよかった‥☺
予想以上に多くの方に聴いていただけて嬉しい限り。
ぜひゆるりと‥公開ブレストとして聴いてください。https://t.co/znOUkyyA3K pic.twitter.com/lyQcbRuqT3
先日 #料理本リレー で紹介したのがこちらの3冊。
— 渥美まいこ|食トレンド研究 (@atsumi_maiko) April 27, 2020
またその内容はnoteにまとめようと思っているんだけど、改めて「栗原はるみ」の存在について考えました。
30代前半の私が一番憧れている料理家は彼女で、このポジションは当面揺るがなそう。未だ60代〜30代の女性から強く愛されるのはなぜだろう? pic.twitter.com/eqDtg0ZRcq
この度はありがとうございます!わたしのメディア「Yellowpage」のニュースレターに登録いただけましたら、とっても嬉しいです。https://yellowpage.tokyo/#newsletter
