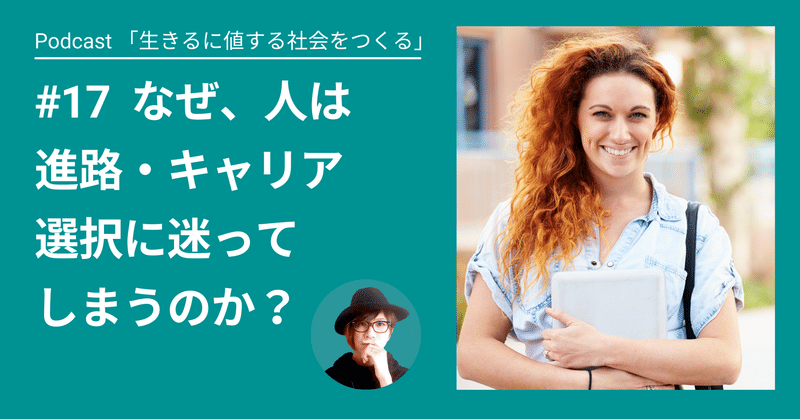
【生きるに値する社会をつくる #17】なぜ、人は進路・キャリア選択に迷ってしまうのか?」
こんにちは、「生きるに値する社会をつくること」を目的に活動しているカウンセラー・コーチ・作家の水樹ハル(@harumizuki423)です。
今回は、
「なぜ、人は進路・キャリア選択に迷ってしまうのか?」
というテーマでお話ししていきます。
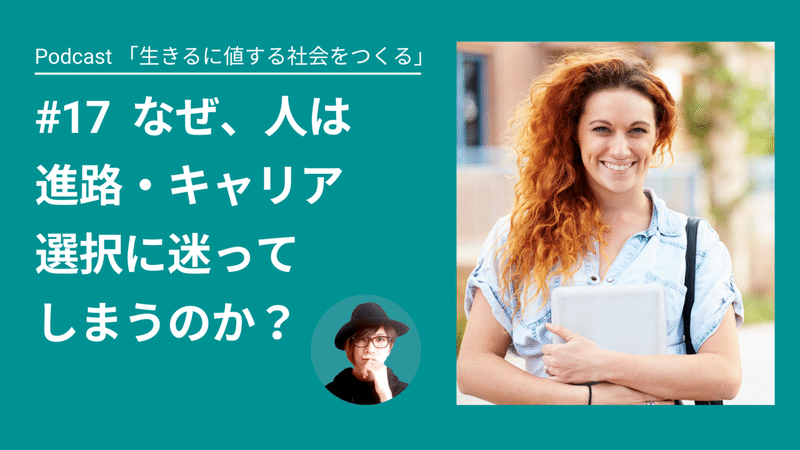
ここで少しだけイメージしてみてください。
あなたは明確に「なりたい自分」や、「したい仕事」があります。
そのため、必要な準備は努力をスムーズに行うことができ、将来についての不安があまりありません。
同級生からは
「なんでそんなに自分の軸を持って進めるの?羨ましいなぁ」
と言われたり、アドバイスを求められています。
自分の進路や就職、職業選択の時ってめちゃくちゃ悩むと思います。なので、先ほど一緒にイメージしたような状態になれたら、めちゃくちゃ楽だと思うんです。
ちなみに学生時代のぼくは、
「ミュージシャンかっこいいなー」
と思ってたけども、ヒヨッてしまい、世間体でなんとなく公務員を目指しました。
「あの時の自分の選択があって、経験できたことがあって、今につながっている」と納得はしてるものの、もう少し考えていれば、違う人生もあったのかなぁとは思います。
なので、
・世間体
・親や先生の意見
・周りが言っていること
などを物差しにして自分の未来を決めるよりも、自分で「こういうことをやってみたいからこの選択をするんだ!」と生きられていた方が、一貫性はありますよね?
あなたにも好きな漫画があると思うんですけど、そのキャラって一貫してませんか? キャラがわかりやすいと思うんです。
「自分は人と向き合う仕事がしたいんだ」と思っているのであれば、営業マンとして働くのも良いし、カウンセラーになるのも良いと思います。一貫性がありますよね。自分自身に誠実であり、「自分はこういう人間だ」って思えると、自信がもてるわけじゃないですか?
でも、ホンネではものづくりをしたいのに、役所のデスクワークをするとかってちょっとブレてますよね?
だから、自分の物差し、軸をですね自分の中で認識する認める受け入れるって言うことをすることができると、冒頭で言っていたような自分軸で人生を切り開いていく自分になるわけですよね。
とはいえ!
こういう「自分のこと」を知るための授業っていうのはないわけです。
高校生までは大体受験勉強になっちゃうじゃないですか?
保護者の方も、子どもが急に進路変更しだしたら驚くだろうし、
「進路についてはうちの家でしっかり考えてますから!」
と、先生と保護者のコミュニケーションがうまくいかないと難しい面があるわけです。
だから大学に入ってからが勝負なんです!
大学生のキャリアサポートのハード面が整ってきている
最近では、大学ではキャリアセンターというものがあり、学生の将来を一緒に考える流れや、企業でもインターンの受け入れが進んでいて早めにキャリアについて考えられる環境が出てきつつあります。
しかし、ソレはあくまでも制度や建物とか空間っていう、ハード面の話で、ソフト面が重要なんですね。
つまり、どういう授業だったり、どういうふうに自分と向き合うかっていう部分がめちゃくちゃ重要!ここの話をしたい!わけです!
ここからが本題です
前回の最後に、
「ある関西の大学で、自分を語る授業をしている情報をファイナンシャルプランナーの金山さんに教えてもらった」
とお伝えしました。
学生自身が自分の物差しで行動し、自分の中の正解を自分で作っていくためのソフト面の話です!
ここからこの話をシェアさせてください。
これは、どういう授業なのかと言うと、生徒が2分間みんなの前で自分のことを語るんです。
例えば、あなたがその発表することになりました。
自分の好きなものとかねやりたいこととかを話すわけです。
そうなると・・・
園児の頃小学生の頃中学生の頃とか、自分の歴史を振り返りながら自分は子供の時からこういうことが好きだったんだ、夢中になっていたんだ!これが私だ!
というふうに自分を理解して、発表していくことになるわけです。
これを聞いてどう思いました?
人前で話すことが少ないあなたは、みんなの前で自分のことを話すのを敬遠しがちかもしれません。 実際その授業もですね最初は50名のクラスだったんですけどやっぱり抜けて、30名が残っている状態ということでした。
自分のことが知りたいけど自分のことを話すことが難しい
恥ずかしい思いをしたら嫌だ
怖い
傷つきたくない
と言うふうになって、抜けていってしまうわけですね。
実はこれは、学生だけに限らないです。なんでぼくがそう言えるかって言うと・・・ぼく自身が社会人版のこういう活動をしてるからなんです。それがオンラインサロン「自分を知る学校」です。
「自分のことを知りたい」と思って入ったけども、「やっぱりやめます」と、これまでたくさんの人が入って、やめていきました。
これは、なかなか学校教育の根深い問題で、学校の授業って基本的には先生の話を座学で聞いて、テストで理解度を確認するっていうことですよね? 「自分のことをうまく話せない」と悩むのは、話す機会が足りない環境だから、ある意味自然なことです。
このことを、英会話で考えてみてください。英語を読んだり聞いたり書いたりはするけども、話はしない。つまり、スピーキングをやってないので英会話が話せないわけですよね。
このことと似ていて・・・自分のことを話す習慣がないから自分のことを話せないのです。だから自分のことを話して、人に伝えていくためにはですねスピーキングが重要。
でも、学校の授業でほぼ聞くことと読むことじゃないすか?
話す時間ってめちゃくちゃ短い。
だから、今までやってこなかったことを急にうまくできるかっていうと難しいと思うんですよ。ぼくは、そういう「人前でうまく自分のことを話せない人」のことを笑ったりとかそういうことはしません。したくないんです。
今回のまとめ
今回、1番お伝えしたかった事は、学生のうちから自分のことを話す習慣をつけていくことってすごく大事ということです。
この話については、ファイナンシャルプランナーの金山さんと対談収録した動画があって、その動画を配信しようと思って編集中です! 編集が完了したらこのページにリンクを掲載していきますのでご覧いただけたら嬉しいです。
学校現場にこういう先生がいらっしゃるっていうのはほんとに最高に嬉しいです!勝手に喜んでます!!コラボさせていただけるように頑張っていきます!
▼今回の話を図解でさらに理解できるInstagram
次回
Instagramを運用するようになって質問いただくことも増えてきました。めちゃくちゃ嬉しいです。
その中でも、
「自分のことを俯瞰して見られるようになるにはどうしたらいいですか?」
という相談をいただいたので、Instagram配信の中で気づいたこととかを含め、今の自分の感じていることをお伝えしていきます。
「生きるに値する社会を作る」連載一覧
▼note「月刊水樹ハル」で配信しているプロジェクト
▼水樹ハルの著書
ここから先は

水樹ハルの「まだ世には出せないお話」
ストーリー制作専門のWebライター、カウンセラーとして、「チャレンジを応援しあえる世界」を実現することを目指す、水樹ハルのnoteマガジン…
いただいたサポートは、ありがたく活動費にさせていただきます😃
