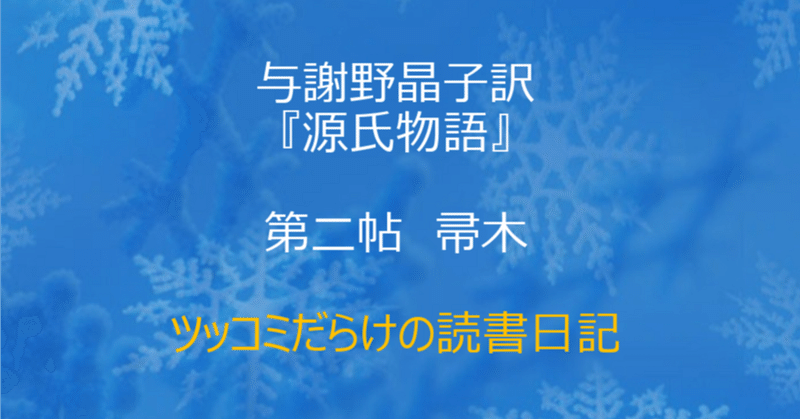
与謝野晶子訳『源氏物語』 二 帚木 ツッコミだらけの読書日記
「帚木」は「ははきぎ」と読むのだそうだ。
信濃国園原伏屋にある木で、遠くから見れば箒を立てたように見えるが、近寄ると見えなくなるという伝説の木であるらしい。そこから、近づいても逢ってくれない人、逢えそうで逢えない人の喩えに用いられる。源氏物語の「帚木」はまさにその意味であって、「逢えそうで逢えない人」というのは「空蝉(うつせみ)」。そういうようなことは、教えてもらわないとさっぱりわからない。
この第二帖の「帚木」であるが、「雨夜の品定め」に始まる(と言われている)。「品定め」とは何かというと、女性の品定めなんである。源氏の謹慎日、宮様腹の中将、左馬頭(さまのかみ)、藤式部丞(とうしきぶのじょう)の三人が源氏の元に集い、女性の品定めに興じるわけだ。この三人は誰ぞ? と聞かれても困る。源氏物語では何の前触れもなく紹介もなく、ひょいと新たな人物が現れるのである。「あんた誰よ」という感じである。三人については、とりあえずググってみた。
左馬頭:
令制の左馬寮(さまりょう)の長官。 従五位上相当。左馬寮とは官馬の調教、飼育、馬具などを管理する組織。左馬頭は、そこのトップに位置することになる。
藤式部丞:
「式部丞」というのは式部省の判官四人の総称。「藤」がつくのは藤原氏に関係するらしい。式部省というは、文部省のようなものであったようだ。この判官四人から、式部少丞、式部大丞が選ばれていく。まぁ、ようするに出世街道まっしぐらのキャリア官僚といったところか。
宮様腹の中将:
「宮様腹の」というのは、ようするに「皇女の子」。「皇女の子」は何人もいたのではないかと思われ、これじゃあどなたの子の中将であらせられるのかさっぱりわからない。私にはさっぱりわからないのだけど、どうやら特定されているらしく、中将の母が今上帝の兄弟。すなわち、源氏の従兄弟にあたる。ちなみに、中将の母(人名が出てこないので煩わしい)は左大臣の正妻で、源氏は左大臣の娘の婿である。ということは、源氏と中将は義兄弟でもあるのか(ややこしい)。
さて、四人が源氏の謹慎日に集うわけであるが、ここでまた、はて? と思う。
「謹慎日」とはなんぞや?
さては源氏の君、何かよからぬことでもしでかしたか。と思ったがそうではないようである。陰陽道に関連するものであるらしく、よくないことがあったりよくない夢を見たような時に行動を慎むというようなものであるらしい。そういうような時は帝が慎むわけで、部下も追随して謹慎していたようだ(多分)。少なくとも、罰を受けているとかそういったことではない。
さて。
五月の長雨の時期に謹慎日があり源氏が桐壺(ここの桐壺は人ではなく場所の意)で休んでいたところへ、暇だ暇だとかなんとか言ってかどうかは知らないけれど友人三人が集まってきたわけで(謹慎日にいいのか?)、そこで何を話すかと思えば女性談義という、今でもありそうなシチュエーションなんである。
ちなみに、この時の源氏の様子がこうである。
柔らかい白い着物を重ねた上に、袴は着けずに直衣だけをおおように掛けて、からだを横にしている源氏は平生よりもまた美しくて、女性であったらどんなにきれいな人だろうと思われた。
『袴は着けずに直衣だけをおおように掛けて、からだを横にしている』とは、いったいどんな身なりでどんな体勢なんであろうか。『どんなにきれいな人だろう』という表現と相まって、なんだか色っぽいというか艶っぽいというか、妙ななまめかしさを感じてしまう。今集っているのは男達ばかりであるが、その場所「桐壺」は後宮なんである。周りの女性達とどう関わっていたのやら。
で、この女性談義であるが、千年前の平安貴族が何を考えていたのかがうかがい知れて、なかなかに興味深い。
まず頭中将が言う。
これならば完全だ、欠点がないという女は少ないものであると私は今やっと気がつきました。
「今やっと」とあるが、そう言えば彼らは幾つなんだろう。源氏は十二歳で元服し結婚しているんである。源氏は妻の家である左大臣家にはなかなか寄り付かないので左大臣がヤキモキしているなどという表現がよくみられる。源氏二十歳だとするとヤキモキ状態が八年も続いているのかともなり、なんだかピンとこない。三年で十五。さすがに若すぎるのか。十七? 台詞の頭中将がもしかしたら幾つか年上かもしれず、だとしても二十歳? いずれにしても二十歳になるなならないかの若者が「今やっと」ということであるらしい。
自分が少し知っていることで得意になって、ほかの人を軽蔑することのできる厭味な女が多いんですよ。
それはまぁ、男であろうと女であろうとイヤでしょう。
仲に立った人間がいいことだけを話して、欠点は隠して言わないものですから、〈中略〉、真実だろうと思って結婚したあとで、だんだんあらが出てこないわけはありません
まぁ、この頃は「仲に立つ人」がいて結婚ということは当たり前だったかもしれない。
世間からはそんな家のあることなども無視されているような寂しい家に、思いがけない娘が育てられていたとしたら、発見者は非常にうれしいでしょう。意外であったということは十分に男の心を引く力になります。
誰にも知られていない、それでいて素晴らしい女性を見つけると嬉しくなるわけだ。「誰にも知られていない」が大切である、というわけかしら。
見苦しくもない娘で、それ相応な自重心を持っていて、手紙を書く時には蘆手のような簡単な文章を上手に書き、墨色のほのかな文字で相手を引きつけて置いて、もっと確かな手紙を書かせたいと男をあせらせて、声が聞かれる程度に接近して行って話そうとしても、息よりも低い声で少ししかものを言わないというようなのが、男の正しい判断を誤らせるのですよ。
『息よりも低い声で少ししかものを言わない』女性がよい?
妻に必要な資格は家庭を預かることですから、文学趣味とかおもしろい才気などはなくてもいいようなものですが、まじめ一方で、なりふりもかまわないで、額髪をうるさがって耳の後ろへはさんでばかりいる、ただ物質的な世話だけを一所懸命にやいてくれる、そんなのではね。
うるさがって悪かったわね、と、ついついひねくれてしまう。
遊戯も風流も主婦としてすることも自発的には何もできない、教えられただけの芸を見せるにすぎないような女に、妻としての信頼を持つことはできません。
教えられただけの芸!
やりたくもないことをやらされていては、そうもなるでしょう。
ですからもう階級も何も言いません。容貌もどうでもいいとします。片よった性質でさえなければ、まじめで素直な人を妻にすべきだと思います。
それでも最低限の階級はいるのでしょうね。
あまりに男に自由を与えすぎる女も、男にとっては気楽で、その細君の心がけがかわいく思われそうでありますが、しかしそれもですね、ほんとうは感心のできかねる妻の態度です。つながれない船は浮き歩くということになるじゃありませんか、ねえ
つながれない船は浮き歩く、ねぇ。
技巧でおもしろく思わせるような人には永久の愛が持てないと私は決めています。
カッコウつけるだけじゃだめということかしらね。
そんなこんなを話している中で、中将がこんなことを言う。
「現在の恋人で、深い愛着を覚えていながらその女の愛に信用が持てないということはよくない。自身の愛さえ深ければ女のあやふやな心持ちも直して見せることができるはずだが、どうだろうかね。方法はほかにありませんよ。長い心で見ていくだけですね」 と頭中将は言って、自分の妹と源氏の中はこれに当たっているはずだと思うのに、源氏が目を閉じたままで何も言わぬのを、物足らずも口惜しくも思った。
ふ~ん。頭中将は妹夫婦のことをそういう風にみてらっしゃったのね。源氏が妹に深い愛着があると。
一方で源氏はというと・・・。
こんなことがまた左馬頭によって言われている間にも、源氏は心の中でただ一人の恋しい方のことを思い続けていた。藤壺の宮は足りない点もなく、才気の見えすぎる方でもないりっぱな貴女であるとうなずきながらも、その人を思うと例のとおりに胸が苦しみでいっぱいになった。
妻である中将の妹のことではなくって、亡き母である桐壺によく似た藤壺のことを想っていたのであった。
さて。
ここまでで第二帖「帚木」の半分を経過しているのであるが、「品定め」で終わってしまってはタイトルである「帚木」が意味を成さない。
品定めの結論は出ないまま朝まで話し続け、明けて翌日。
源氏は無沙汰している左大臣家(妻の実家であり、妻はそちらで暮らしている(と思われる))を訪うた。
『暑さに部屋着だけになっている源氏』であったが、暗くなってきたころに家従が『今夜は中神のお通り路』なのでここで寝るのはよくないという(暗くなってから申し上げるとは随分な段取りだ)。『疲れていて寝てしまいたい』『からだが大儀だ』などという源氏であったが(徹夜で品定めなどしているからだろう)、紀伊守の中川辺りにある家従の家に移動することになった。迎えることになった家従宅では家族が集まっていて、失礼がないかと懸念している。源氏はというと『人がたくさんいる家がうれしいのだよ、女の人の居所が遠いような所は夜がこわいよ。』などと仰せだ(疲れているんじゃなかったのか)。『隠れた恋人の家は幾つもあるはずであるが(やっぱり「幾つもある」のね)、久しぶりに帰ってきて、方角除けにほかの女の所へ行っては夫人に済まぬと思って』いながらも、源氏は左大臣に告げもせずに中川辺りにある家従の家へお出でになる(本当に済まぬと思っていたのかしらん)。
そして「帚木」は、いよいよこれからである。『中川辺りにある家従の家』にいたのが空蝉なのである。といっても、「空蝉」という名前が出てくるわけでもないのだが。
皆が眠りについた夜。源氏は眠れずにいる。『一人臥をしていると思うと目がさめがち』であるらしい。襖一枚隔てた向こうには女が休んでいた。声が聞こえる。
「中将はどこへ行ったの。今夜は人がそばにいてくれないと何だか心細い気がする」 低い下の室のほうから、女房が、「あの人ちょうどお湯にはいりに参りまして、すぐ参ると申しました」 と言っていた。
また「中将」である。ここの「中将」は先ほど源氏と品定めをしていた「中将」とはもちろん違う。女の世話をしている、おそらくは年配の女性だ。その「中将」がそばにいてくれないと心細いと言っているわけだ。そりゃそうだ、すぐそばに源氏が休んでいるのだから。
皆が寝静まったころ・・・源氏がゴソゴソと動き出すんである(ゴキブリか)。遠慮もなく襖をさぁっと開ける。几帳や衣服箱の間を躊躇わずに歩いてゆく。女は中将が来たのだと思っていた。その女の顔を覆うた着物を源氏は手で引きのける。女はびっくり仰天である。来たのは中将だと思っていたら、あろうことか源氏である。恐ろしくて声もでない。その女に源氏はこういうのである。
「あなたが中将を呼んでいらっしゃったから、私の思いが通じたのだと思って」
確かに、彼女は中将を呼んでいた。だがしかし、何故それが源氏の思いと繋がるのだろうか。私はしばし途方に暮れた。与謝野晶子はヒントを残してくれている。
と源氏の宰相中将は言いかけたが、
そう。そうなんである。
何を隠そう源氏も「中将」なんである。
なんてことだ。さっき女が「中将」を呼んだのを自分を呼んだのだと勝手解釈しているわけだ。オイオイ。
源氏はさらに続ける。
「出来心のようにあなたは思うでしょう。もっともだけれど、私はそうじゃないのですよ。ずっと前からあなたを思っていたのです。それを聞いていただきたいのでこんな機会を待っていたのです。だからすべて皆前生の縁が導くのだと思ってください」
前生の縁って。
女が恐れようが怯えようが源氏は関知せず。
小柄な人であったから、片手で抱いて以前の襖子の所へ出て来ると、さっき呼ばれていた中将らしい女房が向こうから来た。
片手で抱いて?
これまたどういうシチュエーションなんだかよくわからないが、とにかく、自室へ女を連れ込もうとしたところが中将(この中将は女の世話をするおばさん)と出くわす。さあ、どうする源氏。
源氏の中将はこの中将をまったく無視していた。初めの座敷へ抱いて行って女をおろして、それから襖子をしめて、「夜明けにお迎えに来るがいい」と言った。
どへー!
何をするんやら。
「中将が中将を無視する」とは中将だらけで困るのだか、ようするに、中将である源氏が、女の世話役であるおばさんの中将を無視したと、そういうことだ。もはやおばさんは路傍の石だ。
「夜明けにお迎えにくるがいい」とは、またなんとも。
女は怯え汗を流して苦痛に耐え、おばさんは男が誰かを承知してなす術もない。他の男であれば抵抗もしようが相手は皇子だ。まして、大騒ぎしても女を窮状に追い込むだけかもしれない。
源氏は誠実に(既に誠実を通り越しているような気もするが)女を説得するが女は承知しない。
卑しい私ですが、軽蔑してもよいものだというあなたのお心持ちを私は深くお恨みに思います。
これにはさすがの源氏も怯んだ。
が、引き下がるはずもなく。
私はまだ女性に階級のあることも何も知らない。はじめての経験なんです。
ええ!?
前夜の品定めはいったいなんだったんだ。
なおも源氏は説得を続ける。
女は折れない。
気の毒ではあるがこのままで別れたらのちのちまでも後悔が自分を苦しめるであろうと源氏は思ったのであった。
うーむ。
のちのちまで後悔するのか。
そうこうしている間にも鶏の声が聞こえ、家従たちの声が聞こえる。朝が来たのだ。
それでもなお、
女を行かせようとしてもまた引き留める源氏であった。
結局のところ女は抵抗し続けた。自分が人妻であるという理由で。たとえ、夫に愛情を抱けないとしても。絶世の美男子である源氏が相手であろうとも。それはそれでスゴいかもしれない。
女と通信する手段を確認することさえできぬままに、今風に言うならメルアドの交換さえできぬままにその邸宅を去ることになった。別れるとき源氏は泣いた。それがまた艶でなのであった。
その後も源氏は中川の女のことを思い続ける。
すぐれた女ではないが、感じのよさを十分に備えた中の品だ
「中の品」ね。
あれきり何とも言ってやらないことは、女の身にとってどんなに苦しいことだろうと中川の女のことがあわれまれて
ええ!? そうなん?
なんで源氏は女が苦しんでると思うんだろう。
「実は自分に惚れているのだから音沙汰なしでは苦しむだろう」と、そういうことか? 「困った人(源氏)が寄り付かなくなってホッとしている」とは考えない・・・んだろうなぁ。
そして、源氏は一計を案じるのである。
先だっての宅の主(紀伊守)を呼び出してこう言った。
「自分の手もとへ、この間見た中納言の子供をよこしてくれないか。かわいい子だったからそばで使おうと思う。御所へ出すことも私からしてやろう」
そうきたか!
「中納言の子」とは「女の弟」だ。なんで「中納言の子」というのか、それは知らない。だが、要するに、この子を間に挟んで女とやり取りしようと、そういう魂胆だな。名案じゃないか!(イヤミ)。
その紀伊守とのやり取り中、源氏はこんなことを問う。
「その姉さんは君の弟を生んでいるの」
「その姉さん」とは、よこせと言った「中納言の子供」の姉であり、先だって夜這いに失敗した相手の女だ。そして「その姉さん」は紀伊守の父親と結婚していて、愛情を抱けない夫とは紀伊守の父親である。「君の弟を生んでいるのか」というのは、女と夫との間に子供があるのかと問うているのだ。知ってどうする? 女と夫との関係を間接的に探っているのか。はたまた、女に出産経験があるかないかが問題なのか。その理由はうかがいしれないが、とにかくも女にはまだ子がなかった。
さてさて、その弟が源氏の元にやってきた。
源氏は姉とのことをかいつまんで、あるいはオブラートに包んで聞かせ、早速とばかりに女宛の手紙を弟に持たせる。弟のことを「小君(こぎみ)」と称しているので、ここでもそうする。姉に手紙を渡すものの、姉は返事をくれない。返事をもらうよう源氏に申し使っているので催促はするのだが姉は応じない。返事がないと聞いた源氏は小君にこういうのだ。
「おまえは知らないだろうね、伊予の老人よりも私はさきに姉さんの恋人だったのだ。頸の細い貧弱な男だからといって、姉さんはあの不恰好な老人を良人に持って、今だって知らないなどと言って私を軽蔑しているのだ。けれどもおまえは私の子になっておれ。姉さんがたよりにしている人はさきが短いよ」
ええ!?(何度目だ)
デタラメである。
先に恋人だった?
頸の細い貧弱な男?
さきが短い?
まぁ、子供相手にデタラメを、よくまぁ、言えたものです。
その後も源氏はせっせと手紙を送り、女は頑として受け付けない。源氏には
女が自分とした過失に苦しんでいる様子が目から消えない。
「自分とした過失」?
って、何?
連れ込んだこと?
それとももっと別のこと?
よくわからない。
そしてまた源氏は企てる。
偶然を装って紀伊守宅へ押しかけるんである。以降の手筈は小君とは申し合わせてある。だが、ここでも小君が源氏と姉との間を行ったり来たりするだけで、何も進展しない。
とうとう源氏は諦めた。
「じゃあもういい。おまえだけでも私を愛してくれ」と言って、源氏は小君をそばに寝させた。
こういう辺り、原文ではどうなっているのだろう。
「よし、あこだに、な捨てそ」とのたまひて、御かたはらに臥せたまへり。
「よし、あこだに、な捨てそ」というのは、多くは次のように訳すようだ。
「それでは、おまえだけは、わたしを裏切るでないぞ」
裏切るな、捨てるな、そう訳されることが多いところ、与謝野晶子は「愛してくれ」と訳したわけだ。与謝野晶子らしいと言えばそれまでなのだが、当時の人々はどう読み取ったのだろうか。
ま、長くなりそうなので、やめた。
帚木はこれで終わって、次の帖は「空蝉」である。
え?
空蝉?
まだ続くのか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
