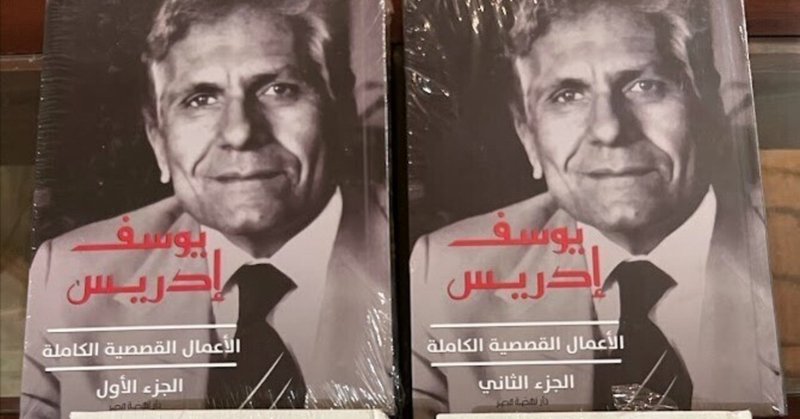
【翻訳】ユースフ・イドリース「肉の家」(エジプト)
ランプの側に指輪がある。
沈黙が訪れ、耳が聾する。
沈黙に、一つの指が忍び込む。
無言で、指に指輪が嵌められる。
灯りが消され、闇に包まれる。
闇の中で、目も盲いる。
未亡人と3人の娘たち。
家とはその一室である。はじまりとは沈黙である。
未亡人は色白、細身で背が高く、35歳であった。その娘たちも背が高く、思春期であったが、喪中も、喪が明けても、黒く身を覆う服を脱がなかった。年少の者は16歳、年長の者は20歳。醜く、父から受け継いだのは、いびつで凸凹とした褐色の体。母からかろうじて受け継いだのは体格だった。
家は狭いけれども、日中の彼女らにとって十分な広さだった。部屋はひどく粗末だが、綺麗に整理されていて、いかにも家という雰囲気が広がっていた。部屋は4人の女の感触に満ちていた。夜には女たちの肉体が、血の通った生暖かい肉でできた大きな丘のようになって散らばっていた。肉体のいくつかは布団の上に、いくつかはそのまわりにあった。熱く、眠らせぬ、そして時に深いうめきのごとき息がその部屋から上がった。
男が死んでから一家は沈黙に覆われた。男は長患いの末に2年で死んだ。悲しみが終わると悲しむ者たちの習慣が残された。特に顕著なものは沈黙だった。底知れぬ長い沈黙。実際のところ、それは何かを待ち望む沈黙だった。娘たちは年頃になり、長いこと待ち望んでいたのだ。しかし、婿たちはやってこない。貧しく醜い女たちの戸を叩く狂人がいるだろうか? それも、外ならぬ彼女らが父なし子だというのなら。しかし、希望はたしかに存在する。どんな豆粒にも量り手がおり、どんな娘にも貰い手がいると言うではないか。もしあるところに貧者がいれば、そこには常にそれ以上の貧者がいる。もしあるところに醜い者がいれば、そこには常にそれ以上に醜い者がいる。望みは叶えられる。辛抱すれば、きっと叶えられる。
唯一沈黙を破ったのは読誦の声だった。目新しいものも、心を高ぶらせるものもない日常の中で、その声は大きくなっていった。読誦をしたのはクルアーン誦みであり、そのクルアーン誦みは盲目だった。彼は故人の魂のためにクルアーンを誦んだ。約束の時間は変わることがない。彼は金曜日のアスル にやってくると、杖でドアを叩き、差し出された手に身を委ね、敷物の上に胡坐をかいた。誦み終わると、サンダルを手探りし、挨拶をしたが、一人として返事をしようとも思わなかった。そうして彼は帰っていく。彼はいつも通りにやってきてはいつも通りにクルアーンを誦み、いつものように帰っていくので、ついには誰も彼を意識せず、気にも留めないようになった。
常にあるのは沈黙だった。金曜日のアスルの読誦は沈黙を切り刻んだとはいえ、それもまた沈黙が沈黙を切り刻むかのようになってしまった。沈黙、それは何かを待ち望むことのようであり、希望のようなものでもあった。少量の、しかし常に存在する希望。それは最小のものに対する希望だった。どんな少量のものにも常にそれより少量のものがある。どんな大きなものも、彼女らは期待していなかった。決して期待していなかったのだ。
沈黙はことが起こるまで続く。金曜のアスルになったがクルアーン誦みは来なかったのだ。というのも、どんな契約にも、たとえ長続きしたとしても終わりはある。その契約も終わったのだ。
未亡人と娘たちはその時になってはじめて、これまでのことの本質を理解した。それは沈黙を切り裂いた唯一の声だっただけではなく、週に一回とはいえ戸を叩いた唯一の男でもあった。むしろ、彼女たちは他のことも理解した。男は女たちのように貧しかった。それはその通り。しかし、男の服は常に綺麗で、サンダルは常に正確に結ばれていた。ターバンは目の見える者には不可能なほどの正確さで巻かれていた。声は力強く、深く、よく通った。
そして、提案がはじまった。どうして契約を今から更新しないのか? どうしてのこの瞬間にもその要求を伝えないのか?
彼は忙しい。そうさせておけばいい。しかし、待つことは新たなことではない。彼はマグリブの頃にやってきて、まるではじめての読誦であるかのように読誦した。そして、提案は膨れ上がる。どうして私たちの家をその声で満たす男と、私たちの一人が結婚しないのか? 彼は未婚でまだ女を知らない。青々とした髭を生やしているが、青年だ。彼と話して見れば、言葉が言葉を引き出すようだ。ほら、彼もまた合法(ハラーム)な女 を探している。
娘たちは提案し、母は娘たちの顔を見た。誰がその提案を受け入れて、その幸運の主になるのかを見定めるためだ。しかし、娘たちは提案者として顔をそむけた。ただの提案者として。その顔は言外に主張していた。「私たちは断食をして、盲人でその断食を解くの?」
娘たちは未だ婿たちを夢見ていたが、婿は普通、盲目ではない。かわいそうに、娘たちはまだ男の世界を知らなかった。男は目ではないと、理解することは到底無理だった。
「彼と結婚しなさいよ、母さん、結婚しなさい」
「私が? なんて不吉な、人がなんと言うか」
「彼らは言いたいことをいうだけ。男の声の賑わいがない家と比べれば、彼らの言うことは些細なことよ」
「あなたたちより先に結婚するの? 無理よ」
「いちばん良いのは、母さんが私たちより先に結婚することじゃなくて? 殿方の足が私たちの家を覚えるようにね。そしたら、母さんの後に私たちが結婚するわ。あの人と結婚しなさい、母さん!」
そうして母は男と結婚した。人数が一人増えて、少し収入が増えた。そしてより大きな問題が起こった。
初夜は2人が同衾して終わった。それはよかった。しかし、2人は例え偶然だったにしても、近づこうとさえしなかった。というのも、3人の娘は寝ていた。しかし、その3人全員の気配が、2対の探索器のごとく、2人の間にある距離を寸分違わず測ろうと狙いを定めていた。それは目による探索器であり、耳による探索器であり、感覚による探索器でもある。娘たちは大きく、色々なことを知り悟っていた。部屋は起きている娘たちの存在によって、まるで昼間の陽光の中に移ったかのようだった。しかし、実際に日が昇れば、もはやそこに残るための言い分がない。娘たちは一人また一人とこっそり部屋から出て行き、日没頃まで戻ってこなかった。戻ってくるときには、躊躇い、恥ずかしがって、家に近づくまで、一歩足を出しては足を止めるというありさまだった。そのとき、男のゲラゲラと笑う声が、女のいちゃつく声に混じって聞こえた。娘たちは驚き、困惑し、家に急いだ。娘たちの母が笑ったことは疑いない。しかし、男に関しては、育ちが良く慎ましい話し方しか聞いたことがなかった。なのに、なんとその男が笑っていたのだ。母が娘たちを迎えると、母はまだ笑っていた。頭は覆われておらず、髪は湿っていて梳かれていた。依然母は笑っている。その母の顔を見て、瞬時に娘たちは悟った。かつて、明かりの灯らぬランプはむき出しで、その中に蜘蛛と数々の襞が巣を作っていた。しかし、突然、明かりがついた。ほら、それは娘らの前にある。電灯のごとく光っている。ほら、それはギラギラと輝く目だ。その目は娘らの目の前に現われ、その存在は明白だ。目は笑いの涙でかがやいていた。それは眼窩の底に隠れていたものだ。
沈黙は消えてしまった。完全に姿を消してしまった。夕飯の時も、夕食の前も、夕食の後も、次々と笑い話が飛び出した。会話や歌が尽きなかった。ウンム・クルスーム やアブドゥルワッハーブ を真似して歌う彼の声は美しかった。彼の声は大きかった。幸せのあまり声がかすれていたが、よく通った。
よくやったわ、母さん! 明日には笑いが男たちを引き寄せて、その男たちがまた男たちを引き寄せる餌になるわ。
そうよ、娘たち。明日には男たちがやってきて、婿たちが姿を現すわ。
しかし、実のところ、娘たちの関心を占めるようになったのは男たちや婿たちではなかった。それはあの青年だった。彼は盲目だった。しかしそれが何だというのか。人々の持つべき見識に関して私たちが盲目になることのなんと多いことだろう。彼らが盲目であるという、ただそれだけの理由で。この力強く、精力・健康・生気の漲る青年。それはかつての夫の病気や性的不能、そして時を経ずして訪れた老いを償ってあり余るものだった。
沈黙は消え、戻ってこなかった。生活の賑やかな音が戻った。夫は彼女の夫であり、合法な相手だった。神とその使徒のスンナに則った夫だ。何か恥じることがあるだろうか? 彼女のすることはすべて合法だ。もはや、ごまかしたり秘密を隠したりすることに注意を向けなかった。夜が来ても、夫婦と娘たちは集まって一緒に寝た。精神と肉体の手綱を解き放っていた。娘たちは四散し離れていたが、事を知り、理解して、声と吐息を震わせていた。娘たちは自分のベッドに釘付けになり、身体の動きや咳を抑え込んでいた。突然、複数の吐息が漏れ出ては、その息が他の息を押し黙らせるありさまだった。
女の昼間の仕事は金持ちの家で「洗濯」することだった。男の昼間の仕事は貧者の家でクルアーンを誦むことだった。はじめのうち、昼に帰宅することは男の習慣ではなかった。しかし、彼にとって夜が長くなり、夜更かしが長時間にわたるようになると、彼は昼に帰宅するようになった。そして一時間、彼は昨夜の苦労から身を休め、来るべき夜に備える。あるとき、二人が夜を満喫し、夜が二人を満喫した後、男が突然彼女に尋ねた。昼間のあれは何だったんだ。どうして今は堰を切ったようにいっぱいしゃべっているのに、昼間は完全に押し黙って口をきいてくれなかったんだ。どうしてその大切な指輪を今はつけているんだ。つまり、その結婚指輪は、結婚が男に課した指輪・婚資・結納金といった贈り物のすべてであった。それをどうして昼間はつけていなかったのか?
彼女は不安で立ち上がり声をあげて震えていたかもしれなかった。気が狂っていたかもしれなかった。誰かが彼を殺してもおかしくなかった。彼の言ったことにはたった一つの意味しかなかったのだ。その意味の何と奇妙でおぞましいことか。
しかし、喉を塞ぎ窒息させんばかりの苦悶がそれらすべてを抑え込んだ。それは同時に息をも詰まらせ、彼女は黙り込んでしまった。彼女は耳を、鼻に、目に、あらゆる感覚に変えて、注意深く耳を澄ませはじめた。第一の悩みはその行為者を知っていることだった。彼女はある理由からそれが真ん中の娘だということを確信していた。その娘の目には、もし銃で撃たれても打ち砕かれない大胆さが宿っていた。彼女は耳を澄ました。響きわたる3人の寝息は、深く、熱に冒されているかのように熱かった。はげしく、欲のままにうめき、繰り返し、途切れては、禁忌の夢がそれを中断した。乱れた息はやがて、乾いた大地の吐きだす灼熱のごとき、ヒューヒューという吐息に変わった。苦悩はより深くなり、さらに息を詰まらせた。彼女の聞く限り、それは飢えた女たちの吐息だ。いくら感覚を研ぎ澄ませても、熱を帯び正体を隠す生きた肉の塊を、他の塊と見分けることができなかった。すべての肉が飢えていた。すべての肉が叫びもだえていた。肉たちの喘ぎが息づいていた。吐息ではない。おそらく、それはSOSだ。それは期待だ。それの何と多いことだろう。
母は神が許した二つ目のことに夢中になり、一つ目のことなど忘れていた。娘たちのことを忘れていたのだ。忍耐は苦い果実になり、花婿という蜃気楼すらもはや現れなかった。突然、彼女は刺されたかのような感覚に陥った。ほら、まるで自分以外に聞こえぬ呼び声に、身をこわばらせながら目を醒ました者のようだ。娘たちは飢えている。この食べ物はまぎれもなく禁忌だ。しかし飢えは更なる禁忌だ。絶対に、それは飢えのように神の法に適わないものではない。彼女は飢えを知っている。飢えもまた彼女を知っていた。飢えは彼女の魂を干からびさせ、その骨を吸い尽くした。彼女は飢えを知っていた。飽き飽きしていた。飢えの味を忘れることはできなかった。
娘たちが空腹の間、彼女は娘たちに食べさせるために、口から食べ物を取り出して与えたのだった。彼女の関心事はたとえ自分が飢えても娘たちに食べさせることであった。自分は母親としてそうしたのだ。それを忘れたのか!?
男は執拗に答えさせようとした。喉を塞ぐ苦悶は沈黙に変わった。母親は口を閉ざした。この瞬間から沈黙が彼女のもとを離れることはなかった。
朝食の時、母がまったくそう予想したように、真ん中の娘は何も言わなかった。永遠に、彼女は口を閉ざした。
夕食の時が来て、青年は冗談を飛ばした。幸せに満ち、何も見えず、楽しくて仕方がない様子で。声の止む気配はない。男は歌っては笑った。だが、その笑いを共にしたのは、一番上の娘と一番下の娘だけだった。
忍耐は長引く。その苦い果実は病に変わり、誰も現れることがない。
ある日、一番上の娘は母の指に嵌められた指輪をじっと見つめると、その指輪が気に入ったと言った。母の心臓はドキドキと鳴った。娘が、一日それをつけてみてもいいかしらと言うと、鼓動は一層激しくなった。たった一日だけ、それだけよ。母は黙って指から指輪を取り、一番上の娘は黙ってそれを同じ指に嵌めた。
次の夕飯になると、一番上の娘は沈黙し、話すことを拒んだ。
盲人たる青年は声を張り上げ、歌っては笑った。笑いを共にしたのは一番下の娘だけだった。
しかし、一番下の娘も忍耐と苦悩と薄幸によって大人になっていった。彼女は指輪遊びの自分の役を乞いはじめ、無言でその役を得た。
ランプの側に指輪がある。沈黙が訪れ、耳が聾する。沈黙の中に、順番の回ってきた指が忍び込み、無言で指輪を嵌める。灯りは消され、闇が辺りを覆う。闇の中で、目が盲いる。
もはや騒ぎ、笑い、歌者は盲人たる青年だけだった。
欲望は青年の騒ぎ立てる声の後ろに身を隠していた。欲望は、今にも彼に、沈黙に反旗を翻させ、沈黙を粉々に破壊させようとしていた。
彼もまた知りたいのだ。確実なことを知りたいのだ。はじめのうち、「これは変化がないことを嫌う女の性というものだ」と自分に言い聞かせていた。彼女はある時、みずみずしく夜露のようにきらめいていた。別の時には疲れ切って池の水のように濁っていた。ある時にはバラの花びらの手触りのように柔らかかった。別の時にはサボテンのようにザラザラとしていた。
確かに指輪は常にあった。しかし、毎回それをつけている指は、まるで一本の不定の指であるかのようだった。彼はほとんど知りかけていた。彼女たちは明らかに知っていた。では、なぜ沈黙は語らないのか? 沈黙は声を発さないのか?
しかし、ある夕食の時、問いが彼を襲った。もし沈黙が破られたとしたら、もし話したなら?
この単なる自問が食事を喉に詰まらせた。
この瞬間から、彼は完全な沈黙という手段に訴え、その沈黙から立ち去ることを拒んだ。
むしろ、彼は一度でも忌み嫌われた行為を行ってしまうことで、沈黙を破ってしまうことを恐れるようになった。おそらく、一つの言葉が漏れ出ただけで、沈黙という建物はそれ故にことごとく崩壊する。もし沈黙という建物が崩壊したなら、なんという災いだろう。
他所から来た別の沈黙、あらゆるものはそこに逃げ込むようになった。
今度の故意なる沈黙、その原因は貧困でも醜さでも忍耐でも絶望でもない。
しかし、それはもっとも底知れぬ類の沈黙だった。というのも、それは合意を得た沈黙であり、どんな契約もなしに成立する、比類なき強さの契約な
のだ。
未亡人と3人の娘。
家とは一室である。
沈黙は新たになる。
盲目のクルアーン誦みがその沈黙を引き連れてきたのだった。その沈黙の中で、彼は確信しはじめていた。彼のパートナーは、ベッドの中ではいつでも、彼の妻であり、神の法に適した純粋無垢な相手であり、彼の指輪を嵌める者であった。振る舞いが子供っぽい時もあれば、年をとることもある。柔らかくなってはザラザラになり、細くなっては太くなる。これは彼女の問題であり、彼女一人の問題だ。いやむしろ、これは目の見える者達とその者達の責任の問題であり、彼らだけの問題だ。彼らは苦労もせずに確実なものを知ることができる。つまり、彼らには判断ができるのだ。そして、彼にできる精一杯のことは、疑うことだ。満足に物が見えない以上、彼の疑いが確信に転じることはできない。視力を奪われている限り、彼は確信を奪われたままだ。つまり彼は盲人であり、盲人に罪はないのだ。
しかし、もし、盲人に罪があるとしたら……?
翻訳:ريحان السوغامي
サポートで頂いたお金は中の人の書籍購入費になります。
