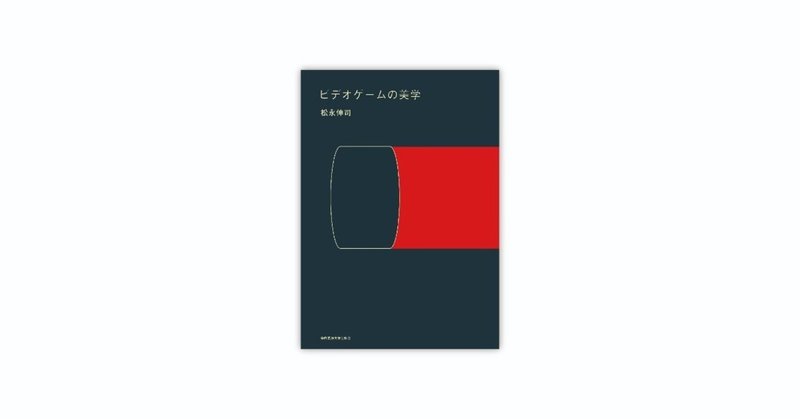
『ビデオゲームの美学』
読むように指定された本シリーズ第4弾です。
表紙のデザインが何を表しているのかわかりませんが、マットな黒地に彩度の高い赤、画像だとわかりにくいですが黄土色の線の縁取りと文字が合間って高級感を感じる装丁です。
【概要】
本書は、産業規模の拡大、技術の進歩とともに、文化的重要性が増しつつあるビデオゲームを1つの芸術形式として捉え、その諸特徴を芸術の哲学の観点から明らかにすることを試みた内容です。スーパーマリオブラザースやテトリス、ドラゴンクエストなど多くのビデオゲームの事例をあげながら、ビデオゲームを考察し、理論的枠組みを提示しています。
【書評】
本書は、過去の哲学者の遊びやフィクションの定義を取り入れたり、混同しないように、丁寧に定義した概念についての説明がされていたりしました。
その中で、ゲームの行為は「自己目的的行為」として定義していました。自己目的定義というのは、ゲームをすること自体がゲームをする目的であるということです。そして、ゲーム行為の内在的性質についての試論として、「美的行為」(ゲームの行為の振る舞いに対する感じ方)という概念を中心に展開していました。このような概念は本書に限られたものではなく、ビデオゲームに関わらずスポーツやボードゲームなどのゲーム一般を「行為の芸術」と捉えてはどうかという著者の理論的な意図のもとに導入されています。
人の活動は、およそ知覚や認知のように、世界から働きかけている側面があります。そのような経験をもたらすべく意図的に作られた人工物が芸術作品だという考え方があってもおかしくはないでしょう。しかし、意図や行為といった世界に働きかける側面にも美的な価値はあり、そのような行為を意図的に作られた人工物であるゲーム行為はそこに含まれているのではないでしょうか。
行為の芸術として古来からゲームは存在していましたが、そこで生み出される行為が多様化し洗礼されたのは、ゲームがコンピューターテクノロジーの進歩と結びついたからです。ビデオゲームは行為の可能性を決定的に広めてくれた代物です。そこから、ゲーム行為の質とは何か、遊ぶことの価値についてをさらに深く探る上で、本書で語られている概念や哲学が役に立つのではないでしょうか。
ビデオゲームの美学
著/松永 伸司
