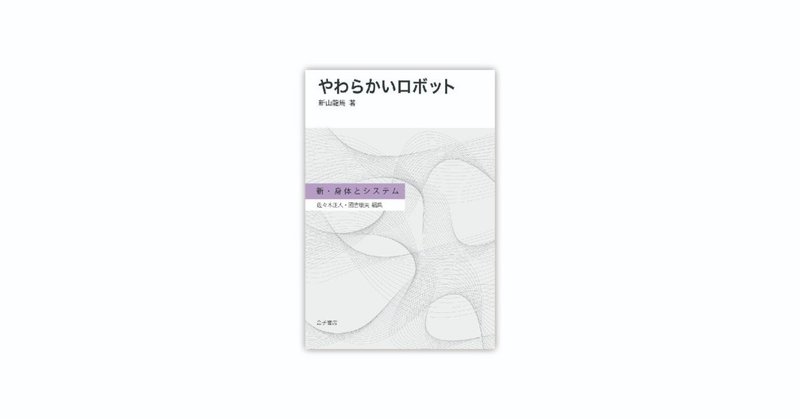
『やわらかいロボット』
本を読むだけでは考えをまとめきれずに内容を忘れてしまうことが多いため、面白いと思った本は書評及びそこから得られたこと書いていこうと思います。
今回は読むように指定された本シリーズ第1弾です。
【概要】
本書はソフトロボティクスの歴史、素材、参考にされた生物・身体などについて、これまでの研究結果と照らし合わせてわかりやすく書かれた本です。
これまでのロボットと言われて想像するものは、硬い素材でできた機械でした。生物とはかけ離れた存在ですが、そこに見た目や触感、動きに「やわらかさ」を導入することによってロボットに生き物らしさが意識され、新しい身体観が生まれました。このことによって、「工学系」「理系」に限らずロボットを研究する視野が広がります。
【書評】
やわらかいロボットを作るにあたって、読む前はやわらかいロボットのための新しい素材や機構についての話がメインになると考えていました。しかし、実際に読んでみると人間の身体の構造、生き物(特に水中で暮らす魚や軟体生物)からいかにリファレンスを得ようとしているかについて多くのことが書かれていました。
例えばタコの触手や象の鼻、舌など、関節や骨がないけれど巧みに動くことのできてやわらかさを併せ持った部分の筋肉の作りや内部構造をロボットに生かそうと試みています。
今現在、食べ物を押しつぶしたり発音を上手にだす舌の研究成果は出ているそうですが自由自在に伸縮してマルチなことに使える舌はまだまだ道のりが長そうです。
そもそもなぜやわらかいロボットを作る必要があるのか。本書を読むにあたって思ったことは、「ロボットはかたい」という固定概念を壊し、やわらかさを取り入れることによって、かたいロボットではできなかった動き、活躍を手に入れるためだということです。また、純粋に生き物のように動くロボットを作ることへの挑戦と憧れを感じました。
本書ではやわらかいロボットという存在が当たり前になり、ソフトロボットという言葉がなくなることがゴールであることを記していました。
やわらかい素材で作られた、生き物みたいにしなやかに動くロボットが人間のすぐ隣で稼働する未来が実現されるかもしれません。
今現在、人間がsiriやGoogle Homeに話しかけることや、駅の改札機のように日常の行為にすっかりロボットが馴染んでいます。しかし、ここにやわらかいロボットが登場することによって人間がロボットに抱く感情が変わっていくのではないかと考えています。
生き物は舌やペニス、自分の手の平などやわらかい敏感な部分で身体接触をすることで親密なコミュニケーションをとります。今まで触れられることを目的としていなかった多くのロボットにやわらかさが加わり、生き物のような振る舞いをすればするほど、人間はロボットと触れ合いたいという感情を抱くのではないでしょうか。
やわらかいロボット (新・身体とシステム)
著/新山龍馬 編集/佐々木正人・國吉康夫
