
【宿題帳(自習用)】研究と教育(実践)

アメリカの文明史家のロバート・スクラーは、映画の聖地ハリウッドを両者の闘争の場所と評して「創造のエリート」がいて「管理のエリート」がいるから映画が栄えたと語った。
管理のエリートは、経費を削り、少しでも収益を高めようとする。
創造のエリートは、おのが感性と美意識の忠実な僕(しもべ)であろうとする。
そのせめぎ合いが映画を育ててきたという。
最近、大学でも教育と研究を分けるべきだという議論が進んでいる。
一面、正しいのだけれど、それではあまりにも寂しいのではないかと思う。
こうした論調に乗って「うちは教育機関だから研究などしなくてもいい」と校長がいう学校もあるという。
教育と研究、研究と教育というのは物事の裏表であって、切り取ればどちらもついてくるものである。
誰かに伝えることのない研究は自閉的で、広がりがない。
研究の裏打ちなしに、ただ教材研究だけをして講義ができると思ったら、それは教育の荒廃を招くだけである。
教師がゆとりを失ったら、学生はもっとゆとりを失ってしまう。
ゆとりを失うと、社会に歪みや軋轢が生まれてくる。
そして、崩壊していく・・・・・・
大学などは独立行政法人になったが、大学が金儲けばかり考えていていいのだろうか?
学者を大事にしない国は滅ぶ、と孔子は言ったのだが、『論語』なんかは論外なのだろう。
自動車の運転でもまっすぐ前を向いている人が優良ドライバーなのではない。
適当に脇見をしながら、全体像を確かめ、時には後ろを振り返りながら前進するものである。
資格や免許ばかりを目指すのは専門学校でいい。
それらも含めてもっと先を見つめる教育が求められているのではないだろうか?
では、科学とは、研究とは、そして、研究者とは、何だろうか?
科学の神髄である独創性とは、どのようにして生まれるのだろうか。
科学者という仕事を通して、科学研究の本質に触れることは、「人間の知」への理解を深めることにつながるという。
「科学者という仕事―独創性はどのように生まれるか」(中公新書)酒井邦嘉(著)

本書は、科学技術創造立国が叫ばれる中で、若者の理科離れが懸念される現在、さまざまな形で科学技術にかかわっている人や、科学に関心を持っている人に、おすすめの1冊であると共に、科学者とはなんぞや、科学者とはどうあるべきか、ということが簡潔にしかし内容濃く書かれている本である。
しかし、何よりも、現在研究を行っている者、とくに若手の研究者にとって、自らの今を問い直し、今後を考える上で、必読の書と言えよう。
以下の通り、全7章からなり、各章は、アインシュタインほか、科学を築いてきた人たちの言葉から始まっており、「創造から模倣へ」「研究の倫理」など、各章に表題を付けた上で、ある科学者1人の代表的な言葉と、その人物の紹介と、著者の考えで構成されている。
アインシュタインからニュートン、ダーウィン、朝永振一郎や寺田寅彦など、その研究者のことを知らなくとも、初めに非常に簡潔にそしてエッセンスの詰まった紹介があるため、誰でも読むことができる。
例えば、ニュートンの業績を紹介しそこから著者は、「すぐれた創造力も模倣なくしては成り立たない。
しかし、模倣だけでは決してサイエンスにならない。
サイエンスは新しい知の創造に他ならないからである。」というように書いている。
第1章 科学研究のフィロソフィー―知るより分かる:
研究者の仕事は、人のやらないことをやり、人の考えないことを考える、ということである。
そして実際の科学とは、事実の足りないところを「科学的仮説」で補いながら作り上げた構造物であり、非常に人間的なものである。
<参考図書>
「思考の体系学 分類と系統から見たダイアグラム論」三中信宏(著)

「統計思考の世界 曼荼羅で読み解くデータ解析の基礎」三中信宏(著)

「進化の技法――転用と盗用と争いの40億年」ニール・シュービン(著)黒川耕大(訳)
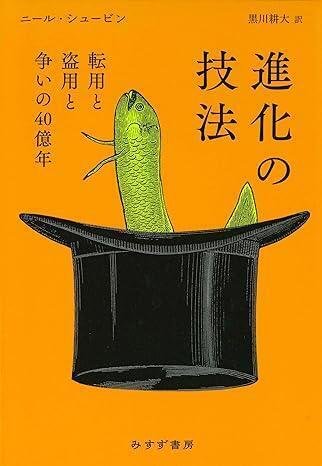
「解像度を上げる――曖昧な思考を明晰にする「深さ・広さ・構造・時間」の4視点と行動法」馬田隆明(著)

「認識とパタン」(岩波新書)渡辺慧(著)

第2章 模倣から創造へ―科学に王道なし:
研究の方法、そして、研究者としての成長を説く。
研究者としての第一歩は、「どのように研究するか」であり、幅広く科学の知識を吸収し、研究の仕方や考え方を確実に模倣した上で、創造的な研究に進む。
<参考図書>
「問いの立て方」(ちくま新書)宮野公樹(著)

「問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション」安斎勇樹/塩瀬隆之(著)

「問いこそが答えだ! 正しく問う力が仕事と人生の視界を開く」ハル・グレガーセン(著)黒輪篤嗣(訳)

第3章 研究者のフィロソフィー―いかに「個」を磨くか:
研究者になる上でもっとも大切なことは、「個」に徹することであり、革新的な発明・発見は個人的になされることが多い。
研究者は、自己と向き合い、自分の天分を冷徹に見定めなければならない。
「研究者は・・・人生のレースは才能で勝負しているように見えるが、実は最後は才能のない部分をいかにカバーできるかが肝心で、本当は「ない才能で勝負」している」という説明は、現代の研究者という職業の本質を言い得ているようで、面白い。
<参考図書>
「暇と退屈の倫理学」(新潮文庫)國分功一郎(著)

「はじめて考えるときのように 「わかる」ための哲学的道案内」(PHP文庫)野矢茂樹(著)植田真(イラスト)

第4章 研究のセンス―不思議への挑戦:
意外性のないところに発見的な価値はない。
インパクトのある意外性の体験、現象の繰り返しの観察を通じ、思いつきから科学的な仮説へと続く。
研究者にとってとくに大切なのは考えることであり、そのためには、常に新しいアイデアを渇望するようなハングリー精神、精神的な飢餓感が必要である。
<参考図書>
「THINK BIGGER 「最高の発想」を生む方法 コロンビア大学ビジネススクール特別講義」シーナ・アイエンガー(著)櫻井祐子(訳)

「スタンフォードの人気教授が教える 「使える」アイデアを「無限に」生み出す方法」ジェレミー・アトリー/ペリー・クレバーン(著)小金輝彦(訳)

「戦略の要諦」リチャード・P・ルメルト(著)村井章子(訳)

第5章 発表のセンス―伝える力:
科学研究は “Publish or perish.” と言われ、論文発表をしなければ消滅するしかない。
研究そのものは自己本位であるのに対し、研究発表のフィロソフィーは他人本位に徹することであり、人に伝える力を磨くことが研究発表の基本的センスである。
論文作成は、査読者による批評に意味があり、一つの論文が完成するまでには、山あり谷ありのドラマを味わうことになる。
<参考図書>
「読む・打つ・書く 読書・書評・執筆をめぐる理系研究者の日々」三中信宏(著)
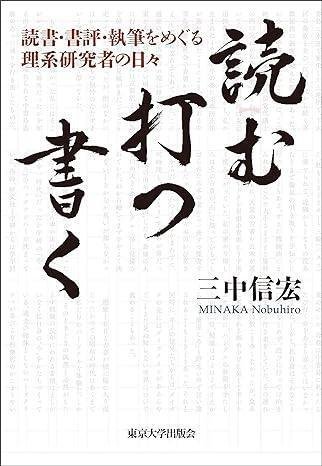
「基礎からわかる 論文の書き方」(講談社現代新書)小熊英二(著)

「できる研究者の論文生産術 どうすれば「たくさん」書けるのか」(KS科学一般書)ポール.J・シルヴィア(著)高橋さきの(訳)

「「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全」山口拓朗(著)

第6章 研究の倫理―フェアプレーとは:
研究の世界も一般の人間社会と何ら違いはなく、利益、名声、ライバル心などの要素が研究者間の競争の火種になりうる。
科学が社会的な信頼を維持できるかどうかは、基本的に研究者一人一人の良心にかかっている。
<参考図書>
「<責任>の生成ー中動態と当事者研究」國分功一郎/熊谷晋一郎(著)

第7章 研究と教育のディレンマ―研究者を育む:
自律した新進の研究者を育てることはとても難しい課題である。
人を育てるのはあくまでも人である。
<参考図書>
「研究者としてうまくやっていくには 組織の力を研究に活かす」(ブルーバックス)長谷川修司(著)

「文系研究者になる 「研究する人生」を歩むためのガイドブック」石黒圭(著)

「研究の育て方 ゴールとプロセスの「見える化」」近藤克則(著)

第8章 科学者の社会貢献―進歩を支える人達:
科学の倫理は人間の文化や社会・宗教観、イデオロギーによって左右される。
科学における革新的な発見や仮説は、一般の社会や思想、宗教観にも多大な影響を与えてきた。
市民も科学の進歩を支える人達であり、その意味で研究者と市民の対話がとても大切になっている。
<参考図書>
「技術倫理〈1〉」C. ウィットベック(著)札野順/飯野弘之(訳)

「未来技術の倫理 人工知能・ロボット・サイボーグ」河島茂生(著)

「はじめての工学倫理」齊藤了文/坂下浩司(編)

本書に紹介されている科学者の中でも、私が印象的だったのは、マリー・キュリー(キュリー夫人)だ。
「放射能」の研究に全力を捧げ、被爆しながら実験を続けたという。
アインシュタインは、彼女のことを指して、「マリー・キュリーは、すべての著名人の中で、自身が得た名声によって堕落しなかった唯一の人である」と言ったそうだ。
科学者たちが繰り広げる壮大なドラマに心躍らせながら、興味深く読み進めた。
また、本論よりも、余談として語られる偉人のエピソードの方が、強く印象に残ることがある。
研究発表の心構えについて触れた章が、個人的に参考になった。
例えば、公の場で何かを話すとき、何を話すかは大抵、あらかじめ決まっている。
問題は、どう話すかなのだけれど、前提として、どこから話すか、の問題があるよな、と思っていた。
あまりに基礎的なレベルから話すと、専門家の聴衆は退屈だろうし、逆に、専門外の聴衆はついていけなくなってしまう。
話すものはどのような態度でのぞめばいいのか。
この本では、発表のコツとして、
1に正しく、
2に分かりやすく、
3に他人本位で話せ、
とある。
3つ目に関連して、M・デルブリュックによる良い研究発表の条件が紹介されていた。
「分子生物学の誕生―マックス・デルブリュックの生涯」エルンスト・ペーター フィッシャー/キャロル リプソン(著)石館三枝子/石館康平(訳)
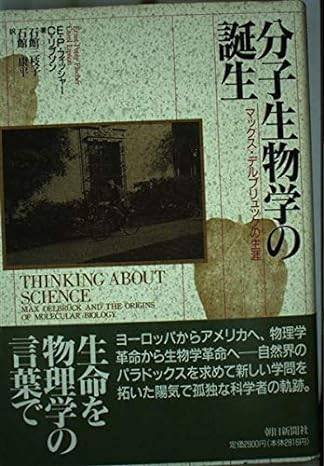
1 聴衆は完全に無知であると思え
2 聴衆は高度な知性をもつと考えよ
そして、その改良版の「堀田の教え」も大切という。
1 聴衆は完全に無知であると思え
2 聴衆の知性は千差万別であると思え
3 聴衆がおのおの自身より一段上のレベルまで理解できるようにせよ
3について解説を引用。
「よく考えてみると、聴衆の中に知性の低い人がいるかもしれないなどと心配する前に、話をする自分より賢く知性の高い人がいることが予想されるのである。
その人も講演に触発されて、話をする人よりもさらに高いレベルに達するようにすべきなのである。
それでこそ話をする意味があるのである。あとでその人からのフィードバックを受けることによって講演をした自分も新しい理解に到達できれば、真のコミュニケーションが成立したことになるのである。」
基本からわかりやすくは当然として、自分よりも上の人にも、新しい発想の材料を提供できるようにせよ、とのこと。
なるほどねと深く納得。
そう言えば、研究者向けの”人生ゲーム”を人工知能学会が開発していた。
ゲームをしながら研究者の人生をシミュレーションでき、資金やポストの獲得競争のような要素がある。
この本についている帯が面白い。
問題1)何かおもしろい問題を考えよ。
問題2)問題1で作った問題に答えよ。
これが解ければ、あなたも研究者
一度でも、テストを作った経験がある方なら実感値があると思うが、問題作成は、意外に大変である。
知識の有無を確かめる形式のテストであれば、それほど苦労はないかもしれないが、「面白い問題」となると、多方面からの熟考が必要となる。
研究をすること(あるいは論文を書くということ)はまさしくこれである。
「「自己本位」の重要性に気づくのに精神的な成熟を必要とし、しかもそこに到達する道が険しいのは、自己とはじめて直接向き合う時に誰もが味わうであろう、「恐怖感」のためではないだろうか。
これは、誰も他に助けてくれない「孤独」という境遇への不安であり、自分の天分を冷徹に見定めなければならないことへの恐れであり、そして「自己」という、いわば底の見えない井戸をのぞき込むような行為への本能的な忌避感である。
自分の強さを過信する人は自分の弱さを知ろうとせず、自己に向き合う時に目をつぶるしかなくなる。
他人に自分を認めてもらいたいという気持ちは自然な願望である。
しかし、他人の評価という極めてあやふやな基準のもとに自分の評価をゆだねて良いものだろうか。
自分に対する家族からの評価は甘くなり、ライヴァルからの評価は厳しくなりがちだ。
教師にも、ほめて育てるタイプと叱咤激励するタイプとの両方がある。
だから、他人の評価に一喜一憂してもしかたがない。
自分で本当に良いと思える仕事を残すことが大切で、評価は二の次なのだ。
冷静に突き詰めて考えれば、自分を正当に評価できるのは自分しかいないはずである。
その明白な事実に目をそらさずに向き合うことができるかどうか、自己本位を貫くことは決してやさしいことではない。」(80-81ページ)
ちょっと長い引用になってしまった。
研究者というのは孤独・孤高である、という話の中で語られたものであるが、そういった文脈なしでもドキッとするような見解ではないだろうか。
研究というのは、偶然やまぐれのような事態(その多くは失敗と思われた事態)から思いがけない大発見につながるということがある。
そういうのを”セレンディピティ”(serendipity)という。
しかし、そうした偶然はただの偶然ではない、と数年前にノーベル賞を受賞した田中耕一氏の次の言葉を引いている。
「このように偶然を積み重ねて大きな発見をすることができたのは、私が毎日こつこつと実験を積み重ねてきたから、いつもとちがう現象が起きたときに、それを見過ごすことなしに、「あ!これは」と、ピンとくるものを感じることができたからだともいえます。」
日頃の積み重ねが大事ということである。
研究とともに、教育に関しても、示唆的な話がある。
「馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を飲ませることはできない」というたとえを示した上で、次のようなことを述べている。
「すぐれた科学の先生は、科学の楽しさと苦しさの両方を知っている。
よく練られた科学教材は、科学の楽しさを感覚的に伝えるのには成功するが、その楽しみがごく短期的なものに終わってしまったり、すぐに結果が出ないようなテーマを避けるようになってしまっては残念だ。
学生を科学の水辺へ誘って、科学を行うための長期的な動機づけを与えるためには、科学の苦しさからいかに楽しさを見つけていくかをうまく伝える必要がある。
また、授業を分かりやすくするように努力するのは大切だが、すべてを余さず説明すれば良いというわけではない。
教育のサービス過剰もまた、「過ぎたるは及ばざるがごとし」なのである。
高校生の時、物理の最初の授業で衝撃を受けたことを私はよく覚えている。
その時先生が、「物理は自分で考えないと分からないから、できるだけ授業では説明しないようにします」とおっしゃった。
うまく水辺まで誘ったら、最後に水を飲む自由や楽しみを残しておくことが大切なのである。
科学教育は、自分で考えるチャンスを与えるものでなくてはならない。」(224ページ)
それが、そんなに簡単にはできないんだっ!と思われる方もいると思うが、その環境におかれているのなら、心の中で叫んでもみてもしかたがないので、今後も努力を続けるしかない。
以前、不正や論文捏造事件が相次いでおり、研究者コミュニティ全体の品性とモラルが問われている。
基本的に、研究者一般については、性悪説的な観点から見ている。
どの世界にも「権力好き」はいるので、権力=お金である以上、いつでもこうした図式は表面化する。
天才軍師・太公望も著書とされる本で人間観察の方法を述べているが、そのうちの一つに、「財産を与えてみて、その振る舞いを見よ」、と看破している。
研究費の不正などは、下の下の下ということになるのだろう。
思うに、研究者(人間一般?)には、2通りしかない。
名前を歴史に刻むことを目指す人。
発明、発見、あるいは論文や著書などを出版し、半永久的に自分の存在、業績を人類史に残そうとする(あるいは結果的に残る、残せる)人だ。
2番目は、権力構造に自らを嵌め込んでいく人である。
経済的にも、権力的地位にも、敢えて競争も辞さない人である。
後者は、ビジネス界にも多いが、前者は、実よりも名を文字通りとる人である。
所詮、死ぬまでに、お金を溜め込んだ所で、死んだら終わりである。
そもそも、必要以上に溜め込む意味がない。
それよりも、名前を人類史に刻み込んでいくことの方が、端的に言って、遥かに価値があると私は思っている。
例えば、受験競争・メリトクラシーの大競争を勝ち残った所で、後者に流れていけば、ひたすら働かされて終わりだ。
金がなければ人間らしく死ねないというが、ひたすら働かされていることが、人間らしい生き方であったと胸を張って言えるのか?
死んだ後に、戸籍から斜線を引かれ、存在していた事実をディレートされて終わりである。
財産があったとしても、課税されて大半は納税に終わる。
何も残らない。
どうせ人間は、どんな生き方をしようが、最後は死ぬ。
自分の評価は、自分で決めるのであって、他人が決めるのではない。
地位やお金ではない。
よほど、自分の業績を、自ら人類史に刻む行為の方が、研究者らしくて良い。
研究者は、そもそも、後者になるのが厭だが、かといって前者をひたすら目指すというわけでもないという人は多いのだろう。
そのため、科学技術分野では、皆で尻を叩くようにして、競争競争と研究費などを獲得させたり、知財を発掘させたりと手練手管を尽くす。
ただ、研究費は、ほぼ皆無でも、業績をあげてきた人はいた。
研究費がないと研究が出来ないというのは、ありえない。
無くても出来る研究、世界的業績をあげられるテーマは幾らでもある。
研究テーマの選び方自体も、既に、前者志向か、後者志向かが見え隠れすることもある。
自ら望んで(周囲や上司から実力を認められるなどして引き上げられるのではなく)、必要以上に、権力的地位に登る・近づきたがる人、人間関係の中核に座りたがる人は、まず、後者である。
研究者や技術者が、人間関係にはしったら、研究者や技術者として終わっていると、陰口を叩かれるのと、根は一緒なのだろう。
そういう人は、結構、周囲に散見するが、適度に距離を保っておかないと、こういう時に巻き添えを食うことだろう。
天才軍師・張良や、太公望、孔明の言動が、良い教訓になっている、今日この頃である。
それと、”知”と”分けること”が大切である。
”学び”の一歩は知ること。
”科学”の一歩は分けること(となぜを問うこと)。
”自立”の一歩は生きること。
「分ける」というのは、科学的認識(概念を得るとか定義するとか)にとって大事である。
本書に、次のような叙述がある。
「科学者をめざすためには、まず科学(サイエンス)が何であるかを正しく知る必要がある。
サイエンス(science)の語源はラテン語で「知識・原理(scientia)」で、「分ける(scindere)」ことに関係している。
日本語でも、「分かる」という言葉が「分ける」や「分かつ」と関係しているのは興味深い。
科学で「分かる」と言う場合、確かに対象となる自然現象を分けながら理解しているつまり、「個々までは分かる、ここから分からない」という線を引き、少しずつ分かる部分を増やしていくのが科学研究だと言える。」(18ページ)
ということで、分けることについて考えてみると、人類の知は、”分ける”ことで発展してきた。
そして、分けると同時に、そのことによって、世の中のすべてを知り尽くしたいという欲求の強さを感じる。
とはいえ、最初から現代のような知の到達点にはない。
その発展の歴史は、知の発展や歴史や文化の発展と大いに関係がある。
アリストテレスの動物分類も、(その下位分類は現代にも通ずる分類になっている面もあるが)もっとも大きな分類は、「有血動物」と「無血動物」の二種類になっている。
実際に、そこに存在する動物や植物の分類(博物学)から、人間が考えたりした抽象的な”概念”なども分類されるようになるにいたり、”百科事典”が編纂されるようになっていく。
それも、最初は、”天・地・人”などが基本になり、その背景に、宗教や社会制度(たとえば封建制)などが大きく影響を与えていることもよく分かる。
しかし、その膨大な知をまとめ分類する作業は、気の遠くなるようなものであったであろうし、ものによっては、何百巻にも及ぶものになっている。
その知の営みには恐れ入るばかりである。
飽くなき知への興味がなせる業とはいえ、すごい。
感じるのは、分類とは、一つの世界観であるということである。
プリニウスの『博物誌』も、『百科全書』も、『四庫全書』も、それぞれ一つの小宇宙をつくっていた。
それらは、自分だけの宇宙をつくろうという壮大な試みだったのである。
しかし、現代は、こうした試みが、困難な時代であると思う。
現在の知の状況はといえば、ますます学問は細分化しており、ルネサンス人のような万能人は生まれにくくなっている。
インターネットは、情報の量において、おそるべき勢いで成長している。
ネット世界では、調べものをするのに分類など必要としない。
検索エンジンで、すぐさま必要な情報源にアクセスすることができるからだ。
はたして、新しい「知」の体系を構築することができるのか。
それが、私たち一人ひとりに与えられた課題だろう。
私たちは、日々、雑学的な知識にさらされている。
だが、たとえ雑学であったとしても、それを分類し、体系立てるひとつの「知」の宇宙ができることを、百科事典の歴史で見てきた。
大切なのは、いかに独自の分類法をつくるかということだ。
もうひとつ気づいたのは、分類が、勉強法に関係しているということである。
菅原道真や『廣文庫』の物集高見のように、文献を分類整理してカード化することによって、偉大な成果を残した人たちがいる。
これは、現代でも学習するときのヒントとなるだろう。
分類は、一種の記憶術でもある。
だから、一見、難解な学問でも、分類の手法によっては、単純化してとらえることができる。
そのような工夫は可能なはずだ。
効率的な学習法の一つとして、分類術が見直されてもいいのではないだろうか。
要は、”知る”ために”分ける”ということが大事だということである。
【関連記事】
【雑考】垂直思考と水平思考
https://note.com/bax36410/n/nc041319885eb
【雑考】対位法的思考
https://note.com/bax36410/n/nef8c398b72cb
【雑考】複雑系思考法
https://note.com/bax36410/n/neaab25206650
系統樹思考はアブダクションとしての推論である
https://note.com/bax36410/n/n13a9cf9a3e9e
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
https://note.com/bax36410/n/nad27a9739ea4
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
