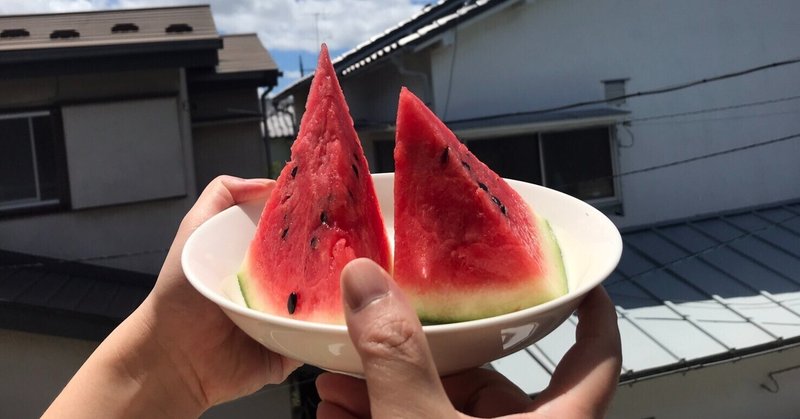
Like a hungry wolf
気候変動により、五臓六腑に染み入るような暑さにみまわれる日も多くなってきた。
『北風と太陽』ではないけれど、寒さは服の足し算で補えるが、暑さの引き算には限界がある。公的空間で全裸になるわけにはいかないし、皮膚を脱ぐわけにもいかない。
だけどどういうわけか、ここ数年、猛暑でも(いや、猛暑の時にこそ)黒いアームカバーをして外出している妙齢の女性を多く見かけるようになった。
あれは何なのか。
ぼく自身、真冬にアイスを食べるのが好きなタイプなので、真夏にダッフルコートを着て歩いていても全く個人の自由だとは思うのだけども、通常の身体感覚からすると、暑い日には薄着のほうが過ごしいいに決まっているし、この歳まで生きてきて、夏にダッフルコートを着ている人間には自分以外(『愚者の石』という映画の追加撮影で夏にコートを着てそぞろ歩いた)お目にかかったことがないわけだから、冗談や思い付きで実行するには無理がある部類の自由なのだろうと推察できる。
だけども、近年では、アームカバーの女性には、結構な頻度ですれ違うのだ。
暑くないのだろうか。
聞くところによると、あれは「UV対策」、つまり紫外線防止のためにあるらしいのだが、その定義でいくと、子連れのお母さんは子どもにも着せてるはずなので、いまいち合点がいかない。
子どもは皮膚がんになってもいいのだろうか。
もうひとつ考えられるのは、美容である。
「美白」を保持するための絶えまなき努力。その一部がアームカバーとして可視化されたのではないか。
己がファッション感覚や生理感覚を鈍磨させながら、過酷な夏をさらに過酷に過ごしている女性達の「美白」への熱情。
誠に不遜極まりない事ではあるが、ぼくはそれを想像する時、何かしら狂信的なものを感じ取ってしまい、夏の暑さも忘れるほどのうすら寒さに襲われるのだった。
同じような戦慄を、過去に一度だけ経験したことがある。
大学を卒業して暫くは、バイトを掛け持ちしながら自宅で絵を描いていたのだけど、朝方の4時から午前9時頃までの間は、ボクシングジムの裏で大型犬の世話をしていた。
そこで、ごくたまに、減量中のボクサーがミット打ちをしているところに出くわすのだが、明朝の薄暗がりに鈍色の瞳を爛々と輝かせ、やみらみっちゃにサンドバックを殴りつけているボクサーは、月並みな比喩だが「飢えたオオカミのような」気配を漂わせていた。
自身の拳以外頼るものもない彼らは、好きな時間に好きなものを食べ、誰かと拳を交えるでもなく、大型犬に餌をやり、散歩に連れていき、そこそこのサラリーを貰いに来るバイトをどのように見ていたのだろうか。
同じ時間を、只管己が能力値を上げることに費やしていた彼らは。
無論、皆自分の意志でそうしているだけなので、不平などないはずだが、過酷なトレーニングによる完璧主義は、凡庸に生きるぼくに複数の怠惰の兆しを認めていてもおかしくはなかった。
とはいえ、当時のぼくはボヘミアンよろしく、生き、そして誰の眼にも触れることのない絵を描くだけの向こう見ずな生活を送っていたわけだから、獰猛なエネルギーを内包した眼でもって世の中を睨みつける他ない彼らを、ある種の親近感を抱きながら、密かに崇敬していたのも詮無い事であった。
その後の人生において、彼らほどストイックだった人間を目の当たりにしたことはなかったし、映画やテレビでも、あの明朝のジムに瀰漫していた殺気のようなものを再現したものは殆ど見かけなかったが、今でもたまにボクシングの試合を観たりすると、あの薄暗がりの「飢えたオオカミのような」気配を思い出し、
「オレハ全然変ワッテナイヨ。目ノ前ノ敵ヲ倒スノデハナク、自分自身ニ打チ勝ツタメニ鍛エ続ケテキタヨ。オ前ハ何ヲシテイル?」
と、鈍色の眼で睨みつけられているような錯覚に陥ったりする。
猛暑の底で、漆黒のアームカバーを装着して外出している妙齢の女性陣を見るにつけ、ぼくは、あの時のボクサー連中が醸し出していた不穏な空気を想起してしまう。
伸縮自在な鎖帷子で、己が「美白」を追求するストイック至極な21世紀の「くノ一」。
斯様な日々の努力でもって獲得された「美白」を垣間見たならば、絶対に褒め讃えよ。褒め讃えなければ殺すぞというような、「飢えたオオカミ」の気配。
それでいて、何故かボクサーの時のようには、素直に崇敬できていない自分。
シミ雀斑のある肌は汚くて価値がなく、純白の肌こそが美しくて守る価値があるなんて、そんな単純な美意識で人間が幸福になり得るはずもなく、経年劣化が怖いというなら、いずれやってくる死をどう受け入れていくつもりなのだろうと他人事ながら心配になってくる。
少なくとも、ぼくはそれを、ボクシングの試合ほどには求めていないのだ。
だが、こんなことは本人には口が裂けてもいえない。
何故かなら、彼女らは、Like a hungry wolf……
面白がってこんな記事を書いているぼくも、ある意味では相当危険なリングに踏み込んでいるともいえる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
