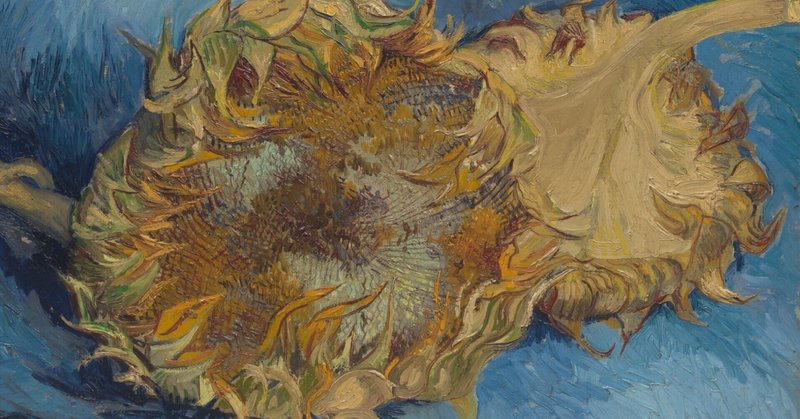
日本語教育能力検定試験の合格体験記
こんにちは。Katsuyaです。
今回は私が実際にやった日本語教育能力検定試験の勉強方法をご紹介しようと思います。
私は2019年に初受験し、不合格。勉強方法を見直して2020年に合格しました。
面倒臭いので結論から行きましょう。
テキスト3割、過去問7割です。(検定試験の全勉強時間を10とした場合)
テキストさらっと、過去問本気!!!!!!です。
もし今このnoteを見てくださっている方で試験に落ちてしまった方、過去問の勉強割合はどのくらいですか?
私は1回目の受験ではだいたいテキスト7割、過去問3割でした。落ちました。
2回目の試験では過去問の大切さに気づき、合格できました。
色々なところで過去問は大切と書いてありますが、私も具体的にどのくらいやればいいのかわからなかったので、私は勉強時間の割合で考えたほうがいいと思います。
スケジュール感としては、
年末・・・初受験の不合格通知が届いて悲しむ
3月〜6月・・・テキスト2〜3週
7月〜10月(試験前日まで)・・・ひたすら過去問を繰り返し解く
12月・・・念願の合格通知!
テキストは翔泳社の『日本語教育能力検定試験完全攻略ガイド』、通称赤い本です。
過去問は公式の過去問を5年分集めてコピーして4周くらいしました。
特に夏に過去問を解き始めてからはかなり本気で勉強しました。
夏以降はほとんどテキストメインで勉強することはなく、過去問でわからないところがあったらテキストを参照するような形で使っていました。
テキストは膨大なので重要な部分だけ勉強するのが得策です。テキストの重要な部分を教えてくれるのが「過去問」だと思います。
過去問の勉強法としては、紙ベースで勉強する人はコピー、タブレットで勉強する人はスキャンアプリなどを使ってPDF化しましょう。
例えば過去問を5年分集めたとしたら、一番最近の過去問から解いていきます。
私がやっていたのは忘却曲線を目安に「1歩進んで1歩下がる方式」で解き進めて行きました。
例えば
1日目 2020年度過去問
2日目 2019年度過去問
3日目 2020年度過去問(2回目)
4日目 2018年度過去問
5日目 2019年度過去問(2回目)
6日目 2017年度過去問
7日目 2018年度過去問(2回目)
8日目 2016年度過去問
9日目 2017年度過去問(2回目)
︙
といった感じです。途中で3回目も足してもいいと思います。コツは「答えを忘れた頃に解き直す」です。
答えを覚えているうちに解き直してもあまり意味がありませんから。
そうして忘れたころに解き直しても8割以上取れるようになったら本番でも戦える知識がついていると思います。私は4周くらいかかった気がします。
それを試験日前日までひたすら繰り返します。
本番当日は自分の苦手分野や暗記しておくと必ず点数に結びつくものを復習しました。
個人的には人の名前を覚えるのが苦手なので日本語教育史や試験Ⅱで必ず役に立つ音声記号あたりを復習しました。
そして本番。試験からの解放をブーストに頑張るしかありません。
ちなみに誰でも試験で得意な分野、苦手な分野があると思いますが、私は試験Ⅱの音声が得意で、人名の暗記と小論文が苦手でした。
小論文は勉強する気にならず、模範解答を眺めるくらいしかしていなかったので点数は高くなかったと思います。
ただ試験Ⅱが奇跡的に1問しか間違えなかったので救われた感じでした。。。
最後まで読んでくださった方に私の不合格時と合格時の点数を赤裸々に公開します。この記事を参考にするかはみなさん次第です。
【2019年試験結果(不合格)】
試験Ⅰ 69/100
試験Ⅱ 29/40
試験Ⅲ 52/100(記述込)
計 150/240(記述込)
【2020年試験結果(合格)】
試験Ⅰ 74/100
試験Ⅱ 39/40
試験Ⅲ 58/80(記述なし)
計 171/220(記述なし)
※自己採点です
以上、少しでもこれから受験される方の参考になればと思います。
他に質問などありましたらコメントください。
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
