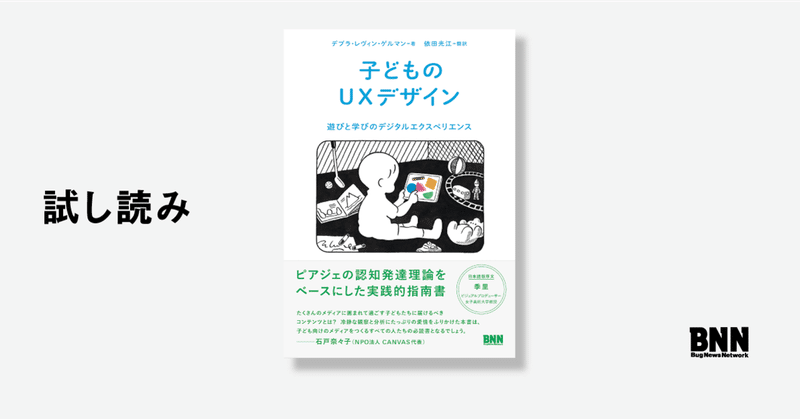
試し読み:『子どものUXデザイン』
少し古い本ですが、2015年11月に刊行した『子どものUXデザイン ―遊びと学びのデジタルエクスペリエンス』(デブラ・レヴィン・ゲルマン 著、依田光江 訳)から巻頭のテキストをいくつかご紹介します。
子ども向けのデジタルプロダクトを作る人に向けた実践的指南書です。ピアジェの認知発達理論をもとに解説されています。
推薦のことばは『劇場としてのコンピュータ』『人間のためのコンピューター―インターフェースの発想と展開』などのブレンダ・ローレルさんが寄せています。
---------------------------------
本書の使い方
対象読者は?
本書の対象読者は、ウェブサイトやゲーム、モバイルアプリの制作、あるいはソフトウェアの開発など、何らかのかたちで子ども向けデジタルエクスペリエンスのデザインに携わっているか、それに興味のある人です。
内容を理解するうえで、デザイナーや開発者の専門知識は必要ありませんが、デザイン用語についての基礎的な知識はあることを前提にしています。
本の中身は?
本書は大きく3つのパートに分かれます。
1つ目のパートは第1、2、3章です。デザインの対象としての子どもが、なぜあんなにおもしろくて危なっかしくてイライラさせられるのかについて述べ、認知発達理論の基礎を踏まえたうえでデザインの枠組みを示します。また、子ども向けにデザインすることと、他のターゲット向けにデザインすることのつながりも指摘します。
第1章「子どもとデザイン」では、子ども向けウェブサイトが、インターネット黎明期から今日までどのように進化してきたかをとりあげます。
第2章「遊びと学び」では、子ども向けにデザインするときの枠組みを定義し、子ども向けのデザインに用いる原則と、大人向けの原則との間に共通点も多いことを説明します。
第3章「発達と認知」では、子どもの認知能力の発達段階が中心のテーマです。また、デザイン時に考慮しなければならない発達の重要な点を強調します。
2つ目のパートは第4~9章です。子ども向けデザインのパターン、原則、ツール、技法について詳細に述べ、ユーザー対象のリサーチおよびテストの効果的な実施方法を説明します。
第4章「2~4歳:小さい身体に大きな期待」では、2~4歳児向けにデザインするときのヒントと技法をまとめます。字がまだ読めないユーザーへのデザイン、慎重な色使い、視覚的な階層構造の適切な組み立て方などが中心です。
第5章「4~6歳:どっちつかずの中間層」では、4~6歳児向けのデザインの取り組み方を概説します。このなかで、社会性(ソーシャル)のデザインと、フィードバックの程度、自由な発想での探索についてもとりあげます。
第6章「6~8歳:大きな子ども」では、6~8歳児向けにデザインする場合に知っておくべきことをまとめます。トピックとして、進歩とレベルアップ、遊ぶときのルールの確立、自己表現をとりあげます。
第7章「8~10歳:“クール”な要素を」では、8~10歳児向けのデザインについて、失敗のとらえ方や、複雑さ、広告、自我のテーマとからめて論じます。
第8章「10~12歳:大人の手前」では、認知能力の面では成熟していながら、デジタルエクスペリエンスの世界ではある程度の特別扱いをしなければならない10~12歳児向けのデザインに伴う繊細さについて論じます。
第9章「デザインリサーチ」では、子どもを対象としたリサーチの技法を年齢層ごとに説明します。リサーチ参加者の見つけ方や、参加同意書、親の関与についても扱います。
3つ目のパートは第10、11章です。前の2つのパートの内容を盛り込み、子ども向けの優れたデジタルエクスペリエンスを制作するうえで重要な項目をまとめます。
第10章「年齢層ごとに見るアプリ」では、異なる年齢層にどのようにデザインパターンを展開するかについてサンプルを示します。2~4歳児向けにデザインした基本的な動画再生アプリが、10~12歳児向けでは、プレイリストや「お気に入り」やシェア機能を備えた複雑な動画貯蔵庫に進歩する様子を見ることができます。
第11章「全体のまとめ」では、アプリをダウンロード可能にしたり、ウェブサイトを立ち上げて稼働させたりするなど、子ども向けデザインのビジネス的側面について述べます。
また、本書のところどころで、子どもおよび業界専門家のインタビューと、ケーススタディを掲載します。
本書に付属するもの
併設サイトにブログと追加情報を記載しています。本書に掲載した図やイラストは、Creative Commonsのライセンスのもと、あなたのプレゼンテーションに組み込むことができます。フリッカーに掲載しています。
---------------------------------
よく寄せられる質問
子ども向けのデザインは大人向けのデザインとどう違うのですか?
似ているところはどこですか?
子ども向けのデザインも大人向けのデザインも、ユーザーを深く知り、彼らが何を望んでいるのかを理解しなければならないところは同じです。大きな違いは、子どもはどんどん変化することです。わずか6カ月間で、2歳児は認知能力も運動能力も細かい技巧も大きく成長します。大人の能力は6カ月程度ではたいして変わらないでしょう。対象ユーザーとともに成長するサイトやゲームを開発する際には、子どものこうした急速な変化に留意することが重要です。
また、大人はインタフェースを使うときに明確な最終ゴールを意識するのが普通ですが、子どもにとっては旅の過程が大切です。コンピュータやiPadに触れること自体が楽しく、全部が冒険なのです。満たすべき要件や達成すべきゴールはあるにしても、デザイナーは多くの場面で細かいところに楽しみを見出すことができます。大人と子どもの類似点と相違点、および実際のデザインの場面でそれがどう関係するかについては、第2章で説明します。
子ども向けにデザインする場合、子どもの発達段階をどの程度深く理解する必要がありますか?
ターゲットの子どもが発達段階のどの位置にいるかについて基本を知っておくのは望ましいことです。認知心理学の深い知識までは必要ないにしても、デザインプロジェクトを開始する前に、認知能力の発達と成熟の段階をひととおり頭に入れておくとよいでしょう。ピアジェの認知発達理論を第3章でとりあげます。子どもがたどる発達段階をまとめますから、子どもを惹きつけるエクスペリエンスのデザインに役立ててください。
子ども向けにデザインする場合に知っておくべきルールや規制はどのようなものですか?
子ども向けのサイト/アプリのデザインに関する絶対のルールはありません。ただし情報収集は別で、多くの国が13歳未満の個人情報の収集には厳重な規制を設けています。第6章の末尾に掲載したリネット・アテイのインタビューのなかで、とりわけ厳しいアメリカのCOPPA(児童オンラインプライバシー保護法)について詳しく触れられていますので参照してください。このような規制は、子どもに関する情報(あとで子ども宛てのメッセージに使われたり、商品の売りつけに使われたり、あるいは行動ターゲティングや地理的ターゲティングなどのための個人情報の識別に使われたりする可能性があります)を収集するには、親あるいは法的保護者が書面で同意しなければならないと明確に定めています。
2008年にストラスブール(フランス)で開催された、第30回データ保護&プライバシー・コミッショナー国際会議の場で、児童のオンラインプライバシーに関する決議の草案が策定されました。こうした指針は概要レベルですが、子どものアイデンティティをオンライン上で保護することについて国際的な合意が形成され始めています。あらゆる個人情報が適切に保護されるように、デザイナーや教育関係者、親、子ども、そして子ども向けのデジタルプロダクトを制作する企業の協力が強く求められています。
子ども向けにデザインする場合に便利な具体的な慣習を教えてください。
対象の年齢層に独特の特徴を意識してデザインする必要があります。たとえば、2~4歳児向けにタッチスクリーン式のアプリをデザインする場合には、タッチするアイテムを、不器用で小さな手でもうまくタッチできる大きさにします。また、デザインするジェスチャーも子どもにとって楽な動きにしてください。フリック(払う)やピンチ(つまむ)やタップではなく、スワイプ(すべらせる)、グラブ(つかむ)、スマック(たたく)を使うのです。これについては第4章で扱います。また、アイコンやシンボルの形状についてもよく考える必要があります。大人にとっては世界共通で理解されているアイコンであっても、抽象思考能力が発達途上にある子どもが理解できるとは限りません。最後にもう1つ、文字による説明を多用せず、なるべく視覚に訴える表現にしてください。子どもにとって―文字が読めるようになったとしても―画面上の文字を追うのは苦行なのです。第4~8章で、異なる年齢層ごとに、最も効果的なデザインパターンを詳しく紹介します。
---------------------------------
本書への推薦のことば
1人の親として、また30年以上インタラクティブメディアのリサーチャーおよびデザイナーとして働いてきた者として、子ども向けデジタルデザインの世界には、子どもを見下し、むやみに単純化し、明らかに手抜きをしたものが蔓延していることに気づいていました。子どもは“大人じゃない”のだから、エレガントで練り上げたデザインは必要ないと思われてきたのです。「子ども向けデザインは大人向けより楽に決まってるよ。だって、子どもは大人より単純でしょ? 『スーパーマン』とか『ET』のライセンスさえ取ってしまえば(昔アタリがやっていたみたいに)、あとは楽勝だよね」。そんなふうに言う開発者もたくさんいます。
本書の著者デブラ・レヴィン・ゲルマンは、子ども向けのデジタルゲームやアプリをデザインするデザイナーに向けて、この、網羅的で、サンプルが豊富で、思慮に富んだ本を執筆することで、デジタル世界にいる子どもたちに巨大な恩恵をもたらしました。文章自体に有益な情報がわかりやすく詰まっているのはもちろん、スクリーンショットと的確な批評のついた多数のサンプルを加えることで、言葉だけでなく視覚的にもたくさんのことが伝わる構成になっています。内容を彩るケーススタディとインタビューからは、彼女が子どもを直に深く知っていることがよくわかります。各章は、2歳ごとに年齢を区切り、その年齢層の発達面および社会性の面の特徴を明らかにしたうえで、経験に即したデザインの知識が披露されています。また、デザインリサーチの章では、子どもと心を通わせ、彼らの考え方と好みを“吸収する”――著者ゲルマンの言い方を借りれば――ための方法が示されています。
本書を読み通してみて、いくつかの知見が私の目をとらえました。ある箇所は私自身が経験したこととよく似ていたため、またある箇所は非常に驚いたためです。たとえば2~4歳児向けのデザインの章を読んだときには、階層構造と注目すべきポイントを子どもにわかりやすく伝えるために、視覚に訴える標識(インジケータ)をどう活用すればいいかについて、著者は念入りに分析しており、私は著者の苦心を知って驚くと同時に感じ入りました。うるさい音を立てながら、同じ行動を繰り返す子どもに親がイライラさせられる様子など、まるで自分の姿を見るようでした(とはいえ、うるさい音を延々と鳴らす地獄のおもちゃなんてドライブウェイに放り投げて車で踏みつぶすべき、という私の長年の考えに変わりはありませんが)。4~6歳児向けの章にあった、「ときには、一人称で表現するだけで簡単に社会性を感じさせられることもあります」という著者の観察には「なるほど」と思わされました。私は性別やテクノロジーやプレイの様子の関係について、何年もリサーチを続けてきましたので、デザイナーが性差に対応するときは、子どもはこういうものだという思い込みではなく、子どもがどんなふうにプレイするかを指針にすべきだという著者の発見的考察に深く共鳴します。
「クリティカルシンキング(批判的思考)」と呼ばれる能力を、デザインを通じていかに上手に育んでいくかについての観察と発見に、私は特に惹きつけられました。広告とコンテンツの違いを認識できる年齢に達した子どもに、両者のデザインを区別して示すことは、メディアの存在やその意図を見抜く力を育てる手助けになります。あちこちにちりばめてあるヒントのなかで気に入ったものの1つは、年少の子ども向けのエクスペリエンスでは「負けること」や「まちがえること」をおもしろくする、ということです。おもしろい失敗という考えは、批判精神や勇気につながり、融通性と創造性を豊かに備えた大人の形成に役立ちます。こうした資質こそ、デザインに関する著者の知見を応用することによって、いっそう伸ばされるものなのです。
本書は主題について簡潔かつ実践的に論じながら、そこここに子どもに対する慈しみと敬意がにじみ出ています。インタラクションを盛り込んだ子ども向けプロダクトをデザインするすべての人が、本書を読んで胸に刻み、実際に役立ててくださることを願っています。
カリフォルニア州サンタクルーズ・マウンテンズにて
ブレンダ・ローレル
---------------------------------
はじめに
子どものメディアに興味を持ち始めたのは、もう何年も前のことです。大学時代に私は、才気あふれるパトリシア・アウフデルハイデ博士の「子ども向けテレビ」に関する科目を受講しました。当時、小さい子どもの母親だったアウフデルハイデ博士は、現実世界の例と認知心理学の原則を結びつけ、子ども向けに価値のあるメディアをつくることが、どれほど知的刺激に満ち、やりがいがあり、しかもむずかしいかを教示してくださいました。博士からの指導を通じて私は、視覚表現のリテラシー(基礎能力)の大切さを学びました。このリテラシーがあれば、子どもはデザイン上の表現が何のためのものか―情報伝達なのか宣伝なのかコントロールなのか訓練なのか―を判断することができます。また、本当に優れたものはごく一部だけで、子ども向けテレビ番組の大半はベールをかぶった宣伝であることを知ったのもこの頃です。子ども向けテレビ番組は、1980年代中頃に規制が緩和され、それまでは制作されていた質の高い番組が、30分間のアニメショーと見せかけて実は商品のコマーシャルという番組に取って代わられました。私はメディアへの興味を募らせ、『セサミストリート』や『リーディング・レインボー』のような番組の台本をいつか書きたいと想像するようになりました。
そしてインターネットの時代が到来したのです。私は大学院に進み、教育工学の草分けであるシーモア・パパート、ブレンダ・ローレル、シェリー・タークルの理論を学び、すばらしく有能なエイミー・ブルックマンと研究を進めることになりました。インターネットは子どものメディアをよくするためのあらゆる種類のドアを開ける力を持っていますが、そこに至るまでにはまだ長い道のりがあることを学びました。
その後、私は子どものウェブサイトをデザインする仕事に就きました。Crayola、Scholastic、PBS、Comcast、Campbell’s Soup Company、Pepperidge Farmなどの企業と仕事をし、その過程で数百人の子どもと出会いました。子ども向けのデザインには、あくまでも彼らは子どもだという姿勢で取り組みました。子どもは小さな大人ではなく、演繹的推理能力も抽象思考も論理的に発展させる能力も持っていないのです。
娘が2歳になった頃、子どものメディアはより身近な存在になり、より批判的に見るようになりました。当時iPhoneは世に出て間もない頃でしたが、キーボードもマウスも高度な微細運動能力も必要としないこの機器を子どもの教育や遊びに使えたら、という考えに私はすっかり魅了されるようになります。子ども向けアプリのデザインについてヒントやテクニックを探しましたが、有益な記事がいくつか見つかりはしたものの、異なる年齢層の子ども向けに優れたデジタルプロダクトをデザインする方法についての包括的な資料はないことがわかりました。そこで、エレベーターピッチ[プロダクトの最も重要な部分を簡潔に(エレベーターを下りるまでの1分程度の時間で)説明すること]を素早くまとめ、ルー・ローゼンフェルドに会いに行きました。そのときの会話が、この本につながったのです。
この本を書き始めたときは、子ども向けデザインの最高のハウツー本にしようと意気込んでいました。しかし執筆が進むにつれ、子ども向けデザインに使う技法の多くは、年齢層を問わない、誰にとってもすばらしいエクスペリエンスをデザインするためにも使えることがわかりました。本書が読者の皆さんにとって価値があり、デザインの道を極めるための―デザインの対象者が誰であれ―一助となることを切に願います。
2014年5月13日
ペンシルバニア州フィラデルフィアにて
デブラ・レヴィン・ゲルマン
----------------------------------
Amazonページはこちら。Kindle版(固定レイアウト)もあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
