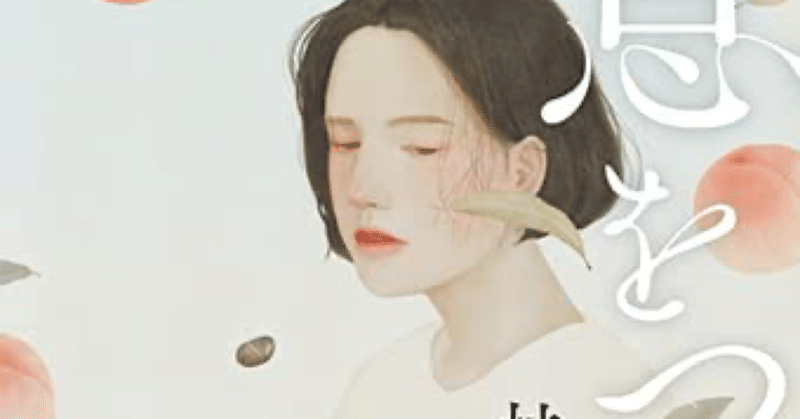
親の役割はどこまで? 息をつめて 桂望実
都会の片隅でひっそりと暮らすひとりの女。何かから逃れるように、孤独な日々を送る。パチンコ景品交換所、連れ込み宿の清掃、訪問介護の現場。仕事を転々とする彼女にも、かつて幸せな暮らしがあった。充実した日々は、ある違和感から少しずつ壊れていく。そして、ついにある事件を発端に、彼女の人生は破滅するーー。衝撃の問題作。
静かで息詰まる物語だ。
ほんの些細なことでも警察と関わるような出来事が起こるたび、職も住まいも転々としている初老の女、麻里。人との関わりも極力避け、同僚にも自分のことは何一つ語ろうとしない。いつでも引っ越せるように、最小限の家財しか持たず、そして実際何かあるたび手慣れた様子ですぐに転居する。
なぜ彼女はこんな生活を続けているのか。なぜか時折彼女に接触してくる元刑事。
そして挟まれる、彼女が幸せだったころの記憶。
意図されてのことだろうが、最初読み手は麻里が前科者なのだろうと思わされる。しかし彼女の過去の語りを読むうち、そうでないことを知る。彼女が罪を犯すところなど想像もできないほど、控えめで善良な女の人生がそこにあるからだ。
その彼女の幸せなはずの人生に影を落とすのは、息子だった。利発でかわいらしい、大切な息子に、彼女は早い時期から違和感を覚えるのだ。幼稚園、小学校、中学校と、人気者で教師からの評価も高い、自慢の息子。彼の異常性に気づいたのは麻里だけだった。友人にランクをつけ、自分にいかに気に入られるかを友人同士で競わせる。彼のためならなんでもするという相手に、自分で自分を傷つけるようなことをさせたり、欲しいものを貢がせたり、およそ就学前の子供が考えつくようなことではないようなことを、平然とやってのけ、母の叱責も意に介さず、罪悪感をかけらも持たない息子を、麻里は恐れていた。夫に相談しても、病院に連れて行っても、教師に相談しても、「考えすぎだ」の一言で済まされてしまう。
麻里も考えすぎだと思おうとしても、どうしても不安を振り払えない。そしてそんな中、中学生になった息子は、同級生を殺めてしまうのだ。世間から好奇の目と激しい非難を浴びせられ、親としての責任を追及される。夫はすでに他界していて頼る者もなく、息子の裁判が結審してから麻里は世間の目から逃れて今のような生活をしているのだ。
反社会性人格障害。我が子がそうだった時、親がどんな衝撃を受けるのか、想像できるものではない。
私は海外ドラマの『クリミナル・マインド』が好きでずっと見ていたのだが、どのシーズンだったか忘れたが、幼い兄弟の兄が反社会性人格障害で弟を殺してしまう話があった。兄弟を2人とも失いたくない両親は、友人の刑事に頼んで小児性愛者による犯行に見せかけて兄を守ろうとする。しかし結局はプロファイラーチームに見破られてしまうのだが、その時にプロファイラーの1人が両親にこういう。
「お子さんは反社会性人格障害です。罪悪感というものを持つことができないんです。そしてそれは治ることはありません。」
正確ではないと思うが、だいたいこんなような意味のセリフだったと思う。そして、このままにしていてもいいことはない、彼らのような障害を持つ子供には手助けが必要で、それを受けるために彼は裁かれなければならない、というようなことを言っていたように思う。
自己中心的で、人の心を考えることができない、倫理観や道徳観よりも自分の利益や快・不快が優先であり、他人を支配したり利用することに躊躇がない。親であろうとも、そうした子の異常性に触れれば恐れずにはいられないだろう。
その息子が、釈放されて戻ってくる。十分に反省し、更生したと評価されて。
それが見せかけだと知っているのは麻里だけだ。息子は何も変わっていない、何も反省していない。もし悔やんでいるとすれば、警察に捕まるようなヘマをしたことだけだ。
そんな息子が、社会と関わり合わないように、友人を作らないように、麻里は世間の目から逃れることと共に息子を監視することに腐心しなければならなくなる。
転々とした職は訪問介護の仕事に就き、少し落ち着いた暮らしになったように見えるが、彼女が1人だったときよりも、神経を尖らせなくてはならなくなた。麻里がいくら気をつけようとも、息子はその手をすり抜けてまた同じことを繰り返そうとしている。麻里にとってそれがどれほど恐ろしいことか。もしも彼にとって麻里が邪魔で不要な存在になったなら、彼は躊躇せずに麻里のことも排除するだろう。どれほどの緊張を強いられる生活だろうか。
そんな綱渡りのような生活を続けていた麻里が最後にした決断は、それしかないだろうとしか思えない。彼女を酷い親だと詰ることは誰にもできないだろう。隠されていた彼女の夫の死の真相、彼女に向けられた息子の憎悪の目。
彼女がした選択は今の現実の日本ではできないものだろう。ある種ファンタジーのようなもので、この結末に納得のいかない読み手もいるかもしれない。
けれど麻里の人生を考えた時、彼女が彼女の人生を諦めるのではなく、この選択をしたことに少しほっとする。麻里の思い詰めていく様を見ていると、もう心中しかないのではないかと思わされるからだ。
もしも、自分に子供がいて、麻里の息子のような子供だったら。自分が産み出した以上、自分の責任と考えて心中するぐらいしか解決はないかもしれない、と考えてしまう。
同じような題材で『Is A.』という映画があったが、その中でも父親は息子を自分の手で連れて逝こうとする。たとえ怪物であったとしても、我が子だ、愛しているからこそ自分の手で連れて逝くのだ、という父親の思いを強く感じるシーンだった。が、その思いは息子には伝わらない。切なく美しく、そして恐ろしいシーンでもあった。
麻里もそう考えることもあっただろう。我が子だからこそ、自分がケリをつける。けれど彼女は訪問介護先で出会った、子供との関係に問題を抱えている人たちと出会うことで、自分の人生というものにも目を向け始めるのだ。
どこまでが親の責任だろうか。育て方が悪かったんじゃないか、家庭環境はどうだったんだ、親のくせに気づかなかったのか。
特に少年犯罪ではよく言われることだ。私だってそう考えたことがある。麻里の決断も逃げだとも言えるかもしれない。けれど、麻里が息子の異常性に気づいた時、社会は何をしてくれたか。「考えすぎ」の一言で済ませて、麻里の懸念に寄り添おうとせず、彼女の息子をこうさせてしまった責任を彼女だけに負わせるのは違うんじゃないかとも思う。手を尽くそうとした親を、助けを求めようとしていた親を、そのことを全く考えもせず責め立てることはそれこそ安全圏からの無責任な言い草なのではないか。
答えは出ない。
それでも、“息をつめて”生きてきた麻里が、ようやく、ほんの少し身軽になって息をすることができるようになるであろう結末に安堵する。
彼女が彼女の人生を取り戻して、笑える日はくるだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
