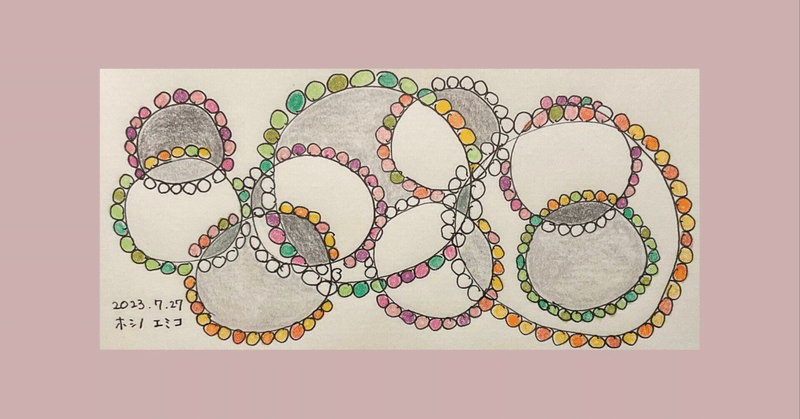
東浩紀『観光客の哲学 増補版』読んだ
2017年に出版された『観光客の哲学』の増補版がでたので読んだ。
世界がナショナリズムとグローバリズムに分断されている現状において、観光客こそが永遠平和や世界市民への道になるというのが本論。たんなる概念の提示ではなくて、著者はチェルノブイリ原発跡地へのツアーを実現しているし、福島原発のツーリズムを真面目に企画したこともある。
増補版では、家族についての論考が追加されており、先日出版された『訂正可能性の哲学』へのつなぎとなっている。
以下、備忘録。
観光が大衆化したのはわりと最近である。以前は貴族が見聞を広めるためにローマやギリシャなどを旅していたが、19世紀後半にトマス・クックが大衆向けのツアーを開拓したことが始まりである。クックは観光によって大衆を啓蒙できると信じていたようだ。
具体的にはブライトンのような海浜リゾートの開発が嚆矢である。ブライトンといえば三笘薫のいる場所というイメージだが、歴史のあるリゾートなんだね。
やがてクックはイタリアなどへの団体旅行も実現させる。ほんでイギリス人観光客のマナーの悪さなどが当時揶揄されていたようだ。バブル期の日本人がそうだったし、今なら中国人がそれに該当するだろうか。海外旅行客を馬鹿にする風潮は今も昔も変わらない。
そもそも論だが、観光客の見るものと、現地で生活する人々にみえているものは違う。
これを二次創作と原作の違いになぞらえている。二次創作を前提としてアニメや漫画の原作が作られるように、観光地もインスタ映えなどを意識して作られる。
そうである以上は、二次創作的なものを否定してもしかたがない。
観光とは二次創作のようなふまじめで社会性を欠いたものである。観光客がすることみるものは、現地の生活者とは乖離したふまじめなものだ。
ここで著者が以前から引用しているルソーにつながる。ルソーといえば社会契約論で有名だが、ルソー自身はどちらかというと社会不適合者で、社会など作りたくない人だったのだ。
ここでカントとかヘーゲルの話になる。
カントは永遠平和の前提のひとつとして訪問権をあげいていた(だし客人として歓待される権利は含まない)。
カントの時代には観光業は存在しておらず、外交官などの政府関係者の訪問を想定していたと考えられる。
カントの『永遠平和のために』は国家の成熟および、成熟した国家による連合を前提としており、成熟しない国家を排斥することになる。ならず者国家として排斥された国家はさらに孤立と怒りを深めることになる。
この悪循環を断ち切れるのは、カントのいう訪問権を互いに観光する権利にまで拡張することである。ならず者国家を否定せざるをえないかもしれないが、ならず者国家からの観光客は受け入れることで友好の道が保たれる。それは商業的な目的であってもいいし、むしろ商業的であるほうが国家間のいざこざと無関係でいられる。
ただし観光客は身の安全は保証されるが、歓待される権利までは保証されない。
カントの永遠平和よろしく、ヘーゲルは世界精神とか言っていたのであるが、世界精神以前に、人は国家に属さなければ精神的に成熟しないとも言っている。
これは当然のことで、ルソーの言うように人間は社会など作りたくないが、人間は協同体がなくては生きていけない。社会などつくりたくなかった未成熟さを、国民になることで乗り越えていくのだ。
そうすると、シュミットの友敵理論のごとく、公的な意味での友敵が発生するほかない。
これに比べると観光客はふわふわした存在である。
国家に属してその価値観を内面化することで精神的に成熟したあとで、世界市民になるというのが、ヘーゲルの考えたことだった。
ヘーゲルの解説書で知られるアレクサンドル・コジェーヴは、すでにヘーゲルやマルクスのいう歴史の終わりを生きており、そこでも人間は活動するがそれは動物の戯れのようなものだと述べた。与えられた環境に自足して快楽を求めて商品を買い漁るだけの動物的な消費者の群れだ。
動物は政治的存在ではないから、友も敵もない。観光客はまさに動物といえる。
アーレントもまたコジェーヴと同じく人間の消失をテーマにした哲学者である。アーレントは行為者の固有名性に着目した。他者とのコミュニケーションが人間の本来的なあり方であり、機械的な労働はそうではないとしたのだ。いうまでもなくこれは危うい発想であり、労働に追われる人々を締め出すことになりかねない。
コジェーヴが動物的消費者を問題にしたのと同じく、アーレントは動物的労働者を批判している。シュミットは友も敵もない非政治的な動物を批判した。
これらは20世紀初頭にまじまったグローバリズムに対する批判であるが、21世紀においてそんなものが通用するわけがないと著者は批判する。
またポストモダニズムはそれらを乗り越えたことになっているが、著者によればそれらは現実政治にほぼ影響を与えていない。文化左翼に甘んじて内輪の議論に終始するか、ポストモダニストの矜持を捨てて古いスタイルの政治参加に戻るかのどちらかしかない。つまり見事に政治とその外部の対立を再生産している。
だから著者は観光客を手がかりとして、旧来の人間観や政治観を根本から問い直そうというのである。
国家にも下半身がある。成熟した国家とは、理性によって下半身を制御できることだとカントはいっている。
政治的にはネーションはいまだに存在しているが、経済活動はいまやネーションを単位としていない。いわば愛を確認してないのに、肉体関係を結んでいるようなものだ。
経済=下半身は欲望に忠実でつながってしまうが、政治=頭のほうは、いまだに国家間のさまざまな問題により信頼関係が育っていない。先ほどの議論とつなげれば、人間の層と動物の層が分かれてしまっているといえよう。
しかし愛がないからといって、経済関係を断ち切るのも弊害が大きい。
このような文脈で、旧来のリベラリズム批判として現れたのが、リバタリアニズムとコミュニタリアニズムである。
19世紀のナショナリズムは世界精神や永遠平和への一段階であった。オールドリベラルはまだその発展図式を信じている。それに対して、コミュニタリアンはそんなものは信じない。
グローバリズムはナショナリズムを温存したが、変容させた。いまや世界精神は世界市場にとってかわられ、ナショナリズムは特定の共同体への愛のままで普遍化されることがない。コミュニタリアニズムはそのことのいいかえである。
リバタリアニズムは国家の関与は最小限であるべきだとして、個々の自由を最大限に尊重する。これはグローバリズムの思想的表現であり、動物の層の表現型である。
ネグリらはグローバリズムのなかで現れる新たな秩序を帝国と呼んだ。そこで可能になる抵抗運動をマルチチュードとした。ネットワーク状の連帯は実際に各地で起きたが、結局のところ確固たる理念もプログラムもなかったので空無化した。
このように現代ではグローバリズムとナショナリズムしかなく、世界市民への道は閉ざされている。そこで著者は観光客への道を考えるのだ。
マルチチュードは帝国内で生じるエネルギーの反作用として生じるもので、いわば否定神学にほかならない。マルチチュードの連帯は、連帯が存在しないことで存在する。そのような否定神学的マルチチュードに対して、観光は郵便的マルチチュードであり、誤配の可能性に満ちている。
ここで急にネットワーク理論の話になる。
6次の隔たりと言われるスモールワールドは誤配の可能性に満ちている。その一方で、この世界はスケールフリーであり、富や名誉を寡占する人々がいる。現実世界のスモールワールド性とスケールフリー性が同時に存在しており、これはコミュニタリアニズムとグローバリズム、あるいは国民国家と帝国に対応しているといえる。
スモールワールド性とスケールフリー性、コミュニタリアニズムとグローバリズム、国民国家と帝国は対立する概念ではあるが、現実には矛盾なく共存しており、そのあわいにこそ抵抗=誤配の可能性があるのではないか、、、と曖昧な感じに議論は収束していくのであった。
そして『一般意志2.0』と同様にリチャード・ローティを引用する。
ローティには『偶然性・アイロニー・連帯』という著書があるが、ここでいう偶然性とは、公的なふるまいと私的な信念の分裂をうけいれて、自分の私的な価値観がたんなる偶然の産物であることを認める、ということらしい。
そして連帯とは、自分の価値観が普遍的な信念とは考えないし、普遍的な信念の実在も信じないが、共感による連帯は信じる。つまり、個人単位の、具体的で偶然的な感情移入、惻隠の情による連帯は信じるのである。
ここで第一部がおしまい。
第2部は第6章「家族」から始まる。
政治的連帯に使えそうな概念は家族ぐらいしかない。家族は自由に変更することが困難だからである。
自由意志で変更可能なものは、自由意志で容易に解消されてしまう。土地はこの時代に主体の拠り所にするのは無理があるし、血や遺伝子は人種主義に結びつきかねないので危険である。
家族から脱出することは難しい。国家や階級も、似たような強制性があると見なされたからこそ、政治的なアイデンティティになり得た。
言い換えれば、ひとは自分のために死ぬことはありうるし、国家や階級のためにも死ぬし、家族のためにも死ぬ。だからそれらは政治の基礎になりうる。死のないところに政治はない。自由に変更可能な趣味的なもののためにひとは死なない、だから政治の基礎にはならない。
さらに家族は偶然性にみちている。死の必然性に対して、出生は偶然性のかたまりである。
死の絶対性から出発して実存哲学を構築したハイデガーは、やがて運命の必然性を強調するあまりにナチズムと接近することにもなった。
しかし情愛や養子縁組によってもメンバーになりうるという柔軟性、拡張性も備えているのが家族である。
この柔軟性と拡張性において、家族は、ローティのいう共感による連帯へと開かれている。
第7章「不気味なもの」は、『サイバースペースはなぜそう呼ばれるか』の続きであり、やや唐突な感も否めない。ここではカリフォルニアイデオロギーとレッテルを貼られたアメリカのITな人たちが、保守でもありリベラルでもあったという指摘が重要かと思われる。先ほどの、国民国家と帝国のあわい、という話といちおうつながっている。
第8章ではこれまた唐突にドストエフスキーを主題として話が展開する。
かつては社会主義者であったドストエフスキーが、やがてチェルヌイシェフスキーのような社会主義者を批判するようになり、『地下室の手記』の主人公のような鬱屈した市民について書くようになる、、、ということで、これまたここまでの二項対立に対応している。
また『悪霊』のスタヴローギンは、両者を兼ね備えた人物である。
ここでフロイトのドストエフスキー論を引用したりするので、その意味でも前章の「不気味なもの」とつながってはいる。
そして急に、ドストエフスキーの主人公は父殺しに失敗して去勢されているとか、象徴的な父として皇帝を求めているとかいう話になる。
さらには亀山郁夫が空想した『カラマーゾフの兄弟』の続編を引用して、そこを強調する。
ここまでくると私はかなり混乱していたのだが、ありがたいことに著者は言いたいことをわかりやすくまとめてくれる。哲学書といえどわかりやすいに越したことはないよな。
すなわち、コミュニタリアン(地下室人)でもなくリバタリアン(スタヴローギン)でもなく、家族的類似性に基づいて、新生児(偶然性)に接するように世界と関わるべき、ということらしい。
そして親にならなければ生をまっとうすることはできないと、かなり踏み込んだことを書いている。
いつの時代でも哲学者は子どもが嫌いである。けれども、ぼくたちはみなかつては子どもだった。ぼくたちはみな不気味なものだった。偶然の子どもたちだった。ぼくたちはたしかに実存として死ぬ。死は必然である。けれども誕生は必然ではないし、ぼくたちのだれも生まれたときは実存ではなかった。だから、ぼくたちは、必然にたどりつく実存になるだけでなく、偶然に曝されつぎの世代を生みだす親にもならなければ、けっして生をまっとうすることができない。子として思考するかぎり、チェルヌイシェフスキーと地下室人とスタヴローギンの三択から逃れることができない。ハイデガーの過ちは、彼が、複数の子を生みだす親の立場ではなく、ひとり死ぬ子の立場から哲学を構想したことにあった。子として死ぬだけではなく、親としても生きろ。ひとことで言えば、これがぼくがこの第二部で言いたいことである。むろんここでの親は必ずしも生物学的な親を意味しない。象徴的あるいは文化的な親も存在するだろう。否、むしろそちらの親のほうこそが、ここでいう親の概念には近いのかもしれない。なぜならば、親であるとは誤配を起こすということだからである。
議論は紆余曲折するけど、それなりに筋は通っていると思われた。
『訂正可能性の哲学』を読むのが楽しみである。
関連記事
サポートは執筆活動に使わせていただきます。
