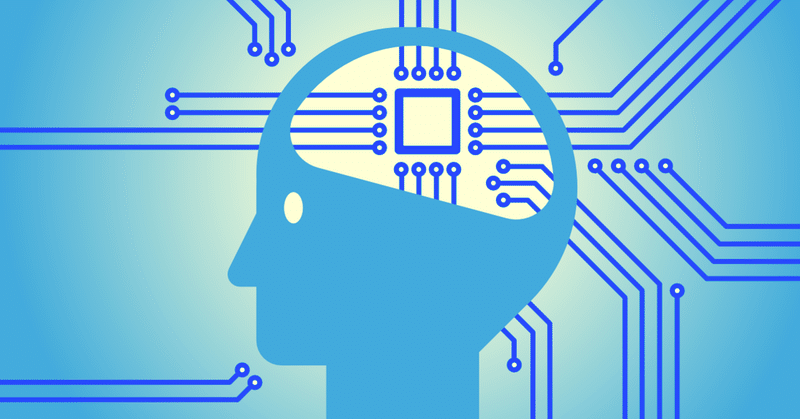
AIの【お茶目な】一面
“AI”というワードが、暮らしに定着しつつあります。
人工知能:Artificial Intelligence。このAIには、実は【お茶目】な一面があるんです。
“AI”と聞いて思いつくものはなんでしょう?
身近なところでは、スマホのアシスタント。「Hey, Siri! 今日の天気は?」と使っているアレですね。
そのほかAIは、掃除ロボット『ルンバ』にも使われているし、パン屋さんのレジでも使われています。パンをのせたトレーを置くだけで料金計算してくれる、あのシステムです。
ごく最近では、コロナで注目を浴びるようになったオンライン診療。あのシステムにもAIが導入されています。
AIには、生活を便利にしてくれるという大きなメリットがあります。その反面、AIの発達は人の仕事を奪うとか、情報漏洩のリスクが高まるとか、メディアは、AIがもたらすであろうデメリットを多く取り上げます。
デメリットが話題になるたび、わたしはAIに対し、ちょっとした猜疑心を抱いていました。AIが発達すると、人の生活もかなり変わる。それって大丈夫なのかしら。
♢
特許翻訳をしているわたしは、今までAI関連発明の案件を多く翻訳しました。
翻訳する前に、書籍やサイトをかたっぱしから調べ、技術分野の情報収集をするのですが、そのプロセスで、うわぁ、これは面白いと思うものを見つけるときがあります。
このあいだ見つけたのは、TED Talksの動画から。プレゼンターは、AIリサーチャーのJanelle Shaneさん。マンガやイラストを使って、AIの【ちょっとヘン】な一面を紹介しています。
**このトークには日本語の書き起こし(トランスクリプト)がありませんが、英語のトランスクリプトを翻訳ソフトにかければ概要は分かると思います。話すスピードがゆっくりなので、英語の学習材料としてもgood。
Shaneさんは、「映画に出てくるAIは、人間に従うのはもうごめん、さよなら、となるけれど、実際のAIはそれほど賢くはない」と言います。
さらにShaneさんは、「AIの危険なところは、人間に反抗することではない。AIが人間の要求を正確に実行する、そこが危険」だと言います。
これはどういうことでしょうか?
♢
Shaneさんは、トークのなかで、AIを使った実験のいくつかをマンガで解説しています。
例えば、AIにロボット部品を組み立てさせ、できあがったロボットを使ってA地点からB地点まで行かせる、という実験をします(動画02:08~)。
その際、AIに示すのは、人間が望むゴールだけ。この実験のゴールは、“ロボット部品を組み立て、A地点からB地点まで行く”ことです。
するとAIは、どうすると思いますか?人間が期待するような方法で部品を組み立て、B地点に到達するのでしょうか。
AIのやりかたはこうです。
ロボット部品を積み木のように高く積み上げてタワーを作る。そして、その高いタワーを棒倒しのように倒すことによって、B地点に到着させます。
確かに、できあがったロボットを使ってA地点からB地点まで行かせる、このゴールは達成している。技術的には、ロボットはB地点に着いたのだからなにも間違ってはいません。
でも、わたしたち人間が同じ目的を達成しようとしたらどうするでしょう。一般的には、ロボットを組み立て、そのロボットをA地点からB地点まで歩かせる、と考えます。
人間が考えつかないようなアプローチをするAI、なんだかちょっと【お茶目】だと思いませんか?積み上げたタワーを倒してB地点に到着させるなんて、わたしには思いつきません。
♢
上の実験では、人間がAIにゴールだけを指示しました。“ロボット部品を組み立て、A地点からB地点まで行く”というゴールです。
するとAIは、そのゴールを達成するように処理を行う。つまり、どんなプロセスを経るかということはすっ飛ばして、とにかく人間の示したゴールを達成するためだけに処理してしまう。
ここが、Shaneさんの言うAIの危険なところ。“AIは人間の要求を正確に実行する”、これです。
Shaneさんはこのロボットの実験をふまえ、AIを使う作業のコツを説明します。人間の要求を実際にAIに処理させるために、AIをどう使ったらいいのかという説明です。
そのコツとは、Shaneさんによれば、人間がどのように課題設定をするのかということ。つまり、ゴールを達成するために、1つ1つの課題を細かく設定してあげるのです。
この例でいえば、ロボットの足をどうデザインするか、その足をどう使うのか、障害物を見つけたらどうするか、などです。
そういった課題を細かく設定したうえでゴールを指定すると、ロボットは、人間が期待しているとおりの動きをしてくれます(動画03:18~)。
♢
こんな実験もあります。
ShaneさんはAIに、新しい塗料の色を発明させました(動画05:19~)。
動画にある左側の4色は、人間がつけた塗料の名前。Peacock Plume (クジャクの羽飾り)やFloric (陽気な)など、思わず手にとってみたくなりますよね。色を表現するのにふさわしい名前です。
それに対し、右側の4色はAIが実際に作ったもの。
画像の上から1番目と2番目のSindis poop、Turdlyは、斬新というか愉快というか。色の表現としては顔をしかめてしまうような、そんな意味を持つ単語です。興味のある人は調べてみてくださいね。
こんな名前のついた塗料が売り場にあったら、思わず吹き出してしまいます。
人間が思いつかない斬新で奇抜な名前を考えるAI、なんだかちょっと【お茶目】だと思いませんか?
♢
Shaneさんは、AIを使った愉快な実験をたくさんしていて、その実験結果をブログにまとめています。
これからの生活に大きな影響を及ぼすであろうAI。ブログではそのAIを、メリットやデメリットという視点ではない、まったく新しい切り口から紹介している。ShaneさんのAIに対するこのアプローチには、AIへの並々ならぬ愛情を感じます。
AIには、実は【お茶目】な一面がある。このことを知るだけで、AIに親近感がわいてきます。
親近感がわくと、もっと仲良くなりたくなるもの。
この親近感が、人間とAIが共存し、協働していくときの一助になるのかもしれません。
大切な時間を使って最後まで読んでくれてありがとうございます。あなたの心に、ほんの少しでもなにかを残せたのであればいいな。 スキ、コメント、サポート、どれもとても励みになります。
