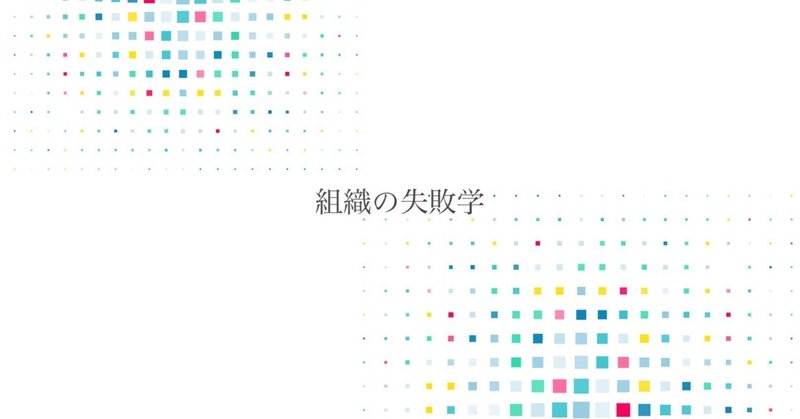
組織考[2]非常事態に強い組織──『組織の失敗学』読書感想文
組織がうまく回らない。
良いところが活かせず、先の見通しがつかず、悩みは堂々巡りで、焦りばかりがつのる。
うまくいっていない組織に対しての突破口はどこにあるのだろうか。
組織課題解決のヒントを得るための読書をした結果シリーズその2「非常事態に強い組織」です(その4まであります)。
今回、取り上げるのはこちらです。
警察組織の幹部職を経て外務省情報調査局、内閣官房内閣安全保障室に出向し、危機管理の現場を経験した著者の視点で語られる「組織の失敗事例から学ぶべきこと」。
以下、気になったポイントを中心に取り上げます。
「失敗」に際する態度で共感した点
批判は後からでいい
緊急事態がまだ終息していない危機管理の渦中では、今後の対策をどうすべきかを検討するのが先決である。事実関係が不明なのにあれこれ批判するのは無責任の誹りを免れず、担当者をいたずらに疲弊させたり、対策への信頼性を失わせたりするなど、「百害あって一利なし」である。過去の対策が失敗かどうかについては、事態が終息して事実関係の全容が判明した段階で、ゆっくり議論すればよいのだ。
安全は100%の安全を意味しない
現実には、どれほど対策に配慮しようとも、リスクを文字通りゼロにするのは不可能である。そこで、リスクが許容可能な範囲に収まっていれば、「安全」とみなしている。つまり、安全とは絶対的なものではなく、あくまで相対的な概念というわけだ。
上級指揮官は陣頭指揮しなくてよい
神経が張り詰めるような緊張の中で、何日も体力が続くわけない。長丁場の危機管理を乗り切るには、陣頭指揮にこだわらずに、適宜休息をとって思考をクリアに保つのも仕事のうちと割り切ることだ。
そのような姿勢に対して、他者が訳知り顔で謗ることもあるだろう。しかし、言いたい奴には言わせておけばよい。判断ミスによって危機管理に失敗することを思い浮かべれば、評判を落とすなど大した話ではないはずだ。
上級指揮官がやるべきことは?
この災害対策で私がイニシアチブを取ったのは、たった一件だけだった。それは食事の手配である。 〜中略〜 食事もせずに作業を続けても能率はどんどん落ちる一方で、ケアレスミスや判断ミスが増えることを、過去の教訓から学んでいただけだ。 〜中略〜 日本人の気質として「みんな懸命にがんばっている時に、食事のことを言い出したたら白い目で見られる」という意識に陥りがちだ。 〜中略〜 この一件のように誰もが口に出すのをためらう案件こそ、指揮官が率先して扱わなければいけない。
ヒューマンエラー回避にはそれなりの投資が必要
エラーの早期発見には、手間や機材、つまり人件費や設備投資の追加がどうしても必要になる。しかし、最近の医療現場はコスト削減を強く要請されており、なかなか安全対策に十分なカネをかけられていないようだ。そのため、第一線で働く者にしわ寄せがなされる構図となっているが、これではヒューマンエラーが続発するのは不可避である。
組織施策として面白いと思った点
管理職に必須の才能を見極める採用”アセスメント法”
管理職に必須の能力として、本書では「仕事頭」という能力を挙げている。これは「外部受容能力」「内部強化能力」「成果管理能力」「概念化能力」の4つに大別されるが、その中でも重要なのが「概念化能力」だと著者はいう。
(概念化能力)多様な情報の軽重を識別して本質的な情報を抽出する情報選択力、情報を統合して問題の本質を見極めようとする「掘り下げる力」、具体的な解決策や方法論に落とし込んで収束される「落とし込む力」などの要素から構成される。
この能力を持つ人は、中途採用市場でも稀であり、100人に一人程度の遭遇率だという。
さらに難しいのは、数回の採用面接でこの能力を見抜くのはかなり難しいということだ。そこで、この本で提示されているのが「アセスメント」という手法。本書で例として取り上げられていた実施方法は”グループ討論”であった。結果、先ほどの概念化能力の資質に足りずと判断し、採用見送りという結果も多いという。しかし、次の実施社社長の言葉は確かにと納得させられる部分がある。
採用アセスメントには一回三十万もかかるので、中小企業としてはきついですよ。だけど、もしも実力の無い人を採用してしまったら、それによる直接・間接ロスは何千万にもなるはずです。それを考えたら、アセスメントを何十回繰り返しても帳尻は十分に合います。
社員の声を吸い上げと育成、両得の”提報システム”
社員の意見を吸い上げるためにサトーが1976年(!)に立ち上げた制度。
社員は仕事の中で気づいたこと、疑問、意見、提案、不満を3行127文字で「毎日」会社に提出する。この提出状況・内容は評価に組み込まれており、このネタを見つけるために社員は自ずと課題意識を持って業務に取り組むようになるという。さらに、全社員から上がる情報をフィルタリングする担当部署が社長直轄で置かれており、そこに在籍するのは社内としがらみが薄い若手社員に限定される。彼らは、この業務を通じて社内の内情を知り振る舞いを知るなど、社員教育の観点でもメリットがあるという。
私がこの施策が良いと思った理由は、”提報”という形態についてではなく、そのシステムが誰にとっても必然的に継続できるように組まれている点だ。
提報をなんのために提出してもらうのか、経営に目的がある。
提報提出が評価に組み込まれているため、実施に強制力がある。
提報の活用法が社員育成と社員の意見吸い上げの二軸あり、どちらもきちんと機能するように体制が設計されている。
多少強制的ではあっても、経営層の目指すものと本気度が現場に伝わる施策というのは、なし崩しにならないことが多いのではないかと思う。
感想
危機管理の現場は、莫大な情報から判断材料を瞬時に選び取らねばならない場面、薄氷を履むような慎重さを要する場面、かといえば大胆に身を焼かれるような決断をしなければならない場面。そんな精神の責苦のようなシチュエーションにあって、さらに周囲からはセオリーしか見ない正論や的外れな批判が轟々とあびせられる。そんなシーンの連続。
危機管理の深刻さに関わらず、仕事においてミスをした際に制限時間内にその場でできることは限られる。だから事前のシミュレーションや、知識獲得が非常に重要なのだと改めて思わされる。
本書は、危機管理から組織のあり方を論じている本である。
(危機に瀕した際に)もしもトップの指示がなければ、何事も前に進まないような組織だとどうなるか。確固たるリーダーシップとは無縁の調整型の人物がトップの場合には、目も当てられない状態になるはずだ。
危機管理のために特別なことをする必要はありません。普段の仕事で活力が溢れている組織は危機管理にも強いということです。
「組織として何をなすべきか」その本質の「なぜ」の部分を、組織を構成する個々の人員がきちんと理解している組織は強い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
