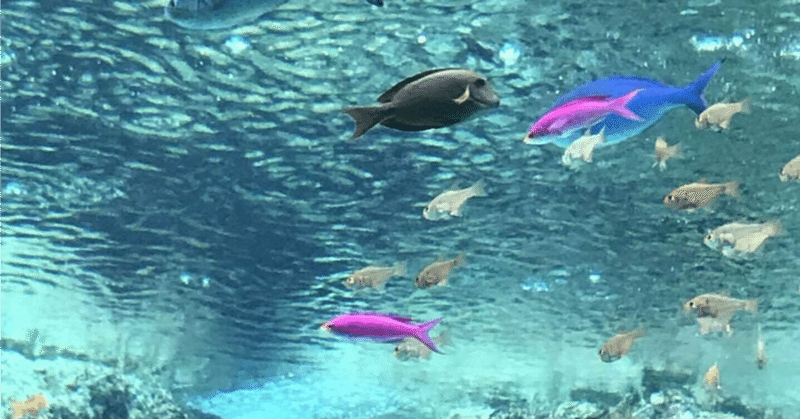
小説「マリンパークと男たち」 住野アマラ
私はサークル型の歩道橋の上からスクランブル交差点を見ていた。
たくさんの人が信号の変わるのを待っている。
街の出す音の種類変わり歩き出す人々。
黒の集合体の輪郭が滲む。
行きかう人波が一塊の魚群に見えた。
一斉に向きを変える魚たち。
銀色の横っ腹と小さなまん丸の目。
個々の意思ではなく、一つの生命体として生きる者たち。
彼らは出口の無い水槽の中にいるのだと気づいていない。
私も群れの中で、知らず知らずに向きを変え、知らず知らずに流されているのかも知れない。
私の家の近くに湘南マリンパークという古い水族館があった。
水族館は五十三年前に開園し、長く地元住民らに親しまれてきた。週末の家族のお出かけの場所、小さな恋人たちのデートスポットとして密かな人気があった。
しかし昨年、入場者数の低迷と建物の老朽化が要因となり惜しまれつつ閉園した。
最終日までの数日間、閉園のニュースを聞きつけた人たちが押し掛け入場制限が設けられるほどの混雑ぶりとなった。
焼きそばやアメリカンドッグを売る店には長蛇の列が出来ていた。いつもは閑散としているお土産店も人手が足りず、ゴム長靴を履きカワウソ担当とネームプレートがついた飼育員までもが駈りだされ働いていた。
花壇の縁に座る女の子は、日差しが眩しい
らしく顔をしかめながら傾いたソフトクリームを舐めている。その横に座る若いママはかなりお疲れのご様子でベビーカーを揺らしながらも項垂れている。その隣に立つパパもペンギン型のゴミ箱に片肘をつきスマートフォンを操作している。時々顔を上げては混雑する園内を見回しだるそうだ。
行き場を失い蠢いている多くの人が今日ここへ来た事を後悔しているように思えた。
故障中と張り紙されたポップコーンマシンは売店の片隅で埃を被り、瓶入りコーラの自動販売機は錆つき園内の片隅に追いやられている。それはレトロと言うよりかは、一つの文明が滅びた後の遺跡の佇まいを呈していた。
「昔、小さい頃よく来たな~」「このゆっくりとした雰囲気がいいわぁ」「やめちゃうなんて残念」「もっと頑張ってほしいぜ」などと閉園を惜しむ客も、恐らくここ何年もこの水族館を訪れていない人たちだろう。
だが私は違う。私は昔から「湘南マリンパーク」が好きだった。週二・三回は通っていたし、年間フリーパスの更新だって三十年間連続の皆勤賞だ。
マリンパークの敷地は海に面しており海風香る絶景ビューポイントが点在していた。離れて建つ建物の間に広々した芝生やベンチがあって寛げる事が出来た。
円形状の「ファンタステック劇場」では迫力満点のイルカやアシカのショーが毎日行われ、皆の人気者「ペンギンアイランド」のペンギンたちへの餌やりの時間は大騒ぎだった。
メインの建物である「魚ワールド館」には地元生育の魚やカラフルな熱帯魚、クラゲ、怖顔の深海魚などの泳ぐ水槽が30槽ほど展示され見応え充分だった。マリンパーク内で一番広く、種類と珍しい魚の数々に子供も大人も専門家さえも感心する展示がずらっと並んでいた。私は中でもチョウザメを見るのが大好きだった。幼いながらも太古の昔から姿を変えていない古代魚に憧れを抱いていたのだ。
薄暗くひんやりした館内に一歩足を踏み入れると、そこは別世界。海の世界、魚の世界だ。
ゆっくり見るもよし、語らうもよし、長い廊下を駆け抜けるのもよしだ。
二階の「回遊式水槽」も私の大の、大のお気に入り。
広い室内の壁一面にドーナツ型の水槽が設置され、360度の視界で魚たちが泳ぐのを眺められる大パノラマの展示だった。
回遊式水槽は、かつては東洋一の大きさを誇り「魚との調和」を理想としたこの水族館の目玉であった。
客の靴でこすれ色褪せた硬い床をコツコツと歩くと靴音が深海に響くソナー音のように聞こえた。水槽の丸みに沿って魚たちと同じスピードで歩いてみる。すると次第に魚と呼吸が合って来る。魚たちと海の中を泳いでいるような気分になってくる。
私は気分が沈んだ時や悩み事がある時など、必ずここで気持ちを落ち着かせていた。
マリンパークは私の精神安定剤的存在だった。水槽の前に来れば細胞の一つ一つが喜び、生命力が湧いてきたものだ。
よちよち歩きの私が父の手を引っ張って、回遊式水槽の周りを何周も何周も歩き父を困らせていた事があったと母がいつだったか話してくれた。
マリンパークからバス停二つ離れた所に私の生まれた時から住んでいる古い家がある。祖父母は早くに他界していたが元は母の実家だった家だ。
母は古民家を改装し、一階を店舗スペース、二階を住居にして小料理屋を営み生計を立て私を育ててくれた。
私は小学校から帰るとすぐに赤いランドセルをほっぽり出して店へと降りて行き、母が働くのをカウンター越しに見ていた。
母手作りのふきの煮物や具沢山のポテトサラダなどが次々と大皿に並べられていく。
私は自分用に取り分けられたおかずでごはんを食べ勉強をした。お小遣いをくれる近所のお客さんもいたし、宿題を手伝ってくれる常連さんもいて店はいつも賑わっていた。
父の記憶はない。
物心ついた頃から父はいなかった。
私が四才の時に父は店と家族を捨てて家を出て行ったらしい。
父と過ごした記憶もないし、父のいない生活が私の日常だから悲しいとも何とも思っていない。
どうして出て行ったのか、今、父はどこにいるのか。母は父の事をあまり話さない。
「海洋学者で写真と山登りが好きな男だった」とだけ聞いている。
ある日、煙草を買いにふらっと出掛けてそのまま帰って来なかったとか、他に女が出来たとか、外国に暮らしているだとかいう話を店のお客さんや近所のおばさんから漏れ聞いた。本当の話なのかは分からない。全部本当かも知れない。
ただ、母の和ダンスの上に飾られているヒマラヤ山脈の古ぼけた写真を見ると、父が撮影した写真なのかも知れないなと思ったりした。
その母も四年前に肝臓がんで亡くなった。年末に調子を崩して検査入院した時には癌は最終ステージで手の施しようもない状態だった。一か月も経たない内に危篤になり、具体的な会話もないままのあっという間に死んでしまった。
今は、私が母の残した店を無国籍カフェへと改装し営業している。
母と私がいつか二人でこんなカフェがやれたらいいねと夢見ていた理想のカフェだ。
世界を旅するバックパッカーが集う安宿のロビーをイメージした店内。異国の地で味わうような美味しい食事と時間を提供する。
天井からぶら下げた古いオイルランプや木目調の床や壁などで山小屋っぽさも醸し出す
ふかふかのソファーにモロッコ製のファブリックを敷き、所々にタイやバリ島の木彫りの雑貨を配置。コーヒーカップや平皿は素朴で温もりの感じられる和食器を使っている。
アジアンなテイストと中東などのエキゾチックな雰囲気とを和の温もりでまとめあげた母と私の理想のカフェに仕上がったと自負している。
いつか私があの世へ逝ったなら、夢のカフェ実現の中で予想外に苦労した、あんな事やこんな事を亡き母に報告したい。
メニューの種類はさほど多くないが、ドリップコーヒーや手作りのスパイスティーがおすすめ。
水を一滴も使わないで作るパキスタン風チキンカレーも自慢の一品。大量の油で鶏肉を柔らかくホロホロになるまで煮込み、そこに配合を工夫したスパイスを投入。トマトと玉ねぎの水分だけでじっくり仕上げていく。
チキンカレーはSNSなどで高評価を貰い、店の評判も上々、経営は波に乗って……というのは去年までの話。
昨年のマリンパークの閉園で、この店の状況は一変した。今では一人の客さえ来ない日もある。かつてのマリンパークの影響は大きかったのだ。
水族館の閉園後の跡地は海の見えるキャンプ場へとリニューアルされた。最近はキャンプが人気なようだ。キャンプ場に来る人達はカフェには来ない。
時は流れ、小料理屋の頃からの常連客も年を取った。
店の改装費はまだ回収できていないというのに、このままだと店を手放さなければならないかも知れない。そうなれば私は仕事も住む場所も思い出も何もかも失ってしまう。
仕込みから接客、トイレ掃除まで、何でも自分一人でこなさなければならないので起床時間は早い。近所の漁師さんと同じぐらい。早朝から準備して十一時半に開店、夕方は十八時頃に閉店とさせる。
店の名前は【カフェ・ゆうき】
店の前に出しているスタンド型の看板には平仮名で「ゆ・う・き」とだけ書かれている。
しなだれ斜に構えた字で書かれた字体の看板は、母が「小料理屋ゆうき」をしていた頃からの物をそのまま使っている。
店名と私たちの名字は同じ。
母の名は結城葉子で道子がわたしの名前。
苗字と店名を同じにしてあると都合が良い。
店と自宅の電話を共通に出来る。
「はい、もしもし、ゆうきです」と電話口に出れば、学校のPTAからでも忘年会の予約電話でもどちらでもいいわけだ。
この辺りは夕方を過ぎると釣り人や観光客がいなくなって人通りがまったく途絶えてしまう。近頃は日が暮れるのも早くなったし、
今日も早めの店仕舞。
看板の電気を消し、コンセントを抜く。重い看板を引きずるようにして店の中に運び入れる。今は一人で。
ある日所用で都内へ出かけた後、私は無性に魚たちが恋しくなり、今までは訪れる事も無かった規模の大きい有名な水族館へと出かけた。
私は水族館が好きなのじゃなくて、マリンパークという水族館が好きだったのだ。だが背に腹は代えられない。鰻だって関西に行けば腹開き。郷に入れば郷に従えの覚悟で電車を乗り継ぎ、数駅先の水族館のある施設へと向かった。
その真新しい近代的な水族館の床はホテルのラウンジでも気取っているのか、柔らかい素材で出来ており靴音がまったくしない。マリンパークの硬い床のようなロマンがない。
握った砂が指から零れ落ちるような環境音楽が流れているが、魚を見るのに音楽が必要なのか?
通路は水槽内の照明だけでやけに薄暗い。天井からのトップライトが床に丸い光の形を所々に作っているが、それ以外は明るさが抑えられている。
どういう仕掛けなのか、その丸い光の中に入ると周りの音が一切聞こえなく感じがして静かになる。まるで光のバリアーの中にいるようだ。丸い光から出ると館内の騒めきが一気に戻る。
遠足の子供たちだろうか、小学生のグループが数人いて賑やかだ。透明度の高い水槽のガラスに小さな手を当て熱心に魚を見る子も、はしゃぎ回る子も楽しそう。
水槽は生息域と種類別に分けられ、縦に細長い水槽もあれば、筒状の水槽、ドーム型の水槽もある。今の技術ならマリンパークの建設当時よりも遥かにガラスの強度は上がっただろうし、透明性も優れているからどの展示も見易くはある。マリンパークは長く広い廊下だったが、ここはもっと入り組んでいてプライベートな空間作りを目指しているらしい。通路がS字に曲がりくねり、その細い通路を抜けると正面に大きな水槽があった。
頭の片隅で予想はしていたが、この水族館にもチョウザメがいた。久しぶりのチョウザメの姿に私の胸の鼓動は高まり、真綿に包れるような懐かしさでいっぱいになった。
鼻孔から細く息を吸い水槽に近づく。
あー、やっぱり私はチョウザメが好き。
かなり大きい水槽に数匹のチョウザメが泳いでいた。その中の一匹に目が釘付けになった。
「あれ?この子…」
マリンパークにいたあの子に似ている。私が幼い頃から大好きだったあのチョウザメに…。
私は周りに人がいなくなるのを待って、水槽に顔を近づけ声をかけた。
「チョウちゃん。チョウ太郎。私だよ。道子。ミッチーだよ。こっち、こっち」
そうだ。チョウ太郎だ。間違いない。
あの尾びれのカーブや愛嬌のある顔に確かに見覚えがある。
ここに引っ越して来ていたんだ。
良かった。本当に良かった。
しかし、しばらく見ているとチョウ太郎は他のチョウザメと違って、どこか動きがぎこちない。他のチョウザメたちは大きな水槽いっぱいを使って伸び伸びと泳いでいるのに、この子は短いスパンですぐにターンを繰り返してしまう。マリンパークの小さな水槽で育ったからその癖が抜けないのだろうか……。
チョウザメの寿命は長い。三十年から五十年は生きる。新しい環境に慣れてどうか幸せに暮らしていって欲しい。
私は大切な友を置いてきてしまった寂しさを胸に水族館を後にした。
すぐに家に帰る気持ちになれず、どこかで何かを食べようと駅の近辺を歩いた。だが都会の人ごみを避けて飲食店街の裏手を歩いていたら、いつの間にか行き止まりの路地に入ってしまった。どうやら日本料理屋の私道らしく路地の奥に高級車が数台停まっている。ちょっと名のある日本料理屋の専用駐車場らしい。
店の裏口の段差に座る白衣姿の板前が、手にスマホを持ち、所在無げにぼんやりと空を見上げている。恐らく昼営業と夜営業の合間の小さな休憩時間なのだろう。
板前の細く筋張った腕や力ない頬がすごく疲れて見えて「あの板前さんは何時まで働くのかな」と思わず考えてしまった。
この人も一流料理店と肩を並べる店をいつかは持ちたいと夢見ていた青年だったのかも知れない。
唾を飲み込むとこめかみに金属的な痛みが走った。少し疲れた。皆疲れている。誰もが疲労している。チョウ太郎も板前さんもこの街も。
ビルとビルの隙間からかろうじて夕暮れの空が見えた。空は徐々に明るさを無くし、ブルーグレーの物憂げな色へと変わってゆく。さらにサファイヤブルーの青・青・青へ。
街が、人が、瑠璃色に染まってゆく。
私はこんな所で一体何をしているのだろう。家に帰ろう。抜けられる道があるのかも知れないが私は元来た道を引き返した。駐車場から先の、あるかどうか分からない道を探す元気はない。
大きな通りに戻るとすでに夜の混雑が始まっていて幹線道路は大渋滞。車と街の出す音の渦の中で溺れてしまいそうだ。
のろのろと進む車が赤信号でブレーキを踏み、赤色のテールランプが一斉に強く光った。
かがり火の様な赤い光はどこまでも続き果てしない。
私は何も食べずに家に帰ろうと思った。
私は母に死なれ、共に育った魚たちと生き別れ、やがては仕事も失うだろう。
私が私から遠ざかってゆく。
この世の中で寄る辺ない夜を過ごす人間は私だけじゃない。寂しさに耐えて生きている人は他にもいる。馴れればいいだけだ。失う事に馴れる。それが人生なのだ。
でも、それでも何かを取り戻したいと思った。奪われるだけでなく、少しでもいいから取り戻したい。私の愛したあの空間と空気を。
私は自らの手でマリンパークを再現しようと思いついた。
やってみよう。愚痴をこぼしてばかりいても仕方がない。
まず手始めに業務用の水槽を注文した。
中古品ではあるが、横幅百八十センチ、奥行き八十センチ高さ六十センチの巨大水槽だ。
運搬費を含めてかなりの出費になってはしまうが仕方がない。マリンパーク再現の夢は私に生きる力をくれる。
初秋の爽やかな午後だった。
矢崎水槽と書かれたトラックが店の前に到着した。
「どこに設置しますか?」
「二階へお願いします」
「二階ですか?また動かすとなると大変ですよ」
「ええ。でも自宅用ですので二階のリビングにお願いします」
矢崎水槽の運搬の人は水槽がかなりの大きさだし、水を入れれば相当の重さになるので店舗用だと思っていたのだろう。
水回りと補強工事をする場合はご連絡下さいと名刺を置いて帰って行った。
でも必要ない。
これでいいのだ。
これでおしまい。
水槽に水は入れないし、熱帯魚も水草も何も入れない。水槽だけがあればいいのだ。
私は水槽の中に入った。
身を屈めて底に肘をつきリビングを一望、見渡した。
ああ、私は魚になった。
いつも眺めていただけだった水槽の内側から魚と同じ目線で世界を見る。この水槽が、ここが、私の本来いるべき場所なのだ。さらに狭い水槽の中で身をよじり体勢を上向きに変え横たわった。
目を閉じて、深く呼吸する。
背中に触れる底板が次第に自分と同化し、私の身体は深い海の底へと沈み込んでいくようだ。
小波が私の身体を揺らす。
どこからかソナー音が聞こえる。
深海の魚が尾びれを動かし砂を舞い上がらせる音。
波のゆらぐ音。
その中の低いチェロの音のような響きはクジラの歌。海底で奏でられるクジラたちの交響曲。
イルカやクジラは様々な周波数の高さで空気を震わせお互いに会話をするそうだ。
ギリギリときしむような声やピュウピュウと笛を吹く様な声。
世界一孤独なクジラの話は一体誰から聞いたお話だったろう。その孤独なクジラの持つ周波数は非常に珍しく、あまりに独特なので他のクジラたちの誰とも交信できないそうだ。
どこからか打ち寄せる小波に聞いた不思議な海の話。
こうやって水槽の中にいると、とても心が安らいでくる。自分だけの特別な場所を私はとうとう取り戻した。
マリンパークが閉園して海に放たれた魚たちは今どうしているだろう。生まれて初めて泳ぐ大海に戸惑っただろうか。それとも初めての自由な世界を知り喜んでいるだろうか……。
そうだ、もう一つ水槽を購入しよう。
もう一つ、もう一つと水槽を増やし部屋をいっぱいにしていくのだ。私は水槽に囲まれて暮らす。
今までもこれからも、ずっと、あの頃のように…。
相変わらず客の少ない日々が続いていた。
持て余す時間に疲労した自分を癒すべく、店先でサンダルウッドの香りの線香に火を点けた。天然の成分を染み込ませた線香は火がつきにくいが香りが優しい。
先端に火をつけ、8の字を描くように動かすと煙がたなびき龍の飛ぶ姿のように見える。
視線のフォーカスを煙の向こうに向けると道の反対側に一人の若い男性が立っていた。
木漏れ日の中に立つ男性の顔半分が陰になっていて表情はよく分からないが、どうやらまっすぐにこちらを見ているようだ。
何となく私も気になって、男性の方を見ていると、その男性は優雅な足取りでこっちへ向かってきた。
「まだ営業していますか?」
彼の口調はとても静かで物腰は柔らかだった。こういう声が上品なお声というものか。
男性のやや色素の薄い瞳は円らかで大きく、日本人離れした立体的な顔立ちだった。
「あ、はい。あ、営業中です、あ、どうぞ」
私は彼の佇まいに何故か気持ちが慌てた。彼の風格はまさにこの店にふさわしいものだった。
顎髭を生やしはいるが中性的なオーラを身に纏い、細身の身体に白いダブダブしたシャツにダルダルとした麻のパンツを履いている。多分、あのパンツはタイパンツだ。頭にエスニックな布をターバン風に無造作に巻きつけ、くたびれた革のサンダルをつっかけてと、まるで本物の放浪の民みたい。
年齢は多分三十代前半。私よりは少し若そうだ。
彼は壁際のテーブル席に足を組んで座り、腕を高く上げて袖をまくりメニューを開いた。注文を悩んでいるのか丹念に時間をかけメニューを見ている。
様子を見てからしばらくして声を掛けた。
「…あの、お決まりですか?」
「ああ、日替わりのカレーとチャイを下さい」
今日の日替わりランチは鯖とトマトのカレー。
何だ…。もう決まっているなら早く注文すればいいのに……と、不思議な人だとこの時少し感じた。
私は仕込んであるカレーを温め直しサフランライスにたっぷりと掛け、キャロットラぺと紫キャベツのピクルスを副菜に添えて出した。普段はあまりしないが初回サービスとしてビーツのポタージュスープとかぼちゃのフリットもおまけした。
彼は黙々と、淡々と、そしてゆっくりと、カレーを一匙一匙丁寧に食べ進めた。サラダをしっかりと咀嚼し、チャイをこれまた少しずつ飲み、最後に大きなため息を吐いた。
私がお皿を下げようとしたら、彼はとても優しく微笑み「ごちそうさま、この店はいい店だね」と爽やかに言うので私の好感度は爆上がりだった。
そして、かれこれ、ランチを食べ終わってから四時間…。もうすぐ閉店時間だ。
馴染みの常連客と市が企画した【ごちそう周遊きっぷ】を使って来店する客も数人来て帰った。
その間、彼は追加オーダーをするでもなく、店に置いてある本を読み漁り、窓から見える夕日に目を細め、すっかり自分の家にいるかのように寛いでいる。十八時の閉店時間を気にする様子は感じられない。
こんなに長居する客も珍しい。
もう閉店時間だと告げようと近づくと彼はおもむろに立ち上がった。中々タイミングが独特な人だ。
そして「この店は本当にいい店だね」と言い、千百円ぴったりの代金をテーブルに置いて店を出て行った。
次の日、開店と同時にさすらいの彼は再びやって来た。「やぁ」と両手をパンツのポケットに突っ込みながら微笑みを携えて。
昨日と同じ席に座った彼は、カウンター上の黒板のメニューをじぃーと見ている。メニューを読んでいるというよりも絵を眺めているような仕草で人差し指を立て片目など瞑って見ている。私は距離を置き、なるべくさりげない感じで彼を見ていた。
彼は顎髭を引っ張りながら首を傾けた。
「あの日替わりのちきそと蕪のカレーって何かな?」
「それはチキソではなく、チキンです」
日替わりのメニュー名は私が黒板に手書きで書いている。オサレなデザイン文字とイラスト入り。
「え〜、ん?ンじゃなくてソだよ、あれは」
彼は鼻をフフンと鳴らし「じゃあ、そのチキソ頂戴」と澄まして言った。この客は服装が変わっているだけでなく性格も少し変わっている。
私は伝票に「日替わり、とり」と雑に書きなぐり、変人男の横顔を睨みつけてキッチンへと引っ込んだ。
もやもやとした気持ちを抑えながらカレーを皿に盛りつけ、軽快にフロアーを横切り、つま先立ちで日替わりのカレーを彼の前にすっと置いた。
「どうぞ~」と口角を上げながら、余裕で。
彼は昨日と同じように腕を高くつき上げてシャツの袖を捲り、カレースプーンを手に取った。
それから昨日と同じく時間をかけてカレーを食べ進め、最後に骨付き肉をぐぅわしっと食いちぎり「旨い!」と唸ったから、私は本当にびっくりした。個性的な人だ。
そして案の定、閉店時間まで居座って……その帰り際だった。
「あ、そうだ…俺、今日お金持っていないや」
はぁ?
「クレジットカード各種もお使いになれますよ」
私はなれますよ、の「よ」を丁寧に発音した。
「いや、財布ごと持って来なかったから。無いの。何にも」
ええ?
「取りに行くのも面倒だから貸しといてよ」
なぁ~にぃ~‼男は黙って食い逃げか~‼
「明日、また来るからさ」
そう言って彼は悠々と森の方へ歩いて行った。
今日は「この店はいい店だ」とは流石に言わなかった。私は狐か狸に化かされているような気持ちになった。
まったく今時こういうケースも珍しい。
店の裏側から小網代の森が見える。
小網代の森は面積約七十ヘクタールの貴重な緑地で生物多様性の宝庫である。この森の中には、長さ一キロほどの川の源流が流れ、湿地や河口の干潟などを形成しながら海まで流れている。絶滅危惧種も含めて二千種類以上が生息する自然豊かな森なのだ。
フクロウや狸もいるだろう。
まさか、あそこに住む狸が…。
そういえば目の周りが黒い感じだったもん。
想像すると可笑しくて一人で大笑ってしまった。
でも、ま、おそらく、明日も彼はここに来てカレーを食べることだろう。
彼は悪い人ではなさそうだ。そう感じた。遠い昔のいつかどこかで私たちは出会ったことがある……うん、そう、そんな感じ……懐かしさに似た不思議な感情……。
私も結構イケメン好きのお人好しちゃんね。
これじゃあ、アイドル好きの智美を馬鹿に出来ないわ。
智美とは小学校も中学校も高校も一緒の幼馴染み。
智美は旦那を放ったらかして、年がら年中コンサートを観に行くべく全国を行脚している。その為に生れてきたかのような熱中ぶりだ。いつも手の込んだ推しのアイドルのうちわやボードを作成して忙しくしている。そんな彼女の明るさやバイタリティに助けられる事が多い。
明日は玉子とポークのカレーにしようっと。
でも次の日、放浪の彼は現れなかった。
がっかりしたが、きっと明日は必ず来るはずだ。きっと何か事情があったのだと思った。
だが、無銭飲食の彼は何日経っても現れなかった。
智美にはまだこの一連の出来事を話していない。まだ話さない方がいいような気がした。話したらきっと私の学生時代の失敗談を蒸し返しかねない。
それに不思議なことに騙された事に憤りは感じていない。逆に気持ちは精妙なオイルのように軽いのだ。
彼に出会ったあの日から店の雰囲気が変わったように感じた。大きな変化があった訳ではないし、店の客が増えた訳でもないのに店の空気が違う。
私自身も前より人の話に耳を傾けるようになった。自分の意識のチャンネルが変わったような感じだ。思えば私は人の話を聞く受信機を今まで使っていなかったのかも知れない。
月曜日の午後、一人で初めてこの店を訪れた初老の男性の話…。
男性は取り憑かれたようにノートに何か書いている。しばらく書いては手を止めて考え込んでいる。
私はランチについているコーヒーのお替りを勧めた。数字の羅列がちらりと見えた。計算式のようだ。
「コーヒーのお替りはいかがですか?」
「すまんね、すぐお暇するよ」
「いえいえ。構いません。ゆっくりしていって下さい」
「世紀の難問に取り組んでいるものでね、つい時間を忘れてしまった」
「何かの研究ですか?」
「一度迷い込めば抜け出せぬ魔宮の研究でね」
「え?」
「ハハハっ、大げさな物言いだけどね」
聞けば数字の素数の研究だそうで、リーマン予想という世界でも有名な難問の一つだそうだ。
百五十年もの間、世界中の多くの数学者がこの難問に取り組んだ末に人生を狂わせたという。
証明されれば宇宙と大自然の仕組みを知る大きな鍵になるのだと老数学者は語った。簡単そうに見えて実に捉えどころがないのだとも。
私は数学どころか計算が苦手で店の経理に苦労しているのだが、老数学者の話にはロマンを感じた。
「いやいや、そんな良いものじゃないよ。この問題を解こうと精神を病んだ人や生活が滅茶苦茶になった数学者がたくさんいるんだよ。孤独な私もその一人さ」と露数学者は自嘲するようなため息を吐いた。
「だが、しかし素数の魅力に人生を賭けて悔いは無いがね」
老数学者はカップに残ったコーヒーを飲み干して席を立った。その背中は少し寂しげに思えた。
何日かして私は図書館に行ったついでにリーマン予想に関連する本を手に取り読んでみた。全く理解出来ないながらも自分も数学の神秘に少し触れたように感じた。
きっといつかは答えが見つかるだろう。
果物が大好きで三食とも果物でもいいと語る男性の食の話も考えさせられた。果物はいくら食べても食べ過ぎと言う事はなくて、健康にも美容にも良いそうだ。確かにフルーツ男子の肌は艶々している。私も食習慣に果物をもっと取り入れようと思った。
この辺りでお嬢様学校として有名な女子高に入学したての女子校生の話も面白かった。今時はワイヤレスイヤホンをしている客も多いのだが、その細身の女性の耳にはめているのは黄色の耳栓だった。珍しいなと思い声を掛けたら、自分は音に異常に過敏なので外出する際には耳栓が欠かせないのだと説明された。
それから彼女は人差し指を両耳に突っ込み
「ほらね。こうやると凄く楽ですよ」と私を促す。
それで私も両耳を塞いでみた。
「あーなるほど、本当だ……楽です……ね」
自分の話し声がいつもと違って聞こえた。くぐもって聞こえた。水の中で話しているみたいだった。
賛同を得て嬉しそうな彼女は左足にギブスをして、顔にも絆創膏をしている。
彼女は子供の頃から自転車のブレーキをかけるのが嫌いで、いつも壁に激突して止まっているそうだ。どうしてブレーキをかけるのが嫌いなのか、どうして大人が注意しても直らないのか。
彼女は「自分でもよく分からないんです。フフ」と上品に微笑む。
ひょっとしたら彼女は将来大物になるかも知れない。何はともあれ無事を祈るばかりだ。
また、ある小春日和に…。一人の中年男性が……。
「あの、ビスケットとか売っていますか?」
「クッキーでしたら、こちらにありますけど」
「あぁ、プレーンなのを下さい」この中年男性はこの辺りをトレッキングして楽しんでいるようだ。出で立ちでそれと分かる。
中年男性は帽子を取り、空に向かって振り回し、「お〜い、こっちだぞ〜」と砕いたクッキーを地面にばら撒いた。どうやら鳥に餌をあげたいらしい。
男性は「お〜、みんなサンキューサンキュー」と、集まってくる鳥たちに満面の笑み。
餌をやり終わった男性は店に入って来て、アイスコーヒーとベイクドチーズケーキを注文した。ケーキも私の手作り。
「鳥がお好きなんですね」と私は話しかけてみた。
「いや〜鳥達が僕に挨拶して来るもんですからね~。困っちゃうんですけどね。でも返事してあげないと可哀そうだから、それでなんですよ」
あ、なるほど。
「街なかで、車に乗っている時でもあいつらお構いなしで挨拶して来るから大変でね…」
ほー。
「この辺はもう忙しいよ本当、鳥達が大勢いてね、ハハハ」
ハハハ。
「だけどね、鳥達からこんなに挨拶される人間なんて珍しいでしょ?」
そりぁ…ま。
男性は実は面白い話があるんですよと話し出した。
「この間ね、ある禅僧に相談しに行ったんですよ…」
男性は東京の青山に住んでいるそうで、仕事は鳥使いではなく不動産関係だそうだ。
その青山の自宅兼仕事場の近くの禅寺に、ある高名な禅僧が講演に来るという話を聞きつけたのだそうだ。
一般向けの講演ではないという事だったが、いい機会だと思い禅僧が寺から出てくるのを待ち続けたのだという。
男性は高僧が出てくる当てもないのに待ち続けた。時折都会の鳥たちががんばれがんばれと応援してくれたので持ち堪えられたそうだ……。
しばらく待って、もう諦めようかと気持ちがぐらついた。だがもうちょっとと思った次の瞬間に門扉が開き、中から一人の禅僧が出てきた。
禅僧は年配ながらも背丈が高くがっしりとした体格で姿勢はまっすぐ。風格からして噂に聞く高名な高僧だと男性にはすぐに分かった。縁取りでもしてあるかのような強い目の印象。表情から急いでおられるのが感じられたが、男性は意を決し話しかけた。
男性は「鳥たちから挨拶されるのは、どこか自分が異常なのではないか」と問い掛けた。
禅僧は一言も挟まず耳を近づけて彼の話を聞いてくれたそうだ。そして禅僧は聞き終わると同時にただ一言「普通じゃ」と言い放ったそうだ。男性は面食らった。
普通…。
普通という言葉だけでは納得できない男性は透かさず「他に自分と同じ悩みを抱えた人をご存じですか?」と畳み掛けた。
男性は禅僧の深い知識に裏付けされた見解を期待し、次の言葉を待ち固唾を飲んだ。
禅僧は男性の顔を正面から見据え、大きく息を吸い、肚に力を込めた大声で「わしじゃ」と即答、男性を一喝した。
男性がその勢いに押されて何も言えずに直立していると、禅僧は一陣の風が吹き抜けるかの如く門前の車に乗り込み瞬く間に去って行ったらしい。
わしって…。
「わしって、自分の事ですもんね…」と男性は首を捻りながら、いたって真剣にお悩みのご様子。
私は聞いていても笑いを堪えるのに必死だった。
男性はきっと自分が特殊な能力を持っていると信じ込み、他人とは違うという優越感を誇示したかったのだろうと私は思う。
禅僧は、そういう心理を戒めるために「普通」だと言ったのではないだろうか。
人と自分を比較するな、差別化するな、誰でも同じ人間だという意味で「わしじゃ」という言葉になったんだろう。
うんうん。まさに「普通じゃ」「わしじゃ」のその二言に尽きる。私には禅僧の簡潔な回答は的を射た答えだと思えた。
しかし男性の心には禅僧の意図する意味合いが届いていないようだが…。
私が「すごく面白い話ですね」と言うと男性は喜んで、また妻と来ますと言って軽やかに帰って行った。
閉店後に一人で夕食を食べてお風呂に入る。厳密に言うと一人ではなく一人と一匹とで。
私は二才になるオス猫のマー君と暮らしている。ネコカフェで出逢った元保護猫である。
マー君は私の食事するのを向かいの椅子に座りじっと見ている。
今夜はしらすと茄子の煮浸しに小松菜ごはんと鯖缶の味噌汁。母がよく作ってくれたレシピだ。
マー君は私が風呂に入れば自分も張り切って浴室に入って来て、水たまりに浸かる奇妙な生き物を怪訝そうに見つめてくる。猫は毛や足が水に濡れるのが苦手だから物凄く嫌そうにしている。嫌なら来なきゃいいのに、毎日同じことをする。
「犬は人につくけど、猫は家につく」とはよくいったものだ。猫は縄張りやルーティンから外れるのが得意ではない。
店を閉めて引っ越したらマー君はびっくりするだろうな……。
ふと、母の店仕舞いの音を思い出した。
暖簾を仕舞い、看板を片付け、椅子をテーブルの上にガタガタと乗せる音。おしぼりウォーマーのスィッチをパチンと切る音。階段をバタバタと登る母の足音……。
風呂場の窓から海の音が聞こえる。
潮の目の変わる音が聞こえる。
目を閉じて深く聞く。風の音か、波の音か。
昔から耳を澄ます癖がある。
何かを思い出そうとしている。
はっきりと思い出せない昨夜の夢の続きか
母の胎内で聞いた音。
血管を流れる血の音は潮騒の音に似ているのかも知れない。
生命の源の海に浮遊して聴いた原子の鼓動。どこかで潮が引けば、どこかでは満ちる。
懐かしい場所。風景。
懐かしい場所。時を刻む波の音……。
お風呂から上がると、マー君は早くも寝る支度を整えて私のベッドに横になり待っていた。
「マー君、今日は土曜日だからね、まだ寝ないよ」
と言うと、マー君は「ウルルン」と甘えたような声で鳴いた。
母の化粧台の引き出しに、青色の封筒が入っている。中には薄い水色の便箋。父からの手紙だ。これを見つけたのは母が亡くなってからすぐ。
それ以来、時たま取り出しては読んでいる。
「葉子へ
君たちを捨てて出て行った僕にこんな手紙を書く資格はないね。だが、この手紙が最初で最後だから許して欲しい。道子は大きくなっただろう。街ですれ違っても分からないだろうな。
俺は余命宣告を受けた。肺がんの末期も末期。非常に進行の早い癌だそうで、医者もびっくりしている。ⅭTを撮ったら一か月で癌は一センチ以上も成長していた。だが抗がん剤治療を受けてどうにか半年くらいの時間の余裕を貰った。
酸素ボンベは必要だが、それでも呼吸ができることがこんなにも有り難い事だとは思わなかったよ。
常に呼吸は苦しいし、時折、胸を貫かれるような痛みがある。レベルの違う痛みだ。これまで経験したことのない次元の違う苦痛だよ。
普段、死を覚悟しているつもりでも、いざ本番となると駄目だね。身体ごと重力を失い、生と死の実感そのものが失われていく。
しかし人生の重荷をこれでやっと下ろせるのかと思うと、正直ほっとする気持ちもあるんだ。
あの世があるかどうかはどっちでもいいし、人は死んだらおしまいだ。何もかもが無になる。そう思っていたよ、今までは。
夜、病室のベッドの上に横になり瞼を閉じると目の前に星空が浮かんでくる。
いや、はっきりと見える。君と見た穂高連峰の星空と同じような満天の星空。
そして、その星の輝きを一つ一つ数える。自分が宇宙の元素の一粒だと感じながら。
それが今の僕の一番の楽しみさ。
君たちを置いて家を出た事は後悔していない。
だが最近、君と初めてデートに行った城ヶ島をよく思い出すんだ。
君は白いワンピースを着ていて、とても眩しかった。君の笑う顔。灯台の横で長い髪をなびかせながら振り向く君。
あの日の空は澄み渡り、遠くに房総半島まで見えて気持ちが良かった。
僕はバスのつり革につかまりながら、いつ
君の手を握ろうかとそればかり考えていたよ。
ふいに君がクスクスと笑って、何が可笑しいのかと僕が聞いたら……。
「このバスね、橋の手前で急カーブを曲がるの。そしたらね、つり革がね、カチャカチャって、フフフ、ぶつかってカチャカチャって、ぶつかって音がするのよ。面白いのよ」
そう言って、クスクス笑う君があまりにも可愛くて…。
僕は、君の話を聞いた後のあの日の記憶が全く無いんだ。変だろ?
君たちの元へ帰るつもりだった。
でもある日、インドネシアのある島の片田舎で大雨に打たれていた時に気付いてしまったんだ。
あまりに年月がたち過ぎたと。
とにかく君と道子の幸せを願っています。こんな男ですまん。
今は病院から一時退院して自宅に帰って来ている。これから布団に入るよ。目を閉じれば闇の中に星空が見えるだろう。今までの死生観を百八十度変える星空は毎日広がり続けている。今夜も俺は心の中のプラネタリウムを見続けて眠りにつくことだろう」 龍彦
便箋を封筒に戻し、引き出しを閉めた。
私はリビングの真ん中に置いてある水槽の中に入り横たわった。
マー君がベッドから下りてきて不思議そうな顔をしながらガラス越しに私を見ている。
人間って何で泣くのかな?とでも思っているのだろうか…。
私は「何でなんだろうね、マー君」とガラスを挟んでピンク色の鼻先を指先でタッチした。深く呼吸しながら目を閉じる。涙が頬を伝い水槽の底に落ちる。
私にもプラネタリウムの星空が見えるような気がした。
ボヘミアンの彼はあの日から一ヶ月ほどして「やぁ」と微笑みながらやって来た。悪びれもせず前と同じ調子で現れた。
私も同じ調子で受けてたつ。
今日の日替わりのカレーは茄子と挽き肉のキーマカレー。
彼は日替わりのカレーとチャイを注文した。
閉店時間ギリギリになってから彼は口を開いた。
「一緒にインドに行きませんか?」
「え…インドって、あの本物のインド?」
「そう、インディア、インド共和国」
「私のカレーが美味しいから??」
「違うよ、行こうよ。ね、行こう」
違う?私のカレーは美味しくないの?なら何でこの人は店に来るの?インド?一緒に行く?と疑問が次々と頭を駆け巡り、思考が渦になって消えた。
突然、一緒にインドに行こうよと言われて、ふわふわとした気持ちになった。
頭がボーとして何も考えられない。
どうしてか…。
どうやってか…。
何で…とは思わない。
私は行くのに決まっていた。
そう。
私はこの人と一緒にインドに行くんだ。
「あのさ、今日もお金持ってきてないんだ」と彼は元気よく言った。
これが一目惚れというものなのだろうか、それとも気の迷いなのか。
別に「好きだ」とか「愛している」とか、彼に言われた訳じゃ無い。むしろ変わり者の彼から「君は変わっているね」と言われるくらいだ。「変わっている君が好きだ」というなら、うん、たしかに、私もそうかも。しかし現状は至ってシンプル。ただ単に一緒にインドに行くだけ。それだけの仲。
きちんと膝を突き合わせて話を聞けば、彼は「ナラヤン山本」という名前でネパール人と日本人のハーフだそうだ。彼曰く最近ではミックスとか表現するらしいけど。
で、彼はちゃんと仕事もしていて瞑想のインストラクターで世界を飛び回っているという話だから驚きだ。
「へー。そういう仕事があるんだ。それでお金が貰えるんだ。生活していけるんだ」というのが初めて聞いた時の私の感想。
彼が今回日本に帰国したのも、キャンプ場になった湘南マリンパーク内でのイベントに講師として招かれ、参加していたかららしかった。焚火を囲み参加者全員で瞑想するらしい。
「へーそういう事をやるの、あそこで」というのが二番目の私の感想。
騙されているのかも知れない。新手の詐欺とか誘拐かもと考えなくはない。考えなくはないが、でも、この私を~?とも思うし、私を騙す理由らしい理由は見当たらない。
とにかく彼を、ナラヤンを信頼している。信用じゃなくて信頼。人を信用するというのは盲目的なビジネス的な感じがする。信頼。
信頼とは、例えば、騙されようと裏切られようと構わないじゃあないかと思える勇気だと思う。
智美は「それは、つまり好きっていう事なんじゃないの?」と言うが、私にはまだ分からない。実感はない。
だがこの頃の私の顔色はトーンが明るくなったと近所の評判だ。自分でも以前よりファンデーションのノリがしっくりくる気がする。
上手くいくとか、何のためにとか、今の私にはどうでもいい。言ってみれば私も水槽の中から本物の海へと、大海原へと泳ぎ出したくなったのかも知れない。
私はインドに向かうべく着々と手筈を整えた。
インドでの飲み水状況も定かでないからミネラルウォーターのペットボトルを六本ほどスーツケースに詰め込んだ。
荷物は大きなスーツケースが二つとずっしりとしたニュックと当日準備のショルダーバッグ一つとなった。
ナラヤンには「飲む水ぐらいインドにも売っているよ~。君はしっかりしているのか、抜けているのか分からないね~。よく無事にお店を経営してきていたね、君は」と大笑いされた。
「……そうよ。経営していたわよ、しっかりと……。あ、それからカレー二杯分の代金は日本で今、ちゃんと払って頂きますからね。オホン」
「ハハハ。いいよ。いいよ。才能あるよ。君は人を笑わせる才能がある。うん、いいよ~。いいよ。フフフふぁハッハッハ……」
何がそんなに彼のツボなのかよく分からない……。変な人。でも笑っているナラヤンを見ていると、こっちも笑いたくなってくるから不思議だ。変なの……。
彼の話ではインド各地の聖地を巡りながらネパールを目指し、ヒマラヤ山脈の中腹にあるアシュラムにしばらく滞在する計画だという。
アシュラムとは所謂、瞑想したりヨガをしたりして過ごす施設という事で、そこでは特にもしなくて、ゆっくりするだけでもいいそうだから安心した。私にはそんな高尚な瞑想など出来ない。
私は、恐らく父が好きだったと思われる国へと赴き、恐らく好きだっただろう山へと登り、父と同じ目線を山々に向けながらゆっくりと過ごしたい。
これは父が、もしくは父と母が私に与えてくれた親孝行のチャンスなのかも知れないと思えた。
店はしばらく休業、今後の事は帰国後に考える。
友人たちは私が突然に殆んど見知らぬ男性と一緒にインドに行くと聞いて驚いた。
私はそういうタイプでは無かった。
私は計画を練り、着実に物事を進めるのが好きで、割と堅実で地味な性格なのだ。
母の生前からカフェの経営をやりたいと考え調理学校に通い、卒業してからも幾つかのカフェで働き経営手腕を学んだ。
だから、まさか、そんな馬鹿な事は本当にはやらないだろうと周りの誰もが思っていた。
私だってだ。
幼馴染みの智美も「あんたインドで殺されるんじゃないの」とか「ヤバイよ、ヤバイよ」とか言っていたが放浪の彼を見るなり考えを変えたようだ。
猫のマー君は智美に預かってもらう。今までも度々面倒を見てもらっているから、マー君もすぐに馴れてくれるだろう。
「一カ月したら必ず帰ってくるからね。すぐに迎えに来るからね。ごめんね。ありがとうね、マー君」と何度もマー君とおでこを突き合わせて謝った。
朝、いつもより早く起床。まだ朝になっていない朝。太陽はまだ開店準備中。
昨日のうちにスーツケースやリュックなどの荷物は玄関横に降ろして置いた。この数日で持っていくアイテムを厳選したので荷物はだいぶ減ってスーツケースは一つになった。
貴重品を入れたショルダーバッグを斜めがけして、マー君を入りのずしりと重い猫用キャリーバッグを持ち上げた。いつもと違う行動パターンにマー君も興奮気味だ。調子が狂い階段を踏み外したりしたら大変。マー君ごとキャリーバッグを落としかねない。いつもならつけない吹き抜けの上の電気をつけて慎重にそっと息を吸いながら階段を降りた。
ついに私たちのインドへ旅立つ日がやって来たのだ。
朝早いのに智美と彼女の旦那が店の前で待っていてくれた。智美の旦那とマー君とはここでお別れ。
智美が彼女の運転で私たちを成田空港まで車で送ってくれる。
智美はこの期に及んでも私の旅立ちを信じられずにいるようだったが、空港に着いてからは注意事項を塗りつぶすかのように連発してくる。
「本当に気を付けてね。着いたらメールしてよね」
「犯罪に巻き込まれないでね」
「パスポートだけは失くさないように気を付けてよ」
「ねぇ、生水に気をつけてね」
「ねぇ、薬は持った?」
「ねぇ、何かあったらすぐに連絡してね」
「ねぇ、無理しないで、具合が悪くなったらすぐに帰って来て」
「ねぇ!ねぇ!ねぇ‼てば‼」
私は重いカートを押し、何度も智美の声に振り返りながらセキュリティチェックのゲートへと向かった。
そして、くぐる手前でもう一度振り返り、智美の方へ「バイバイ」と手を振った。智美の表情は見えなかったが、それは懐かしいものへと変わりつつある。
搭乗時刻になり、私たちは順番の列に並んだ。
この段になって私の心の信号が点滅し
「このままこの人とインドに一緒に行くんだ」
という実感が湧いてきた。異国へと旅立つ不
安と胸の昂ぶりが寒流と暖流とになって私の
心臓へ押し寄せた。
いいんだろうか。本当にこれでいいんだろ
うか。
インド行きを止めるのなら今だ。断るのなら今しかない。引き返すならこれが最後のチャンスだ。手に、額に、腋の下に、背中からお尻にと、冷たい汗が、つたう。
「ほらほら、あれだよ。僕たちが乗るイルカ」と彼が窓の外を指さした。
え?イルカ?
快晴の空の下に丸みを帯びた機体の鼻先がこちらに向いている。
水に浮かぶような感じで全身の力が緩やかに抜けた。
「本当だ。イルカだ」
飛行機って本当にイルカみたいな顔をしている。
私はイルカに乗って旅をするのだ。イルカの背に乗ってみたいと夢見たことは一度ではない。嬉しくなった。
何を今さら私はびくついているのだ。行くしかない。やるしかない。
イルカが私を呼んでいる。待っている。
私は胸に手を当てて前方を見据えた。
列の前に並ぶ女性のリュックサックに魚のキーホルダーが小さく揺れていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
