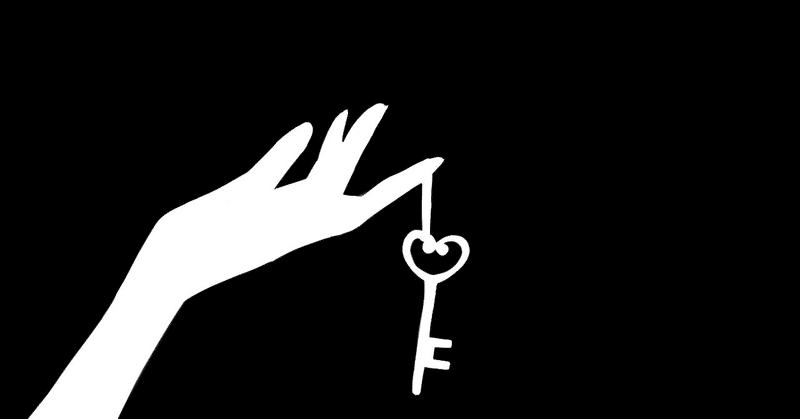
元カノ予兆理論
彼女に振り回されるのと時代に翻弄されるのとが、同じくらいの振れ幅なんじゃないかと思った時期ががあった。
まだ彼女と付き合っていた頃の話だ。
そして今、目の前のスマホが鳴っている。
── 部屋の中。
彼女の名前が画面には出ている。
元カノという表記にはしていない。語呂が良すぎるから。
鳴り止まないスマホ……。
僕がとるまではずっと鳴り続けるだろう。
今夜、彼女から電話がかかってくることは分かっていた。
── それは、わかっていた。
だからこうして待っていた。
……いったい何の電話なんだろう、と僕は、鳴りっぱなしのスマホに向かってため息混じりにつぶやく。
もう、どれ位会ってないんだっけな……。
僕は月日を数えてみる。
月日は間違えなく数えられることを望んでいる。
強烈に彼女の顔が頭の中に浮かんだ。
彼女の異様に長いまつげと、クリクリの目と、常にぶーたれた感じのアヒル口のそれぞれが、強烈に……。
それらを、振り回され続けた日々と一緒に思い出した。
今さらもう僕は彼女のことで傷つきたくなかった。
僕が負った心の傷の大部分はかさぶたになり、取れかかっていた。
──でも、今夜、
彼女から電話がかかってくることは分かってしまっていたのだ。
どうしようもないくらいに。
なぜかというと、今日は朝から彼女が積極的な予兆攻勢をかけていたからだった……。
◇ ◇ ◇ ◇
彼女は昔から予兆なしでは何も話したがらなかった。
ある意味では相手のリアクションを極度に気にしていたのかもしれない。
信じてもらえないとは思うが、彼女は、“ちょっとだけ会いたい”とか“なんだか寂しい”とかを伝えるために、いつもたくさんの予兆を作って僕の前に出現させた。
最初の頃はそれらの行為がとても愛おしく感じていたけど、結局僕の心と体が持たなくなってしまった。
そのことを伝えようとしたら。
突然彼女は予兆なしで僕の前から姿を消してしまった。
そしてごくたまに電話をかけてくるようになった。
近況の報告が主だった内容だった。僕の傷つく内容をあえて報告することが多かった。
そんな積み重ねがあったから、今朝の出来事にもわりと柔軟に驚けた。
久々の予兆……。
今日の朝一番に起こったその予兆はわかりやすいものだった。
僕はいつも目覚ましにカラヤンの名盤が聴けるようにセットしているのだけど、今朝はかからなかった。セットミスすることなんてまずないはずなのに。
代わりにフランク永井の『有楽町で逢いましょう』が流れたから、僕はベッドから飛び起きた。
僕は朝一番の予兆に一通りつき合ってから、いつものように熱い湯で髭を剃った。まだ気のせいだと思おうとしていた。
そのあとで、どの朝とも変わらなく、ブルームバーグchを観ながらコーヒーを飲んだ。
NYダウは大幅に下げていた。彼女から連絡がある時はだいたい下がる。だけど今日はたまたま悪材料が出て下げてるんだろう。
僕は“いつもどおり”であることを装っていた。
それは、朝一番に起きた予兆に対する僕なりの礼儀みたいなものだった。
じたばたしても仕方ない。
ただ、今朝の僕はいつもより早めに家を出る必要があった。
全てがいつもどおりとはいかない。
今日は会社で自分がニュース読みの当番の日だったからだ。早めに出社して全ての株価材料になりそうな情報に目を通してまとめておかなくてはならなかった。
「さあ、いこう」と、めずらしく気合を入れてから僕は玄関のドアを開けた。
だが、気合はすぐに空回りすることになった。
なんなんだよ……、これは……。
ドアを開けた僕は、そこにあったものを目にして、思わずそう声に出した。
おそらく僕以外の人でも同じようなフレーズを口にしたと思う。
それは二つ目の予兆と呼ぶべきものだった。
なんと玄関のドアをあけるとそこにはアロワナがいた。
巨大なアロワナだった。体長1mくらいあるんじゃないだろうか。
これまた巨大な水槽の中央でまるで静止しているかのように佇んでいた。
水槽のガラス面には張り紙がしてあった。
『事情があって飼えなくなりました。どうか、このコを可愛がってあげて下さい。お願いします。
飼い主より』
……捨てアロワナかよ。
そういえば昨日の夜遅く停電があった。この飼い主はカメラをかいくぐり、周到に置いていったようだ。
なぜかこの飼い主はこの光景にBGMをつけていった。ピンキーとキラーズの恋の季節が流れている。
僕は頭を抱えずにはいられなかった。
◇ ◇ ◇ ◇
僕は便利屋さんに電話して来てもらい、巨大なアロワナを巨大な水槽ごと家の中に入れてもらうことにした。
気のせいだとは思いたいたころだが、彼女からの予兆を放っておくわけにもいかない。
何件かかけてみたが朝から電話のつながる便利屋さんはなかなかなかった。
どうしたものかと、スマホをみつめて思案に耽っていたとき、ふと、以前ポストに入っていた便利屋さんのチラシのことを思い出した。
すごく変な内容だったので記憶していた。
たしか、そのチラシにはこうあった。
『どんな急な用事にも駆けつけます!
どんな内容のご依頼にもお応えします!!
それが便利屋たる者の便利道ってものです!!!
※例えば、もしも、あなたが、朝、会社に行こうと玄関のドアを開けたとき、目の前にアロワナの入った巨大な水槽があってお困りの場合なんかには真っ先にお電話ください。○○○-△△△-×××』
まさに、今じゃないか。
なんだか少しハメられているような気もしないでもないが、とにかく、今、ピンポイントで僕の依頼に応えてくれそうなのはそこしかない。
僕は部屋の中からそのチラシを探し出すと、すぐに電話した。
ワンコールで声がした。まるで、僕からの電話を待っていたかのような感じだ。
「ハイ、ハイ、どうも、どうも。お電話有難うございます。幸福印のハッピーライフサポートです」
のんびりとした中年男性の声だった。
「あの……、朝早くからスイマセンが、急な依頼があるんですが……」
「ハイ、ハイ、朝は早いにこしたことはありませんよ。で、どんなご依頼なんですか?」
「ええ、実はですねえ……、私が朝、会社に行こうと思ったらですね、玄関の前に、その……巨大なアロワナの入った巨大な水槽が捨ててありましてですね、放っておくわけにもいかないので、部屋の中に入れたいのですが、ひとりでどうにかなる重さではないものですから……」
いったい何の因果で僕は朝からこんなことを電話で説明しているんだろうか……。
「失礼ですが……、ご冗談ですか?」
便利屋のおじさんは僕にそう言った。
「ええ、いや、冗談みたいな話だとは思いますが本当の話です。でも、ほら、おたくのチラシに書いてあったじゃないですか。こういうケースに、もってこいだって。だから、電話してるんですが」
「ああ、ハイハイ、うちのチラシを見て下さったんですか。それをちゃんと言ってくれないと、500円割引なんですから。お客さん、損するところでしたよ、ほんとに」
「はあ……、そうですか、それはどうも」
朝からこんなことに巻き込まれている時点で十分損しているんじゃないかな、はっきりいって……。
「で、うちのチラシにはなんて書いてあったんですか?」
「え?……ですから、玄関前にアロワナがいて困ったらお電話ください。と、そう書いてありましたよ」
「また、またあ。ご冗談でしょ?」
僕はため息をつかずにはいられなかった。
◇ ◇ ◇ ◇
便利屋のおじさんはすぐに来た。
── びっくりするぐらいすぐに。
僕が電話をかけたハッピーライフサポートという便利屋さんは、実は僕の住むこのマンションの一室に事務所を構えていたのだ。
入居して一年近くになるがそんな会社が入っていたなんて知らなかった。
それに、このマンションは居住専用のはずだ。
「いやー、どうもどうも、この度は誠にどうも。ホントはもっと早く来れたんですけどねぇ、なんせ従業員起こすのに時間食っちゃって。スンマセンねー。まあ、従業員っていってもここにいるうちのバカ息子なんですけどね」
作業着姿のおじさんの後ろには、髪の毛にメッシュを入れた寝ぼけ顔の若者が、オレンジ色のジャージ姿で立っていた。
「でも、びっくりしましたなー。まさかこのマンションの方だとはねえ。で、これが問題のアロワナですか?」
おじさんは水槽をコツコツとノックするみたいに軽くたたきながらそう言うと軍手をはめた。
「これが、問題のアロワナです」と僕は答えた。
すると、そこで突然今までふてくされた感じで黙っていた便利屋のせがれが声を上げた。
「スッゲー、ヤバくないっすか?」
「ヤバくはないと思うけど」と僕は即座に答えた。
「いや、ヤバいっすよ、これ。オレの最近の人生の中ではかなりヤバいほうっすよ。あー、テンション上がってきたー」
彼のテンションはどうやら上がってきたらしかった。
僕は彼の『最近の人生』という言葉がなんとなく気に入った。
彼の中では人生とはひどく断片的なものなのかもしれない。
「それでは、さっそく作業に取り掛かってもよろしいですかな。これを中に入れればいいんですね」
おじさんは早くも額いっぱいにかいている汗をぬぐいながら言った。
「ええ、お願いします」
僕は何度か頷くことによって、この人たちをここへ呼んだ理由をうまくつなぎとめようとした。
「任せてください。ハッピーなライフをサポートするのがわが社の使命ですから」
おじさんは口角泡を飛ばしながら胸を張ってそういった。
……ハッピーな
……ライフを
……サポートする
……会社。
おじさんは「おいこらっ」とか「このバカ息子が」とかいいながらせがれに作業をさせようとした。
するとせがれは、「ちょっと、ちょっと、待ってよ。タイム、タイム」と言って手で『T』の文字を作った。
「あのー、お客さん、ヤバいくらいいいこと考えたんすけど、聞いて貰っていいすか?……あのー、ここで釣堀やったらどうっすか?だってアロワナが釣れるんすよ。やべーって絶対。それに、このマンションに釣堀あったらオレ、毎日でも来ますよ。それってヤバくないっすか?」
「それって、ヤバくないっす」と僕は答えておいた。
毎日彼に来られてもつかれる。
僕はアロワナの方に目を向けてみた。
アロワナは「ホント、ヤバくないっすか?」と、言いたげな顔をして泳いでいた。
◇ ◇ ◇ ◇
アロワナを水槽ごと家の中へ入れる作業は無事に終わった。
思っていたよりも滞りなかった。そのことが逆に予兆感を高めた。
占有面積からすると、僕の狭い部屋はアロワナメインの部屋になったんだと思う。
僕は二人に礼を言い、それから冷蔵庫の中にあったオロナミンCを2本手渡した。
冷蔵庫の中の2個あるプリンの片方に何故か彼女の名前が書かれていたのは見なかったことにした。それにプリンが2個あったらいつも2個とも彼女が食べていた。
僕はおじさんが提示した料金をおつりのないようにぴったり払い、領収書をもらった。
その料金が高いのか安いのかはわからなかったけど、おじさんは「これは割引料金である」ことを強調した。
「ご利用有難うございました。また、何かお困りの際にはお声をおかけください。なんといってもご近所ですから、よろしくお願いします」
そういって頭を下げたおじさんの後ろで、せがれが不敵な笑みを浮かべていた。
その笑みを見た僕は、ほんの少し疑いたくなった。
一瞬、昨日の夜のうちにせっせとアロワナを僕の家の玄関先へ運ぶ二人の姿を想像してしまったからだ。
……まさか……ね。
「こちらこそ」僕は礼を言った。
二人がいなくなったあと、しばらくの間ぼーっとアロワナを眺めていた。
……君はいったいどこから来たんだい?
なんで、僕のところへ……
……君は本当に捨てられたの?
僕はアロワナにいくつかの素朴な疑問をつぶやいてみた。
アロワナは僕とは目をあわそうとはせずに、大きく発達したムナビレを動かして水の中を漂っていた。
君は遺存種なんだろ?……君なりの哲学みたいなものを聞かせて欲しいな。
僕はアロワナになにか名前をつけようとしてやめてそのまま家を出た。
いつもどおり東急田園都市線に乗った。
僕は混雑する車内で電子書籍を読んでいた。
その日の活字はなぜだかいつも以上に踊っているように見えて、なんだか目が疲れた。
あるいは普段の活字がそれほど躍っていないせいだからかもしれない。
二子玉川駅でいつもどおり多くの乗客が乗りかわり、車内が多少すいた。
ふっと、一息つく。
車窓から差し込む朝陽が平日的に眩しかった。
もちろん、それは僕の気分の問題なんだろうけど。
──しばらくして、車内放送が流れた。
油断していた僕はその車内放送に驚かされることになった。
「本日は東急田園都市線をご利用いただきまして誠に有難うございました。最近、車内における盗難の被害が増えております。貴重品はお手元に置かれますようお願い申し上げます。」
と、ここまではいつもどおりだったのだが、問題はここからだった。
「今日はご乗車の皆様にお話がございます。何を隠そうワタクシ車掌になって数十年、決まりきった車内アナウンスに辟易してまいりました。本日は少し趣向を変えまして、ワタクシ流の車内アナウンスをさせていただきたいと存じます」
ん?、何だ?どうしたんだいったい?僕は顔を上げた。
「えー、この世の中におきまして、果たして悲恋なんてございますでしょうか。いいや、悲恋なんてないんだとワタクシは思う所存であります。人を恋しく思う気持ち……。何ものにも変えがたいその気持ち。沢山の恋心を乗せた列車が突っ走る。西へ東へ突っ走る。素敵じゃございませんか。シュッポ、シュッポでございます。ワタクシ、最近、年甲斐もなく恋を致しまして、えー、燃えに燃えております。決してかなわぬ恋……。でも、これだけは云えると思うのです。悲恋というものはこの世にひとつもないんでございます。
それでは聴いてください。チューリップで『心の旅』」
そこまで言うと車掌は突然歌いだした。
“お前が歌うんかいっ”、と、みんながツッコミを入れると思ったけど違った。
信じられないことに、その日の朝、人々はその車掌に共鳴した。
一人が歌いだし、二人、三人と次第に合唱の輪に加わっていき、気が付くと『心の旅』の大合唱になっていた。
♬あー だから今夜だけはー 君を抱いていたい〜
♬あー 明日の今頃はー 僕は汽車の中〜
確かに、ここにいる大半の人は明日の朝も通勤列車に揺られているんだろうけど……。
この三つ目の予兆を通過したあたりから僕はようやく彼女のことを覚悟し始めた。
◇ ◇ ◇ ◇
渋谷駅で降りた僕は乗り換えのためにホームを歩いていた。
僕は人の流れにうまく乗れずに何度か見知らぬ人とぶつかってしまった。
とにかく、朝からひどく疲れる。
僕が大きくため息をついたとき、誰かが後ろから声をかけてきた。
「これ、落としましたよ」
僕は振り返ってその声の主を確かめた。
身なりがよく、管理職っぽい感じの40代くらいのメガネをかけた男性が僕のすぐ後ろにいた。すこし息が切れている。
走ってきたのだろうか?
「これ、落としましたよね」
今度はひどく断定的にそう言われた。手にはコインロッカーのキーを持っていた。
男性は「ね」といって僕の目の高さでキーを揺らした。
僕は“いいえ”と言おうとした。僕はそんなキーのことはまるで知らない。
でも、言葉が出てこない。
さの男性の揺らすコインロッカーのキーがまるで催眠術か魔術のように僕から声を奪ってしまったみたいだった。
僕と男性をよけるようにたくさんの通勤客が足早に通り過ぎていく。雑踏が何か大きな生き物の鼓動のように聞こえ始める。
「これは、あなたのものです。まちがいありません。私はこれをあなたが落とすところをちゃんと見ましたから」
男性のメガネが光った。
僕はもう頷くしかなかった
僕は結局そのコインロッカーのキーを男から受け取った。
『思考が行動を決定するんじゃなくて、行動が思考を決定するのだ』と村上春樹が何かに書いてたのを読んだことがあった。
手にしたそのキーは男性の汗で少し湿っていた。
僕はお返しに、彼のワイシャツの襟のところについていた赤い口紅の跡を指摘してあげた。
男性は素直に「ありがとう」と僕に言い、そしてどこへともなく消えていった。
さてと……、どうしたものか……。
僕はコインロッカーのキーをつまみあげ、顔の前で揺らしながらそう思った。
今日は朝起きたときからこんなことばかり考えているような気がする。
キーのナンバーは 1129
それは189番目の素数だ。
1129……?
なんだ?この数字は。ちょっとでかすぎやしないか。
コインロッカーを普段あまり使用しないので詳しくはないけど、コインロッカーの数字なんて2ケタくらいのものじゃないんだろうか。まあ3ケタくらいまであるところもあるのかもしれない。
にしても、1129って……。
これじゃあ、運び屋が何人いたって足りない数字じゃないか。
それでも僕は、念のため渋谷駅の中の全てのコインロッカーを調べてまわった。
当然というべきか、とにかく1129なんて番号のロッカーはなかった。
多分、どこの駅を調べたって同じだろう。
ん?なんだ!……そうか。
僕はこれが予兆であることを忘れていた。
きちんとそこに立脚した上で考えたら簡単だった。
189番目(いちはやく)分かれということか、なーんだ。
そして1129は 彼女の本当の誕生日だ。彼女は国際的なスパイみたいに幾つもの誕生日を持っていたけど、それについての情報は当時から僕は掴んでいた。
だからといって今となっては覚えていても仕方ない数字なはずなのに、僕はちゃんと覚えている。男の弱さか。
朝からの一連の不可思議な出来事のことと彼女を結びつけないわけにはもういかないだろう。
おそらく彼女に関する何かが僕の身に起こる。
それは、逃れることの出来ない近い未来。
未来同様、予兆だって変えられやしない。
それにしてもずいぶんと大げさだな……。いつものことだが。
めちゃくちゃに人を振り回す感じは彼女の性格そのものだ。
彼女はあの頃、まるでボクサーが繰り出すジャブみたいに、バンバン僕を困らせるようなことを言っては、その距離を測っていた。
……今頃どこで何をしてるんだろう。
いや、もう関係ないことだ。
僕は首をふり、そして会社へと急いだ。
◇ ◇ ◇ ◇
当然のことながら、その日、僕は会社に大幅に遅刻した。
11時29分出社。
もうすぐ取引時間の前場が終わってしまう。
急いでトレーディングルームへ。しこたま怒られる。
昨夜からのアメリカの流れを引き継ぐ形で東証の株価も大幅に下がっていた。特に個人投資家に人気の主力銘柄の下げがきつい。
ほぼ全面安の展開の中で、彼女を連想させる彼女関連銘柄だけは逆行高で異彩を放っていた。
同僚たちは自分の顧客にこの下げはおそらく一時的なものだと説明するのに苦心していた。
でも、
僕だけはわかっていた。
完全に一時的なものだと。
こんなインサイダーってありなのだろうか。
僕はさまざまな数字を目で追いながら、彼女に秘められた力に畏れを抱いた。
仕事が終わり、家に帰るまでもいろいろあった。
もはや予兆をスルーする術を身につけていたのでわりとすんなり帰れた。
ただ、確実に彼女は近づいてきていた。
おそらく今夜なんらかのアクションがあるだろう。
僕はなんの戦力外通告も受けてないし、トライアウトも受けてないけど、電話を今か今かと待たなければならないだろう。
── その日の夜、つまりはこの話の冒頭の、彼女から電話がかかってくるまでの間を僕はそんなことを考えながらやり過ごした。
◇ ◇ ◇ ◇
というわけで、今夜。
“今”にちゃんと至れたかの判断材料は着信音の中に溶けて消える。
── 彼女からの電話は相変わらず鳴り続けていた。
それは、どんな数列よりも果てしがないもののように思えた。
天の覆う限り、地の続く限り、鳴り続けそうな着信音だ。
部屋中が脳震盪をおこしたかのように揺れているような気がした。
いったい彼女は僕に何の話しがあるというんだろう。
結婚の報告だろうか……。
それとも、急に僕の悪口を思いっきり言いたくなったんだろうか……。
もしかすると、新しく買った家電製品の使い方が取説をよんでもよく分からなくて電話してきたのかもしれない。
彼女は、たしかびっくりするくらいのメカおんちだったから。
とにかく壮大な振り回され方だ。
昔と変わらない。
いずれにしろ、僕は傷つくんだろう。
彼女の声に確実に傷つくんだろう。
目の前では、巨大水槽の中をアロワナが泳いでいる
スマホが昭和歌謡メドレーを歌い出したので、いいかげん電話とった。
「もしもし」と、向こう側から久しぶりの彼女の声だ。
「やあ、どうしたんだい?」
「ちょっとね、あのさ、今日アタシから電話があると思った?」
「そんな、まさか。だからすごく驚いてるよ」
「ふーん、そうなんだ」
電話の向こう側で彼女はつまらなそうに言った。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

