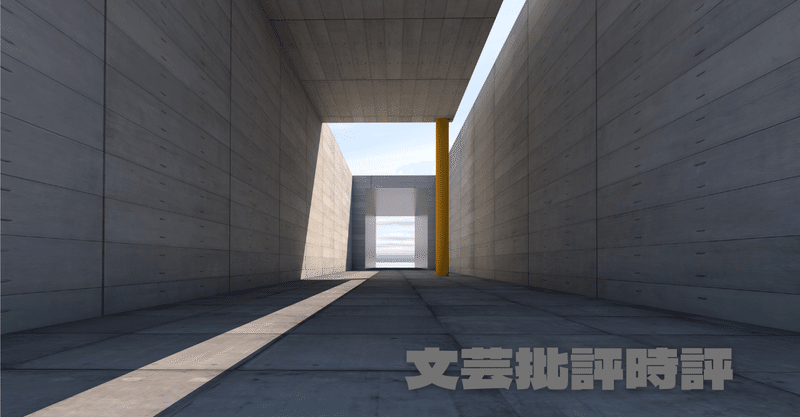
デジャヴュから歴史へジャンプせよ
文芸批評時評・10月 左藤青
文芸誌を買うというのはほとんど博打である。
何冊も買えばなかなか高価だし、かさばるから本棚のスペースを圧迫する。そのくせ、この手の雑誌(文芸誌や思想誌や美術批評誌)に載っている文章ははっきり言って玉石混交だ。面白いと思える文章や特集に出会える機会はきわめて稀少である。
だから、この『文学+』の企画——毎月の文芸誌に掲載された評論について論ずる——に参加していないかぎり、僕がこの類の雑誌を買うという「賭け」に投じるのは半年に二度・三度あればいい方だった。けれど、これからしばらくの間、僕はそのような「賭け」に、隔月で投じてみようと思う。【註1】
もちろん面白くない文章に言葉を割けるほどには人生は長くないから、僕の担当では、毎月の文芸誌に載る評論をすべて網羅的に取り上げることはしない。また、僕は読者にテイの良い読書案内を提示するつもりもない。勝手に読んで勝手に判断するのが読者の最低限の倫理だ。
ただし、もちろん本稿で取り上げなかったすべてについて、「論ずるに値せず」と断じたわけではない。構成上削ぎ落としたもの、僕には論じる資格のないものもある。しかしそれなりにすべてに目を通しはした。なかなかの苦行であった。
【註1】
明記しておくが、この世で最も誠実な文芸同人誌『文学+』は親切にも、原稿料とは別に雑誌購入費をあてがってくれており、そのおかげで僕はなんらのリスクなく「賭け」に投じている。
二人のビッグネーム
講談社刊『群像』は批評に力を入れている雑誌である。休止が宣言されたとはいえ群像新人評論賞は、批評の狭い界隈ではそれなりにエレガントな賞とみなされているし、実際の誌面の全体を見ても、創作以上に論考や対談にページが割かれている。
必然的に本稿の話題も『群像』10月号が中心になる。今号でも、柄谷行人「霊と反復」や蓮實重彦「窮することで見えてくるもの」など、旧来の「批評」ファンを引き寄せるおなじみのタッグの論考が並ぶ。ただし、そういった固有名(ビッグネーム)にいつまで依存するのか、という疑念もなくはない。
実際柄谷のエッセイは、柄谷が自身の仕事を振り返っているという意味では貴重な文章だが、全体として『世界史の構造』(2010)以来の「交換様式D」路線であり、新奇性はない。
正統なマルクス主義者であれば批判するところの、交換から生じる資本のフェティッシュで自己増殖的な性質——「霊」の力(柄谷はそれを比喩ではなく「現実に働く」力だと断言する)の中にこそむしろ可能性を見出すという、やや際どく見えなくもないこの「スピリチュアル」路線は、ジャック・デリダが『マルクスの亡霊たち』(1993)で論じた「亡霊」の効果を思い起こさせもする(柄谷はデリダと自身を——いつものごとく——差異化するが、その違いは明確ではない)。たしかにこの議論の方向性にはいまだ可能性があるように思われる。しかしデリダ同様(?)柄谷もまたその議論の展開になかなか苦悩しているのではないか。
一方、大江健三郎による『水死』(2009)に四度だけ登場する「窮境」という一つの語をめぐって展開される蓮實の論考は、ところどころの手際の鮮やかさなど、「さすが蓮實」と思わされはする、エンターテイメントとして耐えうる文章である。
ただし、これもやはり『大江健三郎論』(1982)ですでに見られたスリリングな「数」の表層批評と手法的には変わることがない。たしかに、最終的に「昭和の精神」幻想——敗戦直前の国の「窮境」を克服する「人間神を殺す」幻想——を裏切る「女たちの蹶起」に触れられる最終地点では、論考はさらなる緊張感を獲得するが【註2】、見ようによっては大江の筋書きをただオーソドックスになぞっているようにも思えてしまう。この局面では、「作家」あるいは「作品」さえも裏切る言葉の躍動を描き出そうとする蓮實の挑発が、そもそも成功しているのかも定かではない(そもそも『水死』とはそのような小説なのではないだろうか)。
【註2】
この点については、『大江健三郎論』を引き合いに出しつつ最終的には『水死』に依拠して大江の天皇制との関係を論じた絓秀実「小説家・大江健三郎――その天皇制と戦後民主主義」(『群像』2020年3月号)を併読するべきだが、紙幅的にも能力的にも本稿で論ずるべき域を超えている。
既視感から出発する
このように、かなり大きく「メイン」の扱いを受けている二人の批評にやや食傷の感を覚える一方、他の論考には見るべきものがある。
松浦寿輝/沼野充義/田中純による「徹底討議 二〇世紀の思想・文学・芸術」第九回「批評の革新」。僕は正直これまでこの鼎談の存在を知らなかったが、見事である。それぞれの領域で第一線で活躍する論者らによる二〇世紀の歴史の総括は、「教科書」としては保存版と言ってよく、僕自身かなり勉強させてもらった。この鼎談を読んで僕は、柄谷や蓮實の文章に感じた既視感の正体、さらにはその良くも悪くも拭えない「時代遅れ感」の正体が暴かれた気になったのである。
ここから先は
【定期購読】文学+WEB版【全作読放題】
過去作読み放題。前衛的にして終末的な文学とその周辺の批評を毎月4本前後アップしています。文学に限らず批評・創作に関心のある稀有な皆さま、毎…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
