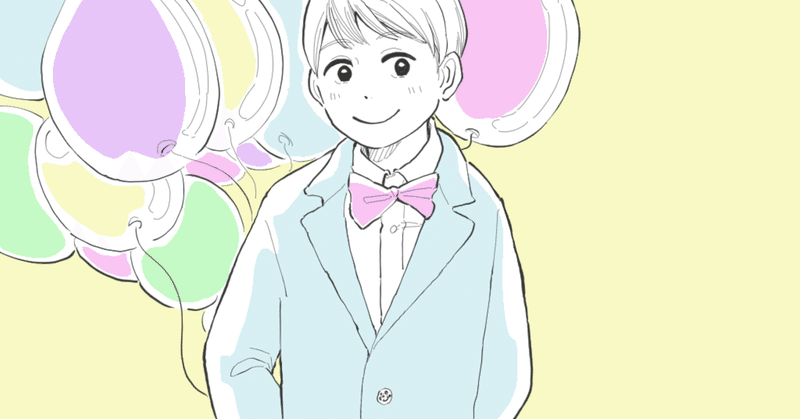
「ボク」と呼ばれるのが嫌いだった
かつて、僕は「ボク」と他人から呼ばれてきた。
幼稚園から小学校高学年くらいまでだろう。期間限定且つ他人限定の二人称、「ボク」。
関西の人たちが二人称を「自分」と呼ぶ文化があるらしいが、この「ボク」という二人称は全国共通なのだろうか。
それにしても、「ボク」と呼ばれてきた人間が徐々に「ボク」と呼ばれなくなり、最近はもっぱら他人からの二人称は「あの、すいません」である。どこか寂しさを覚えるような二人称である。
ーーー
少年時代の僕は既に他人から「ボク」と呼ばれることに違和感を覚えていた。
「ボク」というのは一人称であるから二人称には相応しくないというのはもちろんのこと、何故か「ボク」と呼ばれるのはお坊ちゃんというのか、高貴なニュアンスが含まれているような気がして嫌だった。
第一、少年に対する二人称が「ボク」であるなら、クラーク博士のあの有名な言葉だって何か変な感じになるだろう。
ボクよ、大志を抱け
「ボク」なんて言われたら大志を抱けないではないか。
井上陽水の名曲だって、「ボク時代」になってしまう。そんなんじゃ夏だって過ぎないだろうし、風あざみないだろう……風あざみって何だ?
「少年ジャンプ」は「ボクジャンプ」に。このネーミングセンスだと現在ほどの人気を誇ることはなかっただろう。知らんけど。
ーーー
小学生低学年か中学年か、いつからかは忘れてしまったが、僕は家庭の中で郵便物や宅急便やらの荷物を受け取る係みたいになってしまった。
別に好んで外へ出ていた訳ではないが、ある時を境に僕が出ることが多くなった。
知らない人は出ていけないという教えもあったが、インターホンを通じて見える解像度の高くないカメラからも見るからに郵便局の男性や宅急便のお兄さんだと分かったので、何も警戒せずに扉を開けていた。
ただ、インターホンが鳴ったときに「はーい」と外の人に返答をするのは母か父だった。
母は昔から他人に対して声を「つくる」性分なので、幾分かインターホンに向かって放つ言葉は高いキーになりがちだ。
だからかは知らないが僕が扉を開くと、お前かよみたいな顔をされ、彼らは口を開ける。
「あ、ボク、こんにちは」
本当に一瞬だが、残念そうな表情をするのだ。僕はその頃小学生とはいえ同じ男だからよく分かる。
もちろん、それはごく僅かな時間である。扉を開けて1秒もないくらいの一瞬だ。彼らもプロだから、「ハンコかサインお願いしますっ」とすぐに切り替える。
こういう経験もあって「ボク」と呼ばれるのが嫌になったのかもしれない。
ただ、父がインターホンに向かって返答するときは「ア゛ーイッ」と喉元から大きな低音を発する。いや、発するというか吠えるのだ。これは外のインターホンの前にいる人間からすれば威圧以外の何者でもない。
おそらく、郵便局・宅急便の彼らはすぐに自分が過去、斉藤家に対して何かしらの過ちを犯したのではないかと回想に耽っているはずだ。あの日、あの時、この場所で何か失礼なことしたかな、と。
無論、それは杞憂に終わる。が、どんな強面な男——いや「漢」が出てくるのかビクビクしながら待っていたことだろう。
彼らにとってその時間はすこぶる長く感じたはずだ。実際にはインターホンを鳴らし、父が吠えてから30秒もしないくらいで扉は開く。しかしその30秒の体感時間たるや、満員電車のJR東海道線、戸塚–横浜間かそれ以上に長く感じたはずだ。
扉を開ける。もちろん出るのは僕の仕事である。郵便局・宅配便のお兄さんと目が合う。
そして彼らは安堵した表情を一瞬見せて言うのである。
「あ、ボクこんにちは」
このとき、僕の自己有用感は毎度高くなった。郵便物を受け取るという家庭内での仕事だったが、彼らの表情を見るとそれ以上の仕事をした気になる。
ただ、僕にも「斉藤夏輝」という名前があるのだから「ボク」と子ども扱いされるのではなく「斉藤さん」的な感じで呼ばれたかったのが事実。
そしたら僕の自己有用感は最高値になっていただろう。まあ僕としては「ボクボク」言われているうちに一人称が「僕」になった気もしなくはないので、悪くない経験だったかもしれませんが。
「押すなよ!理論」に則って、ここでは「サポートするな!」と記述します。履き違えないでくださいね!!!!
