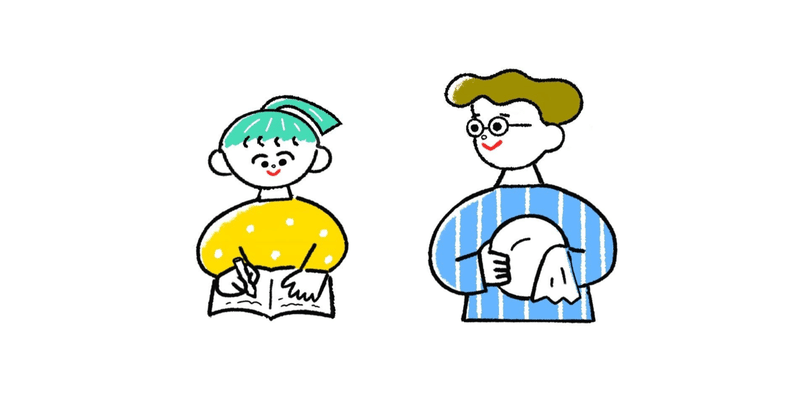
男性育休ブームで、自分の子どもが赤ちゃんの時に何も出来なかったことがひっかかるパパに送るエール
私の所属する職場では、育休を取る男性は前から多くいました。最近話した男性社員は、女の子のお子様に拒否されるのが怖くて、お世話をがんばっているとのこと。自然と娘が父親から離れる頃に、夫婦の仲良し期に戻るといいなと話していました。
かねてより新生児期にママと共に赤ちゃんのお世話ができるかが、その後の夫婦関係の明暗を分けると東京都が警鐘を鳴らしています。
更に産後パパ育休制度も創設され(育休とは別に、産後に休める)ますます、パパの育児参画が進むと期待できそうです。
さて、育休を取る男性を横目で見て、我が子はもう赤ちゃんじゃないけど心がざわつく…そんな方がいらっしゃったら「まだ、できることがあるかもしれません!」とエールを送らせていただきたく、筆を取りました。
☆既に十分育児にコミットされていたり、特に何も感じるところがなければお役に立てず申し訳ありません。あくまで私個人の意見です。
ママさんの支えになることを。それは子供の世話だけとは限らない。
おむつ替え、ミルク、お風呂など、花形業務。確かにママさんも助かります。しかし、お膳立てと片付けをママさんがしていないでしょうか。
使うものを一人で出せますか?終わった後元の状態に戻せますか?ぜひ副担当から主担当へ昇格を目指すのはいかがでしょうか。
子どもに関わることに限らず、ママさんの負担軽減になりそうなことをできれば察して、難しければ指示してもらい実施するとよいと思います。
掃除でも食器洗いでも、資源ごみをまとめることでも、電動自転車の充電でも、手洗い石鹸の詰め替えでも、子どもの上履きを洗うことでも、プラレールの電池交換でも、なんでも良いのです。ママさんは思った以上に多くのことをしてます。
ここまで、ちょっと厳しそうな方。大丈夫です。
ママさんが忙しそうにしているときに露骨にスマホを見るのをやめるだけで、家の空気が変わると思います。ママさんはスマホを見てるパパを見て、お願いする気持ちが萎えているだけかもしれません。いつママさんが忙しそうにしているか、スマホを見ていたら気づけません。注目してみましょう。
新生児過ぎても育児コミットのチャンスは多い。
赤ちゃんの時を過ぎても、土日公園に連れ出す、習い事の付き添いをする、ヘアカットや歯医者や皮膚科などに連れて行く(予約だけはしてもらうでもマル)といった用事は多々あります。お医者さんから言われたことはママに申し送ります。
自転車の練習、縄跳びの練習、水泳の練習、習い事送迎、小学校入学前のひらがな練習など、生活ルーチン以外の担当科目を受け持つのもよいです。子どもが大きくなるほど、日常的な手助けは減り、こうした、日常から切り出せるルーチン業務が増えてくると思います。
家の中でも、子どもの話し相手になる、ゲームを一緒にする、本を読んであげる、新聞記事やニュースを解説してあげる、など出来ることは多いです。子どもの成長とともに興味関心も広がり、ますますパパの活躍の場は広がると思います。小1の壁で挽回もいいですね。
それら全てを有能なママさんがやっていたらママさんは知らず知らずのうちに過労働になってしまうでしょう。職場でも優秀な人ほどなぜか仕事が集まります。
ママさんのイライラを察したらスマホをポッケにしまって様子を見に行きましょう。土日も朝はママさんと同じくらいの時間には起きましょう。家の中ではワンオペの発生を最小限にします。
仕事は自分だけでしているのでなくチーム家族でしている。ヒーローインタビューの決まり文句は「自分だけの力じゃない」。
妻夫関わらず、収入に対して「俺の稼ぎ」「私の稼ぎ」と、1人の成果のように表現するのを避けたいなと個人的には思っています。
日常生活なく仕事は成り立ちませんし、なんなら保育園幼稚園や小学校に無事に通ってくれている子どももチームの一員です。
全員が持ち場で笑顔でプレーするチームになりたいです(自戒を込めて)。そのためには、妻の家でのがんばり、妻の仕事でのがんばり、子どもの園や学校でのがんばりにも目を向けられたらステキです。
ママさんに子育てを全面的に頼り仕事に邁進するパパさんは昔も今もいると思います。ただ仕事の成果を「俺のもの」にしちゃうのか「家族みんなが頑張ってくれた賜物」と言えるのか、その違いがものを言うと思います。
魔法の言葉、ありがとう
「いつもお世話になっております」取引先には電話で言いますね。でも、取引先より毎日お世話になっているのは他でもないママさんです。
夫婦で「ありがとう」が言い合えるだけで、冒頭の愛情曲線は変わる気がします。「いつもありがとう」「○○してくれてありがとう」。その恩恵は子どもへ向かいます。ありがとうが言える子どもになるからです。
ただ、別に!とそっけない返事が返ってきたら、驚いて反応できなかったか、口だけでなく何かしてよ!と思われている可能性があります。後者なら、ぼくも出来るようにならなきゃなあ…などと呟いてみて、「じゃこれやってよ」などとニーズが引き出せないか探ってみましょう。
さて、いかがでしたでしょうか。誰の役に立つかさっぱり不明です。
しかし私も我が身を振りかえるきっかけになりました。
どなたかが一歩踏み出すきっかけになるならば嬉しい限りです。私も幸せな家庭を夢見てがんばります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
