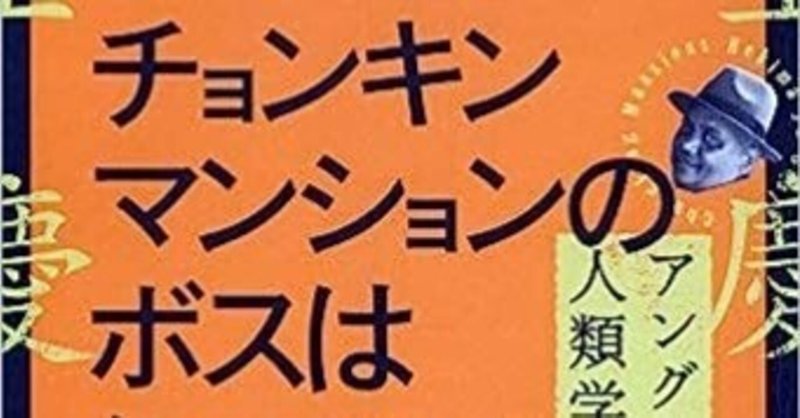
[読書の記録] 小川さやか『チョンキンマンションのボスは知っているーアングラ経済の人類学ー』(2023.08.05読了)
著者は文化人類学者で、タンザニアでのフィールドワークを通じて、「マチンガ」と呼ばれる路上商人たち、ギグワーカーたちの関係のなかに入りこみ、彼らの資本主義経済に対する独特な関わり方を研究している。その成果を元にした一般向けの図書には、『「その日暮らし」の人類学 -もう一つの資本主義経済』(光文社新書, 2016)がある。
本書は、そんな著者が香港に舞台を移し、チョンキンマンションに長期滞在してビジネスをするタンザニア人たちの日常を、文化人類学の観点から記述した本である。
個人にひもづかない信用
書名に含まれるチョンキンマンションとは、香港の大通りにそびえたつ巨大な雑居ビルのことで、一角にはタンザニアから来た個人商人のコミュニティがある。
そのまとめ役がカラマという人物で、「チョンキンマンションのボス」である。カラマは抜け目がないようで抜け目だらけのような、チャーミングな中年男性だ(表紙に写真がついている丸顔のおじさん)。著者はじっさいに彼の客となり、その絡みで出会うタンザニア人たちの生きる姿を丹念に追っていく。
タンザニア人商人の多くは香港で物を仕入れ、アフリカに売るブローカーである。互いの商売は競合することもあるが、商品の知識やビジネスの手法は、教え合って情報をシェアする。例えば中古車ビジネスは、昔カラマが皆に教えたものなので、カラマと同様のやり方で皆が商売をしている。
彼らは無理をしない範囲でなら、相手を問わず助ける。相手を問わないのはなぜかというと、今後の自分の状況に応じて、必要な縁は変わってくるからだ。
「商売が大きくなったら大企業の経営者が、逮捕されたら囚人の仲間が大事になる」とカラマはいう。
ここまでなら、経営学の用語でいう「協調領域」と「競争領域」のすみ分けのような凡庸な話ともとれるだろう。
しかしチョンキンマンションの住人たちのアングラな生態のうち、もっとも特徴的で、読者の常識を覆してくると思われるのが、「この人は信用できる/できない」というふうに、人間そのものへの評価をしない点だ。
彼らはその代わり、「いまAさんはは商売が好調だから信用できる」、「いまBさんは恋人と一緒だから良い奴やつだ」といったように、状況に限定した形でのみ人間を評価する。
タンザニアの場合、日本の経済と比べて不安定であることもあって、商売がうまく行っていれば信用に足る行動をするが、誰しもそんな時ばかりではなく、状況が悪い時は自暴自棄になり、裏切ったり騙したり、信用に値しない行動を取ってしまうこともある。
日本だとそれは、ある程度の情状酌量はあったとしても、努力や頑張り、優しさなどによる「自己責任」と見なされ、その人の過去として信用を測るために使われる。ところがタンザニアの人々にとってそれは誰しも起こり得る状況であり、確かに残念なことではあるが、「その人が悪い、信用できない」という結論にはならないらしい。
皆、口では「誰も信用できない」と言い、一見冷たく見えるのだが、それはひるがえって「状況が悪ければ誰だって悪い行動を取ってしまう、それは仕方のないことだ」という公理の言い換えに過ぎない。逆に過去やってしまった悪い行動は重視されないということになる。
分人主義の実践
ここで前提に置かれているのは、人間に一貫した不変の自己などないという認識だろう。流行りどころにひきつけると、クレイトン・クリステンセンのジョブ理論や、鈴木健あるいは平野啓一郎の「分人」にも通じる人間観だ。しかし平野やクリステンセンの議論があくまで抽象的な思考実験にとどまっているのに対し、『チョンキンマンションのボスは知っている』が描き出すオルタナティブな評価経済の形象はきわめて具体的なかたちであらわれる。
たとえば携帯電話を取引しているシュワという人物のエピソードがわかりやすい。シュワは元々タンザニアで商売をしていて、日本円で月に600万円をひとりで稼ぐほど儲かっていた。ところが、2020年に別の事業に投資して失敗し、さらに配偶者に離婚を迫られて財産を失い、香港に亡命希望者として逃げてきた。
彼はタンザニア時代に、いろいろなひとに奢ったりビジネス資金を貸したりしていたが、羽振りがよかったこともあって返済はうやむやになっていた。
チョンキンマンションには当時の貸し先相手のひとりだったCという人物がいる。Cはシュワに金を借りたあとにその後に農機具の貿易業に転業して成功していたので、シュワは再起を図るときにCに支援を頼んだ。しかし、返ってきた内容がおかしいと怒る。
シュワいわく、「おれがCを助けていた期間は3年で、やつが香港に来るたびに食事を奢ったり商売の相談に乗ったり、交易のついでにやつの商品を無料で密輸して危険を冒したりしてきた。しかし、おれが香港に逃げ込んで支援を求めたときには、ポンと800ドルの金をくれただけだった」と。
著者によるとシュワは、Cが返してくれた金額が少なくて不満だというわけではないという。「おれが欲しいのは金じゃない。おれがもう一回やりなおすチャンスなんだ」というのがシュワの不満なのだ。
著者は、マルセル・モース『贈与論』の図式を援用してこのシュワの不満を説明する。『贈与論』は経済の話として読まれることが多いが、実際に読むと中核はスピリチュアリズムに近い。贈与とは、物に霊が宿ることだというのが同書の要点だ。モースは、「贈り物に対する返礼が起きるのは、贈り物に取り憑いた精霊が与えたひとの元に戻りたいと望むからだ」というマオリ族の話に着想を得ていた。
シュワがCに金を貸すと、そこにシュワの一部が取り憑く。受け取ったCは、それを返すまでシュワの一部とともにずっと生きることになる。そうやって、シュワという個人が、「分人」としていろいろなところにすこしずつ散らばっていく。
シュワの一部は、シュワに戻りたいと望むときに、なにかのかたちで返ってくる。でも、それはシュワが与えた時点で相手が持っていたものではない。託された「シュワ100分の1」みたいなものは、その相手のもとで育まれて、シュワのあずかり知らないかたちに変身する。与えた相手のCは成功するかもしれないし、別の誰かは落ちぶれるかもしれない。いずれにせよ、シュワはシュワの一部を持つだれかとともに、未来にいたる道を分かちあっている。
つまり、「シュワのおかげで成功した見返りに800ドルをあげる」というCのふるまいは、預かっていたシュワの分人を、まるで配当金のように扱う振る舞いなのである。これではシュワの一部が800ドルという金額に換算されたようなものだ。だからこそ、シュワは屈辱を感じたのだと著者は考察する。
人生の保険
チョンキンマンションのタンザニア商人たちは「人生の保険」という言葉をよく使う。ただしそれはわれわれ(日本人)が「人生の保険」ということばから想起するような「出世払い」や「積み立て」、「投資」といったような感覚とはまったく異なる。
「人生の保険」は、自分ひとりでたくさんスキルを身につけるのではなく、貸しを与えることで、外付けハードディスクのようにいろいろな種類の人間を周りに配置していくことに近い。自分はやりたいことをやるが、なにかのついでに、周りのひとたちを支援もする。そして、たとえばパソコンが壊れたときに、「昔ラーメンを奢ったあいつはたしかパソコンが得意と言っていたな」と思い出して、電話で助けを求める。
重要なのは、これがコミュニティを作るということとは異なるという点だ。チョンキンマンションの住人的な意味での「人生の保険」は、ただ個人的なネットワークが重層的につながっているだけに過ぎない。
具体的には、とにかくいろいろなひとに奢っておくということが重要なのはもちろんだが、貸しをすぐ返してもらわないことが同じくらい重要だ。自分が必要となるときまで放置しておく。借りのあるひとたちも、相手が必要とするときまで忘れておく。彼らにとっての貸し借りは、返済の機会が訪れてはじめて、どう返ってくるかがわかるものなのだ。偶然に約束が果たされてようやく、約束の存在も意識される。機会が来なければ、貸し借りはたんに「なかったこと」になる。贈与をしてもなにが返ってくるかわからないから、自分に借りを持つ相手をどんどん増やしておく。これこそ「人生の保険」が指す意味なのである。
彼らはとにかく、稼いだ金を多様な人間というかたちの保険に変えていくので、貯蓄はしない。著者によれば、チョンキンマンションには、1億円を動かしている商人もいれば、月に10万円くらいしか稼ぎがない商人もいるが、売り上げの多寡によらず銀行口座すら開設していない人が多いという。
たくさん稼ぐ商人は、貯蓄をする代わりに貸しを増やし、いろいろなビジネスに投資する。ビジネスに投資しておけば、たとえ狭い意味での「投資」としては失敗したとしても、少なくとも人間関係だけは広がる。だから貯金はないいっぽうで、なにかアイデアを実現したいと思ったときにすぐに頼れるひとはたくさんいる、という状態になるのだ。
つまり、貸しは金でなくてもなんでもよくて、びっくりしないくらいのもののほうがいい。ただ、借りを返す機会がやってきたときには、その返し方が問われる。
返済金額としてはむしろ十分だったのに、それでもシュワは不満をもった。Cがすべきだったのは、かつてのシュワとおなじように、「自分だからできること」を考え、してあげることだったのだろう。これが、タンザニア人商人たちが贈与を通じてつくる「人生の保険」だ。
「人生の保険」という、感覚に基づいたゆるやかな互酬こそが、サブタイトルとなっている「アングラ経済」の正体だ。チョンキンマンションのタンザニア人たちのように、みながたがいに贈与し、必要になるまで借りは返してもらわないという実践をいきわたらせる。すると、ひとりの個人が複数に分割され、全員が部分的にシェアされた世界が遡行的にできあがる。
これこそ「基盤的コミュニズム」にもとづいたシェアの世界だと著者はいう。わたしの一部はだれかのもので、だれかの一部はわたしのものというイメージで、贈与に対する見返りを即時的に期待せず、借りを計算することもできない人格を想定して社会をつくることに繋がる。
人間が幸せな経済
わたしたちはなんのために金銭や物を使うのか。流通させるのか。
それは突き詰めれば、自分の人生をそれぞれのやり方で生きていくことを可能にするためだろう。別にお金がたくさんあることが幸せなわけではない。人間が幸せな経済とは、全人格的な取引が非人格的な取引に変化しない経済のことなのではないか。人格を貨幣や商品のように扱わず、互酬に失敗しても怒られずに生きていける。働いても働かなくても、与えても与えなくても、他人と生きてもひとりで生きても、「まあいいや」で回る経済=アングラ経済を、チョンキンマンションのタンザニア人商人たちは実現している。
ここには、正義や倫理で規定される理想的な人間性ではなく、それぞれの人間がそれぞれの自然を謳歌できる世界の可能性が示唆されている。その世界は、経済的なパフォーマンスに基づくメリトクラシーに支えられ、透明性を重視して広く行き渡る福祉がそれを補うような世界よりも、よほどユートピアに思える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
