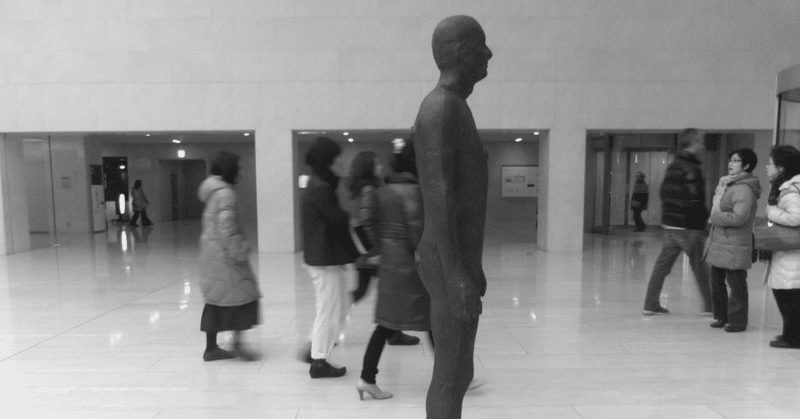
未来をつくる言葉
『未来をつくる言葉』 ドミニク・チェン
表現、対話における技術と進化をめぐるお話である。
著者のドミニク・チェン氏は複雑な言語的文化的背景を持つ。
日本人の母、台湾とベトナムのルーツながらフランス国籍を持つ父の間に、フランス人として日本で生まれ、中学高校はフランスで過ごしアメリカの大学を卒業している。
この刺激的な経歴だけ聞くと、なんと恵まれた、という印象であるし、事実恵まれた環境の育ちであると思うのだが、著者は幼少期より吃音という問題を抱えてもいる。
吃音の原因に何か負の背景があるのかとかいうことではなく、軽度であれそのような不便を抱えて暮らすというのは厄介なことだろう。
100%パーフェクトな苦労知らずではないということだ。
そのようなプライベートな事情を含め、本書で著者は自らの人生の歩み、娘の誕生など大きな出来事に対する感情や発見を、等身大に赤裸々に語り、そこから思考と知識を掘り下げていく。
その特殊な経歴を土台に織り込みながら彼がめぐる話題は、言語、文化、哲学、AI、、、と聞こえはアカデミックだが、ファミコンなど同世代感のある経験を交えながら親しみのある語調で語られ、ベンチに並んで座って気楽に話をしているうちに色々なことを教えてもらっていた、というような、楽しく骨のある講義である。
海の中を泳ぐ魚や空を飛ぶ鳥のように、生き物にはそれぞれの環境に応じた身体があり、その知覚によって全く異なる世界の認識がある。そのような環世界(それぞれの生物によって知覚されている固有の世界)と同じように、私達人間には、使っている言語ごとに異なる環世界があるのではないか。このような視点から著者は思考を広げる。
生まれてから幼児期までは日本語で過ごし、通い始めたフランスの学校でフランス語を学び吸収するうちに全く違う世界を発見したという経験が著者にとっての実感であるが、二か国語以上の言葉を使える方には、一つの言語ともう一つの言語を使用している時には作動している感覚が少し違っているのが実感されていると思う。
言語的環世界の経験の次に著者が出会うのが、哲学、そして表現とアートである。
フランスの学校での哲学教育(結論ではなくそこに至る論の構造を重視し、評価する)で著者は、言語的な構造の力で、異なる意見同士がコミュニケーションできるということに気付き、さらにコンピューターグラフィックの使用などを通じて、環世界を非言語的な方法で表現する面白さに目覚めたという。
アメリカの高校で出会った哲学の先生から与えられた「芸術に人間は何を求められるのか」という課題が、彼の進路を決定するきっかけになると共に、その命題を追求する言語的非言語的な試みが彼の今までの歩みにもなっている。
キーボードでの作文過程を全て文字に起こすという「タイプトレース」や、ぬか床(ぬか漬けの、ぬか床である)にセンサーと音声システムを内蔵し、人間と言葉でコミュニケーションできるようにするというNukaBotなど、著者の開発はバイタリティに富み発想はユーモアに溢れる。
またそのバイタリティは、モンゴルでの結婚式や娘のフランス語教育における試みなど、実生活にも存分に発揮されている。
自由な試みの数々を知るだけでも目が開かされるが、彼が最も重視しているのは、対話というコンセプトである。
「創作とは他者との関係を生み出す契機」と著者は言う。
また、「他者と関係する方法を探るためにこそ、情報技術を活用するべき」と、そのビジョンは明確である。
「表現行為は、決して作者のうちに完結しない。」
「受け取り手が表現された領土を自由に探索し、そこから新しい価値を自らの領土に取り込む運動を通してはじめて、成立するのだ。」
対話にこそ未来がある。
コミュニケーションには挫折はつきものであるが、伝え、伝わる力を信じて対話を続けていきたいと本書を読んで思った。
文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンによるニューギニアのイアトムル族の研究や、言語教育学者の水谷信子の、日本語における「共話」の重要性に関する論など、この本では、もっと知りたいと思わせる研究や話題も多く紹介されている。
著者の次作も楽しみである。
