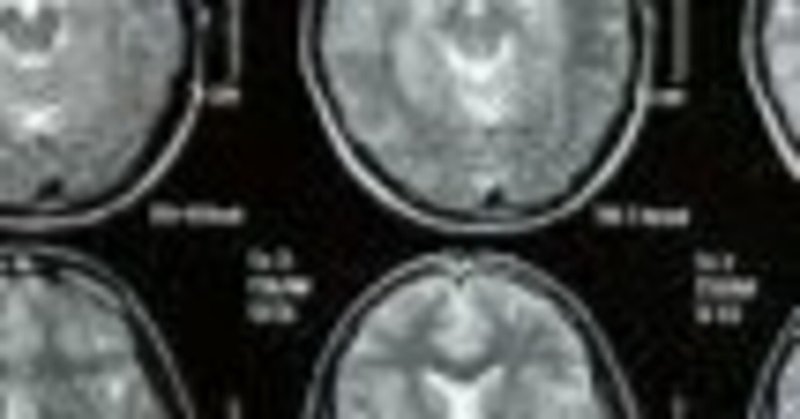
脳死および臓器移植に関する日本を場として神学的判断と牧会神学のための予備的考察
2008年度AGST(アジア神学大学)秋期講義課題
アジア神学大学院牧会学博士課程 濱 和弘
以下は、2008年度のアジア神学大学院の秋期講義の単位所得のための課題に対して書かれたものである。本来は、以下の内容に加えて、キリスト教における死の理解を加えて、脳死臓器職に対する牧会的視点からの試論を述べるものであるが、以下はそのための予備的考察である。
筆者は、知人がアメリカで脳死肝移植をする際に、その支援活動の責を負った経験があるが、その際、キリスト者が脳死移植という医療を受けることについて。直接、間接、また陰で脳死移植に対する批判を受けた。
もとより、意見の相違があり主張の相違があることは、当然のことであり、それは望ましい姿である。それゆえに、公(この場合、筆者が属する教団内で)にキリスト者が脳死移植を受けることの是非が議論されることをのぞんだが、色々と批判(その多くは陰での批判であったが)はあったが、結局そのような議論は起こらなかった。
本論文は、そのことを意識しつつ、上記のアジア神学大学院の単位所得のためにまとめられたものであるが、内容的にはキリスト教としてどう考えるか迄には至っていない。あくまでもその考察に至るための予備的なものであり、それゆえに結論部分を欠いている。
【緒論】
近年の医療技術の発展と共に、従来の人間の死に対して脳死という新しい死の理念が生まれてきた。この脳死をめぐっては賛否両論があるが、おおむね諸外国では脳死が人の死として受け入れられている。しかし我が国においては、現在でも脳死を人の死と受け入れられているわけではない。そもそも、日本では何を持って死と定義するかについての法的に定められてはいない。つまり法的には、死が何であるかは定かではないのだ。
では、いったい何をもって死が定義され社会的に受容されてきたかというと、それは医療現場の判断基準、すなわち死の三徴候(呼吸の停止、心臓の停止、瞳孔散大)によってである。そこに医療技術の発展に伴い脳死という新しい状況が起ってきた。それが臓器移植と関連することによって、はじめて死とは何か法的な立場から問われたのである。こうして、1997年の臓器移植法[1](*1)によって、はじめて条件付きで、脳死を人の死として受容されたわけであるが、これは臓器移植との関連においてなされた条件的受容であり、明確に脳死を人の死であると定義づけたわけではない。
もとより、臓器移植という医療行為と脳死とは別の問題である。しかし、その本来は臓器移植とは別の問題である脳死が臓器移植との関連で受け入れるというところにこの問題の根深さの一端がある。すなわち、脳死した者からの臓器移植は、まだ生きている肉体から臓器を摘出する行為ではないかという疑問である。したがって、脳死の問題と臓器移植の問題は、往々にして一つにして考えられる傾向がある。
たしかに、このように脳死の問題と臓器移植の問題を一体にして考えることが問題をより複雑化させ混迷化させている感もあるが、しかし、移植医療が治療法として存在する以上、両者がより密接な関係にあることも否めない。そこで、本論文では、脳死と臓器移植の問題が、もともとは別の問題であることを踏まえつつ、その両者が渾然一体となって受け止められているがゆえにおこる問題を整理し、脳死、および臓器移植医療についての、神学的判断を試みてみたい。そしてそれにもとづいて、牧会の現場に立つものとして、脳死および臓器移植の現場にあってこの問題に向き合う者にどのように接するべきであるかを問うこととする。ついては、次のような手順にもとづき考察を進めていくこととする。
すなわち、最初の手順として、「脳死とは何か」について明らかにしたい。これは、考察というより現状の把握である。というのも、脳死について神学的理解を試みるといっても、そもそも脳死とは何かについてが、明らかにされなければならないからである。脳死とは何かがわからなければ、神学的判断がなどできようはずものない。脳死が何かが明らかにされて、初めて神学的判断をすることができるのである。そのためには、医学現場の脳死状態がいかなるものかという、医療現場での状況が先行しなければならない。医療現場の問題については、筆者の専門とするところではない。それゆえに、ここではあくまでも一般的知識としての医療現場における脳死とよばれる状況について述べることとする。その上で、その現場的状況において脳死が人間の死として理念化される哲学的背景が述べられるであろう。そこには、自ずと人間とは何かといったことも問われなければならないからである。
このように、「脳死とは何か」を明らかにし把握した上で、次の手順として脳死を人間の死として受け止める上での日本の現場の抱える問題点について考察していきたい。それには、医学的な問題点も有るであろうし、日本人の抱える死生観の問題点などが、その宗教観と共に出てくるであろう。そこでは、何をもって死を認識するかという問題も問われることになるであろうし、法的問題や社会的通念としての死の問題も視野に入れなければならない。このような段取りを経て、初めて、脳死と臓器移植との関連性も考えられてくる。そこには、個人倫理の問題と同時に社会倫理的感覚の問題がある。
さらに、筆者は脳死及び臓器移植に対する生命倫理からの提言である自己決定の問題について述べたいと考えている。それは自己決定が脳死および臓器移植の問題を解く重要な鍵となると考えるからである。また、この自己決定という概念こそが脳死および臓器移植に対する牧会の神学のよってたつところになるであろうと思われるからである。
こうした考察を経て、次の段階として脳死と臓器移植というものに対する神学的判断が考察されることになるが、それは、おおよそ、次のようなプロセスを経なければならない。すなわち、まず神学的死とは何かが個別に明らかにされ、それを持って、脳死をどう受け止めるのかということについて考察されなければならないということである。それは、従来ごく当たり前として受け止めていた肉体の生物学的死、それゆえに救済論的に捕えられていたとしても、肉体における生物学的死とは何かいうことに対する神学理解があまりなされていなかったその神学的死を、脳死という現場から問い直し、神学的死とは何かを考察する事である。それによって脳死をどう受け止めるのかという牧会の現場でのあり方が導かれるからである。その場合、神学的死は、まず第一に聖書から考察されなければならない。それは、聖書が神の啓示であり、信仰の判断と導きとなる啓示であるというプロテスタント的前提のゆえである。そのうえで、神学的死は歴史の場で問われ検証されることになるであろう。そして、そのように問われた神学的死が、脳死の問題について考えていく上で、日本のキリスト教が日本という場において対話する相手となる。すなわち、脳死の是非を神学的死から問うのである。そのうえで、臓器移植の問題に入っていくが、この場合、問題になるのは倫理的問題であるが、その場合は、先の個人倫理や社会倫理という視点ではなくキリスト教倫理が視点になる。キリスト者として臓器移植は倫理的行動になりうるかどうかが問題となるのである。その上で、脳死との連関の中で「脳死と臓器移植」としてとらえられなければならないからである。
以上のように考察を進めていくなかで、最終的には、教会の現場での牧会者としての態度について述べたいと思う。
【本論:第Ⅰ部 日本における脳死・臓器移植】
1.脳死とは何か
1-1.医療現場における脳死と呼ばれる状態。
脳死の定義について、法医学医で元北里大学医学部長の船尾忠孝は次のように述べている。
現在国際的にも一般に広く受け入れられている脳死の概念は、脳の臨 床的に観察された不可逆的な機能停止をback bornとした全脳死である。そしてこの全能死の概念は、1985年の厚生省で作成された脳死判定指針・判定基準(以下厚生省基準)においても1986年脳派学会の提案とともに採用され、“脳死とは脳幹を含む全能の不可逆的機能喪失状態であるとしている。また国によっては、英国のような脳幹死のように多少内容は異なっても、生命維持に不可欠な脳機能の喪失状態を表現している点では共通する[2]
この、脳死の定義は、要は臨床的に脳の機能が停止し、その回復が全く期待できない状況をさしている。つまり、蘇生不能となる境界線上に脳死がある。特に脳幹は、中枢神経系に関する機関で人間の生命維持に重要は役割を果たす。それゆえに、本来であるならば、この脳幹の機能が回復不能な状況で停止するならば、呼吸や循環器系の機能、あるいは体温の調整や血圧の制御などの自律神経に関わるが損なわれる。それゆえに、脳幹の機能が不可逆的に停止すると、人間は生命を維持できず死に至る。英国が、脳幹の不可逆的機能停止(以下脳幹死)をもって、脳死ととらえるのには、このあたりのことが理由と考えられる。
従来の死は、呼吸の停止、心臓の停止、瞳孔散大(対光反射の消失)のいわゆる死の三徴候をもって、人間の死として受け止めてきた。一般に、呼吸が停止すれば、心臓も停止し、脳に酸素が供給されず脳は機能を停止する。瞳孔散大(対光反射の消失)は、その能の機能が停止したことを示すものである。
逆に脳に重大な損傷があり脳(脳幹)の機能が停止すれば自発呼吸は出来なくなり、瞳孔散大を起し、心臓もやがて停止する。このように、従来の死の定義であった死の三徴候は、それぞれが不可分的な関係にあるのだが、しかし実際は呼吸が停止してもすぐに心臓が停止するのでもなければ、脳の機能が停止するわけでもない。水に潜って呼吸が出来ない状況でもすぐに心臓が止まるわけでもなく、意識がなくなるわけでもない状況を考えればよい。つまり、呼吸停止から、脳の機能の不可逆的停止や心臓の停止まではタイムラグがあるのである。
反対に、脳の機能が停止し、意識がなくなり、自発呼吸が停止しても心臓が停止するまでもタイムラグがある。ところが1929年に人工呼吸器が開発されて以降、脳の機能が停止しても、機械によって呼吸が確保されているならば、心臓は動いているという状況がおこった。これが、ここで取上げるいわゆる脳死という状態である。
1-2.生物としての人間にとっての人間の死
脳死という医療現場における状況は、上記のようなものであるとして、問題は、この脳死を人の医学的意味での人の死として認めるか否かである。少なくとも、脳の不可逆的機能停止である脳死も、肺の不可逆的機能停止の呼吸停止も、また心臓の不可逆的機能停止の心臓死も、個別的に言えば個々の臓器の臓器死である。この三つの臓器の不可逆的機能停止である死の三徴候も、人間の生物としての存在全体からみれば、一部分の機能の不可逆停止にすぎない。しかし、その一部分の不可逆的な停止をもって、人間の存在全体の死として受容してきたのは、これらが相互依存的に、人間が生物として存在するのに絶対不可欠な機能を負っているからであり、これらの機能が損なわれることによって、必ず人間の全体の組織が不可逆的に損なわれることが経験則から知られうるである。つまり、死の三徴候によって死を宣告されたものは、絶対に回復しないという経験則である。
このような、相互依存関係について、早稲田大学刑事法学研究会が、その研究報告の中で、医学的見知からということで次のような報告を載せている。
錫谷徹教授[3]は、この『生命の全体性』と死の概念について、次のように叙述する。すなわち、生命維持に必要なエネルギー源、特に個体を構成するすべての細胞に共通して必要な摂取分配は、肺と心臓と脳の機能によって行なわれ、この三つの臓器は互いに支持し合って結びついて単独では存在しえない。三つのものがそれぞれ相互に結びあう関係になるのは、その三つのものが一つの環を形成することである。この環の存在こそが、個体としての生命現象である。つまり、肺・心臓・脳・の三つの機能が揃って存在し、しかも、この三つの機能が血液・血管・神経で連結しているのが、「生命の環」であり、個体レベルの生命である。したがって、個体レベルの死とは、個体レベルの生命の消えることであり、肺・心臓・脳の臓器部分、または、肺・心臓・脳を連絡するとして表現すれば『肺・心臓・脳のいずれか一つの永久的(不可逆的)機能停止が個体死である』ということになる。(錫谷徹「死の判定に関する私見」日本医事新報3022号、1982年、43-45頁)[4]。
ここにおいて言われていることは、人間は自然な状態にある限り、まさに肺・心臓・脳が三位一体となって人間という有機的統合体の生命現象の全体を統合し支えているということである。
脳死においては、少なくともこの死の三徴候の呼吸という肺の機能を人工呼吸器が代行することによって、肺と心臓と脳の機能が相互依存することなく、機械の支援を得ることで、心臓が機能する。しかし、いかに脳と肺以外の機能を維持することを可能し、それによって脳以外の有機体を構成する部分の機能を維持したとしても、肺、心臓・脳という三位一体の構造が壊れてしまっている以上、肺・心臓・脳の「いずれか一つ永久に機能停止した最初の時が個体の死である。(錫谷徹『脳死と個体死』日本医事新報3131号(1984年)五三-四頁)」[5]とする錫谷にとって脳死は人の死なのである。
もっとも、このような見方は錫谷の私見であり、一般には必ずしも、肺・心臓・脳の三位一体のいずれか一つの機能が不可逆的停止した段階で人間の死とは見なしてはいない。むしろ、この三位一体の内の脳に優位性を与え、脳の機能が不可逆的に停止場合を脳死として人の死とするのである。これは、脳が有機的統合体としてのホメオスタシスの統合の中心であり支配的存在であると考えられているからである。
ところで、このように人間を有機的統合体としてとらえるという視点には、人間とは何かという問いがアプリオリにある。つまり、そこには人間の死を問うときには、人間という存在を前にして、人間とはどのような存在であるかという哲学的な問いがあると言うことである。しかも、それは人間の生命をかけた倫理的な問いでもあるが、それに対する生物学的視点にたって答えが、人間は人間を組織する機能の有機的統合体であるということなのである。つまり、このような生物学的視点にたっての哲学的理念に支えられた医学的知見として、脳死は人間の死として受容されるというわけである。
1-3.人格的存在としての人間の死
さて、人間を有機的統合体としてとらえ、生物学的視点からみた医学的見知としての「脳死は人の死である」という捉え方に立つならば、脳死は基本的に脳幹死をもって人間の死と考えてよいということになるであろう。
しかしながら、人間とは何かという哲学的問いとして考えるときに、単に生物学的視点からのみ人間が定義されるわけではない。アリストテレスは「人間はポリス的動物である」といい、デカルトは「われ思う、ゆえにわれあり」といい、またパスカルは「人間は考える葦である」といった。これは、人間が、単に生物学的一面からとらえられる存在ではなく、社会的存在であり、また精神的存在であることを見抜いた言葉であろう。それは、単に身体的な事だけで捕らえられるものではなく、関係性においてとらえられるべきものであり、思考や感情、あるいは性格といったものを含む人格と呼ばれる内面性によっても捕らえられるものであることを意味している。それゆえに、人間とは何かという問いに対して、単に生物学的視点から見た答えだけでは十全ではない。それはつまり、人間の死は、単に脳幹死や肺臓死、また心臓死といった「生命の環」の崩壊だけでとらえることができないものであることを意味している。
このような、社会的存在、また精神的存在である人間を、現実の生理学的レベルにおける死という土壌で考えることが出来るとするならば、それは大脳の回復不能な不可逆的機能の停止(以下大脳死)である。このようなわけで、脳死の問題を考える場合に、大脳死をもって人の死と考える見方がないわけでもないそれは、人間が人間たるゆえんは、その社会性、精神性といった人格にあるという理解によるものである。
それに対して、日本における脳死の定義は、全脳死つまり脳幹死と大脳死の両方をもって脳死と定義している。すなわち、「脳死が人間の死」であるのは、生命活動の根幹を支える脳幹の機能が不可逆的に停止するということだけでなく、それに加えて人間の人格に関わる高次の精神的活動を支える大脳が不可逆的に機能を停止しなければならないのである。
1-4.死は瞬間ではなくプロセスである。
従来、われわれは死の三徴候をもって、死を一点的・瞬間的にとらえてきた。しかしながら、実際には、死は一点的・瞬間的に訪れるわけではない。死の三徴候であったとしても、呼吸停止から心臓死そして脳死に至るまでには時間差がある。これは、脳死から呼吸停止そして心臓停止までに至る過程においも同じである。ましてや、この死の三徴候をもって死と判定した後も、全身の機能、あるいは全細胞レベルにおよぶ死に至るまでは更なる時間差がある。このような状況を、尾形誠広は、次のような説明をもって死は点でなく線であるという。
しかし、従来から死の判定には一般に三徴候説がとられてきており、混乱はなかった。三徴候説とは呼吸の停止、瞳孔の散大、心臓の停止である。これは時間の点(心停止)としてとらえられ、何時何分に死亡したと死亡診断書に記載されるのが慣行であり、一種の慣行法にまで高められているといえる。しかし人間の肉体はその時刻に完全に死んでいるわけではない。一部はまだ生きており、徐々に死んでいくのである。脳の障害ではなく、心臓の障害のように、心臓死(心臓の停止)の場合は、死が宣告されても、その後、大脳皮質は3分、脳幹は8分、皮膚や爪で48時間(2日)、骨や動脈では72時間(3日)も生きているという報告がある。すなわち死の判定後も全臓器の死がやってくるのは3日後ということになる。このことを裏づけるように、2~3日後の死者の棺桶を事情があって開けてみたら、爪や髪が伸びていたという話が語り継がれている。以上のことから人間の死は一瞬にして生から死に至る (点)のではなく、各臓器・組織・細胞の連続した部分的死が続いたあとで終了するという過程(線)であることがわかる[6]。
この尾形の言葉は、脳死に対して言われた言葉ではない。死の三徴候をもって死としたとしても、それは死の過程の中の一点で死を判定したのであって、それは死を迎えるにあたっての約束事であるというのである。だからこそ尾形は「ただ死亡時刻の判定を便宜的習慣的に三徴候揃った時刻(点)として社会的法的な混乱を避けてきただけのことである[7]」(*9)というのである。つまり、社会的取り決めとして死の不可逆的な過程の始まりを死の三徴候が認められたと判定した時点においたということにほかならない。だとすれば、脳死は、その不可逆的な死の過程を、死の三徴候よりも前の脳死と判定された時点においたということになる。結局、こうしてみると脳死か従来の死の三徴候かという議論は、死の不可逆的過程において、何をもってその始まると見るかという問題であるといえよう。同時にこのことは、死は死の過程にある者にとってではなく、残された者が何をもって死んだということを認識し受容するかということを示している。従来は、医者が死の三徴候を確認し、臨終を宣告するその宣告をもって、社会と残された者は、死をとりあえずの現実として受け止めてきたのである。そういった意味では、脳死は、その受容をより早くわれわれに求めるものであるといえよう。
2.日本という場における脳死が抱える問題
2-1.問題とされている事柄の整理
日本においては、脳死が人の死であるということを受け止めることに対しては、多くの批判がある。
もちろん、諸外国においても全く批判がないというわけではないが、それでも脳死は社会的コンセンサスとして受け入れられている。しかし、こと日本においては1997年の臓器移植法によって、条件付きではあるが実質上「脳死は人の死」として受け入れられたが、以前として強い批判にさらされているのも事実である。
この脳死に対する批判は、おもに臓器移植との関連においてなされることが多い。すなわち「生きた人間から臓器を摘出するのか」という批判である。この場合、「脳死は人の死ではない」がある。しかし、この「脳死は人の死ではない」という批判も、厳密に見ていくならば、「脳死は人の死である」とした前提となる哲学理解に対する問題と、純粋に医学的問題からみた問題から見た批判に分けることが出来る。
たとえば、後に述べるシューモンによる報告は前者に属する問題であり、後者は、これもまた後に述べることになるがラザロ症候群などがそれに属する。したがって、筆者はここで問題を整理するために前者を哲学系の問題とし、後者を医学系の問題とに系統立てる。さらに、医学系の問題の中には、前述のラザロ徴候のような臨床上に起る現象の問題と脳死判定に対する批判といった脳死そのものに対する批判とがある。それゆえに、医学系の問題の中をさらに現象に関する批判と、脳死判定に関する批判に分け、前者を現象群の批判と呼び、後者を判定群の批判と呼ぶこととする。
また、「脳死は人の死ではない」という批判の中には、「体がまだ暖かい内は、死んだとは思えない。呼吸と心臓が止まり、体が冷たくなっていくことで死んだと感じられる」という死の受容からの批判もある。筆者はこれを関係系の批判とする。それは、おもに残された者が死者との関係の中で感じる死の問題だからである。つまり、二人称の死からおこる死の認識だからであり、それはつまり関係性の問題と考えられるものである。このような関係性の問題は、私の死という自分自身が自分自身に関わる一人称に死の問題も含まれる。
そして、第4の系統として医療不信に関する問題を取り上げたい。筆者はここではこれを医療不信系の批判と呼ぶこととするが、脳死の問題の中には、実は医療不信が背景にある批判も少なくはない。先に述べた医療系判定群の批判も、一部はこの医療不信系に関わる問題でもある。特に臓器移植との関係における医療不信の問題は根深いものがある。そこでに、ここでは医療不信系の問題という一つの系統として独立して扱う。
そして、第5の系統として、宗教との関係について問わなければならない。これは哲学系の問題の中に入れても良い問題であるが、特に理念や思想以上に、日本人の宗教的霊性が関わる問題がそこにあり、あえて一つの系統とした。その上で最後に、臓器移植に関する批判について触れたい。それは脳死に対する批判を前提とした臓器移植批判ではなく、臓器移植そのものに対する批判である。
以上のようの問題を整理して、脳死と臓器移植に対する批判を検討していくことにする。
2-2.脳死に関する批判
2-2-1.脳死に対する哲学系の批判
われわれは、脳死を人間の死として受け止める前提に、人間を有機的統合体であるという哲学的理解があり、その理解にたって脳が有機的統合体としての生命の統合の中心であり支配的存在であるから医学的見知から脳死は人の死として認められるであるという考えがあること見てきた。いや、ここのところは厳密に言わなければなるまい。脳死は人の死の不可逆的な過程の始まりとして認められるというとである。
このように、脳、特に脳幹が、有機的統合体の統合の中心であり支配的存在であるがゆえに、従来はその機能が不可逆的に停止すると10日から2週間程度で心停止も起るとされてきた。ところが、1988年にアラン・シューモンによって脳死と判定された患者がある程度長期に渡って心停止に至らなかったという事例が複数報告され[8]、それによって脳が有機的統合体の統合の中心ではないとの見方が表れてきたのである。
シューモンの報告には、脳死判定後数ヶ月から数年、心臓が動いていた例が報告され、最長は、14年5ヶ月の例もあり、脳死の肉体の状況も安定してくると言う[9]。このような、脳死後の長期の(従来の死の三徴候の死の概念における)生存を、長期性脳死もしくは慢性脳死とよぶが、このような脳死判定後の長期の生存については、日本の臨床においても確認されている。たとえば井形昭弘(元鹿児島大学医学部教授)は札幌大学教養学の部特別講義(1993年)で次のように述べている。
10年以上も前に、たまたま妊婦が脳死の状態になったケースを経験しました。脳死だから当然数日の内に必ず心臓が止まると思っていました。そこへ家族からお母さんはやむ得ないけれども、できたら子供だけは救いたい、との申し出があり、産科の先生もまだ非常に小さい胎児だから一日でも長く子宮の中に置いていてくれたら助かる見込みがふえると言われ、いろいろ手だてを講じたわけですね。その中に、尿が急に増えて来ました。脳が全部やられますと脳の下垂体もやられますが、下垂体の後葉は、抗利尿ホルモンを分泌しています。これがやられたらホルモンが不足して、尿崩症といって尿が非常に多くなるのです。この方は脳下垂体もやられたために尿量がふえてきたんですね。尿崩症ならば抗利尿ホルモンを補充してやれば良いというので、これを補充して、血圧を上げる薬をやったところが、57日間心拍が続きました。今までは脳死という状態になれば数日以内には必ず心臓が止まるから、死であるということだったんですけれども、こういうことになってから脳死が長く続くようになってきました。ちょうど同じころ大阪大学でも同じことに気がついて、今は脳死という状態が抗利尿ホルモンと昇圧剤を投与すると1ヶ月、2ヶ月はもつようになってきたんですね。このかたは57日間ももって、結局、帝王切開で赤ちゃんを取り出して、その赤ちゃんは今、元気に育っており、間もなく高校生になります[10]。
1993年の講義から10年以上前と言うことは、シューモンの研究以前に、井形は長期性脳死を知っていたことになる。また井形は、当時そのことを学会にも報告し話題にもなった[11]というのであるから、1980年代前半において、日本の医学界においても、そのことは、少なからず知られていたのだろう。しかし、いずれにしてもシューモンは、このような状況から、脳が有機的統合体である人間のその統合の中心であり支配的位置を占めているということに意義をとなえるのである。すなわち、人間という有機的統合体は、脳だけではなく身体の諸部分間の相互のやりとりによるというのである[12]。
このことから、美浜美彦(東京海洋大学教授・科学史、生命倫理学)は「脳死を人の死とする大前提、すなわち『脳幹を含む全脳の不可逆的機能停止』は『身体部分を統合する機能が不可逆的に失われたことを意味』する、という大前提をも覆したことになる。それゆえ、シューモンの主張に従うなら、日本において「脳死は人の死といえないことになるのだ」[13](*15)と批判する。すなわち、脳死は人の死であるということの哲学的大前提が崩れたというのである。
しかし、われわれはここで見落としてはならない事項があることに目を向けなければならない。すなわち脳死は、人工呼吸器によって脳死患者の呼吸が維持されているという特殊な、自然ではない状況下で起っている出来事であるということである。つまり、脳死判定後に、長期に渡って心停止が起らず心臓が動き続けているという状況は、あくまでも人工呼吸器のもとで心臓が動き、それに伴って脳幹と肺以外の臓器の機能が保たれているのである。しかも、確かに従来の10日から2週間で心停止すると考えられた期間よりも、長い期間にわたって心臓は動いているが、しかし、ひとたび人工呼吸器はずすならば、その脳死患者は、たちどころに心臓の鼓動を維持することはできないのである。それは、錫谷のいう前述の、肺・心臓・脳・の三つの機能が揃って存在し、しかも、この三つの機能が血液・血管・神経で連結しているのが、「生命の環」であり、個体レベルの生命であるというその「生命の環」の連結が、脳死者の自然な状況においてはすでに完全に崩壊しているのである。脳幹死をもって人間の死とするのは、このような事情によるといえよう。脳幹が死んでしまったならば、自然な状況では有機的統合体としての人間の身体を維持することは不可逆的に出来ないのである。つまり、脳死した後、その身体の統合を保っているように見えたとしても、それは、ある意味人工呼吸器の元での見せかけの統合に過ぎないのである。そのような状況を船尾忠孝は次のようにいう。
全脳の不可逆的な機能喪失の結果、深昏睡(超昏睡)となり、自発呼吸も永久に停止し、一旦停止した心拍動も肺と共にレスピレーター(筆者註:人口喚起器もしくは人工呼吸器)によって人工的に動かされていることが確認された脳死の場合、本質的には臨床医学的な従来の三徴候による心臓死と同等に考えるべきものである。したがって従来の心臓死の他に、脳死をもって人間の死と認めるという2種類の死の定義は到底適切なものとは考えがたい。すなわち、医学・医療の著しい進歩によって、死の三徴候を確認するための臨床医学的な手段が改良された結果であって、“脳死”は個体死で本質的には、心臓死と同等なものと思考される[14]。
要は、全身の機関の存続は酸素が供給されることによってなされるのであり、脳はその肺の活動を支配するものであるから、脳が不可逆的に機能停止するならば、人工呼吸器によって呼吸と心拍が保たれていたとしても、人はみずからによって呼吸を確保することはもはや出来ないのであるから、すでに、全身に酸素を供給し全身の臓器を支えることは出来なくなっている。だから脳死は人間の死であるというのである。これは、まさに脳幹死をもって生物としての人間の死とするということである。
脳死に近い状態の者が回復することや脳死患者が人工呼吸器のもとで長期に心拍動維持する事例は確かにある。しかし、脳死の患者が回復することはなく人工呼吸器なしで呼吸は確保できないのである。 結局、脳死患者の場合、不可逆的な死の過程に入っているのであり、そこにおいて人間の自然な有機的統合体としての人間の統合は不可逆的に失われており、人工呼吸器という有機的連関とは無関係な機器が、その統合性に不可逆的に参加することよってのみ、その身体が維持されているのである。
もちろん、このような議論は、突き詰めていくと、完全な人工心臓が開発され、重い心臓病患者に対して、人工心臓を移植してその機能を代行させた場合、その患者は、人工心臓によって「生命の環」を支えているのだから死んだ、あるいは不可逆的な死の過程にあるというのかというところに行着くであろう。このような状況は、すでに人工呼吸器や人工心臓といった従来の死の三徴候に関わる臓器に対してその臓器の機能を代替する機械が導入された時点で、従来の死の三徴候という死の概念が崩れてしまっていることを意味する。すなわち、人工呼吸器や人工心臓の導入によって、肺の機能と脳幹に機能の一部、そして心臓の機能の停止は、もはや不可逆的な停止ではなく、少なくとも、機械によってではあるが永久的に可逆的なものとなるからである。
したがって、このような状況の下では、もはや人間が有機的統合体であるという医学的視点に立った哲学的理解それ自体が崩れてしまっている。つまり、人工呼吸器や人工心臓が人間の有機的連関とは関わりなく不可逆的に統体としての人間存在に参加しその機能を代替するのである。このような状況下にある人間は、生物学的にはもはや有機的統体といえず身体的統合性も失っている。
このとき、このような状況下にあって人間の生死が問われる場合、必然的に「人間とはとは何か」という問いに対しする医学的・生物学的な答も違ったものとならざるをえない前提が違ってくるのであるから、当然、死の確認もまた従来の死の三徴候とは異なったものとなる。いずれにしても、人工呼吸器の不可逆的な関与の元にある脳死患者の心臓が長期にわたり動いたという事実を持って、「すなわち『脳幹を含む全脳の不可逆的機能停止』は『身体部分を統合する機能が不可逆的に失われたことを意味』する、という大前提をも覆した」とは、その前提となる人間は有機的統合体という医学的見知にたつ人間理解が、人工呼吸器を導入した時点で崩れている以上、必ずしもいえないのである。むしろ、自然的な生においては、脳が機能しないということは、呼吸活動が機能しないということであり、それは有機的統体としての人間の死の始まりなのである。だからこそ、「深昏睡で呼吸・心停止の場合、レスピレーターによって自発呼吸のない人の呼吸を人工的に維持し、その結果心臓に酸素がゆく状態にすれば、もともと自動的である心拍動はある期間続けるわけで、この場合の全能機能停止時における深昏睡という よりも、正にMollatet[15]の云う超昏睡の際の人工的な呼吸運動および心拍動は、遺体を喚起した結果であり、レスピレーターつきの遺体と理解することができる[16]という見方も出てくるのである。
それゆえに、むしろ脳死と呼ばれるような自然の生と異なる状況にある人間の生を問うとするならば、「人間とは何か」ということに対する生物学的・医学的視点からの別の新たな答えが必要であろうし、それにはそれに先だつ哲学的理解が必要であろう。それにもとづいて、死の三徴候にかわる死の判断基準に立脚した死が問われなければならないであろうし、実際、それが必要とされているのである。
2-2-2.脳死に対する医学系の批判
ⅰ.医学系批判における現象群に対する批判
脳死と判断された患者が動くという事例が臨床の場では数多くあるという報告がある。小松美彦は、その事例の幾つかを以下のように紹介する。
・事例1
1973年、カナダのオタワ総合病院のレスリー・イヴァンは、脳神経学の専門誌Neurogy,(vol23,June)に『脳死における脊髄反射(Ivan[1973])という論文を著わし、脳死者に刺激を加えるとゆっくりとした首の運動をはじめとした種々の脊髄反射が出現することを報告した。彼の調査によれば、その割合は実に脳死者75%に達したという。また同年、デンマークのE・O・ヨルゲンセンらも、63名の脳死者の皮膚に刺激を与えたところ、21名(33%)に腕や四肢全体に屈伸運動が表れたことを報告している(Jorgensen[1973])。このように脳死者に脊髄反射による動きがあることは決して稀ではないのだ[17]。
・事例2
1983年、アメリカのテンプル大学病院のスティーブン・マンデルらは、著名な医学雑誌The New England Journal of Medicine(vol.307,No.8) に目を見張る症例を報告した(Mandel[1982])。28歳の男性の脳死者の身体に連続した動きが見られたというのだ。脳死判定から15時間経った後、四肢の伸張運動に続いて、左足がベッドから自然に持ち上がり、両腕もおよそ45度まで上がった。そして、両手を合わせていのるような動作をして、指を握りしめた。その後、両手は離れて胴体の横へ戻った。この間、両足は交互に動き、まるで歩いているかのようだった。こうした運動は自発的に4日間つづき、刺激を与えるとさらに5日間起ったという。1984年、アメリカのマサチューセッツ総合病院のアラン・H・ロッパーはNeurogy(vol.34,August)誌に同種の症例を5件報告し、それを『ラザロ徴候』と名づけた(Ropper[1984])[18]
小松は、この事例の他にもこのようなラザロ徴候が日本において報告された事例をいくつか紹介しているし[19]、森岡正博も小松が紹介した事例以外の幾つかの事例を紹介している[20]。また、第43回日本リハビリテーション医学会学術集会にても、長期間にわたって脊髄反射や脊髄自動運動が見られた脳死患者の報告がなされている[21]。
このような事例の場合、諸外国それぞれで脳死判定の基準が違うので、そのあたりのことは若干考慮に入れる必要もあろうかと思われるが、いずれにしても、脳死と判定された患者が動くという現象は確認されているのである。
このラザロ徴候に対して、その名付け親であるロッパーは脊髄反射であろうと推定している。また、日本におけるラザロ徴候の報告者である浦崎永一郎も脊髄反射およびであろうと見ている[22]。更に、上記第43回日本リハビリテーション医学会学術集会で報告した丸屋 淳、 高堂 裕平、 高野 裕一も、観察された脳死者にみられる動きを「本症例では、大脳および脳幹と脊髄の間の機能連絡が遮断されている可能性が高く、これらの自動運動は脊髄由来のものであると思われた。[23]」と考察している。
もっとも、先の丸屋、高堂、高野の考察において「脳死患者の複雑な自動運動を解明するには、更なる症例の積み重ねと詳細な検討が必要である[24]」といわれるように、脳死者に脊髄反射、脊髄自動がおこるシステムが病理的に解明されているわけではない。それは臨床的判断[25]なのであって、それゆえにラザロ症候群のような複雑な動きを脊髄反射、脊髄自動とすることに慎重な態度をとる者もいる[26]。
このような現象の他に、妊婦の脳死患者が脳死後に出産するケースや、脳死と判定され臓器移植のために脳死患者にメスを入れようとするときに血圧が上がったり、汗を掻いたりする現象がある。前者については、仮に脳死状態にあり、人工呼吸器のもとでの見せかけの統合であっても脳以外の身体組織が統合されているのだから、当然、起りうることが考えられる現象であるといえよう。いや、むしろ先のシューモンの報告にあるように、有機的統合体である人間が、その身体の器官の相互によって結ばれた有機性のゆえに、人工呼吸器によって支えられている命ではあるがゆえに起こりうる可能性がある。ただ残念なことは、その身体の各器官を維持するのに絶対的に必要な酸素供給において、その有機性に関わらない人工呼吸器によらなければそれを維持することが出来ないということである。 ただし、脳死患者の自然分娩については考慮しなければならない問題がある。それは、出産時の子宮の収縮は脳下垂体から出されるオキシトンというホルモンによるものであり、ホルモンの分泌には下記で述べる間脳の視床下部が深くかかわっているからである。視床下部の問題については、次に述べる発汗・血圧上昇に問題と絡んで考慮しなければならない点を含んでいるのである、
そこで、後者の血圧上昇や発汗の問題であるが、それは脳死患者が移植のために臓器を摘出する際に起る現象であり、メスを入れられるときの激痛や恐怖によっておこる現象ではないか疑われている。たとえば、倉持武は、NHKで報道された「NHKスペシャル『脳死・生と死の選択』」で、フロリダ州オカラ病院で行なわれた脳死患者の全臓器摘出手術の様子が放映された際、麻酔行なわず手術された患者が発汗している様子に対し、「この汗は、冷や汗、脂汗としか考えられない。冷や汗や脂汗は視床下部の情動によって生じる。そして、実際に脂汗をかくということは、視床下部が機能しており、かつ、孤立せず末梢まで連絡がなければありえないことである。彼の視床下部は、冷や汗・脂汗をかく指令を出し得るレベルを維持した状態で生きていたのだと考えられる[27]」と率直な感想を述べている。
また新潟大学の生田房広による脳死患者の心臓死後の解剖例84のうち、約4割に脳死判定後4日を過ぎても視床下部の細胞が生き残っていたという報告[28]もあるのである。
たしかに、血圧の上昇についても、身体のホメオスタシス(恒常性)を保つ働きは視床下部によるものであるから、血圧上昇が見られたということは、視床下部が機能していた可能性を示すものであるということもできよう。
それに対して、このような発汗や血圧の上昇も脊髄反射の一つであると捉えるに見方もある。また、実際に現在の日本で受け入れられている脳死は、既に述べたように全脳死であるが、実質には脳幹の不可逆的機能停止と大脳の不可逆的停止をもって脳死と見ており、そこには視床下部が含まれていない。しかし、いずれにしても、ここで注意しなければならないのは、このような視床下部の問題が、必ずしもただちに脳死を否定するものとしてとらえられていないというということである。
確かに、先の倉持はこのような状況から脳死を人の死とすることに反対する。しかし、それ以上に倉持の反対は、脳死が誰にでも分かる死亡判定基準ではなく、専門家しかわからないものであるからであり、誰にでも見え、分かる基準で死亡判定とすべきであるという理由による。この倉持の批判は、医学的見知からの批判ではないが、脳死の問題に対する一つの見方を含んだものであるといえるが、視床下部の問題が決定的なものではないのである。
また、立花隆も視床下部の問題を問題視する。しかし、立花は脳死そのものを否定し認めてないというわけではない。立花の場合、脳死それ自体は認めるが、ただこの視床下部の問題を通して現在の脳死の判定の時期が早すぎるのではないか、あるいは判定基準に問題があるのではないかと指摘するのである。実際、立花によると、生田は「『脳死』と『脳の死』を区別して考えるべきだ」と言い、
一般に『脳死』といわれているのは、より正しくは『脳死と判定された状態』というべきであり、そのとき『脳の死』すなわち、『脳という臓器の生物学的死』(death of the brain tissue 脳組織の死)は、まだ訪れていない。しかし『脳死と判定された状態』のときから、『脳の死』は不可逆的にはじまる。それは脳幹部から始まり、やがて全能に広がっていく[29]。
というというのである。つまり、「脳の死」は「脳死」から始まる脳全体の「脳の死」にいたる不可逆的過程の始まりにあるといえよう。その上で、立花は、この「脳死」の時点を「脳の死」とし、それにもとづいて脳死を人の死として判断するには早すぎるのではないかと言っているのである。
この立花と倉持の批判の背景には二つのことがある。一つは、脳死臨調の定めた脳死基準に対する問題提起であり、それは次項の「医学系批判における現象群に対する批判」で取り上げる。もう一つは、視床下部が生き残っているとするならば、臓器移植の際にドナーは苦痛を感じるのではないかと言うことであり、先に引用した倉持の言葉がそれに当たる。これは、人間の意識の問題である。
人間の意識については、一般に脳幹上部にある、上部脳幹綱様体が大脳を覚醒させる働きを負っていると考えられている。それゆえに、この理解に基づくならば、脳幹死になっていれば、上部脳幹綱様体も機能を失っており、加えて、大脳の機能も不可逆的に停止している場合、当然、高次の意識はないといえよう。また、現行の日本の脳死判断基準では、平坦脳波や対向反射。眼球頭反射を行なっており、この大脳や上部脳幹綱様体の機能の喪失を確認するので、その意味では問題がない。しかし、このような理解に対して立花は、視床下部は、情動や本能の中枢でもあり、視床下部が残っている限り、大脳(大脳皮質)と脳幹綱様体の機能が失われ、高次の意識と精神活動が失われても、低次の意識は残る可能性があるというのである[30]。奥谷浩一によると、伊藤正雄(全東大医学部教授)や古川哲雄なども同様の主張をしていると述べている[31]。
もっとも、伊藤と古川両者にあってもその主張は相互に若干違う。伊藤は、まさに、ここで取上げている視床下部の問題から、視床下部が残っているのであれば、低次の意識が残ると言っているのだが、古川の場合、唐澤秀治が脳死判定基準にある頭の評議で測った脳波が平坦波で、脳死判定基準に該当する患者でも、脳室内で計ると脳波が確認される場合があり、そのような患者が回復し、社会復帰する例もあるということから、「脳死の患者さんに『いま私の臓器が取られている』というように意識できる、意識の働きが残っている可能性が十分にあるとかんがえないではいられません[32]」というのであって、それはすなわち、高次の意識が残っていると言うことであり、低次の意識が残るという伊藤とは異なるのである。
しかし、そもそも脳死とは大脳の機能が不可逆的に損われ停止している状況を含んでいるのであるから、高次の意識が残っているとするならば、それは大脳の機能、それも大脳皮質の機能が残っているということである。だとすれば、それは脳死ではない。また、無呼吸テスト以外の脳死判定基準を満たししているがゆえに脳死か脳死に近い状態とされる患者が回復し、社会復帰した例があるならば、脳死は不可逆的脳機能の停止であるから、脳死が人の死であるかどうか以前に、脳死それ自体の前提が誤りであるということになる。古川のいうように、脳死者が回復し社会復帰した事例があるならば、まさに、脳死は可逆的な状況であり、不可逆的な死の始まりではないということになる。
もっとも、このような事態に対して、前出の尾形は
脳死を死と認めない人の中で、脳死と思われていた患者が動いたとか、甦ったという事実を取り上げて反対する人がいるが、詳細に判定を行なってみるとすべて正しい判定なされていない場合であって、脳死ではなく植物状態であったり、脊髄反射である場合が多い。植物状態の場合には、脳幹の機能が一部残っているのを見逃したり、自発呼吸を人工呼吸器でカバーして見失ったりしているのである。こうした誤りは医師の中でも見られ、脳死判定の不勉強の結果である[33]
と断言している。
いうまでもないことだが、植物状態と脳死とは異なるものである。前者は、大脳の機能が損傷し意識障害を起しているが、脳幹は機能している。しかし、(日本における)脳死は、大脳の不可逆的機能停止と脳幹の不可逆的停止であって蘇生限界点を超えたものである。ところが、古川の先に発言は1990年以前のものであり、尾形の発言は1992年のものであり、また尾形の発言以降の脳死に否定的な論文等や、脳死否定の急先鋒である小松の2004年の著書「脳死・臓器移植本当の話」にも、古川のいうような事例は見られない。
もし、古川のいうように、脳死、もしくは脳死に近い状態から回復し社会復帰した事例があるならば、これらの脳死に否定的な論文や小松の書籍にも取り上げられようはずである。なぜならそれは、脳死は人の死、あるいは蘇生限界点をこえた不可逆的な人の死の始まりではないことの決定的証拠となるからである。しかし、それが取り上げられていないということは、少なくとも、古川の挙げた事例に対しても、尾形の発言するところにあてはまると考えたほうが妥当であるということであろう。したがって、現時点では、依然、脳死は、大脳の不可逆的機能停止と脳幹の不可逆的停止であって蘇生限界点を超えたものであると考えてよさそうである[34]。
さて、古川の発言をめぐって話が少し遠回りしたが、視床下部の問題にもどりたい。現在の脳死反的基準では視床下部の機能が残っている可能性があるとして、視床下部がかかわる意識は低次のレベルである。この低次の意識であるということについて、生田は、立花のインタヴューに対して次のように答えている。
(筆者註:視床下部に)非常に低レベルな意識ならあるといっていいでしょうね。たとえば、大脳皮質を全部とりのぞいたイヌの場合、動作は緩慢ですけど、ひととおりの行動はする。日があたっているところに自分から出かけていって、ひなたぼっこをするくらいのことはできる。そう言うところを見ていたら、そのイヌに意識がないなんてとてもいえないことですよ。視床下部が残れば、低レベルだが、意識はある。下等動物レベルの意識はあるといえるでしょう。[35]」(*35)
生田はこのようにといい、さらにその上で
生理学的には、視床下部が動物レベルの情緒中枢であることはハッキリしている。そこはみんな一致するけれど、そのレベルの情動があればその人は生きていえるのかどうか。そこはもう哲学の問題だから、人によって意見が違うと思う。[36]」(*36)
と述べている。
この生田の発言は、極めて重要な問題を提起している。すなわち、低次の意識が残っている段階で脳死を人の死と認めるかどうかは、もはや医学的・生物学的視点から、「人間とは何か」を問う問題をこえて、精神という視点から人間とは何かを問う哲学的問題に還元されると言うのである。そこには、極めて重大な問題がある。そこでこの問題も、後の「脳死に対する関係系の批判」で問い直すこととするが、いずれにしても、生物学的に脳死が蘇生限界点を超えた不可逆的な死の過程の始まりであったとしても、その始まりをどの時点に置くかについては、生物学的死という視点だけでは捉えられない部分があることをわれわれは認めなければならないであろう。
ⅱ.医学系批判における判定群に対する批判
現在の脳死判定基準に対する批判は、さまざまな側面からなされているが、根本的批判は、立花の批判であるとおもわれる。すなわち立花は、現在の脳死判定基準は、脳の機能の停止を判定するいわゆる機能死であるが、脳の機能の不可逆的停止をもって「脳の死」と判断して良いのかという問題である。
つまり、脳の機能が停止したからといって、それは機能の停止であって、脳細胞が死んだことではないので、厳密な意味で脳死とはいえないというのである。それゆえに立花は、脳死は機能死で判断するのではなく器質死を持って真の脳死とすべきであると主張する。そして、器質死を確認するために、脳の血流の停止を確認(脳循環検査)すべきであるというのである[37]。
この、脳の機能の停止、それも不可逆的機能停止が、脳の死の始まりであることはすでに述べた通りであるが、立花がこの脳の死の始まりを持って脳死とするのではなく、脳の細胞死少なくとも脳細胞の壊死が始まったこと示す脳の血流停止の確認をもって、脳死とすべきである強く主張する理由は次の二つによる。ひとつは、内的意識が残っている可能性があるという問題であり、もう一つは、脳の機能の不可逆性の問題である。つまり、現行の我が国の脳死判定基準(以下竹内基準)では、可逆性の脳機能停止を不可逆性の脳機能的死とあやまって脳死と判定しないかいう危惧である。
前者の内的意識が残っているのではないかという疑問は、現在の竹内基準による意識の有無の検査は、刺激による反応だけによる判断であって、これは、刺激に対する運動出力系の神経が損傷されているだけで、感覚入力系の神経が生きており、かつ内部意識がそれを認識していても、外部にその意識を出力できないだけではないのかという疑念である。そのため、立花は、感覚入力系が機能を喪失しているかどうかを確認するために、聴性脳幹反応検査を求めている[38]。
このような立花の疑念は、彼の取材手術中に麻酔により昏睡状態にあったものが、内的意識のみが残りそれゆえに手術の状況を知り覚えていたといったこと等々などを聞き及んでいることが拍車をかけている[39](*39)。その中には、「臨死」状態で意識がないものが、別の所から、自分が寝かされ処置されている病室の自分の状況を見ていたものも含まれており、単に内的意識の有無といったものではない宗教的側面を含む別の問題を含んでいるものもある。
筆者も全身麻酔下で手術を受け臓器の半分を切り取った経験があるが、筆者自身は麻酔中の記憶は全くなくブランク状態であったので、手術中の状況を認識しているとか、ましてや記憶しているということは、筆者自身の経験からは理解しがたいことであるし、日々行なわれている多くの手術においても同様であろう、このような内的意識の話は、通常伝え聞こえてこない。仮に、手術中に内的意識があったとして、このような意識は高次の意識であり、大脳皮質によるものである。この大脳皮質の機能喪失は、平坦脳波によって確認されている。先にあげた手術中にも内的意識はあったというような件は、麻酔の深さ等の問題もあろうかと思うが、現在の脳波測定の技術では手術中の麻酔時に出る3Hz以下のδ派の確認も可能になっている。したがって、麻酔中の昏睡状態と、平坦派のもとにある脳死状態のものとは違った状況のものであると考えるべきであろう。
もちろん、脳死を判定するための検査がより丁寧に行なわれることに意義を挟むものではないが、脳の不可逆的機能の喪失が、不可逆的「脳の死」のプロセス始まりであるならば、機能死を脳死とするか、器質死をもって脳死とするかは、そのプロセスのどこで区切るかの問題である。むしろ、もっと重要な問題は、可逆的な機能死を不可逆的脳死と誤って判定しないかと危惧されると言うことにある。つまり、それは竹内基準という判定基準が適切かどうかの問題である。たとえば、先に述べた立花が脳循環検査や聴性脳幹反射検査を求めているのも、現行の竹内基準では、脳の一部の機能喪失しか確認できないという認識からであり、それゆえに、もっと幅広い検査を持って「脳の死」の判断を下すべきであると考えるからである。
同様に、松本歯科大学倫理学の教授である倉持武は、現在の日本の脳死は全脳死の立場をとっているが、実質的には、脳幹死説+頭皮上脳波検査であり、全能死の概念をなし崩し的に矮小化するものであると批判している[40]。加えて倉持は、更に踏み込んで竹内基準の内容自体に欠陥があり、
厚生省基準(筆者註:本小論においては竹内基準)はコーマ・スケールを用いた深昏睡検査の点でも、脳幹反応検査の点でも、脳波検査の点でも、意識の不可逆的消失の証明でも失敗している。それゆえに、厚生省基準によって脳死と判定された者について、統計的・経験的に脳機能は回復しないということができるが、意識が不可逆的に消失しているとか、大脳が死んでいるとかいうことはできない。[41]
と批判するのである。その他にも、無呼吸テストが脳死患者にとって負担の大きい危険なテストであるとの指摘や、脳死判定の感覚が6時間では短いのではといった意見[42]もある。
このような批判に対して、竹内判定基準に関わった側からは、世界で最も厳しい基準であるという自負の声もある。また、産業医科大学の伊藤幸郎のように、この竹内基準に対して
脳幹死だけでなく大脳死の確認のためEEGを義務づけるなど、“保守的”と思われるほどの慎重さである。これ(竹内基準)による誤診の危険は、むしろ聴診器一本による心臓死判定の場合より少なくなるであろう。従来からの心臓死と全脳死に共通している特徴は(医師の不注意による以外)誤診の少ないこと、すなわち不可逆性の判定として有用な点である[43]
と竹内基準内容に積極的評価を与えている者もいる。さらには、東大医学部の伊藤正雄のように
脳死における経過の把握が充分にされ、かつ充分にその後の経過が追われたという前提の下では、竹内基準(時間の点は別として)による判定で間違いはないと思われるが、移植のドナーとするためには交通事故の様に突発的に発生した年齢の若い対象者について限られた時間の中で判定を下すことが多くなる。このような場合には上記の前提が必ずしも成り立たない恐れがあるが、その際にも誤診率ゼロの判定が保証出来るであろうか[44]
と、判定における前提条件によって妥当性と危惧の両方が存在するという意見もある。
いずれにしても、そもそも脳死というものが、人工呼吸器を用い、蘇生術が格段と進むことによって生まれた現象であり臨床的なものであって、そこに倉持がいうように、統計的・経験的に脳機能が回複しない状態は厳然と存在する。そのような中で、このような批判は、脳死とは何かという根本的理解において、脳死とは、全脳の機能の不可逆的停止に対し、何をもって機能の不可逆的停止と認めるかとう理解の違いであり、それを証明するのにふさわしい検査手段は何かということの理解、それはすなわち、機能の不可逆性を担保する検査方法とその有効性に対する認識・評価の違いよるものである。もちろん、脳死の判定基準がその的確さを欠き、不備を有するものであるとするならば、それは是正され、より的確な基準にされるべきであることは自明のことである。
2-2-3.脳死における関係系における批判
ⅰ.人称における死
我が国における脳死否定論者のもっとも先鋭的な存在は、既出の小松美彦であろうかと思われるが、その小松の文章に次のような言葉がある。
だがそれにもまして重要な問題は、そうした自発運動(筆者註:ラザロ徴候)が生じる状態を人間の死の基準としてよいのかということである。要は、ラザロ徴候などが脳死概念に矛盾しようとしまいと、それはあくまでも生理学上の問題であり、そうして生理状態を人間の死(の基準)と認めるか否かは別次元の話だということだ。しかも、目下のところ、ラザロ徴候や呼吸様運動が脳幹の活動に一切関係しないという医学的保証もない。もし今後、脊髄反射に帰着することになっても、あくまでも人間的な動きをする者たちを、ことにそうした肉親を、私たちは死んだものとして納得しうるだろうか。納得し得ないのならば、ラザロ徴候や呼吸様運動が生じる脳死状態を、そもそも人間の死(の基準)として認めてよいのだろうか。前掲の連続写真(筆者註:ラザロ徴候の連続写真)をいまいちど凝視しながら考えていただきたい[45]
この小松の文書は、たぶんに情に訴える扇動的ニュアンスを感じさせるものであるが、しかし、重要な内容を含んでいる。というのも、この文章を突き詰めてディフォルメしていくと、生理学上の(死の基準)がいかなるものであろうと、家族が死んだ者として納得できない限り、それは死の基準としてふさわしくないということを意味するものだからである。そこには、死は個人の死ということだけではなく、個人の死に関わる人との関係における死という極めて重要な問題があるのである。
関係における死とは、いわゆる人称における死である。人称における死とは、「わたし」の死(一人称の死)として死の問題を考えるか、「あなた」の死(二人称の死、この場合、肉親等の身近な存在としての“あなた”)として考えるか、「それ」の死(三人称の死、この場合、自分との関係が希薄な存在を対称とした死で一般化された社会的死といってもよいだろう)として考えるかということである。
ⅱ.一人称の死
ここでいう一人称の死は「わたし」の死であるから、私という当事者自身は「わたし」の死を知ることはできない。知ろうにも当事者自身が死んでいるからである。したがって、一人称の死は、私が「わたし」に対して死ぬと言うことであり、それはつまり人格的存在としての自己意識の消失であるといえよう。ここに、人間の死がなんであるかというもう一つの哲学的な定義が起る。すなわち、人間の死は、生理的問題ではなく、人格が消失することによって人は人間として死ぬのだという理解である。
脳死臨調が、その答申において
身体の基本的な構成要素である各臓器・器官が相互依存性を保ちながら、それぞれ精神的・肉体的活動や体内環境の維持(ホメオスタシス)等のために、合理的かつ合目的に機能を分担し、全体としての有機的統合性を保っている状態を『人の生』とし、こうした統合性が失われた状態を持って死とする考え方である[46]。
として、精神的活動を入れている背後には、このような、人間が人格的の基となる精神活動が喪失することによって、人間としての死をむかえるととらえているからである。また、このようなとらえ方は、竹内基準にもとづく脳死判定下では視床下部の機能は残存している可能性が指摘される、そのことをも(意識的かどうかは別として)射程に入れている。
ここにも、先にのべた視床下部の問題が関係する。すなわち、現在の日本の脳死判定において、視床下部が含んで考えた場合は、脳死患者にも低次の意識が残っているのではないかという問題である。
いうまでもないが、私が「わたし」であるという自己意識にたって意思決定をするのは高次の意識である。ただ所与の本能や反射によって行動する低次の意識とは異なる。私の死ということは、生物としての私の死を私が知ることができないということと同時に、私が私であるという自意識においても、自分の死を知ることができないということでもある。つまり、一人称の死は、「わたし」の死であり、「わたし」という人格的理解を産み出す大脳、特に大脳皮質の不可逆的機能停止による。このような視点に立つならば、視床下部の機能が残存し、低次の意識が残っていたとしても、人格としての死は既に起っており、「わたし」という一人称においては、それは死であると考えられるのである。もちろん、この一人称の死を持って人間の死としてよいかどうかについては微妙な問題(たとえば無脳症の人の問題や精神の状態による優性思想等の疑念等)が残る。しかしいずにしても、脳死後も視床下部は残っていることを明らかにした生田ですら、先に引用したように、「生理学的には、視床下部が動物レベルの情緒中枢であることはハッキリしている。そこはみんな一致するけれど、そのレベルの情動があればその人は生きていえるのかどうか。そこはもう哲学の問題だから、人によって意見が違うと思う。」というのは、このような一人称の死の問題があるからである。
ⅲ.二人称の死
われわれは一人称の死を知らずとも、「あなた」の死という二人称の死か、「それ」の死という三人称は知ることができる。この二人称の死や三人称の死を通してのみ、われわれは「わたしの死」という一人称の死を知ることになるのである。それに対して、先にのべた脳死の医学的・生物学的知見や脳死に対する医学系の批判は、死を三人称の死である「『それ』の死」としてとらえて対称化としている。つまり死それ自体を対象化しているのである。
それに対して、二人称による死の理解は極めて実存的・人格的な死の理解であり、「なんじと我」の間にある関係の死である。そこには、死そのものよりも、死んだ人が対象とされている。この「なんじと我」の間にある死は、ただの「あなた」の死だけではない、私にとっても「死」である。この事は、次の池田清彦の言葉が適切に言い表している。
母親が死んで『おかあちゃん、死んじゃいやだよう』と泣き叫ぶ子供にとって、死んだ母親がかわいそうというよりも、母親にしなれた自分がかわいそうなのである。逆に子供に死なれた母親の最大の悲しみは、もはや誰ともコミュニケーションができなくなった我が子が不憫ということであろう。[47]
ここに出てきた母親に死なれた子供も、また子供に死なれた母親も、それぞれが向き合っている死は「あなた」の死である。しかし、前者の子供は、母親とコミュニケーションが取れなくなった自分の悲しみを訴え、後者の母親は、コミュニケーションをとれなくなった子供の不憫さを悲しんでいる。どちらも、同じ「あなた」の死を悼んでいるのだが、前者は死んだ人を通して自分の悲しみに痛み、後者は死んだ人自身の悲しみを自らの悲しみとして痛んでいるのである。そして、その両者に共通することがコミュニケーションの断絶、すなわち交わりの断絶である。いうなれば、二人称の死の実体は生物学的な死にあるのではなく交わり断然にあるといえよう。
このような、交わりの断絶は、ただ目の前にいる相手が語りかける言葉に反応してくれるかどうかということにかかっているわけではない。たとえ相手が語りかけてくれなくても、自分が語りかける対称である限り、「それ」の死としての第三人称の死が、「なんじと我の」間に介入することを拒む。筆者は以前、子供を亡くした母親が、斎場でまさに火葬されんとする子供の棺に自らも入っていこうとする場面を見た人の話を聞いた。それは、実に悲しい場面であるが、そこにおいて母親は、死の三徴候によって、「それ」の死を告げる医師の言葉であっても、母親にとっての「なんじと我」の間に決して第三者、すなわち三人称の死である「それ」の死を介入させてはいない。その母親と子供は、以前「なんじと我」の強い絆で結ばれているのだ。結局、二人称の死においては、ただ向きあっている「あなた」の死を心がどのように受容できるかどうかの一点かかっているのである。
先の小松の「もし今後、脊髄反射に帰着することになっても、あくまでも人間的な動きをする者たちを、ことにそうした肉親を、私たちは死んだものとして納得しうるだろうか。納得し得ないのならば、ラザロ徴候や呼吸様運動が生じる脳死状態を、そもそも人間の死(の基準)として認めてよいのだろうか。」というような発言や、脳死を否定する者が「まだ心臓が動き、体が暖かいのに死んだとはいえない」という発言をもって脳死を認めないのは、この脳死の問題が「あなた」の死という人格的な関係に「それ」の死という即物的関係をもって強制的に介入されることに対する拒絶反応であるといえよう。
もちろん、このような二人称の死は、必ずしも死の三徴候によって受け入れられるわけではない。先の火葬さようんとする子供の棺に入っていこうとする棺に入っていこうとする母親など、まさにそのよき例であろう。彼女にとって子供との「なんじと我」の関係は、未だ断ちがいものなのである。また、遺影や位牌に話しかける人姿は、以前「あなた」は交わりの対象者であり、そこでは完全に二人称の死は成立していない。ただ、その交わりが此岸内での交わりではなく、彼岸と此岸の間だの交わりに変わっただけなのである。結局、二人称の死の不成立をもって、脳死を否定するとするならば、従来の死の概念、すなわち死の三徴候をも否定されることになる。
しかしながら、この死の三徴候という三人称の死が、二人称の死を乗り越えて否応なくわれわれに死を受容させる。そのことに対する拒絶感は我々の中にけっして多くはない。ひとつにそれは社会的コンセンサスを持って圧倒的力をもって我々に迫ってくる社会的死であると言うことが挙げられよう。その圧倒的力の前に、われわれはこの死の三徴候をもって死を受容する。しかし、心においては「あなた」の死は完全に以前成立していない。結局、死の三徴候によって受容したのは、死の受容ではなく、「あなた」の肉体に対するあきらめの受容であり、此岸における交わりの断絶の受容であるといえよう。それは、心臓が動かない、息が止まる、体が冷たくなる、といった肉体的徴候をもって死を認識するといった態度の中にも見いだせるであろう。それゆえに、実際の死の現場においての二人称の死は、肉体に対するあきらめとそれに伴う此岸的交わりの断絶であるともいえよう。
ⅳ.三人称の死
すでに述べたように、三人称の死は「わたし」の死でもなく、「あなた」の死でもなく、死そのものが対象化された「それ」であり、関係上は「彼」の死であり、かつ社会契約的な「われわれ」の死でもある。具体的には死の三徴候によって確認される生物学的死な死の宣告と承認であり、それゆえに、絶対的圧力を持ってわれわれに「彼」不可逆的な死の過程にあることを迫ってくる。またわれわれも、それを死として受容せざるをえない抗うことのできない死の宣告である
この三人称の死は、社会契約的な死である。それゆえに、そこには死に関わるさまざまな法律的な側面[48]がある。だからこそ三人称の死は、死を線としてとらえることを欲せず、死を1点でとらえることを欲するのである。ところが、脳死は万民共通の現象ではない。それはICUという特定場所での一部の人間に起る特定の現象である。この脳死を心臓死共に認めるならば、死の二元化が生じることになる。それゆえに、法律的問題がそこに生じてくることになる。もっとも、法律は社会的取り決めであるから、社会状況に応じて対処すれば問題はないのであるが、そこには社会的利益・不利益の発生が起ることは避けられない。たとえばそれは医療費の問題において顕著に表れる。我が国は国民皆保険制度であり、医療費の多くはこの保険においてまかなわれている。
もちろん脳死を人の認めるならば、それは死であるから、脳死判定後に医療費は発生してこない。しかし、脳死を人の死として認めない場合には、当然のことながら、脳死と判断されたあとにも引き続き医療が施され、それに伴った医療費が発生してくる。この脳死判定後の費用に関して前田和彦は次のように試算し、こう述べるのである。
脳死判定:保険点数10200点、約10万円。脳死判定後、一週間人工呼吸器で心臓を動かしつづけると:検査費用18029点、18万円。管理費用58万円となる。また心臓が止まってしまった時、遅れて家族が到着してしまったときに、心臓マッサージをしたり、カウンター・ショックで一応臨終の義を行なうとすると約8万円がかかる。したがって家族が納得できる脳死判定から心臓停止までICUで行なうと、それだけで106万円かかることになる。実際は医療費は一部負担金はあるが、保険料から差額が支払われることになる。脳死になる人は年間7000人くらいといわれる。つまり、計算の上では年間相当額の保険料が脳死患者の管理費用にあてられることになる。また一部負担といえど2割となる人(筆者註:現在は3割負担)などは、支払い当初はかなりの負担になる。このようにどちらにしてもおおきな負担になる[49](*50)。
人間の死を金額で判断するなどは、極めて非人間的な行為に思え好むところではないが、現実的には、脳死状態の人を維持するためにはかなりの費用が発生することは間違いない。もちろん、保険制度はそのような医療に関わる費用の相互補助を目的としたものであり、脳死状態の患者に保険を用いその状態を維持すること自体には何の問題もない。むしろ問題は、そのためには脳死を受容するしないに関わらずにも、保険制度上の費用の負担がもとめられるということにある。逆に、脳死を死と認めた場合、脳死を受容できない家族が脳死状態を維持するためには、脳死判定後の費用はその家族が全額負担しなければならないことになる。つまり、三人称の死として脳死を認める・認めないという問題は、保険制度上の金額の違いはあっても利益不利益の問題が発生するのである。
また脳死の問題における利益・不利益の問題は、このような単なる費用負担の問題だけでなく医療資源の配分の問題にも関わってくる。すなわち、限りあるICUの中の限りある人材と資材をどのように配分するかの問題である。そして、問題はこちらのほうがより深刻な問題なのである。
いずれにしても、このように、脳死を「それ」の死として見るときに、様々な解決をしなければならない法的な具体的現実的問題がそこに横たわっている。
2-2-4.脳死に関する医療不信系の批判
脳死に関する医療不信系の批判は、すでに述べた脳死判定に関する批判以外は、おもには臓器移植の問題と関係して起っている批判である。もちろん、先に述べたように脳死と臓器移植は本来的には別の問題ではあるが、しかし梅原猛の次のようにいう。
人類は今まで何十万年の間、心臓死をもって人間の死としてきた。それは分析すれば「死の三徴候」、呼吸停止、心拍停止、瞳孔散大・対光反射消失の三つに分析されるかも知れないが、死と言うことは誰でも知っている。呼吸ができず、脈拍が停止し、そして瞳孔が開いてやがて冷たくなる。これが人間の死であり、この死という不思議な事実を人間はいろいろ解釈しようとし、宗教や哲学をつくってきたのである。しかし、今、脳死は死であると認めることは、この何万年、何十万年と人類が持ち続けた死の概念を変えようとするのである。何のために、それはもっぱら臓器移植をせんがためである[50]。
この、「脳死を死と認めなければならないのは、もっぱら臓器移植のためである」という梅原の主張は全面的に正しいとはいいがたい。そこには終末医療における尊厳死の問題や、先に述べた医療資源の分配の公正性といった問題などもあるからである。しかしながら、移植医療において、特に脳死間移植において、脳死が人の死であることは大前提であるので、その意味で脳死が人の死として認められるかどうかは移植医療にとっては極めて大きな問題であり、移植医療を進めたい側にとっては、脳死が人の死として認められるということが絶対不可欠な問題であることは間違いない。そこに不信感があるのである。つまり、移植したいがゆえに、脳死でないものを早すぎる脳死判定死はしないかという不信である。その背後には、1968年の札幌医大の和田教授による心臓移植が殺人罪で告訴されるという事件や、1984年の筑波大学における脳死者からの腎臓、膵臓の同時移植が同じように殺人罪で告訴されるといった事件がある。そのような中で、M・ロックは次のように述べている。
この脳死論争のあいだ、(筆者註:脳死に反対する)『患者の権利検討会』、弁護士、警察、作家やジャーナリスト、それにかなりの数の医師が常に問題にしたのは、移植医の信頼性であった。彼らは臓器の摘出を急ぐあまり、死のプロセスが早められたり誤った死の判定が行なわれる可能性があることを指摘し、脳死判定を行なう医師団に対する不信が大きな問題であることを繰返し述べた。とくに『患者の権利検討会』は、弁護士たちと共に、医師たちの秘密主義と傲慢な姿勢を批判し、日本人は医師に頼まれるとふつうは断れないことを強調した。このように日本では人々が医師に対する信頼の欠如を表明しているが、これは北米では見られないことである[51](*52)。
ロックの指摘するように、人の死と認めることによって、脳死となりうるような救急医療の場で、臓器移植を意識して充分な救急医療が受けられないのではないかといった不安や蘇生術がもはや患者を救うためではなく、脳死者の臓器を新鮮な状態に維持するために行なわれるのではないかといった批判、あるいは脳死判定が正しく行なわれていないのではないかといった医療に対する不信感は確かに根強くある。このような医療不信の背後には、先の和田事件や筑波大事件、1990年の阪大事件、1993年の九州大学病院での肝臓移植問題、あるいは直接脳死・臓器移植に関わるものではないが。1984年の岐阜大胎児解剖事件など、さまざまな医の倫理が問われる様な事件があるといえよう。それゆえの、先の梅原の「脳死はもっぱら移植医療をせんがためである」といった発言は、そのような不信感の中で、脳死が人の死として認められることによって、医師が移植医療によって殺人罪などで告訴されることに対する担保を求めているといった響きを持っている。
また、ロックがいう「医師たちの秘密主義と傲慢な姿勢」とは、いわゆるヒポクラテスの誓いにみられるパタナーナリズムではなく、行き過ぎたパターナリズムであり、権威主義というべきものである。そしてこの権威主義的体質のなかで、臓器移植を強要されるのではないかといった危惧するのである。
さらには、このような不信は、適正な救急医療が行なわれないのではないかといった不安だけでなく、精神に障害を持つ人たちや無脳症の家族を抱える人たちからも不安の声が聞こえてくる。それは、脳死が論じられる中で、高次の意識が失われることによって人間の死とするいわゆる大脳死が脳死であると考えられると、それが拡大解釈され精神に障害を持った人たちや無脳症の人たち、あるいは痴呆になってしまった人も脳死と見なされるのではないかといった不安である。このような不安は、脳死を人の死として認めることが、優性思想に繋がるのではないかといったところにまで不安は広がっている。もちろん、現在の日本の脳死の立場は全脳死であり、脳幹・および大脳の機能が不可逆的に喪失した場合であるから、精神に障害を持った方や無脳症の方に対する不安は起こり得ない。しかし、そのような不安を抱いている方々の心配は、ひとたび脳死を受け入れると、将来なし崩しになってそのような事態が起るのではないかといった将来に対する不安なのである。
しかしながら、このような不安や批判は、脳死と臓器移植を取り巻く問題ではあるが、脳死・および臓器移植そのものに対する批判ではない。むしろ、それに関わる医師に対する不安であり批判なのであって、それをもって脳死・臓器移植の是非を問うことは本来の論点をはずしている。確かに脳死となりうるような救急医療の場で、臓器移植を意識して充分な救急医療がなさず、単に臓器を新鮮な状態に維持するため医療行為が行なわれるとすれば、それはゆゆしき問題である。しかし、それは医師の倫理の問題であって、脳死それ自体の問題でもなければ臓器移植それ自体の問題でもない。むしろ、このような問題で脳死そのものに関する議論が見落とされるとするならば、そちらの方が問題なのである。
2-2-5.脳死に対する宗教系の批判
日本の脳死論議で必ずといっていいほどに問題になるのが日本の宗教観・死生観の問題である。これは死というものが宗教的観念に結びつきやすい性質を持っていることから起る必然であり、日本の場合、仏教や神道の影響は何かしらの形で死の理解に影響を及ぼしていると考えられるからである。だとすれば、仏教や神道がどのような形で脳死の問題に影響しているであろうか。
NCC宗教研究所編の「脳死。臓器移植と日本の宗教者[52]」にある資料によると、1997年の「臓器移植法」に対して、大本教は明確な反対の立場を示し、真宗大谷派は明確な表現は避けてはいるが反対の意を示している。また、立正校正会も医学的概念としての脳死は認めても、それを人間の死と認めることには反対である。それに対して創価学会は、判定基準の厳密化や移植環境の整備等についての要望をもちつつも、基本的には賛成している[53]。また、同志社大学の小原克博は本願寺派では統一的見解ではないが「生命の尊厳」を論拠とした反対論が多く見受けられると発言している[54]。
確かに本願寺派僧侶石田智秀の論文などを見ると、そこには「脳死」は臓器移植と不可分な概念であるとされ、その上で脳死間移植に反対の意が述べられており、本願寺派が教派として一致して脳死に賛成しているわけではないことはうかがえる。また曹洞宗や真言宗も、同様であっておおむね反対と考えられる。このようにしてみると、仏教界では「仏教では宗派によってとらえ方が違い、統一した見解はなかなか出てこない[55]」という意見もあるが、どちらかといえば否定的であろう。
それでは、神道においてはどうであろうか。井澤正裕は「神道では、原則として心臓死の立場を表明する[56]」と述べている。また小林威朗は、神道において脳死と臓器移植の問題がどのように取り扱われてきたかを、1991年の第9回神道教学研究大会共同討議「神道の死生観-脳死問題と神葬祭をめぐって-」から始めて、歴史研究的にまとめているが、結果として神道としては脳死をそのまま人の死として認め難いことを明らかにしている。さらに小林は、神道においては、脳死を人の死として認めがたいとする状況の中にあっても、臓器移植に対しては、消極的ではあるが容認する雰囲気もあったことを示しながら、しかし、神道においては、臓器移植は不自然感をぬぐえないことを明らかにしている[57]。
以上のような結果から見ても、一般的に日本古来の宗教と考えられる仏教や神道では、脳死を人のとして認める事に対して否定的であるということができるであろう。
しかしながら、このような結果にもかかわらず、1997年10月から1998年にかけて、東海大の高月義照が行なった「日本人の死生観」についてのアンケート調査[58](*59)によれば脳死を人の死として認めるという人は、全体の55%を占め、認めないという人の21%を大きく上回っている。このような結果から見る限り、日本古来の宗教といわれる神道や仏教の死生観が、必ずしも、脳死をめぐる個人の死生観に影響をあたえているとはいえないように見える。しかし、本当であろうか。
高月はこの全体で55%ある脳死を認めるという人、また21%の認めないというアンケートの結果を、さらに10代・20代、30代・40代、50代以上に分けて整理している。それを見ると、脳死を認めるというものは、10代・20代の49%から、順次51%、62%と増加し、逆に認めないという傾向は、10代・20代の23%から順次15%、12%と減少している。高月は、この結果に対して、
死を身近に考える人ほど『脳死』状態で生かされることを拒否する、つまり「安楽死」や「尊厳死」を考える傾向にあるということなのか。おそらく「安楽死・尊厳死」の質問項目を設けておけば、もっとはっきりとしたことがわかったかもしれない[59]。
と述べている。
確かに高月のいうように年齢あがるほど人は死に近づく。それゆえに若い人よりも自分の死についてより実感をもって考えるということはあるだろう。それは、裏を返せば、年が若くなるに連れて死を自分の問題としてあまり実感を持ってとらえていないということである。考えてみればそれもうなずける話である。通常、若い人、それこそ10代・20代の人にとっては、死は自分自身の死によって対象化されるよりも、自分の親や祖父母といったところで感じやすい。普通に考えるならば、自分よりも自分の親や祖父母の方が死に近いからである。それゆえに、彼らにとっての死は「あなた」の死であり、二人称の死で、脳死を考えている可能性が充分にある[60]。それに対して、仮に高月の予測するように、死を身近に考える人ほど、安楽死や尊厳死を考える傾向にあるとするならば、それは、いうなれば自分の死に際を考えるという、一人称の死について考えているのである。
では、その一人称の死を考えた際に、なぜ安楽死や尊厳死考ということを考えるのだろうか。おそらくは安楽死や尊厳死を考えるということは、要は延命治療によって生かされるよりもは、スパッと死を迎えたいという気持ちがあるのであろう。そこには、ひとつに無理な延命治療ではなく、自然な死を望む死生観を見ることができる。たとえば、伊東幸朗は次のようにいう。
人工呼吸器は、昔からの臨終場面をグロテスクなまで引き延ばした。ここでは人は安らかに“息を引き取る”ことは不可能になった[61]。
伊東は、この言葉をもって脳死の状態を含め、人工呼吸器で命をとどめていること自体が極めて不自然な生の状態であるということを言い表している。
自然であるということは、日本古来の宗教であると考えられている神道、仏教にも通じるものであり、その意味では、神道、仏教の文化によって醸成された日本人の死生観といっても良いものである。しかし、その「自然である」ということで、脳死を死の三徴候で表わされる自然の死に対して人為的な「不自然な死」と考えるか、脳死の状態を人工呼吸器によって生かされている人為的な「不自然な生」と考えるかで表れてくる態度は全く違ってくる。それは、生かされているものが脳死と判断されることで死とされてしまうと捉えるか、死んでいるものが脳死という状態のもとで生かされるのかとう視点の違いである。おなじ「自然である」という神道、仏教の伝統の中で育まれた死生観にあっても、脳死を不自然な死と捉える神道・仏教の教団の見方と脳死を不自然な生であると捉える一般人のとらえ方とでは180度違いがでてくるのである。そして、どちらもが生命の尊厳性を考えるのであるが、前者は命あることの尊厳性を考え生かすことをもとめ、後者は生きていることの尊厳性を考え、死を求めるのである。
また、一人称の死において安楽死や尊厳死を考える場合、残された家族を思っての早い死を望むということも考え得ることである。それは、家族に迷惑をかけたくないという思いからのものである。もちろん、このような考え方が無限に延長されるとするならば、そこには岡田麗江が次のように述べている危険性があることは心に留めなければならないことである。
日本でも、尊厳死を求めるという意思表示をしておく、日本尊厳死協会によるリビング・ウィルの運動がある。また、家族に迷惑をかけないよう“ポックリ死にたい”という考えがよくいわれる。ポックリ死にたいということは、一方では障害を持って生きることは良くないとい考えが含まれていて、生命の価値の評価につながっていくものではないだろうか。…<中略>…人間の尊厳のためにといって、尊厳死や安楽死を考えなければならないという社会をつくらないようにしたいと思う。人間の尊厳を護るとして、そこでは生命の価値の比較がなされてしまう。即ち、生きる価値のないもの、生きる価値があるものとしてである。意識がなく、自己決定できない状態の人間は尊厳を持たないとされる傾向をつくってしまう。他者のために存在することも人間としての尊厳があるのである。そのような状態になっても人間として存在することに意味を見出したい。尊厳死を求めるのは誰のためか[62]。
ここにおいて岡田の上記の言葉を否定する意図は筆者にはない。むしろ、生命の価値が比較されてしまう社会に対する危惧は共感さえ感じる。それでもここにおいて述べたいことは、岡田が問いかける「尊厳死を求めるのは誰のためか」というと問いの重要性である。そしてその問いに対して、安楽死や尊厳死を考えるものの中には、残された家族に負担をかけない、まさに家族という二人称のために尊厳死や安楽死を「わたしの死」という一人称の死として考えるものもいるということなのである。
もちろん、それを家族が喜ぶかどうかは別の問題ではあるが、しかし少なくとも、自らの一人称の死において逝き行く者が、「なんじと我」の関係において、「なんじで」ある家族のことを想って、自らの不可逆的な死の過程で人工呼吸器において生かされることを望まない死にざまもありうるのである。そして筆者は、そこには脳死を人の死として認め、不可逆的な死の過程の歩みを、呼吸器なしに歩むことを望むということもありうるのではないかということを述べたいのである。
先のアンケートにおける50代以上という自分の死を身近に感じている者が、他の世代に優って62%と高い率で脳死を人の死と認める背景には、そのように家族との間の「なんじと我」との関係において逝き行く者が、残された「なんじ」を想い、「我」の死を受容している可能性も充分にある。もちろんそれは、医師のためでもなく、看護士のためでもなく、いわんや見知らぬ第三者のためでもない。ただ「なんじと我」という二人称の関係の中で最も親密であろう家族の間にあってのことである。同時にそれは、意識がなくもの言わなくなった「なんじ」に対して、家族が「なんじと我」という不可分に親密な関係において、ものいわなくなった「なんじ」の思いを想い計って人工呼吸器なしでの不可逆的な死を最善の選択として選びうる可能性もありうるということを意味している。
2-3.臓器移植に関する批判
2-3-1.真の反対者は誰であるか。
われわれは臓器移植の賛否を問う場合、真に臓器移植に対し賛成なのか反対なのかを見極めなければならない。というのも、先にも述べたが、往々にして臓器移植と脳死とが一組にして考えられているために、脳死を人の死とする考えに対する反対と臓器移植に対する反対が一緒になって議論されるケースが少なからずあるからである。それゆえに、臓器移植には賛成だが脳死を人の死とすることには反対という場合もある[63]だろうし、臓器移植には反対だが脳死を人の死と認めることには賛成という場合もあるだろう。もちろん、両者とも賛成、あるいは両者とも反対という場合もある。
臓器移植には賛成だが、脳死を人の死とすることには反対という者は、生体移植や死体腎移植や角膜移植および輸血等は抵抗なく受け入れられることであろう。しかし、おそらくは尊厳死は受け入れられないものと思われる[64]。逆に臓器移植には反対だが脳死を人の死とするには賛成というのであれば、移植医療は受け入れないにしても、脳死状態での尊厳死[65]などは認めることであろう。さらには、脳死を人の死とすることにも臓器移植にも賛成という者は、脳死者からの移植も問題なく受け入れられるし、両方とも反対という者は、移植医療も尊厳死も認めないはずである。
ただ、この移植医療に反対という立場は、実際にはもう少し詳細な区分が生まれてくるものと思われる。すなわち、生体移植、あるいは死亡腎臓移植や死亡角膜移植といった心臓死移植、輸血等には賛成であるが、脳死による移植には反対であるというものと、生体移植あるいは心臓死移植、また輸血等にも反対であるし脳死による移植にも反対であるというもの、また生体移植あるいは心臓死移植にも反対であるが、輸血は認めるというものあるであろう。さらには心臓死移植には賛成だが生体移植には反対といったものも考えられるし、臓器移植には賛成だが輸血には反対といった立場[66]もある。
前者の生体移植、あるいは死亡腎臓移植や死亡角膜移植、輸血等には賛成であるが、脳死による移植には反対であるというものは、結局のところ移植に反対なのではなく、脳死に反対なのであり決して移植医療に反対というわけではない。また、心臓死移植は賛成だが、生体移植には反対というものもこれに準ずるものであると思われる。すなわち、生きた人間にメスを入れ、そこから一部分ではあっても臓器を取り出すことに対する問題意識がそこにあるものと思われる[67]。
臓器移植には賛成だが輸血には反対といった立場は、医学的には論理性がない。なぜなら、輸血も細胞移植であり、その意味では輸血もまた臓器移植と言えるものであるからである。当然、この矛盾性は生体移植あるいは死亡腎臓移植や死亡角膜移植、そして脳死による移植にも反対であるが、輸血は認めるという立場に対してもいえることである。それゆえに、純粋に移植医療に反対する真の反対者は、脳死を人の死として認める・認めないに関わらず、生体移植あるいは死亡腎臓移植や死亡角膜移植、また輸血等にも脳死による移植にも反対であるとする立場だけに限られる。そういった意味では、生体移植あるいは死亡腎臓移植や死亡角膜移植、そして脳死による移植にも反対であるが、輸血は認めるという立場や臓器移植には賛成だが輸血には反対といった立場は、なにゆえに輸血だけを認めるか、あるいは認めないかを明らかにする必要があるだろう。
2-3-2 臓器移植に反対する理由
脳死という問題を切り離して、臓器移植に反対する理由は一体どのようなところにあるのであろうか。
臓器移植に反対する意見を集約するとおおむね次の3つの批判に分類できる。その3つとは、医療系の批判、倫理系の批判、哲学系・宗教系の批判である。以下、順次それぞれについて述べることにする。
ⅰ.臓器移植における医療系の批判
心臓死移植のみ認めないという立場は、脳死は人の死ではいないのであるから、脳死移植は生きている人間から臓器を取ることになるという点でその論理は明快である。それゆえに、論点は脳死を人の死として認めるかどうかにかかっている。しかし、生体移植は認めるが脳死移植を認めないとなると、その論点が少しぼやけてくる。生体移植も生きた人間から臓器を移植するという点では同じだからである。ただ、脳死移植の場合においては、ドナーが確実に死ぬが生体移植の場合は、ドナーもある程度のリスクは負うが必ず死に至るというわけではない。それゆえに、その境界はドナーの死亡率が100%か100%ではないかという点にある。つまり、その論点はドナーが必ず死に至る否かにあるのである。
また、日本で初めての生体肝移植がなされたころ[68]、生体肝移植は成功率が低く危険であるので反対だという意見もあったかが、成功率の高い低いで賛成反対ということであれば、成功率の低い手術は行えないと言うことになる。もちろん、その時点で成功するかどうかも分からないパオイニア的な手術もないわけでなく、それだけで完全に否定するということもできない。わずかな可能性であっても、それに賭けていきたいと思うものいるからである。
また、心臓死移植であっても、生体移植であっても、その術後の生存率の低さによって否定されるべきものでもない。わずかな可能性であってもそれに賭ける患者の決断を否定する権利が第三者にあるのであれば別だが、果たして、そのような権利が医師といえどもあるとは思われない。もちろん、そのような危険な手術は出来ないと手術を拒む自由は医師にもあるであろうが、同様に、危険な手術でも受けたいと願う権利もまた受けない自由も患者にはある。
結局、このような危険な手術をどう考えるかという問題は、自分の医療に対する決定権は誰にあるのかという問題である。そこにおいては、パターナリズムによって医師が主導権をもつか、インフォームド・コンセントによって患者が主導権を持つかが問われている問題なのである。このように、心臓死移植にしても、生体移植手術における成功率やドナーやレシピエントの負うリスクといった問題は、たしたしかに移植医療にともない医療技術の問題はあるが、移植医療を決定的に否定する要素にはならない。なぜならば、そのリスクを負うドナーやレシピエントがそれらのリスクを知って負うかどうかにかかっているのであり、それを制約できるものは、ただ法律による社会的制約のみだからである[69]。
ⅱ.臓器移植における社会倫理系の批判
臓器移植を反対する理由としては、ひとつに、医師の倫理問題がそこにある。それは先に述べた脳死問題と相通じ重複する面があるが、臓器移植をせんがために、末期にある患者の心臓死を早めてしまうちということや、心臓か動いていううちに臓器を保全するための処置を行なう[70]といったことがあるのではないかという問題である。こういった問題は、医療従事者の倫理問題であり、移植医療を望んでいるレシピエントやドナーの問題ではなく、レシピエントやドナーにその責を負わすべき問題ではない。しかし、移植医療には、このような移植医療そのものの倫理性を問うもの以外にも、移植医療に伴に看過できない社会倫理的問題があることは確かである。その最も大きな問題が臓器売買の問題であろう。
日本における臓器売買の実体が明らかな形で公に出てくることほとんどない。しかし、日本に限らず、世界的にドナーの数に対してレシピエントの数が圧倒的に多いドナー不足の中で、いかに臓器を捕獲補するかということは極めて大きな問題である。それゆえに、臓器売買という話は、かなりリアリティを持っている。このような事情からか日本における臓器売買といった話が伝わってくるとき、実態は分からないのだが、それがまことしやかに語られるとき極めて信憑性がある話のように聞こえてくる。
この臓器売買について、粟谷剛はフィリピン・インドの状況を調査し報告している。これは、まことしやかに語られているうわさ話ではなく、現地調査をした報告であるが、粟谷はこういうのである。
・フィリピンの事例
調査は1992年に開始しました(その後継続)。フィリピンでは腎臓器売買が公然と行なわれています。調査は主に刑務所(ニュー・ピリピッド<通称モンテンルバ>刑務所)で行ないました。フィリピンでは、臓器売買は違法ではありません。1992年1月『臓器提供法』(1992年3月施行)が制定されましたが禁止規定はそれには盛り込まれませんでした。同法案の想起に当たったナルシソ・モンファト元下院議員は、なぜ禁止規定を盛り込まなかったのか、との私の問いに、『金のやりとりがあろうとなかろうとドナーによる臓器によってレシピエントが助かるのは事実です。ドナー不足は深刻です。禁止するとドナーが減ることになります。せっかく軌道に乗っている移植医療の目を摘みたくありません』と答えました。彼は医師でもあります[71]。
・インドの事例
調査は1993年に開始しました(その後、継続)。ここでは、腎臓売買についてのみ申し上げます。それはいわばビッグビジネスになっていました。統計はありません。(移植自体についてすらありません)が諸種の調査結果から推計して、数千例から数万例に達するものと思われます。数としては、フィリピンなどの比ではありません。あくまでも推測にすぎませんが、世界中の腎臓販売の7割以上をインドが占めるのではないでしょうか。インド国内でみれば、ボンベイおよびマドラスが圧倒的に多いです。ボンベイには中近東からの患者が多く来ていました。また、マドラスには東及び東南アジア諸国からの患者が多く来ていました。もちろんインド人の患者もいました[72]。
このような、臓器売買が実際に行なわれるとしたならば、そこには倫理的問題が生じてくるのは必至のことであるとおもわれるが、臓器売買が本当に倫理的悪であるかどうかについては、単純にいえない問題がある。というのも、そこには臓器は一体誰のものかという問題があるからである。
普通に考えれば、臓器売買は生体移植の範囲内で行われるものであると思われる。しかし、心臓死後の死亡腎移植や角膜移植も全く考えられないわけではない。この臓器は誰のものかということについては、後にもう一度詳しく述べることとして、とりあず生体移植の場合を考える。というのも、生体移植の場合、臓器が誰のものかと問われると、ひとつは「自分自身のものである。」という答え方があるであろうことは、充分に予測できることだからである。そして、自分自身のものであるから、自分の思うようにしても良いではないかという理屈も成り立つ。もちろん、だったら自殺も良いのかというふうに、議論が発展してくるのは目に見えているが、自殺と臓器売買とは根本的に違っている。
自殺の場合は自分の命を投げ出すことだが、臓器売買の場合、移植手術に伴う危険を負うというリスクはあるが、基本的には命を代償とするわけではない。極めてドラスティックな言い方をするならば、程度の違いはあっても、命綱をたよりに高所作業の危険を冒して働くことと同じ部類にはいるものなのである。
しかし、高所作業の仕事には、恐れや驚嘆は感じても、臓器売買というおぞましさや罪悪感は感じない。筆者自身、臓器売買という言葉には、ひとかたならぬ悪のイメージがぬぐえないし嫌悪感を感じるのである。一体、この筆者の中にある倫理的悪のイメージや嫌悪感はどこかからくるのだろか。
先の粟谷の報告には、つぎのような内容が続けられている。
バブ氏(29歳)の場合、レシピエント(マレーシア人)と一緒にならんで撮った写真を持っています。大変仲良くなり、今でも手紙のやり取りをしているといっています。これは珍しいケースでしょうが、臓器売買という言葉につきまとう一種のいやらしさのようなものはまったく感じられませんでした。
それは、インドにおける臓器販売にはほとんどあてはまるものですが…。ガネシュ氏(男性30歳)は腎臓を売って得た金でミシンを買い、今それをつかってスラムの人たちの服の繕いをして、生計を立てています。家族は母親と20歳になる妻、1歳になる息子が一人。彼は今、幸せだといいました。体の体調も悪くないといいます。何か望むことがあるかと聞きますと、『この仕事が死ぬまでつづけられますように』と答えました。[73]」(*74)
また、フィリピンでドナーとなった殺人罪で服役中のリバーン氏についても次のような報告がある。
ーなぜ提供しようと思ったのですか。なぜ提供しようと思ったのですか。
リ氏「金が欲しかったからです。減刑、釈放も期待していました。よい ことでもあります(下線部は筆者による。)』
-いくらもらったのですか。お金以外に何かもらいましたか。
リ氏「現金で5万ペソ(調査当時1ペソ=約5円)貰いました。他に扇風機 とラジオを貰いました。」
-貰った金はどうしたのですか。
リ氏「田舎の家族のために2ヘクタールの土地と水牛1頭を買いました。残りは家族に仕送りしたり、生活費に使ったりしました。貯金も、ほんの少しですがしています。品物は所内で使っています。[74]」
粟谷の報告するインドのバブ氏、ガネシュ氏には話には、粟谷いうようにいやらしさやおぞましさは感じ取られない。むしろ、臓器を売った方も買った方も喜び、幸せを手にしているようにさえ思える。さらには、粟谷は、臓器を売ったドナーたちが、楽しそうに将来の夢を語り合っている姿なども報告している。それは、おぞましさとは縁遠い希望さえ感じられるものである。またフィリピンのリバーン氏も、金品と引き替えの臓器提供を「よいことであります」とまで言い切っている。この違いはいったいどこから生まれてくるのだろうか。
われわれは、一般的に東南アジアにおける臓器売買と聞くと、即座に貧困との関係でとらえているのではないだろうか。貧困の中で、金にものをいわせて臓器を奪い取られているそんなイメージがないだろうか。しかし、粟谷は、インドにおける臓器売買の提供者は、決して最貧困層ではないという。むしろ最貧困層は、栄養状態が悪く、病気にかかっている場合もあり、ドナーになれないようである。なれるのは、一応、粗末ではあるが、家屋に住むクラスの人々であるという。
しかしながら、おそらく富裕層のものが、金銭で臓器を売るということはないであろう。だとすれば、やはり、そこには貧富の問題があることには間違いがない。しかしそれは、社会制度、たとえばインドであるならばカースト制度の問題であろうし、世界的視野から見れば南北問題によるものであり、その意味ではわれわれ日本人が生みだしているおぞましさである。しかし、臓器売買という言葉に感じるおぞましさや嫌悪感は、単にそのような経済格差ということに起因しているものではない。だからこそ、臓器移植に反対する立場に立つ者たちは、臓器移植の問題点を経済格差の問題に焦点を当てるのではなく、臓器売買のそのものを問題として取りあげるのである。
粟谷は、先のインドやフィリピンのいやらしさを感じさせない臓器売買をあげながらも、臓器提供自体が、人体の尊厳性、人間の尊厳性を汚すものがあるという[75]。そこには、人体の尊厳性とか人間の尊厳性いう倫理的な思想がハッキリ打ち出されている。しかし、そのような倫理性はけっして、絶対的なものではなく相対的なものであり、相互契約的性質を持つものである。そこには、そのような倫理観を下支えする、もっと根元的な文化的・宗教的な問題があるのである。おそらく、そこに目を向けないかぎり、幸福感や希望を感じさせる臓器売買の現場と、臓器売買という言葉だけで、いやらしさとおぞましさ、そして嫌悪感を感じるものとの間の内的理解における乖離は決して埋まらないであろう。いずれにしても、これらは、移植医療そのものを対象にした是非ではなく、その周辺部分に起る問題からの批判であって本質そのものを批判するものではない。
ⅲ.臓器移植における宗教的批判
日本における臓器移植に対して、海外はどのように見ているかについて工藤直志は、過去10年間の雑誌掲載論文をあたり、それをまとめている[76]。それによると、海外から見た目からも日本で臓器移植が進まない背景に日本の文化土壌を見ていることがわかる。このような見方は、筆者に限らず、日本において臓器移植問題に関わるものが感じるものでもあるが、とくに海外から見た臓器移植の障害となる日本の文化的背景はつぎの4つに分類できるように思われる。すなわち、日本の宗教的土壌、贈与交換、医療不信、そして人間関係のあり方である。
医療不信については、すでに取り上げた。また日本の宗教的土壌については、もっとも大きな問題であるので後からの述べることとして、まず最初に臓器移植に対して贈与交換について考えてみたい。というのも、筆者自身、この贈与交換という理念が、本当に日本の臓器移植を阻害している原因であるかどうかについては疑問を抱いているからである。
工藤によると、この贈与交換についてはCrowley-MatokaとM.Lock(前出マーガレット・ロック)によって述べられているとのことであるが[77]、要は日本は贈与交換的社会であり、臓器移植は返礼の出来ない贈り物であるので、人間関係が互恵的なシステムで出来ている日本においては、返礼の出来ない贈り物である臓器を提供されることは精神的な負い目が生じてしまうというのである。この場合、返礼の出来ない贈り物である臓器を提供されて負い目を感じるのはレシピエント側である。
しかし、実際には臓器移植を受容できないのはレシピアントではない。レシピエントは、臓移植を望んでいるのであって、臓器移植に反対する側は、レシピエントの感じる負い目、つまりレシピエントの負うリスクを思いやって反対しているわけではない。少なくとも、筆者が臓器を受けることによってレシピエントが精神的負い目を負うので臓器移植に反対するという論調に出会ったことはない。むしろ、臓器移植に反対する側の主張は、おもにドナー側の負うリスク、あるいは社会の負うリスクを危惧してのものである。この場合、社会の負うリスクというのは、先に述べた臓器売買等の問題である。
確かに、臓器売買は互恵的ではない。しかし、臓器移植に反対する側が。その互恵的臓器売買を問題にしているのは、臓器移植が日本の互恵的システムを破壊するからではない。臓器売買という行為自体が社会悪であると考えるから、問題点としてあげるのである。このように臓器売買という行為が社会悪であると考えること自体、そもそも、臓器移植自体が贈与交換を超えたところで考えられていることを示しているのであって、贈与交換のシステムが臓器移植の障害になっているわけではない。
だとすれば、人間関係の問題はどうであろうか。工藤によればLaFleurは、先ほどの贈与交換のシステムに対し、臓器移植は返礼を求めない「無償の愛」によって支えら受容されてきたという。そして、日本においては、見知らぬ他者に「無償の愛」を注ぐよりも既存の人間関係が重視され、その既存の人間関係も現実の親子愛が他者との関係があるべき姿として賞賛される儒教思想の影響下を受けたものであって、それが、キリスト教的な「無償の愛」よりも理想とされるがゆえに、臓器提供に大きな影響を与えているというのである[78]。
この人間関係における親子関係の優先、それは家族関係の優先ということでもあろうと思われるが、このことは、確かに臓器移植に関わる局面で顔を出す。たとえば脳死移植に限らず、死亡腎移植や角膜移植において、また骨髄移植においても、法律的に家族の同意を要するものとなっている。それは、日本においては、家族間での「なんじと我」の関係が極めて強く、個人の意思決定や行動に家族の意思というものが大きく関与しているということを意味している[79](*80)。そういった意味では、このような家族との関係が臓器移植の障害のひとつになっていると言うことはできるかもしれない[80](*81)が、しかし、それは間接的な意味においてである。なぜならば、本人も臓器提供を意思し、家族もそれを望めば、障害とはならないからである。結局、問題は、本人であれ、家族であれ、臓器提供を躊躇させる原因は何かというところに行着くのである。そこで、最後に残った日本の文化・宗教的土壌という問題であるが、これを直接論ずるには、まず日本の臓器移植反対の立場の主張から入るのがよいだろう。
たとえば、移植医療を支えているも哲学的前提にデカルトの二元論があるという主張である。すなわち、cogitoたる自己と空間に位置を占める身体との二元論に立ち、西洋は精神的存在であるcogitoが人間を人間たらしめ、肉体はそのcogitoが空間に位置を占めるためのものにほかならないと考えるが、日本的な文化はそのような霊肉二元論ではなく、身霊一体論であるという批判するのである。
あるいはそこにデカルトでなくキリスト教を持ってきて、キリスト教は霊肉二原論であり、それゆえにキリスト教の影響下にある西欧では脳死を受容しやすい環境にあると主張する者も少なからずあるが、いずれにしても、そこにあるのは人間を霊(あるいは魂)と身体とにわけ、人間の人間たる本性である霊と身体とを分け、霊が身体に優越し、身体はその機能によって機械的に捉えるという身体機械論ともいえる身体観的見方があり、壊れた機械の部品を取り替えるのと同じ感覚で臓器移植医療を受容させているというのである[81]。
このような身体機械論をもって臓器移植をすることを非と捉えるということは、身体を機械的に捉えることは誤った考え方であるというアプリオリな価値判断があるといえよう。仮に諸外国ではそのような考え方があってもよいが、日本ではそのような考え方はなじまないと主張してもことは同じである。そこには同じアプリオリな身体観に基づく日本という場での価値判断がある。問題はそのアプリオリであるが、そのアプリオリが身霊一体論である。この事に関して高月義照は次のようにいう。
西洋の心身二元論に対して日本では古来心身未分離の人間観が一般的であって、心身の身を単なる無機的な物体や人間に対峙した自然と同一視する思想が存在しなかったと考えられる。自然全体が超人間的力に支配された存在であり、ときに自然的物体そのものが超人的力をもつものとして。つまり霊的能力をもつものとして、人々の信仰の対象にすらなってきたのである。ましてや、人間の身体となると、自然的存在の一つであるとともに一つの霊的存在でもあるものとして、それ自体にある種の神聖性を付与される。こうした日本人の伝統的な身体観は、それが遺体となっても基本的にはかわらない。それはアミニズムの影響であったり、神道の名残りであったり、仏教の教えから来る風習であったり、あるいはそれらが混然と混ざり合った日本人の心性として残存する。[82]
確かに、身霊一体論は神道からも仏教からも引き出せる。しかし、実はこの身霊一体論は、脳死に対する 否定の根拠とはなりえても、臓器移植に対する否定の根拠となるかというと、必ずしもなりうるわけではない。高月がいうように、身体の全体性に霊が宿っているがゆえに身体を神聖化し、身体を傷つけることを忌む心情があってこそ、神霊一体論からの臓器移植反対は成り立つものである[83] 。
また、神道も仏教も、身霊一体だからといって臓器移植に絶対反対かというと必ずしもそうではない。
たとえば、仏教においては、その仏典等に身体提供の話が幾つかあり[84]、それゆえに臓器提供は捨身、布施菩薩行として捉えられるのではないかといった見方がある。つまり、教義的には臓器移植を容認する土台があるのである。梅原猛などはこの土台に立って、脳死については断固反対するも臓器移植それ自体は容認する。しかし、それに対して臓器移植はこのような菩薩行の要件である三輪清浄の理念を満たしていないとの主張もある[85]。
小林威朗は、神道の脳死・臓器移植の論議のなかで、基本的には臓器移植は「不自然」なのものであり容認しがたいものであると認識しつつ、しかし、現実にはそれを容認する方向にあることを述べている。そこに働く論理は「共同体のために奉仕する、人類進歩のために奉仕するという精神」であり、「人間誰しも健康で、長寿を望むのは人情」とされる状況においては仕方がないという人情論であると言う[86]。また井澤正裕は、人間の身体は、イザナギ・イザナミノミコトにつらなる命の系譜にあって、その二神の神業による命が両親を通して与えられたものであるから、身体は丁重に扱うべきであり、死後の身体も死体としてではなく、人として丁重に扱うべきであるというが、その丁重に扱うということの範疇に、臓器を提供することが身体を最もいとおしみ、丁重に扱う行為であるとする確信のもとにあれば、信仰的に許されるという[87]。このように、神道では神道思想においては臓器移植に対して否定的見解であるが、実際面では必ずしも否定しないという方向性にある。
以上のような点を見る限り、身体に特別な意味を感じ取るとらえ方は仏教由来のものというよりは、どちらかといえば神道由来のものと考えるほうがよさそうである[88]。
しかし、このような神道・仏教の実際的な現在の動向にかかわらず、一般の日本人の意識の中には、臓器移植を避ける傾向があることは否めない。それは、池田豪泉・石津日出雄によってなされた日本人の死に関する意識調査[89]などを見てもうかがえることである。この調査において、全体の71.9%のものが霊魂の存在に対して肯定的な見方をしており、また、全体の69.9%のものが、葬儀・告別式の時に遺体は元のまま完全な形であることを望んでいる。これは、92.3%が霊の存在は何らかの形で信じているアメリカ人の90%が必ずしも葬儀の際に遺体が完全でなくてもかまわないと考えている[90](*91)のと比べると、実に著しい差がある。そこには、遺体であっても、そこに身体に特別な意味を感じている姿を見ることが出来るのである。
また、M・ロックは、自分が出会った人物の中に、先端技術を駆使する現代日本社会の一員でありながら、自分の母親が死んだとき、彼女も彼女の子どもたちも母親の霊魂が家に残っていることをはっきりと感じたという女性がいたと述べている。そしてその女性が「もし私が移植を受けたら、誰かの霊魂が自分の中にはいりこんだように感じるでしょう。もし移植がうまくいかないとしたら、それは祟りのせいなのです。誰にも教えられたわけではありませんが、そう感じるのです。私は、信仰を特にもっていませんが、自分にはアミニズム的なところがあるような気がします」と語っていたといっている[91]。
死んだ家族の霊が家にやって来たと感じる、あるいは身近に感じるという感覚は、日本人にはよくある感覚ではないだろうか。筆者は牧師であるが、さすがに、「移植をすると誰かの霊魂が自分の中に入ってくるという感覚」を述べる事例はないにしても、「死んだ家族の霊が家にやって来たと感じる、あるいは身近に感じる」という感覚を述べる方がキリスト者の中にも何人もいたことを知っている。そういった意味では、このような霊に関する感覚は日本人に染みついた「日本人の霊性」と言えるものであるといえるかもしれない。
もちろん、霊の存在を感じると言うことが、臓器移植の直接的な障害となるわけではない。問題はその霊が身体と一体化して死後も遺体と共にあると感じる感覚である。確かに厳密に言うならばこのような身体観を持ちながら遺体を火葬するということは矛盾しているし違和感を覚えるものである。しかし、そこには、少なくとも葬りの儀式がおわり、遺骨となったものを埋蔵するまでは、また埋葬後にも、遺骨に特別な感情を持つ日本人の霊性が浸透している。つまり、遺骨という物質と霊とが密着して個人の存在となっているのである。このような日本人の霊性は、戦後未だ続く遺骨収集事業にみられるものである。
いずれにしても、霊と体との一体性の感覚や「移植をすると誰かの霊魂が自分の中に入ってくるという感覚」は、臓器にも霊が宿っていると考える神道の身体観の具体的表れであると考えられる。もっとも、ロックが出会った女性は「私は信仰は特にもっていません」といっているのだから、それは、彼女が神道思想を意識していたというのではなく、神道思想が、日本の文化、日本人の霊性に浸透している現実を示していることだといえよう。そのような、神道思想が日本の文化や霊性に染み込んでいる現実を波平恵美子は、御巣鷹山日航ジャンボ機墜落事件の際の遺族の行動から明らかにしている。すなわち、たとえ遺体を捜しだし、確認し、そして弔おうとする行動から、日本人の死生観および身体観を明らかにしているのだが、そこには、出来るだけ完全な形で遺体を弔おうとする姿が現されている。そして、たとえ完全でなく遺体の一部しか発見できなくても、それを弔うことを大切に感じる霊性が示されている[92]。その場合、遺体の一部であっても、その一部にその人の全人格が代表されているのである。しかも、それは観念的なものではなく、かなり実体的なものとして感じ取られている。そこには、身霊一体の身体観があり、しかも、体のすべての部分がその人の人格のすべてとなりうる身霊一体の身体観である。それゆえに、人の身体は特別な存在であり、損われてれはならず丁重に取り扱われなければならないものなのである。
このような身体観は、通常の場合は表面に出てこない。それこそ事故や事件といった特別な場合に顔を出すのだが、それだけにわれわれ日本人に深く潜行し浸透しているかがうかがえる。そして、そのような身体観があるからこそ、臓器売買などと聞くと、そこにおぞましさを感じ、嫌悪感を感じるのであろう。まさにそれは、日本人のもつ霊性ゆえに感じ取るおぞましさであり嫌悪感なのである。
おそらくはこの霊性は日本人の多くに潜在するものであろう。それが、脳死判定後の臓器移植に対して42%の人間が理解を示しながらも、実際にドナー登録している人の数が8%にすぎない現実となって表れている[93](*94)。そこには、一般的事柄としての脳死判定後の臓器移植というものに対して理性的にはそれを受け入れられても、自分自身の問題として行動に移すには心が受け入れられないという霊性が機能している側面があると考えられる。 このように、臓器移植に賛成するか反対するかという決断は基本的にはわれわれの自由に属する問題である。しかし、その自由はわれれに深く浸透している日本文化といったものと密接に関係している。
そのような構造についてA・ヘッシェルは次のようにいう。
自由という語でわれわれが意味しているのは、心理的および物理的な先行条件からの意思の独立である。だが、意思はその人の性格や環境条件から独立しているであろうか。あらゆる行動は先行的要因の結果ではなかろうか。ある決断がなされるこの瞬間には、過去の圧力が積みこまれているのではなかろうか。ある行為の賛成理由と反対理由とを比較し、そのいずれを選択しうる精神の能力は、意識されている明白なそれらの理由の射程を超えることはない。だがこれらの理由は、無限にさかのぼる系譜を背後に持つ別の理由から導出されたものである[94]」(*95)
このヘッシェルの言葉は、文化が個人の意思決定に無言の圧力となってそれを導くものであるということを示しているが、それがまさに臓器移植という、身体観の問題にも表れているのである。そういった意味では、理性としては、臓器移植に理解を示せても、個人あるいは家族の問題として考えるとき臓器移植に抵抗を感じるというのは、まさに日本の文化というものの無言の圧力を受けているといえよう。
かくゆう筆者自身、臓器売買という言葉に、反射的におぞましさと嫌悪感を感じる事実を内省するとき、それは、筆者もまたキリスト者であり牧師といういわゆる西洋的文化の中に身を置くものでありながら、その根底には日本文化と日本人の霊性に浸っているということに意味することにほかならない。
このことをして考えると、臓器移植に反対である、あるいは抵抗を感じるという人は日本においては精神的にメジャーな存在であり、臓器移植に賛成し、ドナーになるという人は精神的マイナリティであるといえよう。実際、ドナー登録者は8%なのである。脳死以外の生体肝移植であるならば提供するという人を含めれば、もう少しこの比率は増えるかもしれないが、それでもマイナリティであることに代わりはない。しかし、たとえ8%のマイナリティであっても、そこには臓器移植を受け入れるという自由な決断をする人がいるのである。だとすれば、(これは脳死についてもいえることなのだが)この無言の圧力のなかで、それらの人の自由な決断をどのように守るかが大切になってくる。
2-3-3.身体の所有権関する問題
さて、先にも少し触れたが、臓器移植を考える際に、どうしても避けて通れない議論が、身体はだれのものであるかという議論である。それは、脳死の問題に振り返るならば、命はだれのものかと言うことになる。もちろん、命はだれのものかということと、身体はだれのものかということは、多少異なってくる。というのも、命はだれのものかという問題には、一人称の死と二人称の死が微妙に絡み合ってくるからである。ここでは、命はだれのものかということについては、後の自己決定論での議論にゆだねることとして、身体はだれのものかということについて考えてみたい。
この身体はだれのものかということについて、池田清彦は次のように述べる。
我々は、少なくとも私は、自分の直感的な感覚として、臓器売買は禁止すべきだと考えている。しかし、ロック以来のリバータリアンの伝統である自己の体は自分の所有物だとの立場をとると、この直感に反した結論を出さざるを得ない。逆に、私が自分の直感を信じる限り、このロックの前提が間違っているのだと思わざるを得ない。自分の体は自分が作ったものではない。物ごころついた時に、すでに自分と共にあったのだ。だからそれを自分の所有物だと主張するのは傲慢ではないのか。それが、私の結論である[95]」(*96)
池田がいう「ロック以来のリバータリアンの伝統」とは、ジョン・ロックが「統治論」で主張した「すべての人間は、自分自身の身体に対する所有権を持っているという主張である。この主張にもとづけば、臓器販売も認められることになると池田はいうのである。もちろん池田自身は自分自身の身体は自分に属していると言っているわけではない。むしろ池田は、「自分の体は自分が造った物ではない」というところに立って、身体が自分のものではないということを主張している。この「自分の体は自分が造った物ではない」いうような感覚は、一般に耳にする「親から貰った体だから傷つけてはいけない」という意識の中にも見られる。つまり、体は自分が自分で得たものではなく、親から与えられたものだという意識である。そして、このような親から貰った体という感覚は、それが池田のいうところの感覚と同じかどうか分からないが、しかし、われわれ日本人の間には以外と浸透している感覚ように思われるのである。
このように親から貰った体というとき、それは、先の「人間の身体はイザナギ・イザナミノミコトにつらなる命の系譜にあって、その二神の神業による命が両親を通して与えられたものであるから、身体は丁重に扱うべきであり、死後の身体も死体としてではなく、人として丁重に扱うべきである」という井澤正祐の主張に相通じるものがあり、その源泉は神道思想にあるということができるかもしれない。しかし、一般的日本人はそのような神道思想に精通するからそう感じるのではなく、一つの文化的背景の中で何となく、漠然とわれわれの中に浸透している感覚といった方が妥当であろう。
この場合、自分の体は自分自身のものだけではなく、親のものでもあるのである。つまり、個人は個人であると共に家族という集合的人格でもあるので。そこでは、「わたし」の体は親とつながり、また家族と繋がっていく。
しかし、そうはいっても、現実の自分の体を用い、支配し、使っているのは自分自身である。その意味では、自分の体は第一義的に自分の体は自分のものとして理解している。もちろん、観念的、あるいは漠然として理念として、自分の体は神のものであり、自分はその体の管理を託されているというような見方もできるであろうし、親のものであるという見方もできるであろう。しかし、結果としてそれは、「わたし」の第一義性に寄りかかっている。なぜなら、信仰も信念も「わたしの信仰」、「わたしの信念」として、「わたし」という一人称に寄りかかっているからである。そして、その「わたしの信仰」「わたしの信念」として導き出された結果にすぎない。だからこそ、この「わたしの信仰」「わたしの信念」というものは、ときとして家族という集合的人格を乗り越えていく。それは、人間の自律性がそこにあり、それゆえに家族の信仰、家族の信念を超えた「わたしの信仰」「わたしの信念」が築き上げられていくからである。それゆえに人間が人間として生きる限り、わたしは「わたしの身体」に対してプライオリティを持つといえよう。この「わたし」の自律性と家族という集合的人格が混然と存在しているところに日本的な個である「わたし」が形成されている。
同時に、「わたし」という一人の人間は、社会を構成する一員であり、国家を構成する一人でもある。それゆえに、「わたし」という体は社会とも繋がっている。この意味に置いて、「わたし」は社会的存在であり、この社会的存在であるがゆえに、社会との連関の中で、私の「わたしの体」に対する自由は制約を受ける。たとえ、体が「わたし」のものであったとしても、社会の秩序を混乱させ、公序良俗を乱し、社会正義を犯すようなことがあれば当然のことながらその自由は制約を受ける。ここにおいて、自分の体は自分のものであると同時に社会のものともなる。脳死と臓器移植が、「臓器移植法」が必要とされ、その法律の下で臓器移植が行なわれたり、あるいは自殺の幇助が刑法の適用の対象となるのはそのためであり、摘出された臓器がもはや、自分の意思や家族の意思でどうこうされるのではなく、法のもとで管理し用いられるのである[96]。このように、「わたし」の体というものが、「わたし」自身のものでありつつ、家族のものでもあり、また社会のものでもあるというように複雑に関係する。
3.自己決定
3-1 現行の臓器移植法における集合的人格的における自己決定
この混乱し行き詰まる脳死・臓器移植問題の議論に対して、バイオエシックスの立場から「自己決定」という現実的解決方法が提案されている。脳死、あるいは臓器移植における自己決定とは、要は自分の死に対する決定権は自分にあるということであり、また臓器を提供するか否かの決定も自分にあるということである。すなわち、「わたし」の体は私のものであるがゆえに、「死ぬ権利も臓器の提供をも決定する権利も『わたし』にある」ものであって、「わたし」に決定させればよいというのである。
現在のわが国の臓器移植法は、ある程度この自己決定権を尊重したものとなっている[97]。ある程度というのは、第一に、脳死の場合に限ってのみ、脳死を人の死として扱うからであり、第二に本人の自己決定権が尊重されているが、それは決して最終的意思決定ではなく、脳死あるいは臓器移植という最終決断に至る決定権は本人だけのものによるわけではないからである。たしかに、臓器の摘出は、本人の意思がない限り行えないし、本人の臓器移植の意思が示されていない限り、法的脳死判定も行なわれない。この意味に置いて、「わたし」の自己決定が反映されている。しかし、本人が臓器移植の提供者になるという意思を明らかにしていても、家族がそれに同意しない限り、この本人の決定は履行されない[98]。つまり、その本人の自己決定は覆される可能性があるのである。
また、脳死状態の患者がドナーとなる意思表示をしていたとしても、家族の同意が得られない限りその患者は死んだものとしては扱かわず、人工呼吸器のもとでの状態は維持され続ける。もちろん臓器移植はおこなわれない。たとえるならば、本人の移植に対する自己決定が、その人の脳死を人の死とするかどうかを決める議場の扉を開き、自らが死んでいることを認めるようにもとめるが、その議場で、その患者の申し入れを受け入れるか否かの結論を出すのは家族であるということである。このように、日本における脳死・臓器移植に関する自己決定は、単なる「わたし」の決定という自己決定ではなく家族の同意をも含む、「なんじと我」という集合的人格的における自己決定なのである。
3-2.脳死における集合的人格的における自己決定のモデルとその問題点
3-2-1.集合的人格のおける自己決定のモデル
すでに、述べたように集合的人格的における自己決定は「汝と我」の間にある関係を土台とした意思決定である。そこには「わたし」とその「わたし」を「汝」と呼ぶ家族の関係がある。この関係に置いて、「わたし」の決定に家族の意思が関わってくるし、家族の決定には「なんじ」である「わたし」の意思が何らかの形で関わりを持つ。このような集合的人格的における自己決定の背景には、日本における“個”の確立の問題がある。日本においては“個”の存在が全面的に否定されるわけではないが、“家”という存在が“個”と密接に関わっているという背景がある。たとえばそのような精神性は結婚において顕著に表れている。すなわち日本における結婚は“個”と“個”の結び付きであると同時に“家”と“家”との結び付きでもある。それは結婚式において“~家”“~家”結婚式場などという表現が無条件に受け入れられていることに反映されている。だからこそ、結婚の際には親の了解を求める行動にでるのである。つまり、個人の一人称の自己決定は、個人の意思として尊重されるべきものではあるが、前提として家族の承認が求められることが意識の中に暗黙の事柄としてその精神性の中にあり、社会もまたそれを暗黙の了解事項としてうけとめているのである。
このような個と家族の密接な「なんじの我」の関係の中でなされる意思決定は、「わたし」が生存し、自らの意思を示せるならば、それは「わたし」の自己決定であるといえる。たとえ家族との話し合いの中で、「わたし」の最初の意思が覆されたとしても、その覆された状況を「わたし」が承認して受けいれる限り、それは「わたし」の決定だからである。したがって、これは一人称の自己決定である。問題は、「わたし」が自分の意思を示すことのできない状況、たとえば死亡(心臓死)してしまっている場合、あるいは脳死、または植物状態になってしまっているような場合である。
このように「わたし」が、「なんじと我」の間において自分の意思を表明できない場合、家族がその意思決定をおこなうことになるが、そこには4つのモデルがある。
モデルA: 脳死状態ような、自分の意思を表わし難い状況なったときを想定してあらかじめ本人の意思が伝えられている場合。この場合は、家族が本人に変わって(代行して)本人の意思をもって、思決定を表明することが出来る。したがって、そこで表わされた意思は、まったくもって本人の一人称の自己決定である。アメリカニュージャージー州で起ったカレン・クライン裁判[99]などがこれに対する類似の事例に当たる。
モデルB: 本人がドナーとなる意思を示しているか、あるいは延命処置を望まない意思を示しているが、家族がそれを承諾できず延命を希望する場合。この場合は、本人の積極的意思は完全に覆され、家族の消極的意思が本人の意思に優先される形で代行される決定される。
モデルC: 本人が臓器移植を拒む意思を示していたり積極的延命処置望む意思表示をしていたのに対し、家族が積極的延命処置を拒んだり、あるいは臓器移植を望む場合。この場合も、原則的にはモデルBとおなじ状況であるが、モデルBとは違い、本人の消極的意思が家族の積極的意思で覆される。しかし極めて難しい状況も考えられる。臓器移植のみに関して言うならば、現在の臓器移植法では、本人の承諾がない場合、脳死判定も行なわれないし、臓器移植も行なわれないので家族の意思が問われることはない。ただ、本人が望んでいた延命処置を家族の判断で行なわない場合に問題が生じる可能性がある。
モデルD: 本人が、脳死になった場合のことを想定した意思表示がなされていない状況(幼児や論理的判断の出来ない重度の精神障害を持った者の脳死も含む)で、家族が延命をするしないを決断をし、さらには臓器提供をするかしないかを判断するような場合であって、この場合も家族の意思が本人の意思の代理とみなされるモデルである。脳死ではなく植物状態の事例ではあるが、ナンシー・クルーザン事件[100]などがこれにあたる。
モデルAの場合、本人の脳死あるいは臓器移植に対する臨床の場での決断を迫られる意思表示がなくても、本人と意思が、その意思と一致している家族の意思決定人の意思が反映されている。この場合、家族の決定は集合的人格的における自己決定であると同時に、本人の一人称の自己決定でもある。たとえば、過去に置いて本人がドナーとなる意思、尊厳死に関する意思を示していて、その後に家族と話し合う中で本人がその意思を変更していたとしても、変更したことにおいてそれは一人称の自己決定であり、家族がそれを代行した形でその意思が表わされる。それゆえにとくに問題はない。問題はモデルBからモデルDまである。これら三つが、本人の示した意思ではなく家族の意思による決定であり、「なんじと我」の関係でなされる集合的人格的における自己決定であると考えられる。この場合、集合的人格的における自己決定といっても、表面上は家族の決定が「わたし」の決定に優先して最終的な決定となっている。そこで、この三つのモデルの構造について検討してみたい。
3-2-2.集合的人格的における自己決定のモデルの構造
さて、「なんじと我」の関係における集合的人格的における自己決定の3つのモデルの検討にはいる前に、一つ確認しておかなければならないことがある。それは、ここで取り上げるモデルは脳死が不可逆的な死の過程にあるという理解に立っているということである。つまり、ここでの議論はすべからく現在の医療行為では、脳死状態からの回復の期待はなく、ただ人工呼吸器と投薬によって脳死状態が維持されているという現在の脳死状況が前提とされている。したがって、それは植物状態におけるものとは決定的に異なる。また途中、類似した例としてナンシー・クルーザン事件、あるいはテリ・シャイボ事件[101]など、植物状態における出来事を取り上げることがあるが、それはあくまでも類比としてとらえられる参考事例である。
モデルBの場合。
モデルBの場合、本人の積極的意思を、家族の消極的意思が覆すことになるが、この場合、脳死において本人の「わたし」の死という一人称の死は成立している。ところが、家族にとっての二人称の死はいまだ成立していないのである。つまり、「わたし」の死という一人称の死が前提としてあり、それを承諾・承認できない状態であると考えられるのである。そして、そこにおいて臓器移植という身体に関する自己決定は尊重されないのは、肉体に対するあきらめをともなうである二人称の死が成立していないからにほかならない。
この場合、「わたし」の死が前提としてそこにあるゆえに、死に関する本人の自己決定は本人に対して基本的に尊重されている。そえゆえに、本人はもはや自分自身に対して意思を持って積極的に関与することができない。自分の「かつてあそこで」の“意思”を示しうるだけなのである。それゆえに、残されているのは、本人の身体とその“意思”であって、家族がその意思をうけて、その“意思”と身体をどのように受け止めるかという問題である。そして、一人称の死を二人称の死として受け入れがたく、その身体に対するあきらめができないがゆえに、脳死を死として受容できないのであるから、当然、家族にとっては臓器移植も承諾できないであろう。そこには、依然断ちがたい「なんじと我」の関係が、この此岸に残っており、肉体に関するあきらめられない思いがあるのである。それゆえに、ここでは断ちがたい「なんじと我」に立って二人称の死を受容での集合的人格的における自己決定となる。
モデルCの場合。
モデルBが本人の脳死・臓器移植に対する積極的意思を家族の消極的な意思が覆すモデルであったのに対して、モデルCの場合、本人の消極的意思を家族の積極的意思が覆すモデルである。現行の臓器移植法では、本人の臓器移植の積極的意思が書面で表わされていない限り、法的脳死判定も臓器移植も行なわれないことは先に述べたとおりである。しかし、仮に脳死となったとき、本人が出来る限りの延命処置を望む意思を示していた場合はそうであろうか。これに対して、家族が延命処置を拒んだ場合どうなるのであろうか。
このとき、脳死が人の死であるなら問題はない。脳死段階で人の死がそこに存在していると認識されているのであるから、そこに決定以前の前提としての死がある。それゆえに延命のための治療を停止したとしても、それは不自然なことでもなんでもない。しかし、現行の臓器移植法では脳死が人の死であると明確に定められているのではなく、ただドナーとなって臓器移植をする場合のみ、脳死判定を経て脳死した身体として臓器移植を行なう事ができると表現されているにすぎない[102]。
したがって、本人の延命措置を望む自己決定を超えて、家族が延命措置としての治療の停止を望む意思表示をしているとしても、医療側が家族の意思とはいえ延命治療を打ち切るのは難しいものと思われる。そもそも、医療における自己決定は自分の望まない治療を拒否し望む治療を選択することができる権利として捕らえられるものである。それゆえに、家族における「なんじと我」の関係における二人称の死の決定を原則として支えるべき一人称の死もなく、また法的支えとなる三人称の死もない以上、医療側が延命を停止することはできないのである。もっとも富山県射水市民病院事件[103]を契機に、亜急型に限ってではあるが、日本学術会議は2008年2月に、本人の意思表示がない場合は、家族の意思で延命中止を容認することを認め、その趣旨を報告書に織り込んだ。それによって、本人の意思が明らかでない場合に家族の同意の下に延命中止がなされる可能性が開かれたが、それでも現行法の下で、しかも救急型終末医療に置いて本人が延命処置を望んでいるならば、延命を中止するならば刑事罰の対象になりうるのである。
しかしながら、本人の意思、つまり自己決定があったとしても、それで家族の意思を無視していいかどうかについては問題を残す。なぜならば、脳死とくに長期脳死になった場合、経済的にもおいても介護においても治療の負担を負うのは家族だからである。それゆえに、確かに本人の自己決定は尊重されなければならないが、とはいえ回復不能の脳死の場合、それが無限に延長されてよいものかどうかについては疑問が残るのである。というのも自己決定は無条件なものではなく、そこには条件があり、それゆえに限界があるからである。その自己決定の限界について、長沼淳は次のようにいう。
一般に『自己決定権』と言えば、『他者に迷惑をかけないかぎりにおいて人は何をしてのよい』、という権利と考えてもよいかもしれない。またもっと単純に『自分のことは自分で決める』権利ということも可能であろう。前者の場合、『他人に迷惑をかけないかぎりにおいて』の内実の把握が不可欠となる。だが、『他人に迷惑をかけない』を具体的に規定しようとすると、それは非常に困難を極めた作業にならざるを得ない。『迷惑』に関して、多様な解釈があり得る以上、『他者に迷惑をかけない』ということを追求したところで、われわれは一意的な規定を期待することはできない。『迷惑、』はわれわれのあらゆる行ないの中に入り込む余地がある。そうすると、『他者に迷惑をかけないかぎりにおいて』はむしろ、自分の行ないはすべて『迷惑』であるとして、どの程度までは、他者に許されるのものなのか、あるいは許容されるべきものなのか、と考えていかなければならないものとなり得る[104]。
また、岡田信弘も「『他人に関係のない事柄(私事)については自分に決定権があり、自分にしか害が及ばない行為であれば、自らの責任において行為することができる』。これが従来考えられてきた自己決定権です[105]。」(*106)と述べている。これは、いかに自己決定された決断であっても、他者との関わりや周囲に負の影響を与える場合は絶対的なものではないということを意味する。つまり、いかに延命治療を望むという自己決定がなされているとはいえ、それが無限に延長されるものではないのである。というのも、仮に本人が脳死状態での延命治療を望む自己決定をしていたとしても、本人が深い昏睡状態にあり回復しない不可逆的な状況にある以上、脳死に陥ったものが必ずしもその決定によって引き起こされる諸般の出来事[106](*107)に対して「自らの責任において行為することができる」わけではない。結果として、延命治療を望む本人の自己決定は「どこ程度まで他者に許されるものなのか」あるいは「ゆるされうべきなのか」が問われることとなる。しかも、そのような諸般の出来事に対して、様々な負担を負う家族である。それゆえに家族の決断はかならずしも無視できない側面もあるといわざるをえない。
だとすれば、そこにおいては本人の自己決定が、自己決定の要因である「他人に迷惑をかけない」ということや「他人に関係のない事柄(私事)については自分に決定権があり、自分にしか害が及ばない行為であれば、自らの責任において行為することができる」という要件を欠いているのである。
このような論議は、暴走すれば家族に負担になる患者は、すべて本人の意思に拘わらず家族の意思で治療を打ち切って良いうのかというところに走っていく。しかし筆者は、そのような問題まで間口を広げて論じているのではない。あくまでも脳死という特殊な状況のもとでの話である。もちろん、特殊な状況下の議論であっても、それが拡大解釈されていく危険があるという主張もあるであろう。しかし、それは拡大解釈が問題なのであって、本質となっている議論それ自体が非とされることではない。ここで問題なのは脳死という特殊な状況下での本人の意思決定が及ぶ範囲である。
そのような脳死という特殊な状況下にあっても、確かに現行の臓器移植法が、脳死を死としての明確な定義をしていない以上、たとえ脳死した者であっても、臓器を提供する意思を書面で示さないかぎり、現状では法律上は延命治療を中止することはできない。しかし同時に、脳死した者の身体からの臓器の摘出を認めている以上、少なくとも、脳死が不可逆的な死の過程の内にあるということは理解の内にあると考えられる。したがって、そのように脳死が死の不可逆的な死の過程にあるのであるならば、具体的に負担を負う家族が、本人の自己決定をどこまで許し受け入れるかが問題になる。そして、いかに本人の意思が提示されているとしても、その本人の自己決定が家族の許容の範囲を超えて負担を求めるものであると認められるものならば、本人の表わした意思は自己決定のための要件をもはや欠いると考えざるをえない。
だとすれば、延命のための治療をどこで中止するのかということについての家族の決定もまた、必ずしも無視できないもとなるであろうと考えられるのである。もちろんこの場合、家族の許容範囲を誰がどのようにとらえ判断するか、その妥当性が問題となる。そして、それが社会的に妥当であると考えられるとき、二人称の自己決定もまた社会的妥当性を持つものとして受け入れられるであろう。しかし、このためにはいずれにしても法整備もしくは社会的コンセンサスが必要である。
ルDの場合
モデルDの場合、本人が脳死になった場合における医療行為についての意思表示がなされていない状況(幼児や論理的判断の出来ない重度の精神障害を持った者の脳死も含む)での家族の決断で、延命をするか否か、あるいは臓器移植を望むか望まないかの決断である。たとえば、米国の場合、(PSVの事例ではあるが)本人の意思が不明な場合、家族が本人に代って代理として生命維持装置をはずすことができる権利は、カレン・クライン裁判(カレンの場合、家族に対して、口頭での意思表示はあり、その意味ではモデルAのケースだが、しかし、明確な文書としての意思表示はなかった)やナンシー・クルーザン事件を通してそれを認める判例が確定している。
日本においても、先に述べたように、本人による意思表示がない場合の家族による延命拒否は亜急型に限って2008年2月の日本学術会議で容認され、その可能性が開かれた。もちろん、家族よる延命の継続や法的脳死判定の拒否ができるということも当然のことである。このような場合、家族が本人の代理とみなされ意思決定をするのだが、わが国の場合、この家族の決定は、単に家族が代理として決定すると言うだけでなく、一般に本人と家族の他我が一体化した中での家族の決定と見ることができる。
たとえば、2008年2月17 日付けの読売ウィークリーには、山崎光祥の「脳死を生きる子どもたち」という記事が出ている[107]。この記事には14人の脳死あるいは脳死に近い状態と宣告された子どもたちの長期生存例を取り上げた記事である。小児脳の場合、長期脳死が起こりうる場合があることは先に述べたとおりであるが、この記事の場合、すべてが脳死というわけではなく、臨床的脳死とされるものは2例である。残り例は、PVSか重度の脳障害の例もあるが、しかしここには、長期の深い昏睡にある子どもを抱える親の気持ちが記されている。これらは、脳死を抱えた家族の感情に類比できるものであるといえよう。そしてそこに見ることのできるものは、他我が一体化した心情、つまり、昏睡状態にあり意思や感情を示すことのできない者の意思や感情を、親なり家族なりの脳死の人を取り巻く者が、それをくみ取り理解し、本人の意思や感情として理解し受け取っているということである。
たとえば、先に挙げた山崎の記事によると、「子どもたちは何を望んでいると思うか」という問いに対して、ほとんどの親が「家族と一緒にいたいはず」「『生きたいと』いう意思を感じる」という答えが返ってきたと述べている[108](*109)。この「子どもたちは何を望んでいると思うか」という問いは、すでに他我的答え引き出す問い方であり、問いかけた相手が既に脳死の子どもの世話をし、育てている親であるという状況を考えると、若干恣意的になってしまっている可能性があるとは思うが、しかし、それでも子どもたちに生きる意思を感じるというのは、他我の問題がそこにあることを示している。親たちは体温や顔色・心拍数などを通して、子どもの生きる“意思“”精神“を感じ取っているのである。また、脳死状態であっても、その脳死の家族が「いる」ということが家族の支えになっていたり、その世話をすることに意義を見出しているケースも少なくない。脳死の子どもを抱えた母親が「どんなにつらくても、生きようと全身で戦っている。息子は毎日変化しているし、汗をふいたり、熱を冷やしたり、してあげられることがたくさんある」と言い、「ただ眠り続けているだけ。体を触れれば『生きている』と感じる。翔太郎(筆者註:臨床的脳死診断を受けた後2年10ヶ月生存している4歳に小児)がいるだけで、家族が笑顔になれるんです[109]と言う言葉は素直な気持ちであろう。したがってこの母親にとっては、この臨床的脳死診断を受けた息子は存在意義のある存在なのである。
マーガレット・ロックは日本人医師の「意識が不可逆的に失われていても、PVS患者はやはり、意味ある生活を家族と共に送ってきた人間でありつづけ、家族はPVS患者に情愛を抱かずにはいられないのである」と言う言葉を引用しつつ、「彼らは生物学的にいきているだけではなく、社会的にも生きており、周りの人間にいろいろな感情を生じさせる存在なのである[110]といっている。これはPSV患者に対する言葉であり、厳密な意味では脳死患者と事情が違う面もあるが、しかし、脳死患者であっても「周りの人間にいろいろな感情を生じさせる存在」として、家族にいろいろな感情を与える存在として存在意義を持っているということでは、先の母親の気持ちに通じる同じものを示している。
このような、脳死患者と家族の「なんじと我」の結び付き、その関係の中にあっていかに脳死という不可逆的な死の過程にあったとしても延命を望む家族の決定は尊重されるべきであろう。
しかしすべての者が、ここに挙げた親たちと同じような心情を感じるとは限らない。同じような状況下にあったとしても違った受け取り方をすることもありうる。すなわち、生命維持装置につながれて“生かされている”状況を本人が望んでいないと受け取る受け止め方である。
もちろん、“生かされている”という表現は、前提として生があり、それゆえに脳死を死と考えてはいないのでないかという議論が起りうる表現ではある。しかし、それは“脳死”、あるいは脳死、それ自体はだれもが経験できない状況であり、本来自分の経験できない状況は、既知のものをもって表現せざるをえない。したがって、当然脳死を語る際に死をもって表現しようとするならば、従来の生死を分ける心臓死の概念から脳死の状況を表現しなければならなくなる。その際、表現としては従来のターミナル・ケアでの概念表現で語られるところとなる。実は、このような、言葉の表現が、脳死の問題を更に混乱させていると思われるのだが、とにかくここでは、同じ他我が一体化した心情から、脳死を受け入れる心情も起こりうるのだということを述べることに集中したい。
そこで、このような、脳死になった人からに対する他我が一体化した心情から、脳死を受容する心情であるが、残念ながら、そのような心情が語られることは極めて少ない。これはひとつに、現行法のもとでは、2008年2月の日本学術会議の脳死にて「本人の意思表示がない場合は、家族の意思で延命中止できる」という見解が出されるまでは、PVSにしても、脳死にしても、本人の明確な自己決定なしで、家族の決定によって延命治療を打ち切ることがことはできないという事情がある。本人の意思確認が無 いままの延命中止は殺人罪に問われる可能性すらあるのである。実際、先にあげた射水市民病院事件の例以外にも和歌山県立医大病院事件[111]などは、まさにはそのような背景の中で事件としてとりあげられた。したがって、そのような状況下では心情が公の形で表に出にくい事情があるといえよう。
しかし、現実として救急医療の場においても終末医療の場においても、家族の意思で延命治療の中止が行なわれてきた実態は、先の射水病院事件・和歌山県立医大病院事件以後、終末医療の延命中止に対するガイドラインを求めて医療側から徐々に明らかにされるようになってきている。たとえば、2006年に秋田赤十字病院で長期脳死の患者(44歳女性)の人工呼吸器がはずされたケースや2007年には、千葉救急医療センターが、2006年10月から2007年3月の5ヶ月に30代から50代までの5人の患者(内3人は脳死判定後)の延命治療を家族の同意の下に中止したことを公表している[112]。
このように家族が家族の意思で延命中止を求めるといった事例は、以前から医療の現場には少なからずあったといえよう。その際の家族心情については、たとえば、先に秋田赤十字病院の例では、医師から「患者本人だったらどうしてほしいと思うか、代わって考えてほしい」といわれ、家族は5ヶ月かかって「呼吸器も含め延命治療を中止したい」と言う答えを出した[113](*114)。また人工呼吸器につながれている姿を「こんな姿を見るのが耐えられない[114]」(*115)といった心情もある。
先にも述べたように、日本における“個”は“家”との密接な関係にあり、家族は自己の存在の一部分である。そのような関係の中で、脳死状態にある患者に「かわいそうだから」とか「こんな姿を見るのが絶えられない」という心情になるのは、もちろん人工呼吸器に繋がれ生命維持つながれたいわゆるスパゲッテイ・シンドロームの状態の家族を見て「絶えられない」という「わたし」の痛みがそこにあるが、単にそれだけでなく、脳死になった本人の痛みを家族が感じ「かわいそう」に思うのであって、「見るのが絶えられない」というのは「わたし」が「見るに耐えられない」のではであるが、それは本人の痛みを感じるがゆえの「見るのが耐えられない」という心情を産み出すといった一面もある。先の医師の「患者本人だったらどうしてほしいと思うか」という問いかけは、そのような、他我が一体化した心情に対する問いかけである。
このように、他我一体となった心情によって、脳死に生ではなく死を決断するケースも現実に起っている。その場合、家族にとって脳死となった患者は、すでに希望が持てない死の内にあるのであるが、そのような状況にあるにも拘わらず生命維持装置によって不自然に“生かされている”現状が本人とって「かわいそう」な苦痛の状況であり、それは、家族が「見るのか耐えがたい」ほどの「あなた」の苦痛であるので、家族は「あなたの死」という二人称の死として受容していると同時に、集合的人格的に死を受容し、耐え難い家族の彼岸的な関係の断絶を引き受けようとしているといえよう。
それゆえに、家族の決定は、本人に変わって決定を行なうのではなく、表明されていない本人の意思そのものを代理して表明される集合的人格的における自己決定なのである。いずれにしても、脳死に陥った患者の家族が、それを死と受け止めるか生と受け止めるかの決断の背後には、他我問題がそこにあり、他我の問題の中で決断される集合的人格の自己決断であるといえよう[115]。
以上、ここまで見てきたように、脳死状態にある患者の治療に関する決定には、少なからず他我問題が関係している。つまり、最終的には家族が決定するのであるが、そこには脳死となった本人の意思や心情が、汲み取られている。また「なんじと我」の関係と本人と家族との一体化した、極めて密接な家族関係がある。同時に、その「なんじと我」の関係の中で延命治療を中止する場合、そこには前提としての「あなたの死」がある。それは、抗いきれない不可逆的な死の過程に対するあきらめであるともいえよう。先に秋田赤十字病院のケースにおいて、家族は、5ヶ月の考慮の後、医師に「そろそろ見送ってあげたい。呼吸器を含め中止してほしい[116]」と述べた言葉にそれが良く表れているといえよう。
すなわち日本における脳死は、なによりも医師による「かれの死」、つまり三人称の死の宣告ではなく、家族による「なんじと我」の関係における二人称の死の決断である。それは、家族によって「あなたは死んでいるのだ」という二人称の死の宣告でもある。同時に、そのことは「なんじと我」関係においては、関係自らがその関係自身のこの世における此岸的一人称の死を受容することでもある。それゆえに、家族の決定が不可欠なものとなり、最終的な決定となるのである。
3-3-3.脳死に対する集合的人格的における自己決定の問題点
自己決定という理念は、本来、自分のプライベートに関わる事柄は自分の責任において自分が決定できるというものであり、人間の自律性に基づくものである。そういった意味では、ここでいう集合的人格的における自己決定は、自己という存在が社会との関係性、とりわけ家族との関係性の中でとらえることによって発生する概念であって、特に日本の社会事情に基づくものである。この日本の社会事情に対して橳島次郎は、次のように述べている。
つまり、アメリカの論理構造に基づく現代医療は、「人格」をあくまでも一個人の内で独立に発生し消滅するものととらえる。だからその個人の内だけで、生の始まりと終りの時点を追求し、確証することに重きが置かれる。それに対して日本の伝統社会においては、「人格は」集団的なプロセスの中で発生(筆者註:誕生)し、消滅(筆者註:死)する[117]。
橳島が言わんとしていることは、日本という社会においては、いわゆる人間の生死に関わるようなプライベートな事柄であっても、それが自律性に基づく自己決定によって決定されるのでなく、共同体の中で決定されるということである。この共同体は、かつては、村落共同体や親族共同体といったものであった。しかし、橳島も認めるように、近年になってそのような共同体次第に崩壊し核家族化している。そういった意味では、日本社会はかつての共同体という集団意識から、個人という自律した自己へと移行しつつある過程であるといえよう。その過程の中で、家族という共同体の結び付きがあるのである。そして、そこにある家族の結び付きが集合的人格的における自己決定を支えている。
しかし、それはあくまでも移行の過程の中にあるものである。したがって、それは相対的なものであり、絶対的なものだとは言えない。仮に、わが国の「人格」意識が、より個人という自律した自己が強調されるようになるならば、当然、一人称の自己決定が集合的人格的における自己決定に優先されなければならない。その場合、モデルBやモデルCのケースは(延命治療にかかる負担の問題が解決されるかぎりにおいて)起こり得ないであろう。一人称の自己決定を家族といえども覆せないからである。
それに対して、それでも個人が明確な意思を示していないまま脳死に陥るというモデルDのようなケースは依然として残りうる。この場合、家族の意思が一致していればよいが、テリ・シャイボ事件のようにそれが異なる意思を示した場合に問題は複雑になる。テリ・シャイボ事件の場合、延命処置をめぐってテリの夫とテリの両親の意見が異なり問題となってしまった。もっとも、この事例はアメリカでの事例であり、テリの置かれた状況は脳死ではなくPSVではあったが、夫が認識していたテリの意思と、両親が認識していたテリの意思との齟齬であったという点では、本質的には脳死の状況と同じであると言える。つまり家族の意思とはいっても、その家族の意思の最終的決定権、あるいは優先権は誰にあるのかという問題である[118]。
これは、内家族的問題であると同時にそこに遺産相続問題等の利害関係がからむことがある。それゆえに問題が複雑化した場合は法的問題ともなる。しかし、このあたりのことに関しては、わが国においては、まだ法的に整えられていない[119]。このように、集合的人格における自己決定による死の承認には少なからず派生的に法的問題が起ることが充分に予測されるのであるが、2008年に日本学術会議で本人の意思表示がない場合は家族の意思によって延命を中止できる旨が容認され、事実上、集合的人格的における自己決定の可能性が開かれたにも関わらず、この法的な面では、未だ様々な問題に対して充分ではない状況にあるといえよう。
ところで、このような自己決定の前提には、脳死が不可逆的な死の過程にあるという生理学的医学的的前提があることはいうまでもない。不可逆的な死の過程の中にあるからこそ、その死の過程においてどの時点で死を受け入れるかが問題とされているのである。だとすれば、このような自己決定は、一人称のものであれ、二人称のものであれ、どこまで延長されるべきものなのかということが問われてくる。つまり、脳死は従来の心臓死より前に死の承認を置くのであるが、死の承認が自己決定によるとするならば心臓死の後における死の承認をおくと言うことも考え得る問題となるのである。このような事例は1999年のライフ・スペース事件[120](*121)などに見ることができる。
このライフ・スペース事件は家族に対しては2001年に保護責任者遺棄致死罪が確定し、またライフ・スペース代表には2005年に不作為の殺人として刑が確定している。この事件の場合、被告はミイラ化された遺体が発見された時点では生きており、死んだのは司法解剖された時点であるとして、その死生観を争点とした。それに対して、司法による死の定義が明らかにされなかったが、しかし少なくとも保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人が適用されている以上、この事件におけるライフ・スペースの死生観は受け入れられなかったといえよう。この事件において保護責任者遺棄致死罪および殺人罪が成立しているわけだが、この時の「死」の認識は、常識的に考えていわゆる心臓死が基準にあったと考えて良かろう。その意味では、一応、少なくとも心臓死が、不可逆的な死の過程において、日本社会という共同体におけるすべての人が、一律に死と認めざるをえない「死の最終ライン」として引かれていると考えられるのである。
しかしながら、いずれにしても、日本においては法的に「死」とは何であるかというの「死」定義が何であるかは未だ曖昧であり明確な定義が存在しない。そのような中で、不可逆的な死の過程というプロセスとしての死の決定が脳死の場合、家族に委ねられるのである。
もとより、わが国における近代の死の三徴候による死の宣告は、医師の専任事項であった。もちろんそれは、たぶんに儀式的趣もあるが、医師は患者の死を「かれの死」として宣告し、家族はそれを「あなたの死」として受容するしかないのである。ところが、わが国における脳死事情は、脳死によって家族が「あなたの死」を宣告し、医師がそれを「かれの死」として受容する。つまり、そこには従来の構造とはまったく逆の構造がある。
このような死の三徴候による医師の死の宣告が、医師の専権事項としてそれなりにオーソライズされているのは、前提として、医師は医師として医学を学び習得した中で、死の宣告をするという意思決定に先だつ情報として得ているという了解があるからである。しかしながら脳死においては、自らが脳死を自分の死として受け入れるか、家族が家族の「あなたの死」を宣告するのである。当然、そこには死を死として宣告するに先だつ知識と情報が必要である。それは、「脳死とは医学的にいかなる状況か」という知識であり、「今、自分の家族がどのような状況にあるか」という情報である。
そこで、脳死が一人称あるいは集合的人格的における自己決定に委ねられるとするならば、脳死が可能性として誰にでも起こりうるものである以上、すべての人がこれらのことを周知して決断しなければならないことになる。しかし、現実問題として、はたしてそのようなことができるのであろうか。たしかに、「脳死が医学的にいかなる状態であるか」ということについては、啓蒙活動等を通してある程度の理解を広めることは可能であろう。しかし「今、自分の家族がどのような状況にあるか」ということを知るにあたっては、結局その情報は、臨床的判断あるいは脳死判定によるものであって、家族が直接これを行なうことはできない。結局、これらの情報は医師の判断に頼らざるをえないのである。ここに脳死が「見えない死」といわれるゆえんがある。
このように、脳死が「見えない死」である以上、医師ではない一般人が、充分に家族の死を受容したうえで「あなたの死」を宣言する際には、医師からのインフォームド・コンセントが正しく、かつ分かり易く行なわれなければならないのである。この点において、従来にくらべインフォームド・コンセントが浸透しつつあるにしても、もともとパターナリズム的な構造にあった医療現場において、情報がどの程度正確に分かりやすく伝えられるかという基本的な部分に問題を残しているが、この様な問題は医師と患者側の信頼関係である程度乗り越えられていく問題である。幸い日本における医師と患者の信頼関係は米国ほど高くはないが、しかし決して低いもの[121]ではない。それでも、わが国にはいわゆる和田移植事件の後遺症を引きずっている特別な事情があり、臓器移植と脳死とが関係する場合、脳死に対する大きな不安感と不信感とを与えている。それゆえに、医師と患者および家族との信頼関係の構築も重要な課題として残されている。もちろん、それを改善するのは脳死患者でもその家族でもなく医療側にあるといえるが、先に述べた信頼度の高さに解決の可能性は潜在的に十分に開かれている。
もちろん、脳死を死として受け止める自己決定の際における医療側と患者側のかかわり合いにおいては、その姿勢が医療側だけ問われるのではでなく患者や患者の家族の側にも求められるべき姿勢もある[122]。そしてこの患者側に求められている姿勢において、患者側に問題がある場合もたしかにあるのである。近年いわれる「モンスター・ペイシェント」などは、このような患者側の基本的姿勢の欠落を示す一例であるといえよう。
4.臓器移植における自己決定
4-1.臓器移植に対する集合的人格的における自己決定
さて、脳死については、集合的人格的における自己決定によって脳死という死の受容が可能でありうるとして、この二人称の意思決定が同じように臓器移植にも適用できるのであろうか。この点について、検討しなければならない。もちろん、脳死の場合のモデルAのように、本人が臓器移植の提供を望む(あるいは望まない)意思表示をしており、家族もそれに同意している場合は問題がない。しかし、モデルBやモデルCのように本人と家族の意思が一致しない場合や、モデルDのように、本人の意思が明らかでない場合はどうなのであろうか。
脳死の場合、集合的人格的における自己決定が可能であったのは、脳死が死の不可逆的な過程の線上におかれているからである。つまりそれは、患者自身が不可逆的な深い昏睡にある状態のどの時点であっても、臨床的に回復不能な不可逆的な死の過程にあるのであって、そのどの時点で死を受容するかという問題である。そこにある違いは、家族が心臓死によるより遅い死を受容するかあるのか、それ以前のより早い脳死の段階で死を受容するかの違いであり、結果としてどちらも最終的には同じ死の受容に至るものである。だからこそそれは、可能な判断であったといえよう。
ところが、臓器移植は脳死とは異なる状況にある。臓器を提供するとしないとではまったく違った結果に行着く。たとえば、生体移植の場合は移植によって、ドナー自身も自らの体を傷つけ、かつリスクを負うことになる。それゆえに、生体移植の場合は、何よりも本人自身の一人称の自己決定が優先されるべきであろう。もちろん、だからといって、その本人も、他者との関係、時に家族との関係において不可分な「なんじと我」の関係におかれた「人格」として、家族との充分なコンセンサスをとらなければならない。それは日本という社会のもつ精神構造がそれを求めるのであるから、日本という社会内における医療行為において、それは不可欠なものとなるのである。この、自律した個と家族という集団的人格の狭間で、移植医療を考えなければならないところに日本の移植事情の難しさがあるといえよう。
また脳死移植の場合においても、移植のために脳死となった者の体にメスを入れることになることに変わりはない。その行為自体が脳死者の肉体的利益にならないことは明らかである。先に述べたように遺体に完全性を望む傾向がみられる民族に横たわる霊性や宗教的感性といったものも無視できない。 それは極めて重要な、そしてセンシティブな問題である。
仮に、家族の反対があっても、本人の意思であるとして第三者的に臓器提供を行なうとするならば、それは残された家族に精神的負担、不利益をもたらすことが容易に想像できる。それゆえに、たとえば、本人がドナーカードによる臓器提供の意思表示をしていても、家族の同意が得られない場合には、臓器移植を行なわないのである[123]。このような姿勢は、自律した個の存在を認めつつも家族という共同社会の分化が完全に行なわれていない日本の精神構造を考えた場合、妥当なものであるといえよう。
同様に、本人が臓器提供を拒否している場合は、いかに家族であっても本人の意思を乗り越えて臓器提供を行なうべきではない。日本という社会が、共同体中心の社会から個を中心にした社会に移行しつつある中で、依然、自律した個と家族という共同社会の分化が完全に行なわれていない社会であったとしても、そこにはたとえ不完全ではあったとしても自律した個の存在も見据えられているからである。また、本人の臓器提供を拒否する意思が、脳死者の肉体に利益をもたらさず、かつ残された家族に不利益をもたらすこともなく、そこに家族に負うべき負担もあたえるわけではない。そのような中にあっては、本人の意思を家族が覆すにふさわしい妥当な理由を見出すことができないのである。
それでは、本人が臓器提供に関して何ら意思表示せず脳死状態になった場合はどうであろうか。2006年に行なわれた内閣府によって行なわれた「臓器移植に関する世論調査」では、本人の意思が確認されていない場合は臓器移植を行なうべきではないという意見が36.7%、臓器提供を認めて良いは9.4%、家族に判断を委ねるべき48.1%であった。この数字から見れば、本人に意思が明らかでない場合は、家族の判断に委ねるという選択も可能であろう。たとえば、しかしながら、本人の意思が全く明らかにされていない場合は、基本的には臓器提供に対する消極的意思と考えても良いであろう。というのも、臓器提供は積極的奉仕精神によるものだからであり、そのような積極的奉仕精神を持つ者であるとするならば、何らかの形で積極的な意思の提示をするであろうと推察されるからである。
このことを逆から見るならば、臓器提供の意思表示がまったくない場合は、臓器移植に対する消極的態度であることが十分に考えられるのである。もちろん、積極的意思を持ちつつも、まだ意思表示をしていないという者も存在するであろう。ましてや、2006年に行なわれた内閣府によって行なわれた「臓器移植に関する世論調査」では、自分が脳死と判定されたとき、臓器を提供したいと回答したものが41.6%いるにもかかわらず(提供したくないは29.4%)、ドナーカードを所持しているものは、全体の8%しかおらず、しかも、その8%中で脳死と判定された際に臓器提供をするという意思を記入している者は49.3%(提供しないに記入2.9%)であることを考える(したがって、臓器移植の意思のある者の大半はその意思表示を提示していないことになる)と、その数は決して少なくない。しかし、たとえそうであっても、意思表示をしていないものの中に、積極的意思のものと消極的な意思のものとが混在している以上、臓器移植に対する何らかの形での積極的な意思表示が伝達されていない場合は臓器移植を慎重でなければならない。そのような慎重さを求める姿勢は、先の2006年内閣府世論調査の、36.7%という数字に反映されていると言えよう。
このような状況に対して、逆に本人の意思表示がない場合に、仮に家族の判断があっても臓器が提供できないとするならば、町野朔等によって指摘されているように[124]、かつての心臓死後の腎臓および角膜移植を家族の判断で認めてきたいわゆる角腎法との一貫性を欠く。この角腎法との一貫性にたち、かつ人間は見も知らない他人に対して善意を示す資質を持っている存在であるという前提に立って、町野等は意思表示のない脳死者からの臓器移植は可能であるという[125]。もちろん、臓器提供の意思のないその旨の意思表示がある場合は臓器提供が行なわれないことは当然のことである。結局、このような町野案は、消極的意思の積極的表明を求めるものである。平たくいうならば、嫌なら申し出ろということである。
しかしながら、先にも述べたように本来臓器提供は善意にもとづく積極的奉仕精神によるものである。そのような積極的精神に基づく行動は、本来積極的意思表明に求めるべきある。
すなわち、やりたい人は申し出てくださいということである。そうしなければ、それが積極的奉仕精神に基づき、社会的善であるという評価の元にあった、嫌なら申し出てくださいといわれても、嫌だといえない環境を産み出しかねない。さらに、いかに人間が他人に対して善意を示す資質を持っている存在であるとしても、その善意が必ず臓器提供という形で顕れるというのはいかにも短絡的である。したがって、意思表明が明らかでない場合は、かつての角腎法との一貫性は欠くが、原則として臓器提供を行なうことに対して慎重であるべきである。
しかし、家族の意思によって摘出が可能であった先の世論調査の48.1%に意思を汲むならば、脳死・心臓死に関わらず、現行法が求めるドナーカードによる本人の意思が明らかでない場合であっても、何らかの形で積極的意思が何らかの形で伝達されていたことが家族の証言等で明らかにされるならば、それに基づいた家族の集合的人格的における自己決定に委ねるという選択も視野に入れるべきであろう。
この場合、すでにのべたテリ・シャイボ事件のように家族間の証言に齟齬が起ることは充分に考えられる状況である。この点は充分に考慮されなければならない問題であり、現行法においても臓器提供は、最終的には家族の総意としての同意が必要となっている。また集合的人格的における自己決定に置いても、それは、集合的人格としての自己決定であるのだから、当然家族の同意は不可欠である。したがって、家族内で主張が異なる状況のもとで臓器の提供を行なうことは避けるべきであろう。
4-2.小児の臓器移植と自己決定の問題
わが国においては、臓器提供に対する積極的意思表示の方法としてドナーカードがあるが、15歳未満の意思表示は認められていない[126]。この15歳という年齢は、民法961条において、「15歳に達した者が遺言をすることができる」ところから、この遺言の意思表示できる年齢15歳が意思表示できる年齢の境目と考えられているからである。
これに対して、杉本建朗は日本が条約を批准している子どもの権利条約(1989年国連承認)の第12条[127](*128)を根拠に、次のようにいう。
権利条約は子どもの自由な意見表明や社会参加をうたったものである。その主な内容は表2の通りである。条約は憲法に次ぐ拘束力をもつ。今問われている子どもの脳死・臓器移植でもこの条約の精神を討論すべきである[128]」。
杉本がこのように述べるにあたっては、もう一つの根拠がある。それは、日本小児科学会の倫理委員会が発表したアンケートである。このアンケートにおいて、子どもの自己決定が可能な年齢について、6歳未満でも11%、6歳~9歳で11%、10~12歳が34%、13歳以上で38%という数字が出ている。
これは、小児医療にあたる現場の医師の判断であるが、その過半数は12歳以下でも、医療現場における自己決定ができると見ているのである[129]。このような根拠に立って杉本は、「親が子どもの終末医療の内容を決定することに、小児科診療を長年続けてきた管理的立場の医師の半数以上は、危機感や違和感をもっている。さらに、こどもは子どもなりに十分意見表明できることを認めている」[130]と述べ、森岡正博と共に6歳以上12歳以下の小児の意思決定を認めるようにと提案(以下杉本・森岡提案・A案)している[131]。
ところで、仮にこのように小児の事前の自己決定を認めるとして、小児が意思決定に対して、先行する情報それだけ正しく受け止められたのであろうか。これに関して、小児の例ではないが、高校を卒業したばかりの看護学生に、授業において通常与えられていない情報を提示し、学生たちの「脳死と臓器移植」に関する意識がどのように変化したかについての報告がある[132]。
それによると、移植のための手術の場面やドナーの担った息子の「死」を受け入れるために苦悩する母親の受容過程をビデオで見たり、日本における「脳死における臓器移植」の実態を説明し、授業の前と授業の後には変化があるという。授業前には臓器移植は「ただ良いもの」という肯定的イメージでとらえていたが、実際やマイナスの事象を知るにつれて、脳死を「人の死」として具体的な問題を考えなければならないというものに変化したというのだ。そして、このような変化は、学生たちが「脳死による臓器移植」について得てきた情報源が、新聞やテレビなどのメディアであり、その「脳死による臓器移植」関するメディアの報道が肯定的報道に偏っているからであるととらえている。
この報告は、このような学生の変化が見られることからメディアの提供する情報に対するメディア・リテラシーの必要性を述べるのだが、ここでは、メディアの報道が偏っているかどうかについて、あるいはメディア・リテラシーの問題について議論するものではない。しかし少なくとも、事前に得ている情報が「脳死による臓器移植」に対するイメージを形成しているとすれば、メディアの問題だけに限らず、脳死および臓器移植に関する情報全体に対するリテラシーの問題は重要な問題であることは間違いがない。
このような情報に関するリテラシーは、当然、年齢が低くなってくれば能力それ自体が劣ってくる。先の報告では、高校を卒業したがかり年齢の学生(18歳程度)でも、メディアが提供する情報に対して充分なリテラシーが発揮されていないとするならば、それが小児の場合には、より一層見られるであろうことは充分に推察されることである。したがって、年齢が低くなってくるほど、自分の外側に情報を咀嚼しそれを伝達してくれる存在の影響力が増すのは必然であろう。もちろんそれは、臓器移植に対する自己決定にも影響を与えてくる。そのような影響力を与える存在は、心的一体性あるいは親密性・信頼性のなかで起ってくるものであり、われわれはそのような存在として親もしくは家族の存在を考えることができる。また学校の等の影響もあるかもしれない。しかし、臓器移植に対する情報の識別には一定の価値観や宗教的死生観といったものが伴うものであるから、ここにおいて影響を与える存在として意識すべき存在は親もしくは家族の存在である。したがって、小児の臓器移植に関する自己決定を認めるとしても、杉本・森岡提案にあるように、本人の意思決定に影響を与える存在として「親権者の事前承認」を伴うような、現行の臓器移植法の15歳以上の者を対象とする規定よりもより厳格な規定をもって認める必要があるであろう。
このような、「親権者の事前承認」がある程度情報のリテラシーの問題を解決してくれると考えられるからである。もちろん、このような小児の事前の意思決定であっても、救急医療の現場においては、最終的に親権者の事前承認だけではなく他の家族の同意を必要とするのは、15歳以上の者と同じ手続きを踏まなければならないことはいうまでもないことであろう。
4-3.幼児、および知的障害者等の臓器移植と集合的人格的における自己決定
さて、小児に対する自己決定を認めるとして、自らの意思を的確な思考において判断し、有効な意思決定にもとづく決断ことが難しいと考えられる幼児、あるいは精神および知的障害もった者の場合はどう考えるべきであろうか。この場合、本人の積極的意思表示も消極的意思表示もうかがい知ることはできない。それゆえに、この場合においては、本人が積極的意思を持っていたとも消極的意思を持っていたともいうことはできないのである。つまり、そこには子どもの意思表示がないのである。先の杉本・森岡提案では6歳未満の子どもの臓器摘出に対して否定的見解が述べられているのは、一つにこのあたりの事情がある[133]。さらには、幼児脳死の場合、成人の脳死の場合と異なり長期脳死が起こりうるという事情もあるであろう。もっとも、長期脳死状態になったとしても、脳死状態から回復するわけではなく、この場合の問題は直接的には臓器移植ということではなく、この長期脳死の可能性を含んだ幼児の脳死の受容という問題になるが、脳死間臓器移植の場合、脳死が前提にあるのであるから、必然的にそれは幼児の臓器移植の問題に間接的に関与する。いずれにしても幼児の脳死はこの長期脳死という可能性を含んでいる以上、より綿密なインフォームド・コンセントが重要である。長期脳死の場合、その長期の期間の看護の労力や経済的負担を負うのは、主に家族だからである。これらは本質的には幼児の脳死に関する問題ではあるが、しかし、いずれにしてもこのような状況の中で、幼児の臓器移植の是非が問われるのである。
もちろん、この場合、家族によって脳死が人の死として受容されていることが前提条件にあることはいうまでもない。問題は、本人の明らかにされていない意思のもとで、第3者もしくは「他我一体」のもとでの家族による2人称による自己決定が可能であるかと言うことである。前者においては、これは当然否定されるべきであろう。そこには、自己決定の要素は見いだせないからである。では後者に置いてはどうであろうか。
既に述べたとおり、何らかの形で本人の臓器提供に対する積極的意思が伝達されていた場合、それにもとづく2人称の自己決定可能性については既に述べたとおりである。そこでは意思それ自体の有効性が認められている。しかしここでは、積極的意思も消極的意思の有効性も認めることができない。いわば白紙の状況での2人称の自己決定が問われているのである。
ところで、森岡・杉本案では、「子どもは親の意見に左右されから、子どもの意見は法的に信頼できないという意見がある。」と述べ、「もしその立場をとるならば、意思表示不可能な子どもの『法的脳死判定』を行なうことは不可能になり、したがって、臓器摘出も断念すべきである」と述べている。
森岡・杉本案では、「子どもは親の意見に左右されから、子どもの意見は法的に信頼できない」と考えているわけではない。むしろ、6歳以上の子どもは意思表示可能であると見ている。しかし、それでも、6歳以下の子どもについては意思表示が難しいと考えている。だが、だからといって6歳以下の子どもに意思がないわけではない。たしかに、その意思は親の意見に左右されやすい不安定な意思かもしれない。それゆえに問題は、その意思がどれだけ自律性に立脚した意思による自己決定であるかどうかにある。そういった意味では、低年齢の子どもになればなるほど「親の意見に左右される」傾向は強くなり、本人の自己決定とは考え難い面がある。そういった意味では、本人の自己決定に重きを置き6歳未満の「法的脳死判定」と「臓器摘出」に否定的立場をとる森岡・杉本案は、それなりの一貫性を持っているといえよう。
しかし、だからといって現実の医療現場に置いて6歳以下の幼児に対して、インフォームド・コンセントにもとづく治療や手術等の治療がなされていないわけではない。実際にインフォームド・コンセントに基づく治療は幼児にも、精神および知的障害を患っている患者に対しても行なわれているのである。この場合、治療に対する自己決定を幼児自身が行なっているわけではなく、実際は親がその幼児に代わって代理決定を行なっている。このように、治療の場においてはすでに親の代理権が受容されている。だとすれば臓器提供に対する親の代理権も認められるということは考えられないだろうか。このような親の代理権に対して、町野朔は法学者の立場から次のように述べる。
親権者に、その子の意思決定の代行としてではなく、子が生きているときに、その死後のその臓器移植のために提供する意思表示を行なう固有の権限を認めることも困難である。それは民法(820条)の認める「子の監護および教育」という親の権利・義務には含まれない[134]。
たしかに、治療の現場において受容されている親の代理権は、子どもの健康の回復を求めての代理権であり、その意味に置いて子の監護にあたり、親の権利であるといえよう。それに対して、法定脳死判定および臓器移植は、子どもの健康の回復を求める監護にはあてはまらない。したがって、子の監護にもとづく親の権利として臓器移植の代理権を主張することは町野の言うごとく難しいであろう。それに対して、法的脳死判定に対する代理権は、臓器移植の代理権とは異なる。法的脳死判定は、患者がいわゆる脳死状態であるかどうかの判定であり、脳死と判定されるならば、それは不可逆的な死の過程にあることが確認されるのであり、脳死ではないと判定されるならば、当然、治療は継続される。
したがって、脳死と判定されない限り、法的脳死鑑定の結果は(患者に負担を与えるものではあるが)親の監護の権利を保障するものとなり、その後の治療を求める根拠となる。もちろん脳死であると判定された場合は、それは不可逆的な死の過程にあるのであるから、その死の過程において、いつ死を受容するかの問題であり、それはまさに家族の決定によるものとなる。
それでは、臓器移植における親の代理権は全く認められる余地はないのだろうか。町野は、民法(820条)における親の権利と義務は「監護と教育」であるという。この場合、監護という側面から臓器移植にける代理権が認めがたいことはすでに見てきたとおりである。それに対して教育という側面から考えてみてはどうだろうか。
ここまで、臓器移植における自己決定ということからその可能性を見てきた。もちろん、それゆえに、自らの主体的意思を決定しがたい幼児、あるいは精神障害の患者の臓器移植が問題となったのである。しかしながら、幼児の場合、成長と共に意思決定を行なう存在となっていく、その成長過程で、ある程度有効な意思決定とみなして良いと考えられる年齢は、現行法では15歳でありもっとも低い年齢では杉本・森本案における6歳以上であった。
言うまでもないことだが、仮に、臓器提供可能な年齢を最も低い森岡・杉本案においたとしてもこの6歳に至るまでも子どもは成長している。この成長の間も当然、親は教育の義務と権利を持つ。それゆえに、森岡・杉本案において「子どもは親の意見に左右されから、子どもの意見は法的に信頼できないという意見がある」と述べられるような事態が想定されるのである。逆に言うならば、6歳までの子どもは親の教育のもとで意思を形成していくと考えられる。特に、死生観をともなう宗教的な事柄や奉仕の精神に関わる倫理的な信念はその傾向が強いと思われる。そういった意味では人間の自由な意思の決断は、ヘッシェルの言うようにその背後にある社会環境の影響下に無言のうちに拘束されるといえる。その社会環境としてもっとも身近に、しかも密接にあるのが家族であり、親であるといえよう。したがって、死生観をともなう宗教的な事柄や奉仕の精神に関わる倫理的な信念に関する事柄は親の判断と子どもの意思は不可分に結びついて一致する方向へと向うと考えられる。だとすれば、親の意思を子どもの意思とみなす意思の推定が可能となり、推定された意思ではあるが幼児の自己決定にもとづく臓器移植は可能であると考えられないであろうか。
もちろん、子どもの意思は子どもの成長と共に必ずしも一致しなくなる。それゆえに森岡・杉本案でいわれるように、子どもの意思が尊重される段階に移行しなければならないし、成人の自己決定に移行していかなければならない。その年齢については、議論がされなければならないだろう[135]。
このような意思が尊重されるべき年齢に至らない子どもに対して親の承諾の元で臓器移植を認める場合、その背後には親は子どもに対し最善を尽くし、保護し最も良いと考える選択をするということが了解事項として前提にある。それゆえに、宗教的、倫理的信念は、それが子どもの生、生き様そして死にざまに最も良いと信じるがゆえにそのように教育をするのである。もちろん、この場合の宗教的倫理的信念は、社会的通念や、医学的見知を超えてものではないことは当然の前提である。如何に親の宗教的、倫理的信念があったとしても、社会通念上の死の理解、および医学的見知を超えて、生の可能性を子どもから奪って良いものではない。親が、子どもに対して最善を尽くして保護するというのは、この脳死は、人の死として不可逆的な過程に入っているという社会的理解と、医学的見知という了解のもとにあってである。
いずれにしても、もし親が子どもに対して最善を尽くし、保護し最も良いものを選択し与えようとしないならば、親の承諾のもとでの幼児の臓器移植の前提は崩れるが、一般的に考えるならば、親は子どもに最善のものを与えようとする存在であると考えるのが妥当である。
もちろん、幼児虐待などの事例が全くないわけではない。森岡・杉本案において、幼児虐待による脳死が対象から外されているも、このゆえであろう。いずれにしても、このような幼児に関する臓器提供の意思決定については、森岡・杉本案が指摘するように幼児虐待等の問題も考慮に入れなければならない。というのも、脳死が起る原因として、脳出血、脳挫傷等の一時性粗大病変によるものがあげられるからである[136]。つまり、幼児虐待などに起因する脳死がありうるのである[137]。
だとすれば、幼児(15歳以下の小児を含んで)虐待に至る親に、子親の権利と義務としての「監護と教育」を見ることはできない。だとすれば、臓器移植が脳死という自らの死生観に関わる問題を含み、さらに善意にもとづく積極的奉仕精神によるものであることを考えるときに、この死生観や善意にもとづく積極的奉仕精神を養う死生観をともなう宗教的な事柄や奉仕の精神に関わる倫理的な信念の教育を幼児虐待に至る親に期待することができないと考えられる。むしろ、そこには、脳死に対する親の承認が認められる前提である親が子どもに対して最善を尽くし、保護し最も良いものを選択し与えようとする善意の精神の欠落が認められるのである。したがって、このような、幼児虐待の可能性が認められる場合は、幼児の臓器移植は認めるべきではない。
ところで、ここまで述べたことは、幼児に関する問題であり、親の教育という視点からみたものであるが、精神および知的障害を負った方々に対してはどうであろうか。精神及び知的障害を負った方々については障害の程度等で非常に多様であるので単純に一括りにするのはかなり無理があり、少々危険ではある。しかしあえて一般化するならば、精神障害、および知的障害によって健常者と同じような判断プロセスが出来ないとするならば、たとえ家族が教育によって宗教的死生観や倫理観念が、影響を与えていたとしても、それが成長の過程で正常な状況の中で理解され受け止められていくとは言い難い面もあると考えられる[138]。したがって、臓器提供者となる対象からは外して考えた方が良いだろう。
5.誰のための脳死・臓器移植論議か。
以上見てきたように、脳死・臓器移植の問題の鍵は自己決定というところにあるといえよう。その際、日本の社会状況を鑑みるとき、それは個人の自己決定と言うことに留まらず、家族という集合的人格における自己決定といったところにまで広げて考えなければならない。
しかし、脳死及び臓器移植については、依然としてわが国では賛否両論がある。またわが国だけでなく脳死を受容していたアメリカやドイツでも脳死に関しても、一部には従来とは異なる見方もあるのも事実である。たとえば、ドイツにおいて1990年代半ばから、一部で脳死は死につつある状態ではあるがまだ生きている人であると考えなければならないという見方が出てきている[139]。
これらは、既に述べたように人の死が医学的には点的に捉えられるものではなく線的プロセスによりものだからである。しかし、考えてみるならば人は生まれたときから死ぬことが定まっている存在である。これに運命という言葉を用いるならば、人は死すべき運命にあると言うことができよう。このような運命的な生から死に至るまでの過程において、人間は(社会や環境の影響下にあるとしても)意意思的存在であり、自己決定的に生きる決断的存在なのである。それゆえに、人間は自己の死の過程においても自己決定的に死の受容がなされるべきであろう。人間は生物学的存在であると同時に、自らの生を意識し、それを探求する精神的存在だからである。
もっとも、このようにいうと、人間が死すべき運命にある以上、人間は生まれたときから必然的に死の過程にあるのであって、その死すべき運命における自己決定権を認めるならば、倉持武が危惧するように原則としては、「姥捨山という慣習や、逆にライフ・スペースのミイラについても、それを承認せざる得なくなる」[140]という事態も原理上はありえることとなる。
しかしそれは極論であり、そのような極論に陥らないためにも、脳死という医療上の特殊な事態が起る現実の中で、脳死から心臓死に至るまでの不可逆的過程を死の線的過程とした枠組みがもとめられるのである。それは、医療の現場における意識の回復と延命治療の効果が期待できない特殊な状況下での「わたしの死」という一人称の死と「あなたの死」というプライベート関係の中での宣言する死と「彼の死」という三人称の死がもつ社会的生の中で宣告される死を包括するものである。そこには関係的存在としての人間が見据えられている。
しかしながら、我々が脳死について議論する場合、最終的に行着くところは「誰のための脳死議論なのか」ということであろう。実際に、脳死の問題は脳死患者および、その家族となった当事者にとって重要な問題であり、仮に第三者が賛否を主張したところで、第三者はそれによって直接、負うべき責任も負担もない。また負いもしない。あくまでも直接的責任と負担を負うのは本人であり家族なのである。確かに、第三者にも脳死・臓器移植の是非に関する議論は議論として可能であろう。またそれに対する意見は述べられなければならない。しかし、脳死という特殊な状況下においては、脳死が、死の不可逆的過程にある限り、最終的にはその当事者たる本人と、その家族の決定を尊重されるべきであろう。
したがって脳死・臓器移植に対する議論は、そのような決定をなす当事者にとっての決定要因のひとつ、あるいは状況に対するリテラシーとしてのみ意味をなすものであって、決して当事者の自己決定に優先するものであってはならないし、また優先しない。脳死肯定論者によって死の受容が強制的に早められてはならないし、脳死否定論者によって死の受容を拒否されてもならないのである。
その意味では、1997年制定の臓器移植法における脳死の取り扱いは、個人の自己決定、および家族の意思が尊重されている点で一定の評価は出来る。しかし、1997年法[141](*142)は、その自己決定が臓器移植との関連する場合においてのみ認められるのであって、脳死そのものを問うているものでないところに不備がある。脳死間移植は、それに先行する脳死という問題があっても次の段階の問題である。それゆえに、脳死の問題に対して臓器移植を前提におくのは正しくはない。脳死は脳死として独立して取り扱うべきであり、それがあって、初めて次の臓器移植の問題が問われるべきなのである。
そこで、臓器移植の問題であるが、臓器移植に関しては、かつての死亡腎移植、死亡角膜移植が社会的にも受け入れられていた背景を考えれば、移植医療それ自体が問題というのではなく、脳死間移植が問題とされていることは明らかであり、問題の中心は脳死にあるといえる。したがって、臓器移植に関しても、その当事者たる本人とその家族の自己決定が尊重されなければならないであろう。
もちろん、判断を下す際に意思決定者が冷静に判断できるかどうかが問われるところである。特に、脳死は救急医療の場で起る。それゆえに家族の気が動転している場面は想像に難くない。そこで正しい判断ができるかどうかには問題が残ると言わざるを得ない。しかし、それでも決断をし決定することが家族に求められているのである。それだけに、決断のための、事前の脳死・および臓器移植に関する知識や理解が必要であるし、より適切なインフォームド・コンセント重要である。
しかし、いかに脳死および臓器移植に関するリテラシーが高められ、より正確なインフォームド・コンセントがなされたとしても、自己決定をする当事者、特に家族という集合的人格的決定に参与しつつ、死に行く本人にとは違い残された家族に対する責任と負担はやはり大きくのしかかるであろう。また、その決断・決定が残された家族に残す痕跡も決して小さくはないと思われる。ここに、家族が意思決定に際し、また意志決定した後に家族をどのように支え支援するかという問題が起る。そこにはカウンセリングによるケアの問題等もあるであろう。そして、仮にそれが教会に関係する者であるとするならば、そこで牧会者がとる態度があたえる影響は少なくはない。むしろ大きいと言っていいだろう。脳死問題に対する牧会の神学が求められるのは、まさにこのような場面においてなのである。
[1] 法律第104号「臓器の移植に関する法律」官報2181号 1997年 (以下臓器移植法)
[2] 船尾忠孝「脳死をめぐる諸問題」北里大学 NO.20 1990年 pp293-294 なお、引用文中の1986年脳波学会の提案というのは、1968年の脳波学会「脳死と脳波に関する委員会」の見解、「脳死とは回復不可能な脳機能の喪失。大脳半球だけでなく、脳幹部分も含む。ただし脊髄反射の喪失は必須条件ではない。」であると思われる。また、1973年の国際脳波学会では「脳死とは大脳・小脳・脳幹・第一頸髄まで含めた全脳髄機能の不可逆的停止状態」と定義している。
[3] 錫谷徹 元北海道大学医学部教授(法医学)
[4] 早稲田大学刑事法学研究会「死の概念と脳死説」早稲田法学61巻(2号) 早稲田大学法学会 〔編〕 1986年pp179-180
[5] 同上書、p180
[6] 尾形誠宏「脳死と臓器移植」神戸市立看護短期大学紀要第11号 1992年 pp118-119
[7] 同上書 p119
[8] Shewmon.D.A:Chrinic ’Brain Death’,Meta-analysis and conceptual consequence,Neurology No.51,December 1988 pp1538-1545 邦訳では、小松真理子訳で、「科学」vol.78 岩波書店 2008年8月号「長期に渡る『脳死』―メタ分析と概念的な帰結」として、pp885-905に訳者の解説付きで掲載されている。
[9] このシューモンの報告は、邦書では、小松美彦「脳死・臓器移植の本当の話」PHP新書299 PHP研修所 2007年pp109-112にもある。そこでは、175人の「脳死患者」の心臓がすくなくとも1週間は動き続けていたことが判明した。そして、そのうち80人が少なくとも、2週間、44人が少なくとも4週間、20人が少なくとも2ヶ月、7人が少なくとも6ヶ月、4人が少なくとも1年以上のあいだ心臓が脈動し続けた。1年以上の中には2.7年と5.1年が一人づつおり、最長のケースは何と14.5年だったのである。」となっている。また同書116-125には、この報告にある結果にもとづいてなされたシューモンの脳が有機的統合体を統合する(中心的支配的である)存在であることの批判に対する小松による説明が記されている。
[10] 井形昭弘「脳死について( 平成五年度教養部特別講義平成五年十二月九日札幌大学講堂 (<特集>(1)世界への目)」ルベラル・アーツ:札幌大学教養学部教育研究No10 北海道大学1994年 pp63-64。
[11] 同上書 p64
[12] rf. Shewmon,Chrinic ’Brain Death’,Meta-analysis and conceptual consequence,NO.51.,p1544. 邦訳「科学」vol.78 896参照
[13] 小松「脳死・臓器移植の本当の話」p115
[14] 船尾「脳死をめぐる諸問題」p296
[15] Mollsret,P,et Goulon, M;Le coma Depasse Revue Neurel,101,1959 pp3-15
[16] 船尾「脳死をめぐる諸問題」p296
[17] 小松「脳死・臓器移植の本当の話」p93
[18] 同上書 pp93-94
[19] 小松「脳死・臓器移植の本当の話」pp100-102,そこには、浦崎永一郎による社会保険下関病院と産業医科大の事例、
また野倉一也による藤田保健衛生大学の事例が出ている。
[20] 森岡正博「日本の『脳死』法は世界の最先端」中央公論 2001年2月号 pp.318-327参照。
[21]丸屋淳 ・ 高堂 裕平 ・ 高野 裕一 「長期間にわたり脊髄反射および脊髄自動運動が認められた臨床的脳死患者の一例(ビデオセッション(2)脳卒中,ビデオセッション,一般演題,リハビリテーション医学の進歩と実践,第43回日本リハビリテーション医学会学術集会)」リハビリテーション医学 : 日本リハビリテーション医学会誌Vol.43 2006年 p307 参照
[22] 浦崎永一郎「意識障害」臨床看護vol.31 No.2(通号421)、臨時増刊号、2005年、へるす出版、p.772
[23] 丸屋 淳 ・ 高堂 裕平 ・ 高野 裕一 「長期間にわたり脊髄反射および脊髄自動運動が認められた臨床的脳死患者の一例」 p307
[24] 同上
[25] 浦崎永一郎「意識障害」臨床看護vol.31 No.2(通号421)、臨時増刊号、2005年、へるす出版、p.772
[26] 斎藤誠二「脳死・臓器移植の議論の展開-医事刑法からのアプローチ」多賀出版 2000年p132には、ドイツにおけるラザロ徴候の説明が載せられているが、そこにはこうある。「能には背髄(筆者註:脊髄)にまで通じている抑制的なノイロン(筆者註:ニューロン<神経細胞>のこと)と活性的ノイロンがある。脳の機能がとまると、活性的ノイロンばかりでなくて、抑制的なノイロンも、その働きをやめる。背髄への抑制的なノイロンの影響がなくなると「型にはまった(定型的な)背髄反射の『脱抑制』の状態」(eine Enthemmung<Spinaler Reflexschablonen)が生じる。(それで、こういうラザロ徴候のような現象が見られるわけである。)こういう反応は、なにも患者が脳死になった特ばかりに見られるわけではない。こういう反応は①人工呼吸取り外されたあとでも、また、②ときには心臓死(Herztod)の場合にもみられることである。この二つの場合には、背髄ノイロンを刺激することのできる突然の酸素の欠乏が生じるからである。」 ここでは臨床的判断の根拠となる説明ではあるが、ラザロ徴候発生のシステムの説明がなされている。しかし、それは現象の説明であって、本文でも述べたように、我が国の議論では、2006年時点でラザロ徴候が脊髄反射であることに、脊髄由来のものであると思いつつも、しかし慎重な態度を示す者もいる。したがって、本小論は最終的に日本を場として牧会的視点から脳死・臓器移植の問題に対する神学的検討をするという性質から、あえてドイツでの説明は欄外註におくことにした。
[27] 倉持武「脳死移植再考」松本医科大紀要Vol.32 松本医科大学 2005年 p38
[28]この生田の報告は、立花隆「脳死臨調批判」中公文庫 中央公論社 1997年173-176等の幾つかの書籍、論文に引用されているが、その大元となる論文、生田房弘・武田茂樹「『脳死』の神経病理学」神経研究の進歩Vol.36 No.2 1992年 pp322-344 は国会図書館を始めとして、所有する図書館等を見つけられなかった。そのため、今回は一次資料としては確認できず、孫引きとなった。
[29] 立花隆「脳死臨調批判」文庫版 p178
[30] 同上書 pp196-199
[31] 奥井浩一「我が国における脳死・臓器移植の現在とその新たなる法改正案の問題点」札幌大学人文学会紀要、第78号、札幌学院大学、2005年、p.120
[32] 渡部良平監修「異議あり!脳死・臓器移植」、天声社、1999年、pp.91-92
[33] 尾形「脳死と臓器移植」p120
[34] このように、脳死が蘇生限界点を超えた不可逆的な死の始まりだとしても、既に述べたとおり、現在は心停止に至るまで長期に至るケースが出てきた。その意味では、脳死から心臓死に至までの道のりは、長い道のり場合もあり、短い道のりである場合も出てきた。しかし、それが不可逆的なものであることに代わりはない。
[35] 立花「脳死臨調批判」文庫版p197
[36] 同上書 p198
[37] 脳循環検査は、主だった国のなかでは、スェーデンのみが脳死の必須条項としているだけで、それ以外の多くの国では必要項目ではなく、わずかに日本と米国内の一部が参考検査項目としているのみである。現在の我が国の脳死判定において脳循環検査は、臨時脳死及び臓器移植調査会「脳死および臓器移植に関する重要事項について(答申)」1992年(いわゆる脳死臨調最終答申、本小論でも以下脳死臨調答申と称する)の(Ⅰ-3-(3)の条項)で、必須検査ではないが補助検査項目として、実施が可能なものは行なうことが有意義であるとして行なうことが奨められている。
[38] 聴性脳幹反応検査も、上記脳死臨調答申では補助検査項目になっている。
[39] 立花隆「脳死再論」1988年 中央公論社 pp137-140参照
[40] 倉持武「脳死移植と倫理学」松本歯科大学紀要 松本歯科大学Vol.33 2005年 pp14-16 参照
[41] 同上書 p23。また、pp17-18には、国立台湾大学医学部院名誉教授の洪祖培氏の言葉を借りて上部脳幹反応検査についての批判を、またp21-22においては平坦脳波検査には欠陥があると批判している。なお、意識の不可逆的に消失していると言うことができないということについては、先に若干触れた視床下部による低次の意識の問題に類すると思われる。ただし、倉持の場合はその低次の意識ではなく、自我意識という高次の意識までも問題にする。自我を伴う高次の意識は、大脳新皮質、とくに前頭連合野がかかわる。この大脳新皮質は脳幹綱様体賦活系によってその覚醒が維持されるが、倉持は、視床下部が体性感覚をこの大脳皮質に伝える機能がるあることから、フェルドマン、ワラーの説にたって、高次の意識を司る大脳新皮質の覚醒を維持する働きへと結び付けて考える。
[42] 奥谷浩一「我が国における脳死・臓器移植の現在とその新たな法改正案の問題点」札幌学院大学人文学会紀要Vol.78 札幌学院大学p133
[43] 鈴木秀郎・伊藤幸郎「脳死に関する考察」産業医大誌 Vol.8 No.2 産業医科大学 1986年 p273
[44] 日本医師会生命倫理懇談会「脳死および臓器職についての最終報告」1988年の付属資料3より、なお、本小論では、上記文書を立花隆「脳死再論」中央公論社 1988年 pp297-336から引用した。その中で伊東の発言はpp330-332
[45] 小松「脳死・臓器移植の本当の話」pp107
[46] 脳死臨調最終答申2-(2)
[47] 池田清彦「脳死臓器移植は正しいか」角川ソフィア文庫 角川書店 2006年 pp40-41
[48] たとえば遺産相続や医療保険金の支払い、脳死に至らせた原因となる人物の刑罰の問題、また死を宣告する医者の保護など。
[49] 前田和彦「脳死における法の認識」日本法政学会法政論叢 日本法政学会 1988年 p69
[50] 梅原猛編「『脳死』と臓器移植」朝日新聞社 1992年 p214
[51] マーガレット・ロック「脳死と臓器移植の医療人類学」坂川雅子訳 みすず書房 2004年 p154
[52] NCC宗教研究所編「脳死・臓器移植と日本の宗教者 ーアメリカの宗教学者の提言をうけてー」ムガール社 1997年
[53] 小原克博「脳死・臓器移植をめぐる日本のキリスト教界の動向――欧米および日本の宗教界との比較の中で」:「宗教と社会」学会、「日本社会とキリスト教」プロジェクト 研究会 2000年7月 口頭発表。
[54] 曹洞宗については、曹洞宗宗務庁「脳死と臓器移植」問題に対する答申書や駒沢大学仏教経済研究所の岩井貴生の論文「仏教者から見た脳死判定と臓器職の問題」駒沢大学仏教経済研究所 2007年等を参照、真言宗については、東洋大学名誉教授で真言宗妙薬寺住職の金岡秀友が、吉田恵子編「脳死 私はこう思う」北窓出版 1990年に掲載された主張や智山派勝覚寺発行の「四天尊たより」1999年12号(通)、密教ホーラム21の動向などを参考にした。なお真言宗では臓器移植については「菩薩行」として布施行としてとらえ認める可能性はあるが、菩薩行の要件を満たしていないという主張もある。
[55] 日本ルーテル神学大学教職セミナー編「いのちを深く考える-医療と宗教から見た死生観(下巻)」キリスト新聞社 1990年 p124 同書収録藤井正雄講演「仏教から見た脳死・臓器移植」より、
[56] 井澤正裕「脳死における諸問題-神道の対応をめぐって」『神道と生命倫理』、神道文化会、弘文堂、2008年、p.198
[57] 小林威朗「神道の生命倫理 -臓器移植をめぐって」神道と生命倫理 pp7-27 参照
[58] 須藤正親・池田良彦・高月義照「なぜ日本では臓器移植がむつかしいのか」東海大学出版会 1999年 pp214-229 参照。また、これとは別に有馬善一「脳死と臓器移植についてわれわれは何をとうべきか」経営情報研究Vol.15 No.2 摂南大学2007年 pp163-178のp165の欄外注記2にて、朝日新聞の脳死世論調査の推移について述べているが、それによると、97年5月の調査では脳死を認めるが40%で、脳死を認めないで心臓死だけに限るべきだとするものが48%となっており、こちらでは認めないという人の方が上回っている。ただし、有馬は84年当時は、脳死を人の死として認めるものが30%ほどであり、一概に人の死といえないものが50%であったことも告げている。さらには、99年の調査では、脳死を人の死と認めるが52%、認めないで心臓死に限るが30%となっているという。
このようにみると、84年-97年-99年と推移していく中で、臓器移植法成立前後が、脳死を人の死と認めるか認めないかが97年の「臓器移植法」を境に逆転したものと思われる。先の高月と有馬のあげた資料の差は、まさに97年が脳死に関する認識の交差点であったことを示すものであろう。なお、有馬は、さらにP166で2005年7月2日付けの読売新聞をあげているが、それによると、2005年は、脳死を認めるが59%となっているという。これらの資料をみるかぎり、数字の上では日本においても脳死は受容されつつある傾向にあるといえよう。なお、脳死臨調最終答申のⅣの脳死を認めない少数意見の3の項目で、「91年11月の読売新聞の世論調査において『脳死』を死と認める人が前年の50%から46%に減り、認めない人が23%から26%へと3%増えた。『脳死』を死と認めるひとが半分にも達していないのに社会的合意が達成されたというのはあまりにも暴論である。しかも死と認める人がかえって前よりも減っているのである。」とあるが、これは、90年から91年の推移というミクロ視点での話で、マクロ的には脳死臨調少数派の主張する流れとは逆の流れであったということであろう。
[59] 須藤・池田・高月「なぜ日本では臓器移植がむつかしいのか」、p217
[60] 若い世代の死に関する意識について参考となる資料として、月田佳寿美・池田歩未・藤井和代「看護学生の死生観に影響する要因と脳死の捉え方」福井大学医学部研究雑誌Vol.7 No.1,2合併号 2006年 pp7-13がある。これによると、自分の死についての考えに影響を与えているものとして、もっとも影響与えたものとして考えられるものが、「身近な人の死の体験」であった。この調査結果には、身近な人の死という二人称の死を通して自らの死という一人称の死を考えている実体がよく表わされている。この調査では、同時に脳死についての調査も行なっているが、その際、脳死を人の死として容認できないと答えた人の中で、要因できないと答えた理由の主なものは、「人間としての関係性や尊厳性」と「心臓が動いていて体が温かい」というもので、ここでも二人称的なところで脳死をとらえていることがうかがえる。(ちなみに脳死判定に疑問という、医学的見知からの反対は、33名中1名だけであり、5名は脳死を植物状態と勘違いしての反対であった。)特筆すべきことは、看護大学生という医療現場に近い若者であっても、全体の57%が、脳死について人の死と考えるかどうかについて分からないと答えている点である。この結果は他の先行研究と同じ結果であるというが、分からないと答えた理由は、知識不足や関心の低さではない。むしろ分からないと答えた者たちの言葉を見ると、彼らは「多くは立場や関係によって考えが変わり、生とも死とも答えが出せない複雑な問題であることが分かった。」というのである。つまり研究結果として「脳死に対する態度を考えるとき、対象者は脳死を科学的な次元で知的に捉える一方、医療者や家族、また自分自身といった様々な立場に置き換え、他者とのつながりや関係の中で脳死を捉えていることが分かる。」という状況を認めることができるのである。だからこそ「先行研究では、脳死下での臓器提供を考える時、自分が脳死になった場合の臓器の提供には積極的であるが、家族の場合には消極的になる」とも言うのである。これは、看護大学生という極めて特殊な環境の人たちに対する研究であるが、そのような医療の現場にいるものでも、二人称の死でみるならば、脳死に対して躊躇を感じるという実例である。しかし、死に対する影響をどこから受けたかについては、普通の若者も看護学生も条件は同じである。その中で看護大学生という医療に近い現場にいるものですら、二人称の死に対しては躊躇を感じるならば、ごく普通の若者が、死に対する影響を受けた身近なものの死の経験から脳死を二人称の死をもとで考える可能性は充分にあるといえよう。
[61] 鈴木・伊東「脳死に関する考察」 p273
[62] 岡田麗江「生命(いのち)への対応の傾向について考える」大阪府立看護大学医療技術短期大学部紀要 Vol.9 大阪府立看護大学 2003年 p91
[63] 脳死臨調最終答申の少数派の意見もどちらかといえばこの立場である。
[64] ただし、尊厳死に関しては、脳死に反対するものが、必ず反対するとは言い切れない。というのも、脳死を人の死として認めるという問題と尊厳死とは厳密な意味においては異なる問題だからである。したがって、傾向としては認めない傾向にあるということ、あるいは論理上は認められないということである。たとえば、それは違法阻却措置等の問題に等に表れてくる。また我が国の臓器移植法も、形としてはこの違法的阻却処置であるといえる。
[65] この場合、脳死状態での尊厳死とは、脳死状態における人工呼吸器のswich offを意味する。
[66] エホバの証人などがこの立場にある。ただし、エホバの証人などは、社会情勢によってその立場やその主張の内容を変えるので、これは2008年時点での立場である。
[67] 脳死・臓器移植を考える会委員会編「愛ですか?臓器移植」社会評論社 1999年 pp160-186には、マーガレット・ロック(比較人類学者)・唐澤弘七郎(東京女子医大名誉教授)・藤田良夫・阿部知子(小児科医)の対談があるが、そのp170において、唐澤は生体移植が傷害罪にあたる可能性を示唆し、欄外中にて、そのあたりの問題性について編者による説明がなされている。なお、唐澤の立場は、心臓死からの移植は認めるという立場であることを同書にて述べている。
[68] 1989年、島根医大で行なわれた父から子(1歳)への生体肝移植手術。術後半年で患者死亡。
[69] 先の欄外注でも述べたように、脳死・臓器移植を考える会委員会編「愛ですか?臓器移植」(社会評論社; 増補改訂版 、1999年において、唐澤は心臓死移植に対しては遺体損壊罪が、生体移植に対しては傷害罪が問われる可能性があると述べている。もっとも、現在の日本では、心臓死移植にしても生体移植についても法的には認められており、社会的制約がかかっているわけではない。
[70] 大阪千里救命救急センターにおける九州大の心臓死直後の肝臓摘出に関する疑惑等がこれにあたる。
[71] 脳死・臓器移植を考える会委員会編「愛ですか?臓器移植」社会評論社; 増補改訂版 、1999年、pp136
[72] 同上書 pp137-138
[73] 脳死・臓器移植を考える会委員会編「愛ですか?臓器移植」、pp136
[74] 同上書 p138
[75] 脳死・臓器移植を考える会委員会編「愛ですか?臓器移植」 pp143-144
[76] 工藤直志「海外から見た日本の脳死・臓器移植 -近年の雑誌論文の検討を通して-」医療・生命と論理 No.6 大阪大学医学系研究家・医の倫理教室 2007年 pp57-65
[77] 同上書p61参照。なお、Crowley-MatokaとM.Lockの原文はCrowley-Matoka,Megan and Margaret Lock,2006,“Organ Trnsplantation in a globalised world,“Mortality,11(2):pp166-181
[78] 工藤直志「海外から見た日本の脳死・臓器移植」 p59 参照。なおLafleurの原文は、Lafleur Willam R.,2002“From
Agape to Organ:Religious Difference Between Japan and America in Judging the Ethics of the Transplant“Ziyon,
37(3):pp623-642
[79] 同上の工藤の論文では、Bagheri Alirezaがその論文”Criticism of ‘Brain Death’ Policy in Japan” Kennedy Institute of Ehics Journal,13(4):356-372,で日本の臓器移植法において個人の想起提供意思があっても、家族の同意がなければ、本人の意思であっても覆されることを示し、家族の意思が個人の意思に優先されることを述べている。しかし、同時に、個人の臓器提供の意思がない場合、家族が臓器を提供することを望んでも、臓器提供が出来ないことも示し、その2重性を批判とし「矛盾している」と述べている。
[80] 池口豪泉・石津日出雄「“死に関する日本人の意識の特質:臓器移植に関して」医と生物学 Vol.151、No.2 緒方医学科学研究所医学生物学速報会 2007年の自由記述には、自分の臓器を提供することにも、また自分がレシピエントの立場になったら、臓器提供を望むが、ドナーになるのは嫌だという意見も少なくはない。また、自分の身内に対してドナーとなることは出来るが、第三者のためのドナーになるのには抵抗があるという意見もある。いずれにしても、このアンケートの自由記述には、家族との強い絆を感じさせる記述が非常に多い。
[81] この主張は脳死臨調最終答申Ⅳの少数派の意見4においても脳死に摘要されて述べられている。
[82] 須藤・池田・高月「なぜ日本では臓器移植がむつかしいのか」 p200
[83] 小林威朗は、「臓器が神であるということではない。神との血縁によりもたらされた臓器というものを所有し、その処分を自分自身で決めるというのは、神道的ではないということである。むしろ神道的に考えたならば、それは人間の驕りである。…<中略>…以上のことより、臓器移植の不自然さを神道的に表現すると、神との血縁によってもたらされた霊魂の宿る臓器を、人間が所有し処分するという驕りであるといえよう」(「神道の生命倫理」 pp19-20)という。また藤井正雄は「生きる、死ぬということは一如(筆者註:生死一如)で、肉体と心を一体として捉えたところから臓器移植ということは仏教の教義からは生まれてこないというふうに唱える人もかなりいるわけです」といっている。(藤井正雄「仏教から見た脳死・臓器移植」いのちを深く考える-医療と宗教から見た死生観(下巻)キリスト新聞社 1990年 p116
[84] 法隆寺の「玉虫厨子」にある飢えた虎の親子に、自分を食べさせるために、釈迦の前世であった薩タ王子が、虎のいる谷に飛び込んだ話(出典は金光明経第26章:捨身品)等々、金岡秀友は「これらの行為は「捨身」といわれ、精神は「不惜身命」と名付けられ、仏教において、もっとも崇高なる行為・精神として取り上げられてきた。…<中略>…最高の布施は自分自身なのであった」(「脳死 -私はこう思う」)
[85] 木村文輝「臓器移植問題に対する仏教者の立脚点」禅研究所紀要、愛知学院大学 Vol.130 、2002年、p140-144参照。また真言宗豊山派・南蔵院住職・種智院大学助教授 野口 圭也なども同様の主張を展開する
[86] 小林威朗「神道の生命倫理」 pp19-20 参照
[87] 井澤正裕「脳死における諸問題」 pp199-200参照。
[88] 藤井正雄は、脳死や臓器移植の問題は、仏教的な教義から解かれるのではなく、日本人の死生観は仏教と民俗信仰と集合して初めて出てくるものだという(藤井正雄「仏教から見た脳死・臓器移植」p128参照)この場合、藤井のいう民俗宗教の核をなすのは神道思想といってよいだろう。
[89] 池口・石津「“死に関する日本人の意識の特質」p297
[90] 池口豪泉・石津日出雄「“死に関する米国人の意識の特質:臓器移植に関して」医と生物学 Vol.150 No.8 緒方医学科学研究所医学生物学速報会 2006年、pp294-295
[91] M・ロック「脳死と臓器移植の医療人類学」、p159。参照
[92] 波平恵美子「脳死・臓器移植・がん告知」福武文庫、福武書店、1990年、pp.20-52、参照
[93] 内閣府調べ「臓器移植に関する世論調査」2007年1月
[94] A・J・ヘッシェル「人間を捜し求める神」森泉弘次訳、教文館、1998年、p.500
[95] 池田清彦「脳死移植は正しいか」
[96] この法のもとでというとき、当然のことながら国家間で、異なってくる。たとえば、山口龍之(「人体の処分性についての『法と経済学』的一考察」沖縄大学法経学部紀要創刊号 沖縄大学 2001年 p71によると、フランスには自殺関与罪に罰則規定はないという。また、筆者が先に示したようにフィリピンでは臓器売買についても罰則規定はないといった事情もある。さらに山口は、同書でフランスの身体の処分性(不可侵性)の概念を述べると共に、「人の生命は個人の法益ではあるが、社会・国家の存続基盤となる法益として最高の価値を有するものであるから、法益の主体といえども生命を勝手に処分することは、法律上許されるものではない」という意見を紹介し、個人の所有の身体であっても、個人が自由にそれを処分することができないとする法哲学があることを紹介している。
[97] 臓器移植法第2条 参照
[98] 同上第6条第1項および第3項 参照
[99] 1975年、カレン・クラインが植物状態になり、人工呼吸の使用によって生かされていたが、カレン
の両親が、そのような状況で生かされていることを望まず、娘の人工呼吸器のswitch offを求めた。両親はかつてカレンが植物状態になったら延命を望まない旨の発言を聞いていた。それに対して医師は、どの程度回復するかは分からないが、しかし回復の可能性が全くないわけではないとして延命処置をやめようとしないので、両親が延命停止を求めて起した裁判。裁判は最終的に1976年に父親の代理権が認められ、カレンの呼吸器がはずされたが、その際カレンの自発呼吸がもどり、彼女はそれからもしばらく生き続けた。しかし、最終的には肺炎で呼吸困難に陥り亡くなった
[100] ミズーリ州で1983年に起された裁判。ナンシー・クルーザンが植物状態になったが、そのような状況になった際の治療に延命治療をするのか尊厳死を望むのかについての法律で認められた明確な意思表示がナンシー自身によってなされていなかった。そのため、延命措置を望まない両親が延命措置停止をもとめて裁判を起した事件。裁判自身は州最高裁も連邦最高裁も、両親が敗訴したが、法的に認められた方法でなくても、本人の意思を証明できるものがあれば、その意思は尊重されるとされた。
[101] 1990年に重度の脳障害のためPVS(永続的植物状態)になったテレサ・マリー・シャイボ(以下テリ・シャイボ)に対し、夫が本人が尊厳死を求める意思があったとして人工呼吸器をはずし尊厳死を求めたのに対し、両親が本人はPSVではなく、回復の見込みがあり、本人も延命治療拒否の意思をしめしていたわけではないとして、まったく逆の主張を繰り広げて裁判となった。2003年に、フロリダ州における判決としては夫の主張が認められたが、その後、社会問題になり、別途にテリ・シャイボ救済のために連邦レベルでの裁判ができるよう法案が連邦議会可決されたが、結果として裁判は両親が敗訴となり、テリ・シャイボの延命措置は停止され、2005年に死亡。
[102] 臓器移植法第六条にて「この法律に基づき移植に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ)」から摘出することができる」というとき、カッコ書きで(脳死した者の身体を含む)とされた脳死者は、死体ではないと理解することもできる。実際、そのような理解があるからこそ、脳死者からの臓器摘出が刑法罰の対象にならない法理として、違法性阻却説、責任阻却説、可罰性阻却説などの諸説が議論されているである
[103] 2006年に富山県射水市民病院おこった終末期の患者の人工呼吸器を取り外されて患者が死亡したが、この件に関して外科部長が殺人容疑で書類送検された事件。射水病院では、2000年から2005年の間に外科部長が、家族の同意のもと(内一人は本人の同意)、意識がなく回復の見込みがない担当患者7人(内5人はがん)の人工呼吸器を外したという。
[104] 長沼淳「脳死・臓器移植問題と自己決定権」哲学誌 No.41 東京都立大学哲学会 1999年 pp41-42。なお、引用の中の『他者に迷惑をかけないかぎりにおいて人は何をしてのよい』は太田和夫日本移植学会理事長による発言、『自分のことは自分で決める』は戸嶋祐徳日本循環器学会心臓移植適応検討会前会長の発言である。
[105] 明治学院大学法学部立法研究会編「シンポジウム 脳死と臓器移植」明治学院大学法学部立法研究会 1993年pp36-46にある岡田信弘「自己決定権 -人権の立場から-」p39
[106] 医療費といった経済的な問題や、医療資源の公平な配分の問題等が考えらえる。
[107] 山崎光祥「『脳死』を生きる子どもたち」読売ウィークリー 2008年2月17日号Vol.67 No.7 (通)No.3116 読売新聞東京本社 pp24-28
[108] 山崎光祥「『脳死』を生きる子どもたち」p25
[109] 同上 pp24-25 参照
[110] M・ロック「脳死と臓器移植の医療人類学」pp236-237 参照
[111] 2007年、和歌山県立医大紀北分院で脳内出血で脳死状態に陥った女性(88歳)に対して、医師が家族の求めに応じて人工呼吸器を止め、延命処置を中止したことに対して、医師の行為を和歌山県警が死期を早めたとして殺人容疑で書類送検した事件。そのままでも、2、3時間後には死亡したとおもわれるが、医師は、家族の申し出を二度断ったが、「かわいそうだから」と懇願され、人工呼吸器を取り外した。
[112] 秋田のケースについては、2007年12月23日付け東京新聞27面、千葉のケースについては2007年10月26日付け読売新聞1面、参照。
[113] 2007年12月23日付 西日本新聞1面、3面、参照
[114] 2007年6月13日付 山陽新聞「特集・揺れる臓器移植」30面、参照
[115] 宮本均は「脳死と他我問題」(佐賀医科大学一般教育紀要 No.20 佐賀医科大学 2001年 pp69-76)で不可逆的な意識喪失状態であり覚醒しない状態である脳死は、決して一人称の「わたし」が経験できないものであり、「私の精神が死ぬ」ということを、私の体験から捉え直すことは不可能であるから「他我理解のベースとなる一群の一人称命題との間に、充分な意味上の関連を持たせることができない。であるならば、自他変換を行なった後に出来上がる他人症命題群もまた、公理系になぞらえるような命題相互の関連意味を持つことができないのである」(p73)という。確かに、人は「わたし」として「精神の死」を経験できない。その意味においては宮本がいうとおりであろう。そしてそれは一人称の死が、経験できない「わたし」の死であることと等しい。しかし、一人称の死は「二人称の死」、あるいは「三人称の死」を通して思推の対象となり認識の対象となる。それは、自らが経験する生との連関の中で捉えられ可能となる。すなわち、死を自らの生に有らざるものとして観察することにおいて、「わたし」という自らの死を思推し理解するのである。つまり、自らの死の経験から、自らの死を認識するのではなく、自らの生の経験から“非生”である「わたし」の死を認識するのである。
ところで、先の脳死の家族に対して「こんな姿を見るに耐えがたい」という家族の心情は、自らの生きているという体験から出てくる心情である。われわれは、「有らざるもの」に直面し、それを生きるということは、日常性の経験の範疇にある。その「有らざるもの」が脳死の現場においては、自からが経験する生に対峙する人工呼吸器によって“生かされている”「生有らざる生」として表れる。そして自らの“生きている”という経験から「生有らざる生」の状態を“生きている”のではなく“生かされている”家族に対する心情から「かわいそう」という心情が形成されるのであって、そこには自らの“生”の経験を通して“非生”である脳死の“有らざるもの”の痛みが捉えられることによって、他我問題となりえるであろうと考えられるのである。
[116] 2007年12月23日付け 西日本新聞1面
[117] 橳島次郎「脳死・臓器移植と日本社会-死と死後を決める作法」弘文感 1991年 p17
[118] 西邑亨の報告によると、わが国初の生体間移植の際に最終的な決断は祖父にあったことがうかがえる(「杉本裕弥ちゃんの肝臓移植と家族の決断」『科学と技術』5月臨時増刊号 脳死・臓器移植に反対する市民会議 1991年pp.126-127 参照)。また同報告には、筑波大学膵腎同時移植の場面でも見られたという。西邑の意図は日本発の「生体肝部分移植」という実験医療、人体実験の場面で、意思と患者の権威の構造が逆転したことを述べるものであるが、結果としてそこには、一体化した家族の家父が家長的リーダシップとして決定権を持っていることが示されているといえよう。つまり、わが国においては、未だどこかに旧来の家族制度が残存しており、そのもとでの意思決定が家全体の意思決定として受容されていく様な構造があるということである。しかし、同時に橳島も指摘するように、この家族制度は、核家族化し個人化しつつある(橳島「脳死・臓器移植と日本社会pp.21-22」。つまり多様化しているのも認められる事実であって、それゆえに家族の決定が家族の決定としていかになされるかが問題になるのである。
[119] 確かに、1997年10月に厚生省保健医療局長通知として、「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)」が出された(1998年6月に一部改訂)が、第2 の遺族及び家族の範囲に関する事項 で、臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、喪主又は祭祀主宰者となるべき者において、遺族及び家族の反して、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、喪主又は祭祀主宰者となるべき者において、前記の「遺族」の総意を取りまとめるものとすることが適当であるとされたが、これでは、意見が分れた際にどの意見が優先されるかという法的根拠には乏しいものであるいわざるをえない。
[120] 1999年高橋弘次が主催する「ライフ・スペース」が成田のホテルにて治療と称して死亡した男性を放置してミイラ化させた事件。この事件においては死亡した男性の家族が「ライフ・スペース」をたよって、重篤の家族を病院から連れ出し高橋のもとに連れて行った。「ライフ・スペース」側は、死亡した男性が発見された時点でも、男性は生きており、治療によって回復したはずだと主張している。したがって、「ライフ・スペース」は、心臓死も「死の不可逆的過程にある」とは考えていないことになり、厳密な意味は、不可逆的死の過程における死の受容の問題ではないが、医学的私見をこえた自己決定という典に関しては問題を提起する事件であったといえよう。
[121] 池田豪泉「臓器提供における態度と意識に関わる諸因子の構造解析-日米間の比較を通して」(岡山医学会雑誌 Vol.119 2007年pp.153-163)によると、アメリカ人の95.1%は医師に対して信頼するかどちらかといえば信頼すると答え、どちらかといえば信頼していない4.9%、信頼していない0%に対して高い信頼度を得ている。それに対し、日本では、87.7%が信頼するかどちらかといえば信頼すると答え、どちらかといえば信頼していないが11.2%、信頼していないが1.1%である。
[122] この患者に求められる姿勢について浅井篤は高橋隆雄・八幡英幸編の「自己決定のゆくえ 哲学・法学・医学の現場から」(九州大学出版会 2008年pp.179-193)において「医療現場で自己決定を実現するために必要な10の徳」というタイトルで医療側および患者に求められる基本的な姿勢を10の徳としてまとめている。そこで述べられている10の徳とは要約すると概ね次のようなものである。
1.慎重さ(医療従事者に求められる徳)
医療従事者に求められる徳で意思決定する患者および家族が正しい意思決定ができる能力・状態にあるかを見極め、確認する慎重さ。そのうえで治療の選択をする。
2.思いやり(医療従事者および患者親族に求められる徳)
意思決定者が、意思決定者にとって最良の決定ができるような思いやりのある支援。
3.節度(自己決定を行う者、患者に求められる徳)
自己決定、リクエストのすべて尊重されるわけではないことを知る節度、たとえば、「今いる患者をどけて自分のベッドを窓際に移動しろ」という要求などは受け入れられない。むしろ「他者に害を与えないかぎり、個人の自由は制限されてはならない」というミルの自由原則(the principle of liberty)や他者危害原則(the harm principle)が、自己決定の場に置いても働くことを患者側は節度を持って知るべきである。
4.勇気(患者を含めたすべての関係者に求められる徳):
決定をしなければならない状況におかれたとき、それに関わるすべての者は、決定を避けるのではなく勇気を持って決定する。
5.責任感(自己決定を行う者、患者に求められる徳)
自分の決定の結果生じた問題に対して責任をとろうとする責任感が自己決定を行う者には必要である。
6.想像力(医療従事者および患者親族に求められる徳)
自分の望んでいることを相手になせということではなく、相手の立場で考える想像力を持ち、相手の主張を尊重することが大切。相手の気持ちに鈍感であってはならない。
7.合理的である(医療従事者および患者親族に求められる徳)
医療従事者も患者の家族も、理屈の通らないことを他者に強要しない。
8.寛容さ(医療従事者および患者親族に求められる徳)
医療従事者も患者の家族もまったく価値の違う人間の態度に寛容であること。自分の使命感を他者に押しつけないことが求められる。
9.謙虚さ(患者を含めたすべての関係者)
自分の考え、主張、価値観が絶対ではなく誤りもあることを認め、他者の意見に耳を傾けて聞くといった、自分の考えや価値観を相対化させる謙虚さ。
10.善意(医療従事者および患者親族に求められる徳)
他人のためになるように思う気持ち、他の人の利益になるようなことをしようと思う気質。自分の哲学的立場や考えを主張したいがために、自己決定尊重に置いて現実的には実際に問題にならないような問題点を騒ぎ立てるとか、ありそうもない「滑りやすい坂理論」を述べるのは悪意の人である。
[123] 「臓器移植法」第6条第1項および第2項
[124] 町野朔・長井圓・山本輝之編「臓器移植法改正の論点」信山社 2004年 p29参照 町野は、この中で、人間像を善意を示す資質を持つ存在であると定義し「我々は、死後臓器提供へと自己決定している存在である」という。これに基づいて、臓器移植法に対する町野の改正案、いわゆる町野案を提案している。
[125] 同上書p29にて、町野は「およそ人間は見も知らない他人に対して善意を示す資質をもっている」と述べている。
[126] 1997年厚生省保健医療局長通知の「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)」第1参照、そこには有効な意思表示は15歳以上であること、また知的障害者の意思決定は無効であることが記されており、現行の臓器移植法はこのガイドラインに沿って運用されている。
[127] 子どもの権利条約第12条「(意見表明権)自己の意見をまとめる能力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の意見を表明する権利を保障し、かつ子どもの意見はその年齢および成熟度に従い、適正に重視されなければならない。」
[128] 杉本健郎「子どもの脳死と臓器移植」小児科 Vol.46 No.2 金原出版 2005年 p240
[129] 杉本健郎「子どもの脳死と臓器移植」 p241
[130] 同上書 p241 なお、ここで言う管理的立場の医師というのは、先の日本小児科医学会倫理委員会のアンケートに回答した代議員を指すもの考えられる
[131] 森岡正博・杉本達郎「子どもの意思表示を前提とする臓器移植改定案」2001年2月14日、森岡・杉本案については、http://www.lifestudies.org/jp/moriokasugimoto-an.htmにて掲載
[132] 荒木玲子「『脳死による臓器移植』に関する意識調査 -メディア・リテラシーの視点による考察-」足利短期大学研究紀要Vol.24 2004年 pp.45-49
[133] 杉本・森岡提案(A提案)においては、すでに述べたように6歳以上自己決定が親権者の承認のもとに認めるよう提言とする一方で6歳未満の「法的脳死判定」も「臓器摘出」も行わない旨が提案されている
[134] 町野・永井・山本「臓器移植法改正の論点」p26
[135] この子どもの意思決定が尊重されなければならない年齢として、先に述べたように森岡・杉本案では、6歳を基準としている(ただし、同案においては、並行的にB案として12歳以下には、法的脳死判定も臓器摘出も行なわないという案も提示されている)。また日本移植者協議会は、15歳を境目として、15歳未満の子どもについては、親の承諾のみで法的脳死判定、および臓器移植ができるように提案している
[136] 厚生省脳死に関する研究班報告書による。
[137] 杉本「子どもの脳死と臓器移植」の表1によると、幼児虐待による脳死がおこった事例は8例、表3によると、1999年から5年間で身体的虐待が疑わしかった症例が1452件あり、うち129例が、脳死または重度脳障害を残した事例であった。
[138] 精神障害を持っている人の自己決定と治療同意判断能力の問題については、高橋貴雄・八幡英幸編「自己決定のゆくえ 哲学・法学・医学の現場から」熊本大学生命倫理論集2 九州大学出版会2008年の第6章にて北村俊則・北村總子によって述べられている。ここで述べられているのはあくまでも治療を対象にした自己決定であり同意判断であって脳死や臓器提供に関するものではない。しかし、精神に障害をもつ人の判断能力と言うことについては参考になるものであるといえる。
[139] 斎藤誠二「脳死・臓器移植の議論の展開-医事刑法からのアプローチ」pp.153-162参照
[140] 倉持武「脳死移植再考」 p32
[141] 本論文執筆中(2009年)に、国会にて臓器移植法の改訂の審議が行なわれ、最終的に脳死は一律に人の死として認められ、臓器移植に関しては、幼児の移植も認められることになった。この法案の脳死に関わる部分においては、脳死を人の死としたことは、ある程度評価はできる。もっとも、厳密に言うならば、脳死は不可逆的な死の過程にあるということを意味するのだから、それを明記して、家族に死の受容による死亡判定とすべきではなかったか。その意味では不十分である。しかし、一応、脳死判定を拒否することができるという一文がそれを留保しているとは言えよう。また、臓器移植に関しては、小児に移植を認めた点は評価できるが、本来、人の善意によって成り立つ臓器移植を、町野案に則って、一律に臓器提供の対象者にし、嫌なら申し出ろという形式を取った点は全く評価できない。これによって臓器提供が通常で拒否が例外であるという社会的威圧のもとに置かれる可能性がある。これは、臓器移植が善意で成り立つ医療であるという移植医療の最も崇高な部分を踏みにじる行為である。また臓器提供に対する社会的圧力を生みだすような構造は、レシピエントが、自分の命のために他者を犠牲にしているというイメージを与えかねない愚行であり、全く評価できない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
