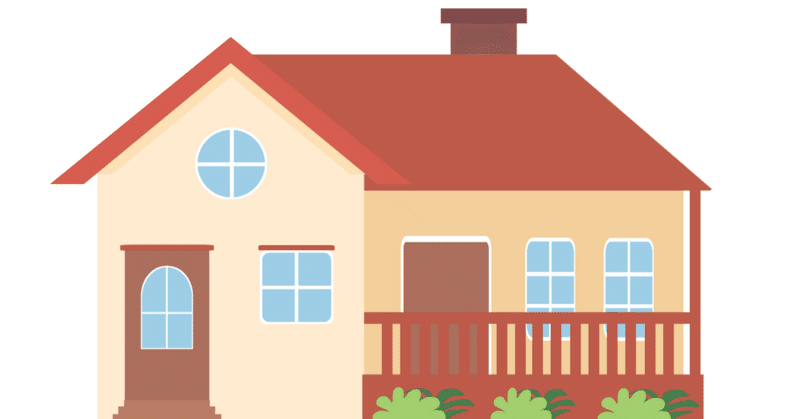
ショート小説『母娘喧嘩』
「私、今日ご飯いらないから」
と美里が言い放つと、母はすっかり押し黙ってしまった。
沈黙に包まれたリビングを後にした美里は、少しの罪悪感を感じながら、家を出た。母にとって料理は、代えがたい自分の仕事であるし、この家での自分の存在意義であるような意識をどこか持っている。美里に明確な悪意はなかったのだが、「ご飯いらない」という発言は、母娘の溝を決定的に深めてしまいかねない。
発端は、母が娘の部屋に長居をしていたこと、そして手帳の置き場所が変わっていたことだった。「見た」「見てない」の押し問答の末、
「お母さんはいっつもそうだよね」
「だったら、いつの何のことか言ってみなさいよ」
「だから先週もそうだったって」
「先週の何曜日の何時よ」
いつも通りの喧嘩の流れに達したころには、後戻りの仕方が分からなくなっていた。母に言わせると、美里は蛇年なので、ちょっとしつこいところがあるらしい。美里に言わせると、このように母は適当なことを言って娘の性格を決めつけるが、いっぽう人の発言の揚げ足を取ることには長けている。因みに母も蛇年である。
そんな母娘喧嘩の終戦はたいてい、お互いに頭を冷やそうと距離を取って、2,3日経った頃にはすっかり忘れて元通りになっている、という具合だ。
だから美里は、今日もいつも通り何気なく距離を取り始め、何気なく外出を増やして会話の機会を減らせば良かったのだ。
「ご飯食べない」なんて、わざわざ口に出して言うことではない。「今日は忙しいから外で食べて来る」とLINEでもすれば済んだはずだった。口に出すと、隠しきれない苛立ちが言葉に乗っかってしまう。すると、母の料理に対する感情ではない別の攻撃的な要素が、母の料理と、存在価値を批判してしまうのだ。
それでも、その場で取り繕って発言を撤回できるほど、美里の頭は冷えていなかった。仕事中も母のことを考えてしまって作業効率が落ちるくらいに、頭の中を占領されていた。
夜、近所のカレー屋で大人しく一人飯を食べた美里は、帰路についていた。
駅から家に歩く間にも、未だ頭の中に母への苛立ちが残っていたので、帰宅したあとも必要最低限以上のことは話すまい、と心に誓っていた。
外灯の少ない真っ暗な街路で、大きな犬とすれ違った。犬も飼い主もこの近所では見たことがなく、犬の方は動物嫌いの美里は思わず後ずさりするほどの、オオカミのようなサイズとフォルムを持ち、薄暗い住宅街の細道で存在感を放っていた。
犬は飼い主に似ると聞くが、彼らも例外ではなく、飼い主の方もかなりの大柄で、バスで隣の席に座られたら少し落ち込むだろう、というくらいの迫力を持っていた。
美里は、犬とすれ違ったあと、少しだけ振り返って、犬のお尻を見た。美里は、動物に遭遇すると、離れたところからお尻を見てしまう癖がある。今日の大きな犬は、やはりお尻の穴まで大きかった。
犬が通り過ぎた先に、女性らしき人影がのろのろと歩いているのが見えた。母に似たカバンを持っていて猫背なのだが、今日は来ていなかったような気がするチェックのワンピースを着ている。
美里は無意識のうちに、早歩きになっていたことに気付いた。
女性らしき人影は、どんどん大きくなって、やがて突き当りの曲がり角に吸い込まれた。
美里の足を動かすリズムは、だんだん歩く速さでは超えられない範囲になって、小走りで女性を追いかけて行った。美里の表情には、ちょっとした高揚感がにじみ出ていて、それはランナーズハイによるものではなく、曲がり角の先にある対象への期待感であった。
曲がり角を曲がると、はす向かいのおばさんがいた。母と同じスーパーのエコバックを持って、母が持っていないチェックのワンピースを着て、猫背で歩いて行った。
家に帰ると、母は相変わらず台所に立っていた。
「今日は忙しかったから食べてきたー」
「そう」
と興味なさげな母は、チェックのワンピースを着ていて、美里が思っていたよりもずっと、少なくともはす向かいのおばさんよりは、背中が真っすぐ伸びているように見えた。
(完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
