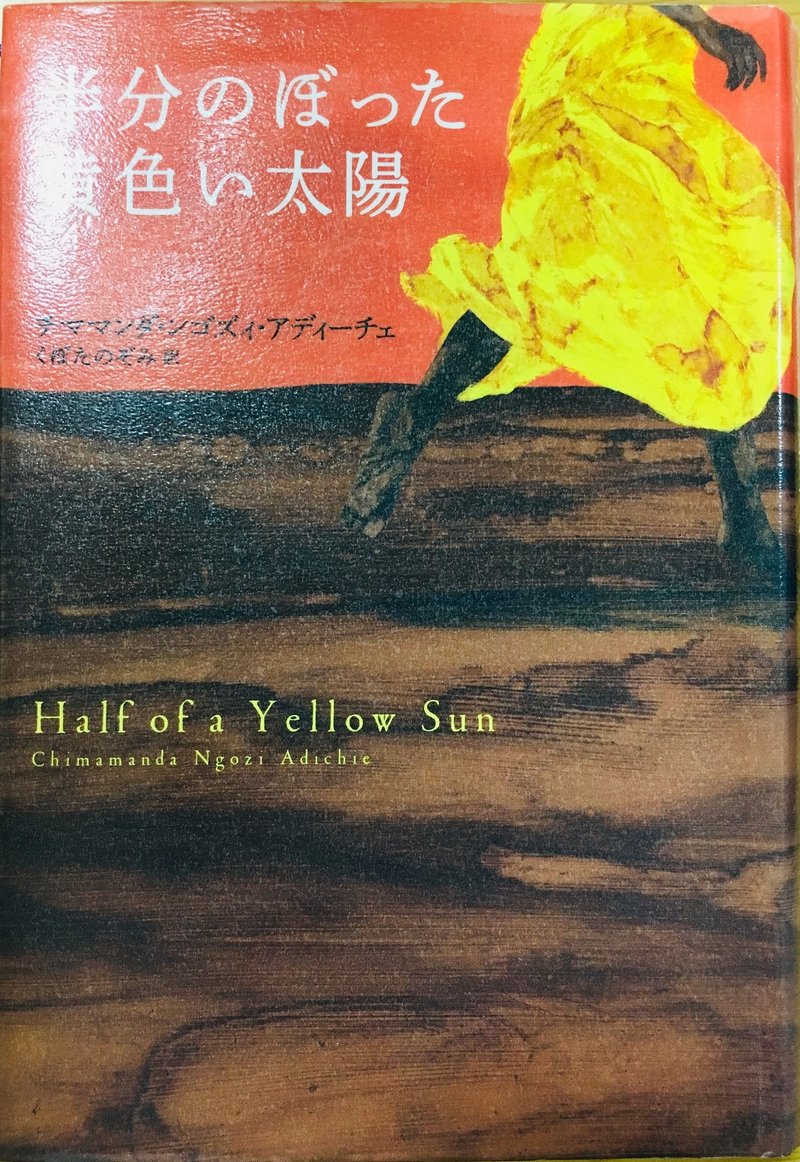1960年代のわたしたち。アディーチェ「半分のぼった黄色い太陽」
概要
1960年前半から1960年後半のナイジェリア、主にはビアフラ戦争終末までを背景とした3人のナイジェリアに住む人々の物語。ビアフラとは、東部に集中するイボ民族がナイジェリアの他民族による排斥に抵抗して立ち上げた国家のこと。「半分のぼった太陽」はそのビアフラ共和国の国旗のことだ。
当時の中産階級や民族の村の暮らしぶり、家族(恋愛)観、友情、人生の襞に分け入って、わけいって、アディーチェは物語として、人間の尊厳と愛の襞を描いている。言葉として分け与えられた読者として、わたしは幸運な体験をした。実は2段組で500頁になろうかという大著だが、読んでいてしんどいということはなく、もう一度読みたいと言う気持ちさえもある。とくに、物語で唯一と言っていい読者にとっての種明かしの行われる2度目の1960年代前半の物語はよかった。本書では徐々に進行する戦争に対して人々が気炎をあげ、生活が弾丸の雨の下で粛々と続き、生命はずっと脅かされ続ける。これは「この世界の片隅に」で描かれた近代の資本主義国家を打ち立てようとしてもがいて(あるいはもがかされた)、行き止まりにぶつかった日本の市井の人たちと同じなんだと気づく。(もちろん、ナイジェリアの語り手のほうがずっとポストコロニアル的なのだが)が、アディーチェがより克明なものにしたのは、その歴史的事実によって生じる、個人の感情の寄せては返す波が、ひとの核心を明らかにするということ。さらにわたしは、アディーチェの筆力にかかればセックスとその前後の描写が、そのひとの核心をより一層たしかめられるようにすることに、とても吃驚したのだった。
著チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、訳くぼたのぞみ『半分のぼった黄色い太陽』
※普段はamazonから画像を拝借するが、気に入った装幀ではなかったので手元にあった本の書影を取り込みました。
さて、本書は3人の語り手によって物語がつくられている。冒頭にも描いた、愛情の襞がこの物語の固有なものとしているのは、同一の出来事について3人それぞれが語ることで、より奥深い事柄となって私たち読者の前に立ちあらわれ、3人が悩んだり、見ないことにしたり、一つの結論を出すことに、誰かや我が身を重ねることになるからだと思う。ナイジェリアの1960年代の物語でありながら、家族間の微妙な人間関係や、重要な価値観こそ一致していると思っていたパートナーとの間で微妙な距離を見たりする、極めて「わたしたち」の物語であるように感じられたのだ。
オランナのこと
この物語を読んでから、同居人や同僚との日常的な会話のちょっとした沈黙に2行か3行の逡巡の物語を読み解きそうになる。例えば自分の人生で最悪な出来事が訪れた時に、こんなことが起きたのならもう自分にはしばらく悪いことが訪れるはずはないだろうと思うこと。圧倒的な信頼感に少しずつ水を差されても、それでも空間と時間を共にするということこと。愛している、という言葉の下敷きにある見下した態度。謝罪し、落ち込んだ相手に対するこれからの関係への期待。ある事柄を「できない」「自信がない」と表明したときの、自信満々な相手の様子に静かに、小さく、諦めること。もやもやとした揺らぐ気持ちを、他の何かに代替させて、決然と受け止めて言い放って欲しくなること。
こうした感情のさざ波は0と1の間の出来事で、外見的には変化が見えない。主観的にもただ、もやもやしているだけと言えるかもしれない。そのため、語り手の3人のうちの一人であるオランナは、さっぱりとした双子の姉であるカイネネから親やパートナーに対していつも従順であるか、明白な対抗ができないと思われている。それでいてオランナの美貌を周りが放っておかないこと等が、カイネネをして気に入らない人間の仲間入りをさせている。本当はいろんなことを思っているけれど、それが客観的には行為としては認識できない。
彼の話を聞いていると、自分が卑小で、聞き分けのないだだっ子みたいに感じる。さらに悪いのは、彼のほうが正しいのではと思ってしまうことだ。いつもそうだ。彼のほうが正しいのではないかと思ってしまうのだ、一瞬、理不尽にもオランナはオデニボから去ってしまいたいと思った。やがて、理性が戻ってくると、彼を必要とせずに愛せたらいいと思った。必要が努力することを免除する力を彼に与えていたから。必要は彼のまわりに頻繁に感じる選択肢のなさでもあったから。_p122
でもそうした0と1の間の出来事の積み重ねのなかで、内戦下のおそらく男尊女卑溢れたナイジェリア社会で、家族を形成することについて決然とした決定をオランナはおこなう。その決然とした決定を決定するに足らしめたいくつかの要素を書き残しておきたいと思った。
一つは、ものすごく酷く落ち込んだ時には、日々の仕事を淡々とやって息を整えることだったり、動物の日々の営みを観察することだったり、粗野で決して馴染みきれない生活を送っているが安寧にやり過ごされているような田舎に帰って、学びを得ることだったりする。何かが起きても、最後には元に戻るような、かくあるべしといわしめる平安に落ち着くことが、ふと何かをもたらしてくれることがある。
「いってやったんだよ、なんであれ、わたしの面目をつぶすようなことをしたら、あんたの股間のその蛇を切り落としてやるって」
イフェカおばさんはまた、かきまぜる動作にもどった。おばさんたちの結婚生活にオランナが抱いていたイメージが内部から崩れ始めた。「自分の人生を男に預けるような振る舞いは絶対にしちゃダメだよ。いいかい、あんたの人生はあんたのもの、ソソ・ギ(あんただけ)のものなんだから。土曜日に戻るといいよ。あんたに持たせる土産のために、急いでこのアバチャを作ってしまうからね」
おばさんはペーストをちょっと口に含み、味を見てからぺっと吐き出した。
オランナは、田舎から飛行機で彼女たちの住まいであるスッカに戻る。そこでとてもハンサムな男がわざわざ隣席に移動し、話しかけてくる。オランナもとんでもない魔法のようなことが起きればいいと思い始める。しかし、彼はイボ人を嫌悪している男だった。オランナが「イボ人です」と伝えると、彼はそっぽを向くようになった。でもオランナは、
男の偏見のおかげで、オランナはどんなことも可能なんだと気づいたことを彼に教えてあげたかった。恋人が村娘と寝たために傷ついた女である必要などない。機上でフラニ人の男といっしょに、イボ民族をあざわらうこともできる。自分の人生にみずから責任を負う女である事もできる。なんにだってなれるのだ。
オランナは、オランナである。結婚しているとか、子どもがいるとか、イボ人であるとか、そのことによってオランナの価値が低くなったりすることはないし、オランナの決めることに影響することはない。オランナのことは、オランナのものである。紙一枚も、所属のことも、その重要性を決めるのは自分であり、彼である。オランナはそのことに気づいてから、隣の男にありがとうとは言わなかった。彼の驚きも、痛恨の思いも、そのままにしておきたかったから。
他のふたりと、魔物文化について
オランナ、という人物のことが魅力的すぎて、オランナのことしか書けなかった。他の二人の語り手もすばらしい。カイネネのボーイフレンドであるリチャードに自分自身は気持ちを重ねることが多かった。彼の自己憐憫への認識は、いたいたしい程である。黙っていれば冒涜のそしりを逃れられると思っていることもそうだ。彼のことを文字で追っていると、何かを決めるときに後戻りできないことが分かっていても足を踏み入れざるえないなら、自分を憐れみながら黙っているのも一つの権利だとは思う。その先に、だんだんと執着と責任が芽生え始めるかもしれないから。オランナのようなあり方では当然ないけれども
ウグウは、オランナの恋人であるオデニボのハウスボーイである。ナイジェリア社会でもっとも脆弱で、周辺的で、境界に生きるウグウであるが、彼の目を通してこそ、この物語が朝ドラっぽくはならなかったのだと思う。さいごにウグウを紹介して終わろう。彼に魅力を感じられたら二段組500頁もそう難しいことではないと思う。
どうしてソックスにアイロンなんかかけたんだろう、どうしてサファリスーツだけにしておかなかったんだろう、自分でも理由がわからなかった。魔がさしたんだ。悪い魔物がさせたんだ。やっぱり、やつらはどこにでも潜んでいるんだ。彼が病気で熱を出すといつも、昔木から落ちた時も、母親が彼の身体にオクウマを揉みこみながら「かならず退治する、あいつらが勝つことはない」とずっと唱え続けてたもんな。p21
実はソソ・ギ(あんただけ)と、この魔物観は通底していると思っている。個人は個人で素晴らしい。何か悪いことが起きた時、それはあなた自身の問題じゃない。あなた自身の価値を毀損することじゃない。オランナは欧米で生まれたフェミニストではなく、ナイジェリアの土着宗教が味つけをしたフェミニストなんだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?