
『ジャン=リュック・ゴダール 遺言 奇妙な戦争』レビュー:「黒画面(=無)」の探求の涯てに彼はGOD+ART(D)となる
0.ジャン=リュック・ゴダール遺作、ついに公開
2022年9月13日、ヌーヴェルヴァーグの首領ことジャン=リュック・ゴダールが亡くなった。91歳だった。彼の最期は、スイスでの自殺幇助。映画は完成せず、『気狂いピエロ』のラストを彷彿とさせる唐突さが全世界の映画人を震撼させるとともに、どこか納得いくようなものも感じさせた。
それから1年後、サンローランプロダクションが彼の遺作をカンヌ国際映画祭に届けた。それが《Film annonce du film qui n'existera jamais: 'Droles de guerres'》、完成しなかった映画の予告編であった。
ようやく日本でも公開されたわけだが、残念なことにパンフレットの納品が間に合わず、我々観客は具体的で抽象的な彼の難解な遺言状を内に反芻することしかできなかった。
わたしは、この映画を迎えるために事前にジガ・ヴェルトフ時代のゴダール作品を中心に10本ほど鑑賞。併せてカイエ・デュ・シネマや関連資料を取り寄せて、彼の作品を解剖研究していた。
その上で本作に挑むと、彼が探究し続けてきた映像論の集大成といえる作品で2024年のベストに入れたいレベルの大傑作であった。
ゴダール映画を分析する上で、「具体」と「抽象」と2つのアプローチが取れる。残念ながら「具体」は、経験値不足であまり掘り下げることができなかった。一方で「抽象」に関しては、ある程度参考になる語りができると思う。
そこで、今回は『ジャン=リュック・ゴダール 遺言 奇妙な戦争』(以下、『奇妙な戦争』)について掘り下げていく。
▲動画版レビュー
1.『ジャン=リュック・ゴダール 遺言 奇妙な戦争』構成
音のない劇場、緊迫感が立ち込める中、2枚の写真と手紙の切れ端のようなものが提示される。顔、手、そして赤いインクのようなものがついた手紙。1枚の画であるが、複数の構成要素によって暴力による凄惨さが現出する。
そして、次にはポスター写真にもなっているジャクソン・ポロック風の画が叩きつけられる。ただでさえ、荒々しく見えるものが、直前のイメージによる連鎖でより暴力的なものに感じる。
抽象的な画から我々は具体的な暴力を想像していくのである。これこそが今回のゴダールのテーマであり、もとい彼が90年以上の時をかけて見出した映像論の集大成ともいえよう。
ここで重要となってくるのは無音であろう。ジョン・ケージは「4分33秒」にて、沈黙を通じて観客に音への関心を促した。「無」は存在しない、「無」はある種の「有」なのだ。「無」を意識することで「有」が意識される。
『奇妙な戦争』も同様に、無音を通じて「音」、そして「画」に対する凝視を促す。無音空間における抽象的な画への想像力が本作における肩慣らしの役割を担い、だんだんと語りによる本題へと誘われていくのだ。
そして、映画は『アワーミュージック』のフッテージに新作『カルロッタ』の説明が加えらると共にシャルル・プリニエ「偽旅券(Faux Passeports)」への想いを寄せる。シャルル・プリニエは1928年のアントワープ大会中にトロツキズムを疑われ、共産党から排除された。共産主義者でありながら国際赤色救援会に所属していた彼は1937年に自身の経験に基づく「偽旅券(Faux Passeports)」を発表しゴングール賞を受賞する。ジガ・ヴェルトフ時代に帝国主義、修正主義、双方に批判的眼差しを向けていたゴダールにとって、プリニエは自分の分身のように感じたことだろう。『奇妙な戦争』は、ようやく本編の核心に迫る議論が開始されたかと思った瞬間に終わる。対話の途中で打ち切られたこの予告編を前に我々は困惑することだろう。
さて、ここでゴダールにおける抽象的な画に着目していく。キーワードは「黒画面」である。映画を観た人なら「どこに『黒画面』があるのか?」と疑問に思うであろう。それを説明するために、ジガ・ヴェルトフ集団時代へ遡ることとする。
2.「黒画面」への探究
2.1.ジガ・ヴェルトフ時代における「黒画面」の扱い
1967年の『ウイークエンド』を最後に、ゴダールは商業映画と決別し、『勝手に生きろ/人生』(1979年)に復帰するまでの間、ジガ・ヴェルトフ集団を形成し、政治的実験映画を制作し続けていた。ジガ・ヴェルトフとは、もちろん『カメラを持った男』(1929年)の監督である。『カメラを持った男』は、多重露光やスプリットスクリーンなど、映画が現実を捉えながらも現実ではあり得ない画が生み出せることを実践していった作品であり、その監督の名を冠したジガ・ヴェルトフ集団は実験的な手法を用いて政治や社会を「映画」に収めようとした。その実験の中で、よく研究されたのが「黒画面」の用法である。
たとえば『プラウダ(真実)』(1970年)では、「黒画面」の中で以下のように語られる。
7.和解女性労働者ビキニ姿 だがアメリカのCBCに売り払ったので権利がない
映像メディアはありのままの事実を映し出すことができるが、映像メディアの切り取り方によっていくらでも操作することができる。ゴダールは帝国主義や修正主義を批判する中で、映像編集の側面と向き合う。そして逆説的に同じ映像メディアである「映画」によってそうしたものに抵抗できるのではと説く。その中で映像から距離を置くために「黒画面(=無)」の用法を模索したといえる。そして、『ウラジミールとローザ』(1971年)などでも応用されていく中で『ありきたりの映画』(1968年)が面白い用法を編み出している。
労働者、労働組合、経営者の関係について原っぱで若者たちが議論をしている。労働組合の欠点を指摘した上で革命の重要性を訴える。これは個人の意見であるのだが、映画は遠巻きに顔を映さないようにしている。それにより、イデオロギーに個が取り込まれていく様子が強調されていく。自由意志が存在せず、必ず誰かの影響から成立している抽象的な概念を画で的確に捉えていく。画を見せつつも、肝心なものを見せないことによってある種の「黒画面」が生み出される。それが社会の本質を捉えることとなるのだ。本作での演出は今観ても色褪せることがない。むしろ、SNS時代において有効な手法ですらある。個々は様々な思索をSNSに書き込む。だが、その思索の集合が一定のイデオロギーを生み出す。それを映像で表現するにはどうすればいいのだろうか?
ルーマニアの鬼才ラドゥ・ジューデ監督は『アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ』(2021年)にて、ランダムに画を並べていくパートと、コスプレをした人々が一方的に物言いをするパートでもってSNS的猥雑さを抽出していった。ここでは匿名的な映像と、顔は見えているがSNSのアイコン的に処理されていく言論がSNSらしさが個と匿名性を強調していた。
シンプルに顔を隠した状態で議論するだけでも十分SNS的演出が見込めることを60年代に見出したゴダールは慧眼といえよう。
閑話休題、少し話が逸れたところで、ゴダール映画への理解を深める意外な一手を提示したい。それは「ギー・ドゥボール」である。次の章ではドゥボールとゴダールの関係性について論じていく。
2.2.ギー・ドゥボールとの関係性
思想家であり映画監督であるギー・ドゥボールとジャン=リュック・ゴダールとの関係について論じられている文献は少ない。「フィルムメーカーズ[21]ジャン=リュック・ゴダール」にて佐々木敦は、ジガ・ヴェルトフ集団時代における「黒画面」の役割について論じているが、彼について触れていない。
しかしながら、3つの理由からゴダールはドゥボールを意識していたと考えられる。
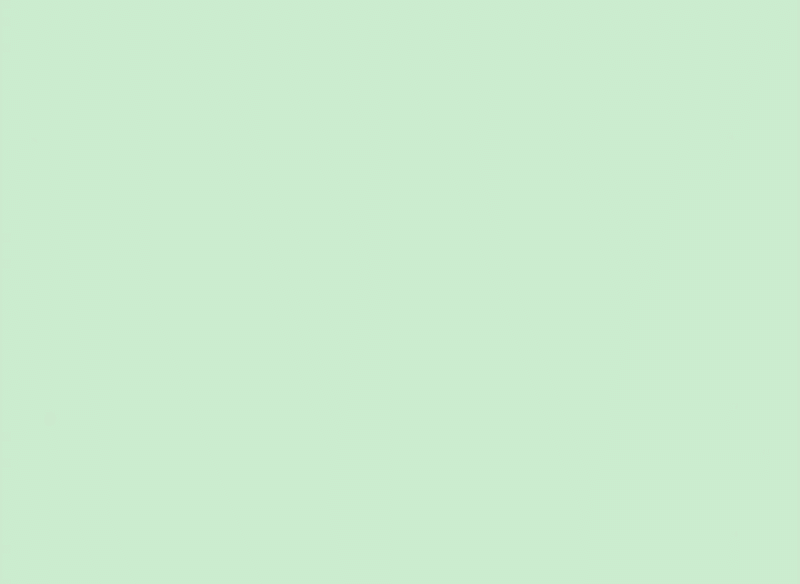
一つめは、ジガ・ヴェルトフ集団時代よりも前にドゥボールは「黒画面」の用法について検討していたことにある。彼はイジドール・イズーのレトリスム映画『涎と永遠についての概論』(1951年)に影響を受け、『サドのための絶叫』(1952年)を制作する。ジェイムズ・ジョイスや新聞、民法典の文章を朗読する「白画面」と無音の「黒画面」を交互に提示し、最終的に24分にわたって「黒画面」を展開する。
70年代に入ると、自身の理論を「スペクタクルの社会」にまとめる。ひとびとはサーカスや映画だけではなくスキャンダルや経済活動ーたとえば日経平均株価がバブル時の史上最高値を超えて興奮したり、円安で1ドル150円を突破し落胆するような状況ーといった「スペクタクル」に支配されていると批判した。これは映画化もされた。晩年に制作した『われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを』(1978年)では、中産階級の裕福に見える写真に社会システムの奴隷となった人間像を解説し、理論を深めていった。ゴダールが『ブリティッシュ・サウンズ』(1970年)で提示する理論ー労働者は商品ではなく、賃金を稼ぐために生かされているーや『プラウダ(真実)』、『イタリアにおける闘争』(1970年)などで実践される「黒画面」の用法を踏まえると、ドゥボールの影響を受けてないとは言い難いものがある。
二つめは、1981年のカイエ・デュ・シネマベストにて『われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを』が選出されている点にある。
【1981年のカイエ・デュ・シネマベストテン】
1.『飛行士の妻』エリック・ロメール
1.『フランシスカ』マノエル・ド・オリヴェイラ
3.『海辺のホテルにて』アンドレ・テシネ
3.『ある愚か者の悲劇』ベルナルド・ベルトルッチ
5.『ドイツ・青ざめた母』ヘルマ・サンダース=ブラームス
5.『隣の女』フランソワ・トリュフォー
7.『ストーカー』アンドレイ・タルコフスキー
8.『音楽サロン』サタジット・レイ
8.『レイジング・ブル』マーティン・スコセッシ
10.『グロリア』ジョン・カサヴェテス
10『われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを』ギー・ドゥボール
10.『パレルモあるいはヴォルフスブルク』ヴェルナー・シュレーター
10.『鳩の翼』ブノワ・ジャコ
そして、三つめはギー・ドゥボールがゴダールを批判していたところにある。ジョルジョ・アガンベンの論文"Difference and Repetition: On Guy Debord's Films"によれば、1968年に「ゴダールは親中派スイス人の中で最も愚かだ」と語っているとのこと。ゴダールがこのように批判されていたことを知らなかったと考えるのは無理がある。
以上から、ジガ・ヴェルトフ時代のゴダールを語る上でギー・ドゥボールが重要である。次に、ドゥボールの手法を踏まえた上でのジガ・ヴェルトフ集団時代の手法を振り返るとともに、『奇妙な戦争』における演出を分析していく。
2.3.「黒画面」への置換としてのキヤノン(Canon)
ドゥボールはレトリスム運動の中で「黒画面(=無)」に可能性を見出したことに対し、ゴダールの場合は先述の『プラウダ(真実)』における「黒画面」をはじめとし、「黒画面」そのものにも意味を持たせようとしている。『アワーミュージック』(2004年)では、明確に「無」に対しての見解を提示している。
イメージは喜びだが、かたわらには無がある。
無がなければイメージの力は表現されない。
言語は恣意的に対象物を分割するというがまるで私たちの過ちのように言われる。
本作ではパレスチナやサラエヴォの具体的な問題を、具体的に文学を引用しながら語る。だが、それは具体的すぎて分断を引き起こす。イメージの喜びはそれを中和するが、ジガ・ヴェルトフ集団時代の作品で見出されたようにメディアにより歪められてしまうがある。イメージをありのまま受け取ることは危険である。だからこそ無が必要で、それが我々の想像力を掻き立てる。ゴダールはこのように理論づけているのである。
「フィルムメーカーズ[21]ジャン=リュック・ゴダール」に掲載された論考「ジガ・ヴェルトフ集団の映画いわゆる『黒画面』について」において佐々木敦は、「黒画面」は映画批判であり「耳の擁護」を認識させる狙いがあると語った上で、次のように締めくくっている。
ジガ・ヴェルトフ集団の映画において度々挿入される「黒画面」の意味とは、現実批判としてのイメージ批判、その極点として「耳の擁護」である。ひとたびそれが認識されたならば、もはや「黒画面」である必要はない。この世界を見つめよ、ありのままの現実を凝視せよ、ではなく、時にはそこに、ここに見えているものを、敢然と拒絶し、その代わりに耳を澄ませ、そこに「革命(世界変革)」の鍵がある、ということなのだ。
まさしく「黒画面」以外の方法で「黒画面」を捉えた作品こそがこの遺作だ。映画の中で、キヤノン(Canon)と書かれた画、つまり写真の裏側が反復される。本作を観る者に対し「耳を澄ませよ」とゴダールは語りかけているのだ。
2.4.写真を同時に並べるということ
ギー・ドゥボールが『スペクタクルの社会』(1973年)や『われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを』では、写真や動画を1枚ずつ提示していった。対してゴダールはメディアから複数の読みができることをいかにして「ひとつの画」で演出できるのかを試行錯誤している。
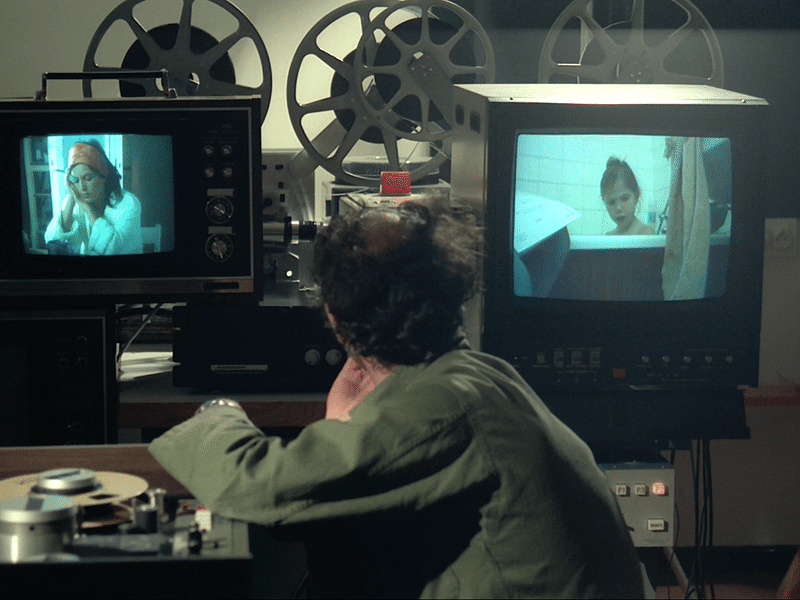
実際に『ジェーンへの手紙』(1972年)では写真を重ねながら語りを添えていくスタイルが採用された。『パート2』(1975年)では、テレビを複数台並べ、実体とメディアによって現出する画を同時に提示していく演出が披露された。振り返ってみるとゴダールの初期作『カラビニエ』(1963年)でもユニークな写真の使われ方がされている。金儲けのために戦争に行き、残虐の限りを尽くした若者に残されたものが「虚無」であることを強調するためにポストカードが使われている。ポストカードをばら撒きながら彼/彼女らは喜ぶが、実体としての富は存在しない。にもかかわらず、ポストカードに映るものに夢を見ながら喜び続けるのだ。本作はメディアという境界線の使い方に特化しており、この場面の他にも『キートンの探偵学入門』へオマージュを捧げた場面がある。スクリーンに映る裸の女に魅了され、飛び込もうとするが失敗。スクリーンがビリビリに引き裂かれる外しのギャグなのだが、これもまたメディアの向こう側に夢をみて虚無が残る描写となっており、初期の段階からメディア批判の姿勢を持っていたことが分かる。
『奇妙な戦争』でも、このアプローチは健在である。先述の写真の裏側を背景に写真を並べていく。「無」と「有」が同時に現出する場面である。これは映画の本質ともいえる。映画は、画や音といった複数の要素がレイヤーを形成して成立しているのだ。通常の映画では、画と画の連続によって展開される。ジガ・ヴェルトフ時代における「黒画面」はそこに行間を与えるものだった。やがて、複数の画を重ね合わせる手法を見出していき、ついには「無」と「有」を同時に提示する手法を発見したのである。これには感動を覚えた。
またこれだけではなく、フィルムカメラの画と、ゴダールが鏡に向かってスマートフォンで撮影した自撮りを同時に魅せる場面が印象的であった。『イメージの本』(2018年)で、ちびっ子が列車の到着を待つインターネット動画を引用することによってリュミエールから始まる映画史(もしくは映像史)の点と点を結んでいたが、本作では「写真」を用いてフィルムからデジタルへの流れを掬い取ってみせた。
3.映画を微分して見えるもの
3.1.例としての『アワーミュージック』
『奇妙な戦争』はさまざまな場所で言及されている通り、『アワーミュージック』を参照している。セリフ面に関して、たとえば以下が引用される。
それは何かのイメージだ。
ぼんやりしてる。
二人が横に並んでる。
私の横に女性がいる。
見知らぬ女性だ。
自分は分かる。
だが私には覚えがない。
そこで、一度『アワーミュージック』について整理する。
『アワーミュージック』はダンテ「神曲」における地獄編、煉獄編、天国編の構成をエッセイドキュメンタリーとして落とし込んだ作品である。第一部の地獄編では、セルゲイ・エイゼンシュテインから『キッスで殺せ!』、『トップガン』にいたるまで膨大な戦争映画など暴力映画のフッテージから構成される地獄が展開される。第二部ではサラエヴォ在住の女学生でテロリストと間違えられたため、エルサレムで殺害されたオルガ・ブロツキーの映像を受け取ったゴダールが描かれる。「神曲」における煉獄編は罪を贖う物語であり、パレスチナやサラエヴォなどの問題を前にどのように前進していくのかを模索する内容となっている。そして、天国編ではあまりにも美しい森の中でオルガが現れ、糧を分け合う。
ゴダールは本作において、社会問題を文学に微分する。ホメロス「オデュッセイア」をはじめとする神話は現実問題を形而上に落とし込んだものであると定義する。これを踏まえると『イメージの本』公開時に、とあるジャーナリストがマイケル・ベイの『13時間 ベンガジの秘密の兵士』を引用している件について質問したことに対し嘲笑ったのも納得がいく。つまり、膨大な映画の引用ひとつひとつは重要ではない。その繋がり全体として意味をもっているのである。『アワーミュージック』ではわかりやすく映画による形而上学と文学における形而上学を並べ、普遍的な問題を見出そうとしているのである。
3.2.「具体」と「抽象」
『アワーミュージック』がなぜ『奇妙な戦争』において重要かが見えてきたのではないだろうか?
改めて『奇妙な戦争』の序盤に目を向ける。映画における「画」は具体的なものを捉えるはずにもかかわらず抽象的な黒と赤の暴力的な線が収められる。語りではパレスチナ問題やロシアのウクライナ侵攻を示唆するようなことが断片的ではあるが具体的に語られていく。
ゴダールの映画史を振り返ってみると、「具体」と「抽象」を巧みに編み込みながら普遍的な問題を映画という媒体で捉えてみせた監督だと分かる。今回は最後のメッセージとして、より力強く「具体」と「抽象」のボディーブローを観客に浴びせていた。
3.3.和解の場としての抽象画
では、最後のメッセージとは、つまり彼の「遺言」とはなんだったのか?
これははっきり「和解の場が必要だ」と言及されている。
抽象的な画により生まれる想像力が、具体的すぎて複雑化する社会問題を解決へと導く。想像することにより互いに歩み寄り国際平和が実現する。これをゴダールは言い残したかったのだろう。
映画は中断される。本作はあくまで予告編であり、本編は存在しない。でも、その本編に想いを寄せることで、ひとりひとりが和睦の使者となれるのだろう。
4.最後に
気がつけば、1万字近くに渡って書いてきた。『奇妙な戦争』に向き合うために1ヶ月ぐらいの時間と10本近い彼の作品に触れた。ジャン=リュック・ゴダールは気難しい人ではあるが、映画人の中でいち早くインスタライブを行うお茶目さがあったりする。時代と生まれる場所が違えば、音MADや猫ミーム動画を作っていたんだろうなという認識であったが、集中的に研究をしていくうちにメディアに対する真摯さに胸が打たれた。
おそらく本作は2024年のベスト映画に選ぶであろう。
まさしくGOD+ART(D)な有終の美であった。
最後に現時点での私的ゴダールベストを貼って、当記事は終わりとする。
読んでいただいた方、ありがとうございます。
P.S.公開日初日にパンフレットを読みたかったのだが、製本が間に合わなかったらしく販売延期となった。最近、パンフレットが公開日に買えないケースが相次いでいる気がする。ひょっとすると物流の2024年問題が映画のパンフレットに影響しているのだろうか。本作に関しては流石にインターネットで有識者による詳しい解説が出回っていないかつ、他の方の見解を伺いたかっただけにとても残念だ。販売されたタイミングで映画館へ再度足を運ぶとしよう。
▲ジガ・ヴェルトフ集団時代に関しては別途動画作りました。
5.私的ジャン=リュック・ゴダール映画ベスト10
1.ジャン=リュック・ゴダール 遺言 奇妙な戦争(2023年)
2.ヌーヴェルヴァーグ(1990年)
3.ウイークエンド(1967年)
4.アワーミュージック(2004年)
5.ゴダールの決別(1993年)
6.パート2(1975年)
7.イメージの本(2018年)
8.はなればなれに(1964年)
9.ゴダールの探偵(1985年)
10.さらば、愛の言葉よ(2014年)
6.参考資料
【映画】
◾️カメラを持った男 Человек с киноаппаратом(1929年)
◾️涎と永遠についての概論 Traité de bave et d'éternité(1951年)
◾️サドのための絶叫 Hurlements en faveur de Sade(1952年)
◾️カラビニエ Les Carabiniers(1963年)
◾️たのしい知識 Le Gai Savoir (1969年)
◾️ありきたりの映画 Un film comme les autres(1968年)
◾️ブリティッシュ・サウンズ British Sounds(1970年)
◾️プラウダ (真実) Pravda (1970年)
◾️東風 Le vent d'est (1970年)
◾️イタリアにおける闘争 Lotte in Italia (1970年)
◾️ウラジミールとローザ Vladimir et Rosa(1971年)
◾️万事快調 Tout va bien(1972年)
◾️ジェーンへの手紙 Letter to Jane(1972年)
◾️スペクタクルの社会 La Société du spectacle(1973年)
◾️パート2 Numéro deux(1975年)
◾️われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを In girum imus nocte et consumimur igni(1978年)
◾️アワーミュージック Notre musique(2004年)
◾️イメージの本 Le livre d'image(2018年)
◾️アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ Babardeala cu bucluc sau porno balamuc(2021年)
【文献】
◾️フィルムメーカーズ[21]ジャン=リュック・ゴダール(2020/8/15、宮帯出版社、宮下玄覇 発行、佐々木敦 責任編集)
◾️カイエ・デュ・シネマ・ジャポン(1991/7/15、フィルムアート社、奈良義巳 発行)
◾️CAHIER DU CINEMA SPÉCIAL GODARD(1991/8/10、カイエ・デュ・シネマ)
◾️スペクタクルの社会(2003/1/8、筑摩書房、ギー・ドゥボール 著、木下誠 翻訳)
◾️ニューメディアの言語 ――デジタル時代のアート、デザイン、映画(2023/7/10、筑摩書房、レフ・マレヴィッチ 著、堀潤之 翻訳)
◾️映画に(反)対して ギー・ドゥボール特集(山形国際ドキュメンタリー映画祭)
【Web】
・Espace Nord"Faux Passports"
・カイエ・デュ・シネマ 歴代トップ10 完全版(1951~2023)!!!(2019/4/20、note、Knights of Odessa)
・第151回 ゴダール、ダコール Godard, d’accord(2022/10、現代思潮新社、鈴木創士)
・Difference and Repetition: On Guy Debord's Films(Giorgio Agamben)
・ギー・ドゥボールの初期映画におけるニュース映画の 「転用」(2023、若手研究者フォーラム要旨集、武本彩⼦)
・スペクタクルの支配とメディア文化(2008/3/1、鎮西学院大学機関リポジトリ、亘明志)
・『サドのための絶叫』(山形国際ドキュメンタリー映画祭)
・『われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを』(山形国際ドキュメンタリー映画祭)
・artscape「レトリスム」
映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。
