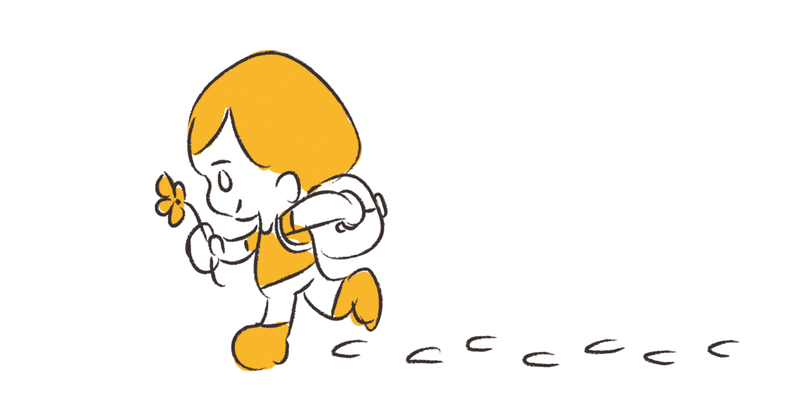
ゼロ距離からの出発 改
昨日、五歳の娘の乳歯が一本抜けた。
永久歯への生え替わりの初めての一本だった。
「ああ、ついに抜けてしまった」と思った。
乳歯は小さな子どもだけのもの。それが生え替わるのは、まぎれもなく、大人に近づくことの証だ。いつもそばにいると思っていた娘が母から離れていく。生え替わりを、もちろん娘と一緒に喜んだが、わたしは少し悲しかった。
五歳といえば、親から離れて、外の世界に踏み出そうと、チャレンジを始め、親が「安全基地」の役割を果たすことにより、子どもは安心して外の世界に踏み出していけるようになる時期とされる。
今のわたしと娘の距離はいわゆる「ゼロ距離」だ。娘は、親というゼロ距離から物理的に少しずつ離れていく年齢になったのだ。
それを歯の生え替わりによって、さらに目の前に突きつけられた気がした。
しかし、この悲しみは、過去にも覚えがある。あれは、何か月の頃だったかな。
娘の下の顎の、何も生えていないピンク色の歯茎に、初めての乳歯がニョコっと顔を覗かせた。
白い色がうっすら見え始め、歯と認識するにはよくわからず、目をこらしてみたり、指でさわってみたりして、硬い感触が手に触れるのを確認して、それがやっと歯だとわかった。
その小さな小さな白い歯は、日に日に成長し、いつの間にその全貌をあきらかにした。
にっこり笑った顔に、下の顎の前歯二本だけが見えた。
覗く白い歯がアンバランスでなんとも言えずに可愛らしかったことを、今も覚えている。
あの時も、歯が生え始めた喜びの裏側には、母から離れる寂しさを感じた。
離乳食を初めて口に運んだあの日もそうだ。
初めての子育てで、離乳食の作り方もよくわからなかったけれど、本を見ながらなんとか作った。
米を茹で、こし器で裏ごしをして、ドロドロに仕上がったその白いご飯。
小指の爪くらいの少量を匙ですくった。
「そもそも食べられるのか?」
「食べたことないのに?」
「本当に食べさせていいの?」
「一体どうなっちゃうんだろう」
子どもを食べさせる体勢に整えて、夫は隣でカメラをスタンバイ。わたしはほんの少しの粥をすくった匙を、娘の口もと寸前まで持っていきながら、内心はそんなことを考えながらドキドキしていた。
いざ、娘の口の中に半分だけ匙を入れて待つ。
しばらくすると「ちゅるっ」っと音がして、そのぷにぷにで柔らかくてとんがった唇の向こうに、吸い込まれていった。
「食べた!」
あの時の感動は忘れられない。嬉しかった。ちゃんと食べられた。成長を喜びながら、またその裏には娘が離れていく日を感じた。
そして、来月には六歳の誕生日を迎える娘。
時々歯茎が痛いとか言い出したのはひと月くらい前だっただろうか。
娘が「ぐあっ」っと大きく開けた口の中を、くまなくのぞいてみても、悪そうなものが見当たらない。娘の痛みの箇所も、痛みも続かない。
「何か歯に当たったのかな?」
「ついに生え替わり?」
「よくわからないけど歯医者にいくべき?」
そんなことを考えながら数日過ごすうち、今度こそ夫があきらかな異変を、娘の口の中に見つけた。
下顎の前歯の後ろ側に、ぴったり沿って、白い歯が生え始めていた。そして、その前にいる乳歯もグラグラしている。
「もう、わたし、お役御免が近づいてきました、おかあさん」ってグラグラの歯が言っていた。
「なんてことだ!」小さな歯が生え並んだ『乳歯フェイス』いわゆる、幼児の小さな顎と小さな歯ならびによる可愛らしいバランスのお顔、の終わりが近づいていた。
そしてついに……。
今日は近所のお祭りに行った。縁日と初めての大きな花火に、娘は大興奮。
花火の音だけで怯えて泣いた、三歳の娘はどこにもいなかった。五歳の娘は「うわ〜、うぉ〜」と激しく手を叩いて喜んだ。
家族三人で見上げた夜空の花火は、とても綺麗だった。
幸せを体に滲ませながら、のんびり自転車で走りながら家路に着いた。
自転車置き場で、自転車を止めていると不意に娘が言った。
「なんか口の中にある」
そう言って開けた娘の口の中の舌の上には、小さな白い破片が転がっていた。
「ああ、ついにきたか」わたしは先にそう思った。
「これ、歯だよ!」
「え?見せて見せて!」
わたしの、手のひらに乗せた歯を見て、娘は嬉しそうに声を上げてにっこり笑った。嬉しくてくるくる回りながら跳ねている。
家に帰るのにマンションの階段を踊るように上がる娘について、わたしも階段を上がった。悲しみも後をついてきた。
娘は、物理的に親から離れていく年齢になった。六歳を間近に控えた夏だ。とうとう、幼児の証であった乳歯が抜けた。
母であるわたしは、それを見て困惑した。人間の当たり前の成長過程である、その事実に。彼女が自分から離れていくことが寂しくなった。
保育園の送り迎えが必要だったり、自分でなかなか服を選べなかったり、体調が悪いとべったりと母に張り付きに、離れないでまとわりつくそれも、終わりが近いことを感じたから。
これから迎える六歳といえば、小学校に上がる。一人で学校を登下校する。一人で着替えをする。大きなコミュニティで自分の力で生きていく。
それは、親の力を借りずに、自分の力で勝ちとっていく自立の力を養う最初の一歩の年。
ただわたしは成長を喜んで応援するだけ。悲しみを後ろに隠しながら。
娘の、花道を願おう。
親の安全基地からの出発。
母と娘のゼロ距離からの出発だ。
------
今、エッセイの練習をしています。以前読んだ「エッセイ脳」をもとに、以前書いた記事を書き直しての練習です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
