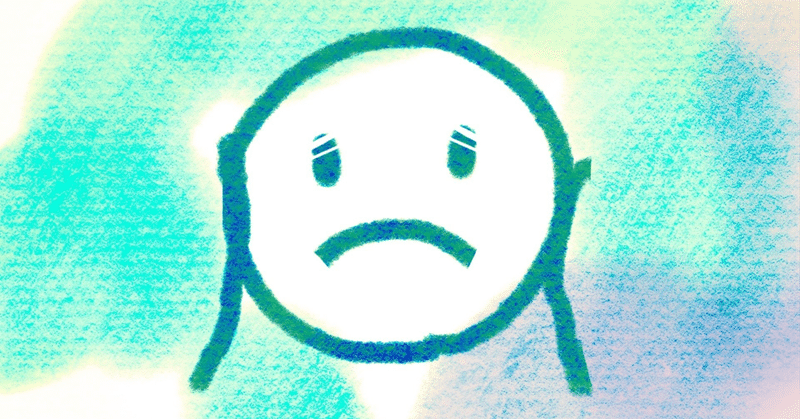
世直しリョウ君 第一話:イタ過ぎたオトコ②
それから月が変わったある日の夕方、僕は仕事帰りに立ち寄った書店でヤツの奥さんに偶然会った。
「あの…さん、ですか?」
笑顔で軽く会釈した彼女だが、声の調子まで優しさと気品に満ちていた。彼女に会うのは結婚式の二次会以来でまだ二度目だが、僕にはすぐに彼女だと分かった。
「…コイツ、使えねぇ新人クンでさ、オレが面倒見てやってるんだ。」
式の二次会で僕が挨拶した時の、ヤツのコトバだ。酔って上機嫌だったが、隅々まで無礼とか不躾とかいう表現でしか言い表せないようなイタさが溢れていた。『彼女が誰を好きになろうが僕には関係ないが、でもよりによってどうしてコイツなんだろう?先の苦労が見えないのだろうか?』
僕は作り笑顔で新郎新婦に挨拶をしつつ、ココロではそんなことを考えていた。
「ご無沙汰しております。先日はありがとうございました。」
僕たちは互いに社交辞令な挨拶を済ませ、それじゃあとお別れしようとしたのだが、その時僕は彼女の顔を見つめてふと気づいた。何かを言いたそうな、何かを聞きたそうな、そんな表情に見えた。下手に関わってヤツに絡まれるのも面倒だったが、それよりも僕は彼女の現況が気になっていた。
「あの、何かありましたか?失礼ですが、そんな風に見えたので…。」
僕の意外なコトバに彼女は驚いたようだったが、でも意を決したように僕に相談を持ち掛けた。
立ち話も何なので、と近くの喫茶店でお茶をしながら彼女のハナシを聞くことになった。ヤツと結婚するくらいだから、このヒトも実はそれなりにヤバめのキャラなのかも…となかば警戒と期待を抱きつつ、僕は彼女の前に腰を降ろした。親しい訳でもなく、所詮はダンナの職場で働く後輩新人。僕らの関係性はその程度だ。だから僕はその第三者感を利用して、赤の他人だから大丈夫とさり気なく彼女を誘導した。
「あの、主人って会社ではどんな風なんでしょうか?」
彼女は言いにくそうにしながらも、胸の内を吐き出すように僕に聞いた。
「どういうことですか?逆に、家ではどんな風なんですか?」
ここでは僕は聞き役に徹した方が良い。僕は彼女から情報を引き出し、彼女の不安や不満の根っこを聞き出そうとした。
「あの、こんなこと言いにくいんですけど…」
そう言って、彼女は胸の内をおずおずと語り出した。後で聞いたのだが、最近ヤツに『アイツ、意外に話が分かるんだよ。オマエより遙かに話が通じる。』、そう言われたらしい。
どうやら彼女のハナシに寄れば、彼女は俗にいう「お嬢様育ち」のヒトだった。あまり世のオトコを深く知ることもなく、有名企業の役員をしている親戚叔父に進められるままに今回の結婚に至ったそうだ。知人友人も年収や職業からヤツを優良物件として認定していたそうだ。未婚の僕には想像できないが、意外と結婚してから相手の本症を知る。そして自らの見る目のなさを後悔する。初婚時の高揚感や夢はそうして呆気なく崩れていくモノのようだ。最近の晩婚化や未婚率の上昇は、この情報化社会にあっては当然のことなのかも知れない。彼女も今にして思えば???と思うことは多々あったものの、周囲の羨望や嫉妬に囲まれ流れに任せるまま結婚に至ってしまったようだ。
「あの、上手く言えないんですけど、主人って少し変わったトコがあるんじゃないかって、普通じゃないトコがたくさん見えてきて…それで色々悩んでるんです。」
彼女のコトバはおよそ予想通りだった。ヤツにこの件が知られることは、かなりの面倒事には違いない。でも少なくとも彼女もまた被害者のひとりであり、僕が無関心でいるには何かしら後ろめたさを感じていた。
「そうですね…。でも…さんも少なくともご主人に惹かれてご結婚されたんですよね?」
「…そう言われると…何も言えなくなっちゃうけど。でも、そうね。私って、きっと舞い上がって何も見ていなかったのかも…」
『他人の不幸は蜜の味』昔の日本人が好んだ言葉だ。僕は正直あまり好きではなかったが、でも彼女のコトバに胸が沸き立つような思いがして、僕は浅ましい自分をひとり恥じた。
イラストは、いつものふうちゃんさんです。
いつもありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
