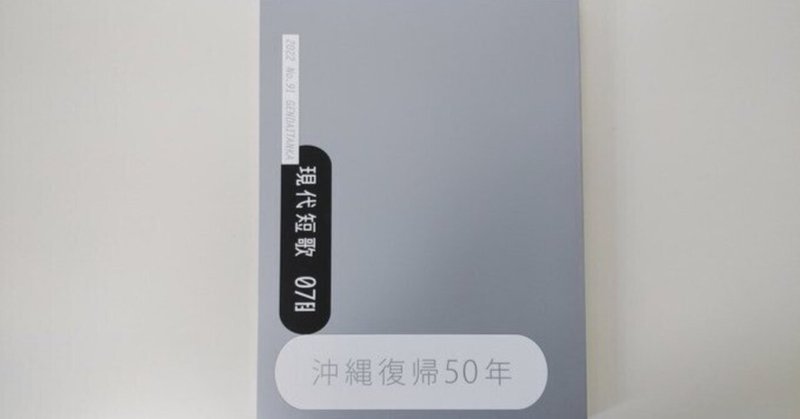
『現代短歌』2022年7月号
この号の特集は「沖縄復帰50年」。とても読み応えがあり、夢中で読み耽ってしまった。何かが分かったとはまだとても言えない私だが、この特集を読めて良かったと思う。
①いづこからいづこへ返還されたるか琉球諸島は青海(あをうみ)のもの 川野里子 人間が引いた境界線によって所属が決められる土地。しかし土地は本来人間に属しているのでは無い。土地はその土地のもの。沖縄の歴史と現在を、伝統的な機織りの音を通奏低音として詠った連作。
②中程昌徳「「祖国」をめぐって」〈戦後三〇年目、「復帰」から四年目にあたる一九七五年には、早くも「吾を救う何物もなしさわやかに胸の中なる祖国を捨つる」(平山良明)といったような歌が出てくる。「祖国」への幻想を捨てたことで清々したというのである。〉
〈「復帰」四〇年を迎えるころになると、そのように「祖国」とはもう呼ぶまいといった歌が出てくる。そして「祖国」という語も消えていく。「死語「祖国」はた詩語「大和」いくたびとなく聞く日ぐれなかなか暮れぬ」(豊島英子『黄金森』一九九五年)の歌に見られるように、「祖国」は、すでに「死語」となりつつあったのである。〉
寺山修司の「マッチ擦る…」の歌から説き起こして、沖縄にとって「祖国」とは、を論じた文。復帰した祖国への失望。祖国という語の消失にそれが表れている。読まれるべき文だ。
③屋部公子選「復帰50年沖縄のうた50首」
命あるはかく燃ゆべしと火炎木の啓示するかに咲き極まれり 平良好児
軍命のわずか二文字を復活せむ死ぬべきでなかった人たちのため 古堅喜代子
ただに散る大和の桜思うとき散らぬ愚直の島の緋桜 伊波瞳
伝聞でガイドの語る戦争を伝伝聞で語る日の来ん 屋良健一郎
屋部公子〈伊波瞳作〈ただに散る〉は、散華の精神が沖縄に移植された異文化であることを桜の対比によって伝えている。(…)屋良健一郎作〈伝聞の〉は、体験者が減り、ガイドも伝聞で語る時代の先に「伝伝聞」の時代が来るという。その時に果たして過去の戦争は正しく伝わるか。危惧が湧く。〉
この特集の良いところはアンソロジーが全部で4つあったこと。人によってアンソロジーは違いがある。屋部のアンソロジーから好きな歌を4首選んだ。火炎木や緋桜などが背景として心に残る。
④伊波瞳選「沖縄のうた50首」
樹によれば樹、地に臥せば地の命なり 弾(たま)はずれ来て我を生みし母 仲西正子
きんいろの巨大な象が土砂吸って吐いて官邸埋めてゆく 夢 島袋香代子
伊波瞳〈辺野古新基地建設への抗議の歌が現在まで続いている。基地の歌ばかりというが、それが現実なのだ。〉
伊波の言葉は重い。島袋の歌は夢の形を借りた願望の歌だが、最後に一字空きで「夢」と付けたところに、夢でしかない歯がゆさが感じられる。初句二句のイメージに惹かれる。
⑤平敷武蕉「怒りと抒情 玉城洋子歌集『儒艮(ザン)』を中心に」
〈「山羊だった真っ黒こげのまう人でない児がリヤカーに乗せられていった」宮森小学校を襲った米軍ジェット機墜落事故を詠んだ歌である。当時、事故現場近くにいた玉城は、現場に駆け付け、地獄の惨状をむざむざと目撃している。〉
ここに引かれた玉城の一首はこの特集の中で最も衝撃的だったもの。その衝撃の元は初句の比喩だ。真っ黒になるまで焼かれた山羊のような、もう人間ではない子供の身体。この比喩がまず胸に飛び込んで来るのだ。しかし、小学校に米軍機が墜落、という事件を詠んだ歌の比喩を云々する時に兆すこの罪悪感をどうすればいいのだろう。こうした事件に対し修辞を使って力ある歌を作るのはあるとして、その修辞を「効いている」というように評するのに心理的な抵抗がある。
玉城の歌集タイトルのザンはジュゴンのこと。辺野古の歌から論は説き起こされている。
⑥名嘉真恵美子「沖縄の短歌半世紀をふりかえる」半世紀を振り返った、示唆に富む文。特に4章の「小高賢氏の批判について」に考えさせられた。論の最後の明るさにも感動した。ぜひ多くの人に読んで欲しい論だ。
⑦屋良健一郎選「沖縄の歌50首」
灯を持ちて魚に近づくキジムナー赤(あか)ら髪(がんたー)が月にほろほろ 平山良明
ごぼごぼと大型ヘリが兵を産む真昼一陣の疾風はたてり 新里スエ
嘉間良(かまら)坂下り行くときしろがねに街の屋根より海高く見ゆ 佐久本進
「まーだだよ」洞窟(がま)の奥から聞えてくる幼友達かー子の声が 大城静子
城跡に薄紅色の捩花が時のらせんをのぼりつつ咲く 伊波瞳
とても印象的な歌が多かった。大城の歌は2003年の歌集から。戦争末期にがまの奥に入って行ったままの幼友達の声が聞こえてくるようだ。
⑧吉川宏志「連作と沈黙と」〈戦中世代や戦後まもない世代は、沖縄戦で多くの無辜の人々を死なせてしまった罪悪感が強く、旅もできず、歌うこともできない、という後ろめたさや恥の意識があったのである。「沖縄行を拒みて過ぎつ海に消えしひめゆり部隊と同世代ゆゑ 尾崎左永子」という歌が、その心情をよく表しているといえよう。〉
私が子供の頃、周囲の大人たちが、時々、こうしたことを言っていたことを思い出した。
2022.7.6.~7.Twitterより編集再掲
