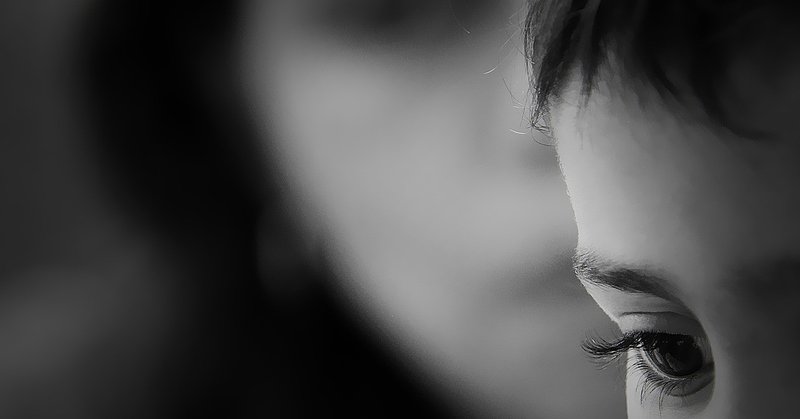
「わかってほしい」気持ちと「解決したい」の距離
息子の小1からの友達Ken。息子と同じ自閉症の診断を持ってる。
Kenには「怒り」の感情がない。
ないっていったら語弊があるかな。
「自分の気持ちを表現するのに”怒り”を使う選択肢がない」って言う方が近いかな。
とにかく、Kenは怒った事がないんだよね。
例えば、みんなで遊びに行く場所を相談している時に、自分の意見がことごとく却下されてる状況で「もう!僕は○○に行きたいのに!!!」って言っても良さそうな場面でも、それを怒りで表現しないんだよね。その代わりに「あ~僕の意見もきいてほしいな」「だれか聞いてくれないかな」「チャビ君なら僕の気持ちわかってくれるよね~」と言い続け理解者を求め続ける。
そんな場面を見てる大人は、「じゃんけんで決めたら」「多数決にしたら」ってその場をうまく解決しようとしがちだけど、Kenはそういう時いつも言うんだよね。「違うんだなぁ~。僕は僕のはなしをきいてくれる人がほしいんだなぁ~」って。
そんなKenを見てると幼かった頃の息子と重なるんだよね。
今でこそ「あいつには腹が立つ!」とか「これは許せない!」って怒りの感情を表出するようになった息子だけど、昔は”怒り”よりも「自分の事をわかってくれない辛さ」にフラストレーションを感じて、それを悲しい感情として表現してたんだよね。「自分の思い通りにならない怒り」よりも「自分のことをわかってもらえない悲しさ」。
パニックはまさにそんな感じだよね。怒りじゃない。辛さ・悲しさ・わかってもらえないフラストレーションの表現。
発達障害の人たちは、こんな「わかってほしいのにわかってもらえない」フラストレーションを日常的に抱えてるんだと思うんだよね。
息子にアスペルガーの告白をした後から、息子が度々口にするようになったのは、「僕は、僕のことわかってほしいんだよ。わかってくれる人がふえてほしい。障害があって辛い事もあるけど、僕は僕が好き。だから治してほしいなんて思わない。僕のこと変えてほしいわけじゃない。僕のこと、理解してほしいだよ。だから僕のことをわかろうとしないで、変えようとする人がいたら悲しくなる」と。
Kenにしても、息子にしても「大人がよかれと思う自分の意思そっちのけな解決」より「理解者」を求めてるんだよね。
でも、時として大人や支援者は、”その子の気持ちの理解”や”その子の気持ちに寄り添う”ことよりも「事態を解決する」ことに躍起になりがちなんだよね。
例えば、不登校の子がいたら、大人は「不登校」を解決するのに躍起になるケースが多いよね。「なんとか学校に行ってもらいたい、学校に来てもらいたい、解決してあげたい、解決したい」。
でも不登校の子からすると「自分の気持ちがわかってくれる人がほしい」「私の気持ちを理解してほしい」であって、「学校に登校する」っていう大人からみたら「解決」だけど、子供にしてみたら「まず、私の気持ちによりそってほしい」なんだと思うのね。
字が覚えられない・書けない子の場合、大人は「書けるようにしてあげたい」って解決を求めちゃいがちで、「この方法はどう?あの方法はどう?」と解決する為にあの手この手に一生懸命になりがちだけど、子供にしたらまず「書けない悔しいきもち」「頑張っても頑張ってもできないフラストレーション」に寄り添ってほしいかもしれない。
こんな風にね、「その子がわかってほしい気持ち」と「大人にとっての解決」は、イコールじゃない事って多いと思うんだよね。解決を急ぐと、子供が本当に求めている事が置き去りになっちゃうかもしれない。
「あ~僕のきもち、きいてほしいなぁ」とちょこんと私の横に座ってきたKenを見ながら思ってたことを書いたのが、今日のnote。
たくさんの方々に読んでいただいたり、支援方法を参考にしてもらえたらと思い記事を無料公開していますが、 今までもこれからも勉強を続ける私の為に「投げ銭」という形でご支援いただければすごく励みになります。 よろしくお願いします。
