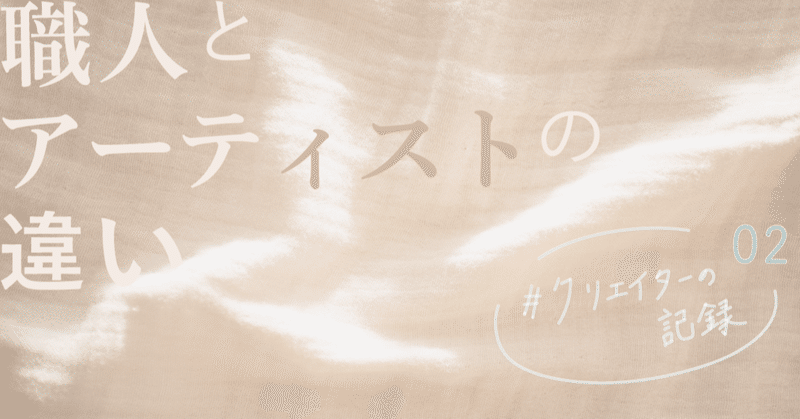
職人とアーティストの違い
これは無駄話だが・・・
昨年までの私からすると、
SNSは素敵な写真の展覧会会場でしかなかった。
デザインの勉強のために他者を真似て
Twitterでの発信や情報収集をし始めたのだが、これが結構苦手だ。
こう思うのは
「壁打ちしている」感覚を感じるからだと思う。
明確な相手がないのに発信するのって「壁打ち」に過ぎないと思う。
自分もラケットを持っていて打ち返す技術があれば
壁打ちの間に入ってラリーにしたり、
「あ、これはコート外。」とスルー出来る。
技術がない、ラケットがない人は
身のまま壁打ちの中に入ってボコボコになる。
私はラケットも技術もない。
壁打ちのやり方も確立できていないから苦手なんだろう。
他者の壁打ちを見て、傷ついたり悩むことも多々ある。
他者のツイートを見て、考えていた
以前Twitterで
「意匠はうまいけど、デザインはできていない人がいる」というツイートを見た。
また、スクールや独学デザイナーもよく言っている
「デザインにセンスは不要。勉強で誰でもできる」というフレーズ。
私から見るとデザイナーってセンスがあるし、独自性があるしで
良くわからなかった。
だが最近『13歳からのアート思考』をはじめ、いくつかの本を読んでなんとなく理解した。
デザインの腕を磨くということ
デザインに関する本は昨年からいくつか読んではいたが
最近読んだ『インタフェースデザインのお約束 ―優れたUXを実現するための101のルール』が
デザインとは何かを明確に教えてくれた。
人は特性によってこのように捉えるから、
過去に作られたものを継承した方が使いやすいと感じるから、
オリジナリティは極力省きなさいということが書いてあった。
筆者の“強く言いきる口調”のおかげでもやもやした認識が消えたかもしれない。
デザインは
・人の特性を踏まえる
・人が抱く共通的な感覚に従う
これにより上手く作れるのだと思った。
だからこれを知識として貯めて実践できれば、デザインの腕は磨ける。
職人的なものだ。目を養って腕を磨けば一人立ちできる。
だから、"デザインができる"までがゴールなら「センス不要!」なのだ。
ただ、デザイナーとして活躍したいのであればそこから先は違う。
職人ではなくアーティストになっていくのだと思う。
アーティストになるとは
『13歳からのアート思考』を読んだ。
学生時代に学んだ美術は
技法に沿っていたり、よりリアルで綺麗なものが評価される教科だったような気がする。
この本で美術、アートに対する見方が変わった。
アートは皆が同じように書いているものを捉えたり、同じ感覚を覚えたりするように制作するルールはない。
上手いとか下手とかそんな概念はない。
自分のとらえ方でいい。型など存在していないのだ。
主観的、人と違う、自分なりの考えを沢山貯め混んで温めて
やっと表現できたものがアートであり、アーティストであった。
『好きなものを「推す」だけ。共感される文章術』を読んだ。
文章をうまく書くために小手先のテクニックをつかみたいと思って買った本。
きっと筆者側もそのように使用することを想定しており、先で言う
『インタフェースデザインのお約束 ―優れたUXを実現するための101のルール』のような教本的な本だったはずだ。
しかしこの本はまさしくアートであった。
まず筆者の文章は、テクニックで面白いのではない。
筆者が持つ膨大な教養や考え方が面白いのだ。
テクニックの例文でさえも
モノに関する背景や歴史、想像もできなかった考えがポンポン出てきて
「ん?なになに?」と惹かれていってしまう。
様々な知識を蓄えて、深く考え
やっと外に出している文章なのである。
筆者は推し文職人で売っているのだが、押し文アーティストだと思った。
仕事としては職人、人としてはアーティスト
結論思ったことは
お金を稼ぐには人を知り、人が好むのものを作る必要があると思う。
なので職人を目指し、腕を磨くのが良いと思う。
アーティストはたぶん、人生をかけて積み重ねないとなれない。
そしてお金を稼ぐまでに時間がかかる。
でも、積み重ねてやっと出すモノは面白い。職人が作ったモノよりも何倍も人を惹きつける。
いま、私は目指しているものが明確ではない。
ただ、他者の正解に擦り寄せていくような仕事としてのクリエイターはやりたくない、そう思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
