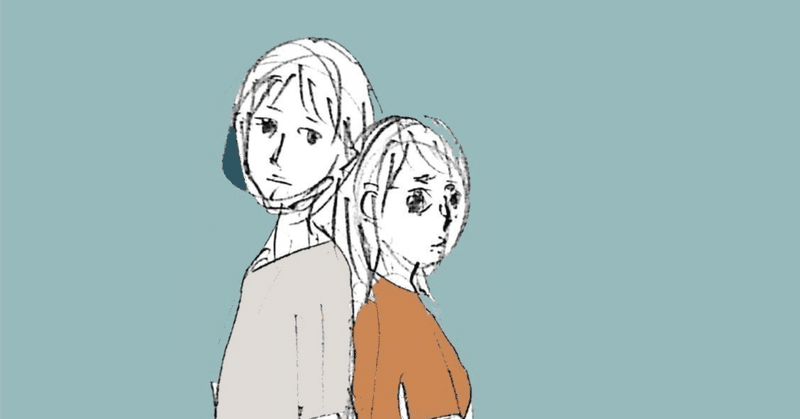
【短い物語】 リサと私はベスト・オブ・ベスティー
リサが私を不安げにチラッと見た。村井さんが変なこと訊くからだ。どうして私とリサが仲良くしてるのかなんて、変なことを。
学食のテーブルを挟んで私らの向かいに座っている村井さんは、全然悪気なんて無さそうに私らの答えを待っている。リサはどうせ答えないだろうから、私が答えることにする。いつものことだ。
「なんとなく、気が合ったんですよね。学部も一緒だし」
そうなんだ、と、つまらなそうに村井さんが言うと、リサが隣でそう、そう、と頷くのが分かった。
リサは別に無口なわけではない。自分自身のことについて尋ねられれば、すらすらと、丁度良い笑みを浮かべて、誰にでも好かれやすい口調で答えることができる奴だ。けれど、私との関係性については、絶対に自分から何か言葉にすることはしない。それに気づいたのは、リサと話すようになって数ヶ月後のことだった。
一般的な「友情」というものが何を指すのか私も漠然としか分かっていないけれど、たぶんリサと私の関係はそれよりもう少し強い結びつきだと思う。でも恋愛関係というわけでもないし、性的な関係があるわけでもない。
どこで出会ってくるのか、リサはしょっちゅうろくでもない男と付き合いだしては、私に紹介する。そういう男らは皆、リサをリュウと呼んでいた。
自分を女だと思ってないような奴と付き合って、つらくないの? そうリサに問うても、リサは決まって、照れたような顔をくしゃっとさせて言うのだ。
「でも、しょうがないよ」
だから私は、三人目のケンタロウって男以来、そういうことをリサに言うのはやめた。
私は私で、面白みのない男と大して意味のない付き合いをしては、リサに紹介しようかななんて思っているうちに、別れることになるのだった。
男同士の恋愛なんてそんなもんだよね、と言うと、リサはすごく真剣な顔をして「そんなことない、いつかいい人と出会えるよ」と励ましてくれる。そうだよね、きっと、なんて思いながらも、私は同時に、別に「いい人」なんかに出会う必要はないかもしれないなんて思っている。大学の授業もまあまあ楽しいし、毎日のようにリサと昼ごはんを食べたり買い物に出かけたりして、時々マッチングアプリで出会った男とセックスしてる、そんな日々で、別にいい。
「ノンバイナリーでゲイって、どういうことなの?」
村井さんは好奇心の塊だ。世界中の好奇心を集めて電気を通したかのように、両目がキラキラと輝いている。あまりにも眩しくて、私はついイラッとするのを忘れてしまう。
男でも女でもないのに「同性」愛を意味するゲイという言葉を使っている私が不思議なんだろう。でもそんなの私だってよく分からない。自分はゲイってやつなんだろうなって思って育ったから、今更その言葉を手放したら自分が何者だか分からなくなってしまいそうで、とりあえず考えることを保留しているだけだ。どう答えようかなと言葉を探していると、リサがいつもの穏やかな微笑みを浮かべて言った。
「カテゴリーって、やっぱ取りこぼすものがあるんですよね」
リサはこういう時に、その場の誰も傷つけない言葉を咄嗟に思いつく。かっこいいなあ。
「自分自身を説明する言葉って、常に不十分だから」
リサの少しだけ哲学的な表現で煙に巻かれた村井さんは、口を窄めて「じゃあさ」と続ける。
「リサは、トランス女性ってカテゴリーに、必ずしもしっくりきてるわけじゃないの?」
「私は別に、しっくりきてなくはないかなあ、って感じですね。女性だし、トランスしてるし」
ふうん、よかったね、と村井さんが言うので、今度はきちんとイラッとできた。そういうところだ、と思った。リサと私の間には、そういうのが無いんだよ村井さん。カテゴリーの狭間に落っこちちゃったような私を、リサは絶対に否定しないんだ。私も私で、カテゴリーからカテゴリーへと移行しているリサを否定しないし、したくない。私らはだいぶ違うけど、それでも私はリサが好きだし、多分リサも私が好きだから。
村井さんが食べ終えた食器をトレイごと持ち上げて立ち上がる。椅子が勢いよく後ろに跳ねた音がした。ニカっと笑って「じゃ、俺この後インターンだから、またね」と言うと、いつもの意識高い系の速度ですたすたとトレイを返却口に置き、食堂を出て行った。
「村井さんってさ、ちょっとかっこいいよね」
テーブルが二人きりになった瞬間にリサが言った。私は目一杯顔を歪めることで、それをリサへの返答とした。
