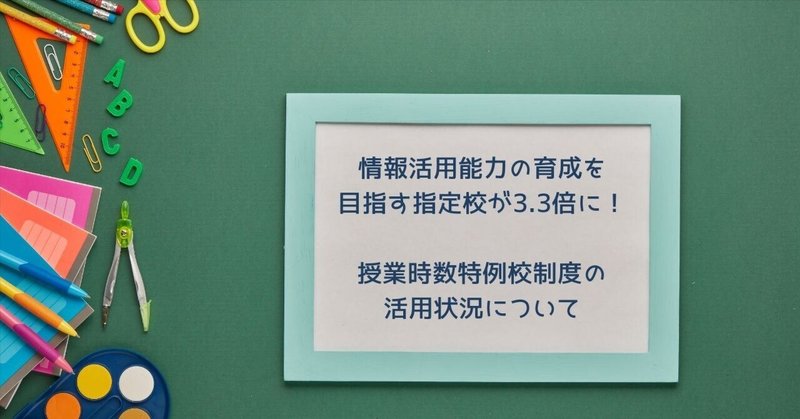
情報活用能力の育成を目指す指定校が3.3倍に!授業時数特例校制度の活用状況について
こんにちは。みんなのコード政策提言部の田嶋です。
小・中学生のころ、「なんでこの教科は毎日あるのに、あの教科は1週間のなかで少ししかないんだろう」と、時間割を見ていて不思議に感じたことはありませんか?ちなみに私は、小学生のころ「毎日国語と算数だな、もっと理科で観察・実験をしたいな」と思っていました。
義務教育段階(主に小・中学校)では、学校教育法施行規則という法令によって、各教科等の学年ごとの年間授業時数が「標準授業時数」として定められています。
昨年度から、その時間数を一定の枠内で変更することを認める「授業時数特例校」制度が始まったことをご存じでしょうか。
今回は「授業時数特例校」と、その制度を活用している学校についてご紹介します。
学校の新たな可能性?「授業時数特例校」とは
標準授業時数と授業時数特例校について、文科省は以下のように説明しています。
標準授業時数について
学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するのに要する時数を基礎として、学校運営の実態などの条件を考慮して国が定めたもの
授業時数特例校について
学校や地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、総枠としての授業時数(各学年の年間の標準授業時数の総授業時数)は引き続き確保した上で、教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習活動の充実等に資するよう、カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の幅の拡大の一環として、教科等の特質を踏まえつつ、教科等ごとの授業時数の配分について一定の弾力化による特別の教育課程の編成を認める制度
この2つを簡単に要約すると、
国は学習指導要領で示している内容を指導するのに、このくらい必要だろうという時間数を各教科等ごとに定めている
より効果的な教育を行うのであれば、授業時数特例校を申請して授業時数の配分を変更しても良い
ただし、各学年の総授業時数は確保する必要がある
ということです。
制度の概要をより詳しく見ていくと、具体的には各教科等の授業時数について、1割を上限に標準授業時数を下回って教育課程を編成することが可能です。下回ったことによって生じた授業時数を別の教科等の授業時数に上乗せし、教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習活動の充実に資する教育課程を編成することができるのです。

なお、上乗せした時間で充実させる学習活動としては、以下のような内容が例示されています(一部抜粋)。
学習の基盤となる資質・能力(言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力 等)の育成
現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成(伝統文化教育、主権者教育、消費者教育 等)
※ 複数の学習活動に取り組むことも可能ですが、受験対策のみを目的として、特定の教科等の授業時数を増減させることは、制度の趣旨に沿わない旨も言及されています
授業時数特例校の活用方法とは
例えば、小学校において、国語・算数・理科・社会の時間で断片的に実践していた情報活用能力の育成に関する学習活動を、より効果的に実施したいと考え、4教科の時間を減らす代わりに、総合的な学習の時間に上乗せし、まとまった時間の中で体系的な学習活動を行う、といった活用方法が考えられます。
私たちは、この制度を、学校裁量の幅を拡大させ、情報教育を充実させたいと考えている学校が活用できそうだと注目していました。ところが、開始初年度である2022年は、指定を受けた学校は全国でわずか28校にとどまっていました。
制度の概要等が十分に周知されていないのであろうと考え、ました。そこで、授業時数特例校制度(以下、本制度)がどのようなものか知りたい、実際に活用している事例を聞いてみたい、という学校現場の要望に応えるため、2022年8月に「一歩先の情報教育を考え、授業時数特例校に」と題したセミナーを開催しました。
本制度の概要のみならず、実際に制度を活用している東大和第八小学校、戸田東中学校の両校長をお招きし、取り組みの具体例や申請を決めたきっかけなどをお話いただきました。

情報活用能力の育成を目指す学校が3.3倍に!
2023年度に指定された学校は、2022年度の約2.8倍、77校まで増加したことが確認できました!の指定校の一覧はこちらのページから確認することができます。また、指定校のうち、「情報活用能力の育成」を目指す学校数は2022年度の16校から53校へと、実に約3.3倍増えています。
上乗せした時間で充実させる学習活動は、上記でご紹介したものを含む17の内容に分類されています。そして、最も多く取り組まれている学習活動が「情報活用能力の育成」であることにも注目したいと思います。
本制度を利用していない学校も相当数あることを考慮すると、多くの学校現場は、まとまった時間を確保して、情報活用能力の育成に取り組む必要性を感じているのかもしれません。
千葉県印西市立原山小学校の事例
本制度を活用し、情報活用能力の育成を目指す学校の一つに、千葉県印西市立原山小学校があります。みんなのコードと印西市は今年4月に、新しい情報教育に関する連携協定を締結し、推進校において、先進的な情報教育の共同研究を実施することをこちらの記事で公表しています。推進校の一つが原山小です。
原山小では、低学年の生活科や中・高学年の総合的な学習の時間を年間25時間増やすことで、「SDGsやコンピュータサイエンスなどについての探求的な学習」の内容を充実させています。そこで、みんなのコードは、カリキュラム・授業開発等をご支援させていただいています。
先日、AIに関する全8時間の授業づくりを支援しました。うち2コマでは、児童が文章生成AIのしくみや特性を知り、実際に使ってみることで、どうすればうまく使えるか、何に気を付けるべきかを授業の中で学びました。
生成AIどう使う、千葉・印西市の小学校で体験授業 日本経済新聞 千葉県版.
2023-06-15
こうした先進的な実践が可能なのは、本制度を活用しているからです。そして、学校全体で児童にどのような情報活用能力を身につけて欲しいかが整理され、そのために必要な時間数を確保できていることが大きな要因だと考えます。
本当に、子どもたちにとって最良なのか?という目線
「既存の授業時数を減らす」という事実だけに着目すると、教科書の内容が終わらないのではないか、学力は下がらないのだろうか、と不安を抱く方も多いかと思います。
しかし、本制度は、「授業時数を柔軟にして、先生方が工夫できる余地を増やした方が、目の前の子どもにとって良い結果となりうるのではないか」ということを問いかけているのではないでしょうか。
子どもたちの実態は、地域や学校によって様々です。先生方が受け持つ児童生徒を見ながら、授業時数という制約を超えて、もっと自由に教育課程を編成したい。そうすることで、効果的に資質・能力を育成したいと考えている先生方も多くいらっしゃるはずです。
そんな先生方は、例えば、教科Aの教えるべきことを教えずに、教科Bを充実させようと考えているのではありません。教科Aで育成したい資質・能力を、教科Bと合わせた方がより子どもたちの力がつくのではないか、と考えているのです。
現在行っている教育以上の、あるいは新しい形があるのではないか。現場の先生方は日々、自問自答しながら子どもたちに最良の授業を行っていらっしゃることと思います。
子どもたちのことを考えて創意工夫しようとしている先生方を応援する「授業時数特例校制度」の活用が、今後、より拡大することを願っています。
=========================================
ここまでお読みくださりありがとうございます。
みんなのコードは、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに掲げています。2015年の団体設立以来、小中高でのプログラミング教育等を中心に、情報教育の発展に向け活動し、多くの方からのご支援をいただきながら取り組んでまいりました。
私たちの活動に共感いただき、何かの形で応援したい、と思ってくださった方は、みんなのコードへの寄付をご検討ください。
https://support.code.or.jp/
引き続き、21世紀の価値創造の源泉である「情報技術」に関する教育を充実に向けて、これからも取り組んでいきます。
■公式ホームページ
https://code.or.jp/
\SNSもやっています/
■Facebook
https://www.facebook.com/codeorjp/
■Twitter
https://twitter.com/codeforeveryone
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
