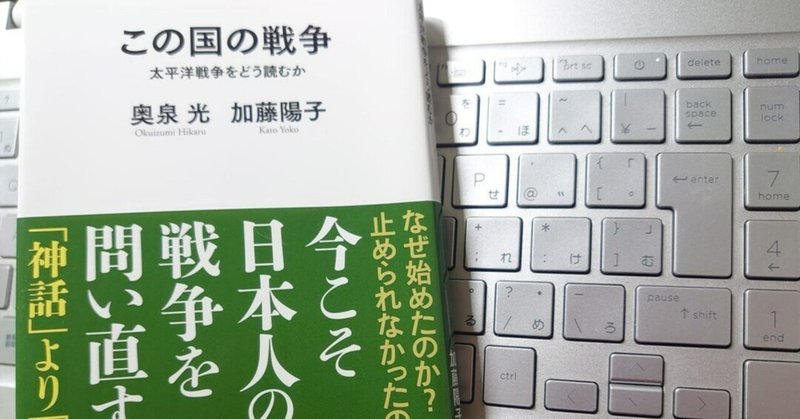
読書メモ「この国の戦争 太平洋戦争をどう読むか」
加藤陽子が日本の先の戦争について一般向けの書籍を書くとき、常にふたつの問題意識が示される。
①なぜ開戦を止められなかったのか?
②なぜ、ボロボロになっても戦争をやめられなかったのか?
加えて、「後世の人間は歴史の「物語化」とどう対峙すべきか」という通奏低音が流れ、終盤には主旋律をなすのが本書の特徴。3章目だけでもとてもおもしろく勉強できると思う。(おもしろく、というと語弊があるが‥‥)
明治以降の日本は、日清、日露、満州事変、日中戦争そして太平洋戦争といくつもの戦争を戦った。
なぜ、それらの開戦を止められなかったのか?
たとえば、国や軍隊のような組織は(私たちの職場や学校と同じように)一枚岩ではない。複数の意思や派閥がある。自分たちも相手もそうだから、合意形成や意志疎通が難しい。直前まで戦争を回避すべく交渉をしていた日米が結局開戦することになったのは、互いに意思を「読み違えた」結果だというのが現在の通説らしい。
また、国や軍は往々にして、真の目的を隠し、「表向きの理念」をこしらえ、国民の感情に訴える宣伝をする。いわゆるプロパガンダだ。
たとえば、満州事変に際しては、2タイプの宣伝をした。
知識層には、「条約を守らない中国が悪い」という批判。
農民層に向けては、「満州の土地をもつチャンス」。
そのようなプロパガンダが浸透するのは、国民の側が受け容れやすい物語を求めているからでもある。生活が苦しければ不満のはけ口を求め、わかりやすい敵や救世主が歓迎される。国家のために犠牲を払えば、それに報いる成果を求める。
日露戦争では10万人の戦死者と未曽有の戦時増税。
日中戦争がはじまって3年が経つ1940年には、85万人が大陸に出兵し、翌年12月の真珠湾攻撃までに既に20万人の将兵が戦死していた。
多大な犠牲を強いられた国民は、それに見合う大義や戦果を求める。
その熱量は、アメリカとの開戦を後押しする燃料の一部にもなった。
国民ひとりひとりの命は鴻毛より軽くても、「スイミー」よろしく、その声がまとまって「群衆」「世論」となれば強大で、国家や軍によるプロパガンダは、時に想定以上の効果を上げて、国や軍への追い風・圧力にもなるのだ。
さらに、実際に戦争が始まると、情報が厳しく統制される。
正しい情報が得られない中、長引く戦時体制に疲弊・窮乏し、思考力・判断力の鈍った国民は、荒唐無稽な物語を受け容れてしまう。
たとえば、
「敵は大和民族の殲滅を図っている。負ければ男は全員去勢される」
のような。冷静に考えれば、そんなことは不可能だとわかるのに。
一方で、特攻機で出撃する兵士が口にする「天皇陛下万歳」には、親兄妹や故郷の山河のイメージがかぶせられていたりする。
どちらも、「国家と個人のあいだに社会というものがなかったことを示している」と本書では考察される。
敗北が確実になっても一年以上戦争を止められなかった原因は、国民が国家に直結してしまったからだと。
「社会が必要だ」というのは現代に通じる教訓だ。
日本の戦死者の圧倒的多数は、1944年秋以降のもの。
敢えて歴史に「たられば」をいうなら、1944年6月、サイパン陥落で敗戦を認めていれば、それ以降の死者の大多数の命は救われた可能性が高いといわれている。
国や軍によるプロパガンダも、国民の「戦争のために多大な犠牲を払った」という記憶も、物語の一種だ。
人は物語でしか物事を理解できない。個人が体験した戦争を語るときも必ず物語になる、なってしまう。
その弊害から逃れるには、数多く、多方面の声を集めて戦争を「立体的に」立ち上がらせること。
また、作家や歴史家は、たえず物語に批評性を持ち続けなければならないと著者2人は述べている。
たとえば、戦争の物語を伝える資料には、血沸き肉躍る勇壮な戦闘が描写される小説や、家族や郷土への愛惜と高邁な志が綴られた特攻兵の遺書がある。
それだけではなく、来る日も来る日も先輩兵に殴られる恐怖に怯えていた兵士や、対ソ戦向けに作られた超重量級の大砲(据え付け用)を押しながらフィリピンのジャングルや川を空腹のまま何十キロも行軍させられた兵士の声にも耳を傾けなければならないということ。
個々の戦争体験は、本人にとってはまぎれもない真実である。しかし、ひとつの物語に戦争の姿を代表させて普遍化・固定化してはいけない。
「ある意味眉に唾をつけつつ、しかし絶対的に尊重しつつ新鮮に聴く」という態度は、インタビュアーのはしくれとしても、とても腑に落ちるものだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
