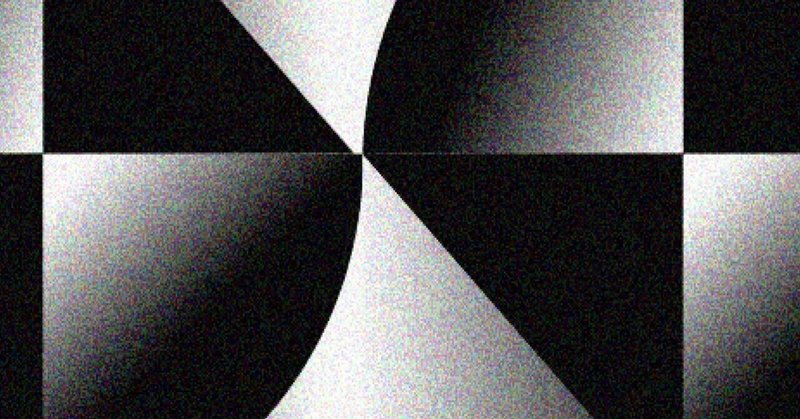
短編小説『孔』
よほど遅くまで残業しない限り、会社帰りに必ず会える猫が居る。猫はかわいい。大好きな生き物だ。一ヶ月ほど前から、その茶トラ猫の居る辺りに、べつの猫が居つくようになった。白と黒の毛が混じった、牛のような柄の猫。わたしはこれまで、一度も他の生き物と生活したことが無いので、生態というのか習性というのか、そういうものは分からないが、二匹はいつも半径二メートル以内に居るにも拘らず、じゃれ合うのはおろか、互いに視線を合わせているような場面すら見たことが無い。
元々居る茶トラ猫は誰かの飼い猫だと思われるが、後から来た牛柄の猫は、明らかに野良猫だった。牛柄は、皿に盛られた茶トラの餌を勝手に食べていて、しかし茶トラはそれを歯牙にも掛けず、欠伸をしたり伸びをしたりしている。もしかしたら人間には分からないだけで、手前勝手にでは無く、きちんと許可を取っているのかも知れない。茶トラは初対面の時からわたしが近づいても逃げなかったが、牛柄は怖がって一目散に逃げてしまうのでかわいそうに思い、立ち止まって不躾な視線を遣ったり無闇に近づいたりしないようにしていた。また、牛柄は右後ろ足を引き摺っていて、それがとてもかわいそうだった。早く治ると良いと思った。
特に懐いてもらえるような何かをしたのでも無いが、茶トラがわたしに対し無警戒・無防備であるためか、単純にほとんど毎日見掛けるためか、先週辺りから、牛柄も逃げなくなった。右足の怪我も、少しずつではあるが快方へ向かっているようだった。嬉しいことだと思いながら、近所の国道沿いにあるコンビニの前を通り過ぎると、「ねえ」という声が聞こえた。周りには自分以外にも何人か歩いている人が居たので、気に留めないでいたが、また「ねえ」という声がすぐ後ろでし、直後に右肩を叩かれた。驚いて振り返ると、見知らぬ男がわたしのほうを見ていた。続いて男は何やら短い文章を言ったが、何を言ったのか一つも聞き取れなかったので聞き返した。男は少し声量を上げ、「たまには飲みに来なよ」と言った。それもこもった声だったので定かでは無い。ただそのように聞こえた。
男の容貌自体はごくありふれたもので、取り立てて特徴が無かった。身につけているものも濃いグレーの上着と黒いズボン、黒い帽子を被っているだけで地味だった。彼の身体的特徴の中で、最も印象的なのが目だった。重たい一重まぶたの奥にある目は、不気味かつ異様なほど暗く淀んでおり、咄嗟に誰にも知られたくない、最も恥ずべき過去の記憶を思い出しそうになり、途轍も無い不快感と居心地の悪さを味わった。また、男は松葉杖をついており、右足を引き摺っていた。やっとの思いで「どういうことですか」と訊くが、男は「いや、いい、何でも無い」と帽子の鍔に触れ、踵を返し去って行った。
わたしは数秒間放心していたが、すぐに男が向かったのとは反対の、自宅のある方向へ歩き始めた。彼が誰なのか、全く思い出せない。変質者にしては、いやに落ち着いていた。記憶を手繰り寄せようとすると、頭の中からあのどんよりとした暗い二つの目が、わたしを見つめ返してくる。
翌日から、帰宅する際に──何時であっても──例のコンビニの前を通ると、決まってあの男の姿を見掛けるようになった。コンビニ前のベンチに腰掛け、俯いている。こちらを見ていなくても、男の視線はしっかりとわたしを捉えているような気がしてならない。彼を、正確にはこの不吉な感覚を避けるために、異なるルートで帰宅せざるを得なかった。しかしどんなに遠回りをしても、あの目は頭の中から消えて無くならず、日中、仕事をしている時もジッとこちらを見ていた。そのせいで、年度末だというのに仕事がほとんど手に付かなかった。
十日ほど経った頃だろうか、帰宅して部屋の照明をつけると、ソファの上に裸の女が横たわっていた。たった今目を覚ましたのか、女は首を擡げ、眠たそうにこちらを見上げた。女は“ウ”のような音を口から発した後、喘鳴に似た奇妙な笑い声を上げ、その拍子に、黒ずんだスカスカの歯が見えた。左耳の辺りに、悪趣味な花飾りを差していた。白人のようなくっきりとした二重の大きな双眸は、女性器のような形をしていて、巨大な乳房の先端にある乳輪は直径二十センチくらいあった。女は東南アジア人のようでもあったし、東欧人のようにも見えた。
ソファの足元には、昨日客から貰った上等のウォッカの瓶が置いてあり、既に半分以上無くなっていた。柔らかそうな腹部に置かれた左手には、三つの結婚指輪が着けてあった。彼女は紛れも無く美しかった。この世に存在するすべての美しさは、彼女に似た部分を持つ者のことを指すのだとその時知った。わたしは、キッチンから飲みかけのウイスキーの瓶と炭酸水を持ってきて、椅子に座り、女の体を眺めながら酒を飲んだ。酔いが訪れるに従い、頭の中に音楽が流れ始めた。女は突然立ち上がり、その音楽に合わせて踊り出した。それは今まで見た何よりも最悪だったが、最悪なものこそが何よりも美しい、という意味をも含んでいた。女は時々歌いもしたが、歌詞らしい歌詞は聴き取れず、祈祷を捧げるような歌声だった。音楽は気紛れに終わる。瞬きをして次に目を開けた時には、女は大蛇の姿と化してわたしを丸呑みし、ゆっくりと時間をかけて消化する……ついそんな連想に恍惚としてしまう。永遠に続く安らぎと歓び。
顳顬の辺りに冷たい液体の垂れた感触があり、顔を上げた。朝だった。ソファにはもう誰も寝ていない。昨晩の、その後の出来事は何も覚えていないが、あらゆる余韻が至るところに残されている。すると今度は、目の前に液体が垂れた。咄嗟に顔を天井へ向ける。天井の一部分が剥がされ、大きな赤い花が咲いているように見えた。液体はそこから垂れていた。あれは何だろうと見つめ続けていると、花のように見えたのは、皮と肉を抉られた人間の顔だということが分かった。カーテンの隙間から覗く黄色い空の中で、男の目がこちらを見つめている。
無職を救って下さい。
