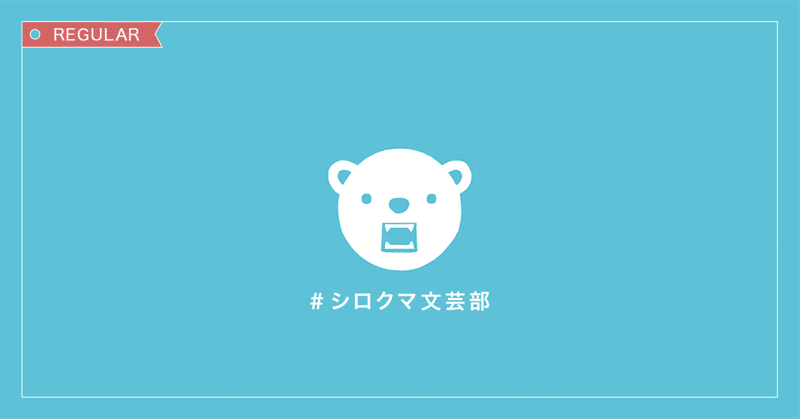
オールドウィッチの化粧水(#シロクマ文芸部)
「雪化粧水を……ください」
ガラン、ガラン。
錆びた音を立ててドアベルが揺れた。
その店はオールドウィッチ通りにあると聞いた。
トラファルガー広場からシティへとのびるストランド大通りを東に歩むと、貴婦人のドレスのごとく優雅な弧を描くオールドウィッチ通りに行きあたる。ロンドンの法曹界や金融・官公庁のいかめしい建物がひしめくこの界わいに、サリーが足を向けることは少ない。すぐ向こうのテムズ川から吹く風が今日も霧をヴェールのように広げている。コートの襟を立て、錆色の空を見上げる。教会さながらのファサードをもつ白亜の王立裁判所が冬まで跪拝させてそびえていた。
裁判所の先、石造りの立派な建物群に両脇からはさまれ、息をひそめるようにして間口わずか1ヤードほどの古い店があった。
擦りガラスを嵌めこんだ扉に「オールドウィッチ化粧品」とある店名も消えかかり、往来を行き交う人びとは気づくけはいもなく足早に通り過ぎる。いや、実際に見えていないのだ。店は必要とする人の前にだけ姿を現すという。どういうしくみか、わからないけれど。
擦りガラス越しの光は力をそがれ、店内は昼でも仄暗い。
黒いレースのヴェールがついたトークハットを目深にかぶったサリーは、おずおずと扉を押して目を凝らした。
「そろそろ来るころだろうと、待っていたよ」
店の奥から声だけが浮かび上がった。
目が慣れると、床まで届きそうな黒髪の女の姿が見えた。傍らの止り木でカラスが鋭い瞳を向けている。黒いロングドレスと漆黒の羽根が弱い冬の光を吸収する。サリーも喪服のような黒のロングコート姿。
――みんな真っ黒。まるであたしの心のよう。
サリーはため息をもらす。
「あなたがオールドウィッチ? ずいぶん若くみえるけれど」
「鼻のひん曲がった皺くちゃ婆あでも想像してたのかい?」
皺ひとつない顔がにっと笑う。
「あたしたちは、これで化けるのさ」
魔法の杖ではなく、棚にずらりと並んだ茶色いガラスの小瓶に目をやる。
「化粧は化けるための道具だろ」と片目をつぶる。
はっとするほど艶やかなウインク。
「で、ほんとうにいいのかい?」
「ええ、私の心はもう凍りついてしまったから」
ウィッチはサリーの顔に手を伸ばす。
サリーはびくっと肩を強ばらせ、一歩後ずさる。
「ああ、これは」
黒いヴェールをあげてまじまじと見つめる。
「ずいぶん大きくなってるね」
サリーの右頬には1ポンド硬貨よりもひと回り大きな薄墨色の心沁が浮き出ていた。
「抑えようとしても、抑えようとしても、もうだめなの」
サリーが喉を両手で押さえてあえぐ。
「そんなふうに首を締めるんじゃないよ。ほら、これでも飲んであったまりな」
ウィッチがぱちんと指をはじくと、サイドテーブルに湯気のあがったマグカップが現れた。
「毒じゃないからね。エルダーフラワーのコーディアルさ。気分を落ち着けたいときには、これが一番」
毒でもかまわないと、サリーは思った。心の内からどす黒い心沁に覆われてゆくくらいなら、毒を飲むほうがまし。そのうち得体のしれない穢れが口からどろどろと溢れ出しそうで恐ろしくなる。
「で、なんでそんなに心沁が育っちまったんだ」
マスカットのような甘酸っぱくてすっきりとしたシロップが、黒く淀んで苦しかったサリーの胸をすうっとあたためる。ほおっと白い息を一つはき、頬をゆるめて顔をあげた。
「エリックに、恋人のエリックに裏切られて」
ふた月前のことだった。
エリックとは結婚の約束をしていた。いつ、とは決めていなかったけれど、そのうちささやかな式を挙げようと話していた、それが。知らない女と腕を組んでピカデリー・サーカスを歩いているのを見かけた。夜の十時を回っていた。女は襟と袖口に毛皮のついた仕立てのよさそうなキャメルのコートを羽織っていた。胸騒ぎがして二人のすぐ後ろを尾けた。
そこまで早口で語ると、サリーは一つ大きく息をついた。
「きっと、その時からもう、胸に黒い影が巣食ったのだと思う」
エリックと女が何を話していたのかはわからなかったけれど、時々、「お父様が」とか「ウェディング」という単語が聞こえた。翌日の夜、エリックのアパルトマンを訪ねて問い質そうとしたの。けど、部屋にも入れてもらえなかったわ。取引先の社長令嬢と婚約したから、もうここに来るなって追い払われそうになった。二股をかけていたのって罵ったら、「指輪も渡してない口約束を真に受けたのか」って嗤われた。
サリーは吐き出すようにいうと、片頬を引き攣らせて笑った。
「そこらへんにごろごろしてる話だね。ろくでもない男とうっかり結婚しちまわなくて良かったじゃないか」
ウィッチはつまらなそうに鼻を鳴らす。
「あたしもそう思ったし、そう思おうとした、でも。黒いタールのような感情が……抑えても、抑えても湧きあがってきて苦しくて」
忘れようとした。失敗しなくて良かったじゃない、周りも慰めてくれたし、自分でも言い聞かせた。「だいじょうぶよ、心配しないで、せいせいしたくらい」無理をして笑った。黒い想いから目を背け、仕事に没頭した。
ひと月前にメイフェアの宝石店から出てくる二人を見かけた瞬間、音を立てて何かがはずれるのがわかった。
――悔しい。許せない。
どす黒く濁った感情が喉をせり上がってきて止まらない。
その翌日、右頬に小さな薄墨色の心沁が浮き上がっているのに気づいた。日ごとに大きくなっていく。鏡をのぞくのが怖くなった。
「もう、もうだめなの、抑えきれないの」
涙がひと筋、心沁をつたって流れた。
「そんなときバーで雪化粧水の話を聞いたわ。雪の日の朝のように、醜いもの、汚いものを隠してくれるのだと」
「あんたに耳打ちしたのは、こいつさ」
羽繕いをしているカラスを顎で示す。
「騙されてるとは思わなかったのかい?」
「騙されてもいいと思った。これを覆い隠すことができるなら。命を差しだすことになったとしても。こんな醜い感情を抱えているよりは」
「そうかい」
ウィッチはまたぱちんと指を鳴らす。棚から小瓶がひとつ、すうっと飛んできた。
「確かにこの雪化粧水は、心沁をきれいに隠してくれる。だがね、こいつは雪とおんなじ。醜いものも汚いものと一緒に、きれいなものも大切なものも覆ってしまうんだよ。それでもいいか」
「もうあたしに、きれいなものなんて残ってないもの」
「あんたのその澄んだ優しい瞳も表情を消しちまうし、そのふっくらとした頬が笑うこともできなくなっちまうよ」
「根雪のようになって凍り付いても、汚れを吸いとって、閉じこめてくれるのならかまわない」
サリーは瞳に最後の光を宿してウィッチを見つめる。
「なら、これだけは覚えときな。この世のたいがいは、まやかしなんだよ。誰もが、顔だけじゃなく心にも化粧をしてる。まやかしの笑顔と、嘘っぱちの涙。けどねぇ、それでいいんだよ。本心も素顔も、特別なだれか一人のためにとっておきゃいいのさ。そんな誰かに出会えるまでさ」
「出会えなければ?」
「いいじゃないか、美しく装っていればさ。忘れちまったのかい? はじめて化粧した日のときめきを。いい女ってのは、平然と美しく嘘をつける女のことさ。根雪の底で真実の愛を抱えていればいいさ」
ウィッチはふいと窓の外に目をやる。
「ほら、粉雪が降りはじめたよ」
サリーの手に雪化粧水の小瓶を乗せる。
「長く生きてきてわかったことがいくつかあるけどさ。春の来ない冬はないよ」
<The End>
………………………………………………………………………………………………………………
この短編の舞台としたオールドウィッチ街の綴りは、「Aldwych」。
古英語で「古い貿易町」という意味の「Ealdwic」に由来するそうです。かつて辺りを流れていたフリート川の河口付近にあって、7世紀から貿易船の停泊地として栄えていた町でした。
老魔女の「Old Witch」とは綴りも違い、発音も微妙に異なりますが、日本語で表記するとどちらも「オールドウィッチ」になることをご了承のうえ、お楽しみいただければ幸いです。
ご参考までに。オールドウィッチ街と王立裁判所です。
………………………………………………………………………………………………………………
今週はタイムアウト……でした。
でも、締め切りは気にしなくてもいい、という小牧部長の優しいお言葉に、さっそく甘えてしまいました。
1月から3月半ばまで副業が多忙になるため、「おさぼり」が増えるものと見込まれますが、できるだけなまけ癖に喝を入れて努力したいと思います。
(いやあ、もう、サボる気まんまんなコメントですね。はあああ)
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
