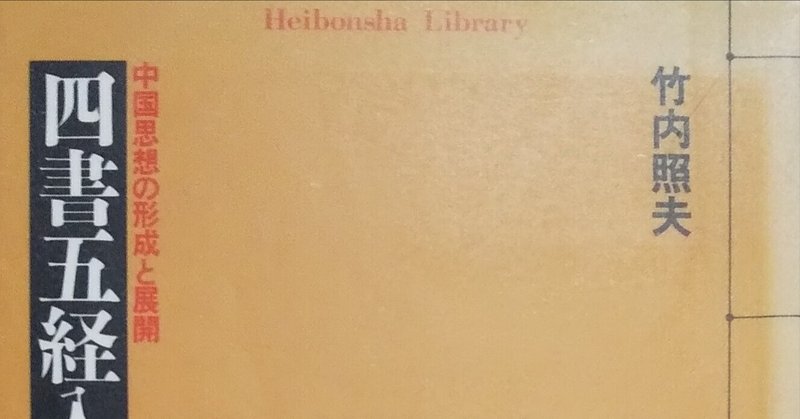
道と形而上学
形而上学の「形而上」って『易経』由来だったよな……ところで『易経』って五経でよかったんだっけ?そんな気持ちで手に取ったのは竹内照夫著『四書五経入門』(平凡社ライブラリー)。初めて学ぶ分野である。ちなみに『易経』は五経で合っている。次からは自信をもって答えてもらいたい。
さて、「形而上」の由来についてだが正確に言い直そう。「形而上学」という言葉は『易経』の 「繋辞伝」を典拠とするもので、「形而上者謂之道、形而下者謂之器」(形より上のもの、これを道と言い、形より下のもの、これを器と言う)という一節から採られた、井上哲次郎による"metaphysics"の訳語である。これを踏まえると私の関心は、なぜ『易経』「繋辞伝」において「道」が問われたのかという点。そして道概念の存在論的性格はいかなるものかという点。この二つにあるように思う。
竹内氏は『易経』の構成と成立を以下のようにまとめる(71-72頁)。
第一部:六十四卦の図形、卦名、および卦爻辞(周王朝樹立時には既に成立)
第二部:卦爻辞の解説たる「彖伝」と「象伝」(春秋時代末期より後、戦国時代に作成)
第三部:易の哲学たる「繋辞伝」「序卦伝」 など (戦国時代末から秦朝を経て漢代に入る間に作成)
なるほど「繋辞伝」は『易経』 全体から見ると後の時代に成立した文書なのか。いやそもそも周から漢って何年だ……840年もあるの?それはすごい。
竹内氏は第一部から第二部へと至る『易経』の変転について、これを予言思想の進歩と説明する(66頁)。すなわち卦爻辞が原初的・功利的な託宣に留まるものであったのに対して、「彖伝」「象伝」はそれに倫理的な根拠づけ・解説を与えたものであるとする。これはある種の発展史的解釈であるが、わかりやすいので私もこの方向で考えてみよう。
そうなると、第三部における「繋辞伝」の成立はいかなる発展と解すればよいか。注目すべきは儒家へ及ぼした道家の影響であり、道家の形而上学における根本原理が「道」の概念なのである。
道概念の検討に先だって、道家の政治思想に関して確認したいことがある。儒家と道家の思想に関して、竹内氏は「儒家は人間の理知や道義の進歩が人間の安全と利益を増大すると信ずるが、道家は逆で、文明の進歩は人類を裏切って不幸を増大すると判断している」と二家の思想を対比させる (286頁)。ある意味で道家は儒家における合理主義的、君子本位的傾向への批判として成立したのであり、有為の政治学への逆説として無為の政治学を主張するのである。『老子』における「大道廃れて仁義あり」とか「聖を絶ち智を棄つれば、民利百倍す」といった教説は、この無為を理想とする立場から理解できよう。
そしてここからが面白い話なのだが、道家においてはこの政治学が形而上学と連続している(というか、そもそも実践知と理論知の別を重視していない?)のである。すなわち政治の理想は無為であり、同様に天地の本性も無為と見なす。「天地は不仁、万物を以て芻狗となす」という時の天地は人間に対して何の関心も向けていない。『老子』ではこうした無為の天地を生み出した何か、これを便宜上「道」と呼んでいる。天地というと何らかの全体概念のように思えるのだが、それはあくまで有の次元での話であり、そうした万有を生み出す原理としての「道」を無の次元において措定している。つまり、無は有に対して理論上先行する……とでもいえばいいだろうか?
どうも有と無との関係が不明瞭だが、そろそろ私の余力が無くなって来た。暫定的にでも最初に自分で提示した問いに回答を与えた方がよいだろう。まず『易経』「繋辞伝」において「道」が問われた理由について。『易経』は予言思想の発展として個人の運命以上のもの、運命を根拠付ける世界原理の説明を必要とした。これが「繋辞伝」であり、そこで個別的存在者(器)を条件づける上位概念として「道」を導入したと私は考える。そしてこの道概念には道家思想の影響が強く見られる。道概念は存在論の観点から見ると、存在と存在者との区別における「存在」の概念であり、道家においては「無」と規定される。今回の考究ではそこまで至らなかったが、道概念は一般形而上学と特殊形而上学の両側面を備えているようにも思える。道概念の存在論的性格については、こんな感じにしておこう。
疲れた……もっと短い感想にするつもりだったのに。ところで『四書五経入門』自体は『易経』以外の四書五経についてもちゃんと解説してくれるし、そもそも形而上学についての本ではないので安心して欲しい。ちなみに一番面白かったのは第八章「四書五経の伝承」である。特に竹内氏による道家政治思想への批判が軽快で、それに章全体を通して中国思想の通史的勉強にもなってお得だ。なお本書を読む際の最大の障壁は漢字がすごく難しいという、ある種一番辛いところにあるが、読み仮名も多く振ってもらっているのでそこは忍耐である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
