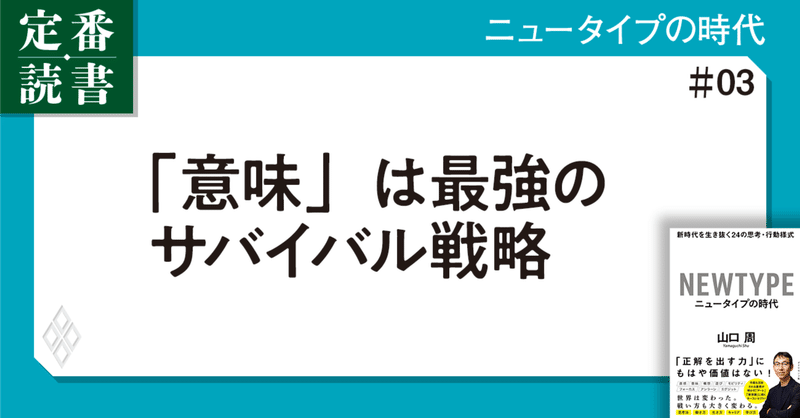
成功の明暗を分ける「真似されてもコピーできないもの」とは?
『ニュータイプの時代』著者・山口周氏に聞く
情報が次から次へと溢れてくる時代。だからこそ、普遍的メッセージが紡がれた「定番書」の価値は増しているのではないだろうか。そこで、本連載「定番読書」では、刊行から年月が経っても今なお売れ続け、ロングセラーとして読み継がれている書籍について、著者へのインタビューとともにご紹介していきたい。
第1回は、2019年に刊行された山口周氏の『ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式』。「人生のゲーム」が変わってきていることを、明快に記した1冊だ。4話に分けてお届けする。(取材・文/上阪徹)

構想や妄想ができない。だから、予測に頼ろうとする
新しい時代を生き抜くための24の思考・行動様式が説かれている『ニュータイプの時代』だが、日本人がとりわけ苦手としているものがあるという。未来を「予測」するのではなく、未来を「構想」することだ。
「構想や妄想ができない。だから、予測に頼ろうとする。一つのボトルネックは、構想したことができたとしても、堂々と人に語ったり示したりする勇気がない、ということでしょうね」
本書では、こんな記述が並んでいる。
これだけVUCAな世界になってなお、他人に将来を予測してもらって受験勉強よろしく「傾向と対策」を考えようなどというのは、まさに浅知恵と言うべき典型的なオールドタイプのパラダイムといえます。
本当に考えなければいけないのは、「未来はどうなるのか?」という問題ではなく「未来をどうしたいのか?」という問題であるべきでしょう。
人工知能の登場によって「人間の仕事が奪われてしまうのではないか」という不安が取りざたされてきたが、この問題についてもこう記述する。
あらためて考えたいのは、この「問い」の前提となっている視座の低さです。人工知能という汎用性の高いテクノロジーが実用になりつつある今、私たちが問わなければならないのは、むしろ「人工知能を人間が手にしたことで、私たちにどのような可能性が開けるのか」という問いであり、さらには「テクノロジーによって私たちはどのように人間を進化させられるのか」という問いであるべきでしょう。
「真似する力」すらも衰えてきている
日本の構想力の弱さの背景には、経済成長期に欧米のキャッチアップだけを目指してきたことが挙げられると山口氏はいう。自分でビジョンを作る必要はなかったのだ。しかし、「真似する力」すらも衰えてきているのではないかと語る。

独立研究者、著作家、パブリックスピーカー電通、BCGなどで戦略策定、文化政策、組織開発等に従事。著書に『ニュータイプの時代』『ビジネスの未来』『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』など。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修士課程修了。株式会社中川政七商店社外取締役、株式会社モバイルファクトリー社外取締役。
「例えば、昭和の名経営者は、みんな海外に行って視察し、謙虚に学んでいたんですよ。トヨタ自動車の大野耐一さんもそうだし、ヤマト運輸の小倉昌男さんもそう。もっといえば、東郷平八郎はイギリス海軍に留学したし、伊藤博文も海外に学んだ。その上で、ビジョンを作っていったわけです。今はビジョンも作れない上に、ちゃんと真似もできない。これでは厳しいですよね」
もちろん、日本にも良さや強みはある。例えば、モノづくりの精密さや仕事の律儀さ、丁寧さなどもそうだ。それは各方面から高い評価を得ている。だが、こうした力も、残念ながら価格に転嫁できていない、と語る。これも日本人が苦手とするものだが、「意味のポジション」を市場で取れないのだ。
本書でも自動車メーカーのブランド比較で、なぜイタリアやドイツの車が高い価格で勝負できるのかが紹介されていたが、インタビューではこんな話をしていた。
「やっぱり意味づけが苦手なんですよ。今、シンガー・ポルシェが世界中で大人気になっています。10年前なら300万円ほどで買えた古いポルシェを仕入れてきて、エンジンをチューンしたり、外装を飾り付けたりして、シンガー・ポルシェで売り出したら、最も安いものでも4000万円ほどする。高いものになると億を超える。それでも、ウエイティングになっていて、買えないわけです」
デザインはコピーされるが、「意味」はコピーできない
日本では、ポルシェはオリジナル至上主義で、手を加えると価値が下がると考えている人が多いのだという。
「でも、新しい時代の文脈に合わせて意味づくりと価値づくりをしてビジネスをすると、とてつもなく利益率が高くなり、しかも世界中で求められるようなことが起きるわけです。新車のアストンマーチンよりも、高いわけですからね」
テクノロジーやデザインは、コピーされやすい。しかし、「意味」は簡単にコピーできない。本書にあったこの記述は、極めて説得力がある。
たとえばアップルという会社の製品や機能を、表面的にコピーすることはいくらでも可能でしょうが、アップルという固有のブランドが顧客に対して与えている感性価値としての「意味」はコピーすることができません。なぜなら「意味」の形成には膨大な情報量が必要であり、膨大な情報量を市場に蓄積するためには非常に長い時間がかかるからです。
個人の思考・行動様式のみならず、ビジネスも「ニュータイプ」への移行が求められているのだ。最終回は、刊行後に驚いた意外な反響について聞く。
(次回に続く)
上阪徹(うえさか・とおる)
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)、『子どもが面白がる学校を創る』(日経BP)、『10倍速く書ける 超スピード文章術』(ダイヤモンド社)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。
