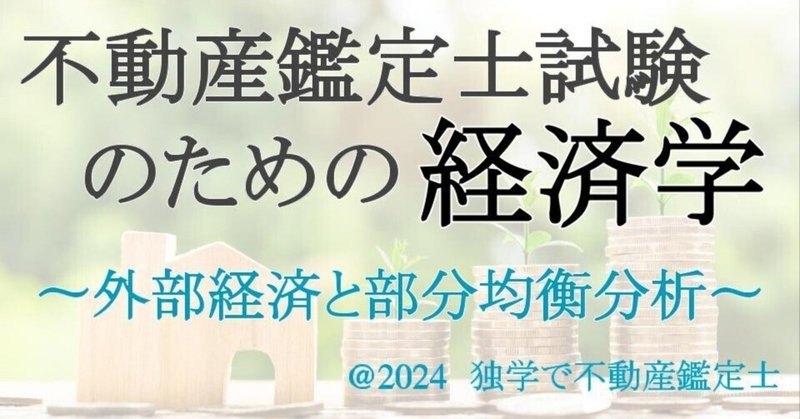
【ミクロ-15:不動産鑑定士試験のための経済学】 外部経済と部分均衡分析 をわかりやすく(余剰分析)
1. 外部経済とは
外部経済とは、ある企業や個人の経済活動が、その活動に関与していない他の企業や個人に与える影響のことを指します。外部経済は関与していない第三者に利益をもたらす場合があります。
例えば、ある会社が研究開発を行った結果、新しい技術が生まれた場合、その技術が周辺の企業や業界に波及し、全体の生産性が向上することが考えられます。
2. 外部経済がある場合余剰分析
2.1.補助金支給前の消費者余剰
消費者余剰とは、消費者が実際に支払った価格と、支払ってもよいと感じる最高価格との差額のことを指します。外部経済が存在する場合、市場価格は第三者への影響を反映せず、消費者余剰は小さくなります。
例えば、ある商品の生産に伴い環境が保護される場合、その商品の真の価値は消費者が支払う価格よりも高くなるかもしれません。しかし、その価値が市場価格に反映されないため、消費者余剰が実際よりも低く見積もられる可能性があります。
2.2. 補助金支給前の生産者余剰
生産者余剰とは、生産者が実際に受け取る価格と、最低限受け取りたい価格との差額のことを指します。外部経済が存在する場合、生産の過程で第三者に与えるプラスの影響が生産者の収入に直接的には反映されないため、生産者余剰が実際の貢献を正確に反映せず、小さくなります。
例として、ある商品の生産が環境保護に寄与する場合、この環境への貢献は一般に市場価格に直接的には反映されません。しかし、この環境への貢献により、生産者の商品には付加価値が生まれ、それが反映された価格で販売されると、生産者余剰は増加します。このような場合、政府や関連機関がこのような商品の生産を奨励し、その結果として生産者余剰を増加させるための政策を導入することが考えられます。
2.3. 補助金支給前の社会的総余剰
社会的総余剰は、消費者余剰と生産者余剰の和に外部経済による価値を加算して計算します。
外部経済により、市場の均衡価格や均衡数量が社会的最適からずれる場合があります。このずれが大きいほど、社会的総余剰の損失も大きくなることが考えられます。
2.4. 死荷重の発生と過少供給
外部経済の存在により、市場が効率的な均衡に達しない場合、社会的総余剰の損失が生じることがあります。この損失を死荷重と呼びます。
例えば、外部経済により供給量が社会的最適量よりも少なくなる場合、過少供給が生じます。これにより、社会的総余剰が最大となる均衡点を達成できず、結果として死荷重が発生します。
3. ピグー的補助金と余剰分析
3.1. ピグー的補助金とは
ピグー的補助金とは、外部経済の存在により生じる市場の非効率性を是正するために、政府が導入する補助金のことを指します。
例えば、環境保護に貢献する商品の生産者に補助金を支給することで、その商品の生産量を増加させ、社会的総余剰を最大化することが考えられます。
3.2. 補助金支給後の消費者余剰
補助金が支給されると、商品の価格が低下し、消費者はその商品をより多く購入するようになります。この結果、消費者余剰は増加することが考えられます。
補助金により、消費者が享受する商品の真の価値が市場価格により正確に反映されるようになり、消費者余剰が増加するとともに、社会的最適へと近づくことが期待されます。
3.3. 補助金支給後の生産者余剰
補助金が支給されると、生産者はその商品をより多く生産するインセンティブを受けることになります。この結果、生産者余剰も増加することが考えられます。
補助金により、生産者が負担する生産コストが一部補填されるため、利益が増加します。このように、ピグー的補助金は消費者余剰だけでなく、生産者余剰も増加させる効果があります。
3.4. 補助金支給後の社会的総余剰
社会的総余剰は、消費者余剰と生産者余剰の和に外部経済による価値を加算して、補助金支出を控除します。ピグー的補助金により、最適な資源配分を実現することができます。
ピグー的補助金は、外部経済の影響を考慮して市場の非効率性を是正するための政策ツールとして有効であり、適切に導入されると社会的福祉の向上に寄与することが考えられます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
