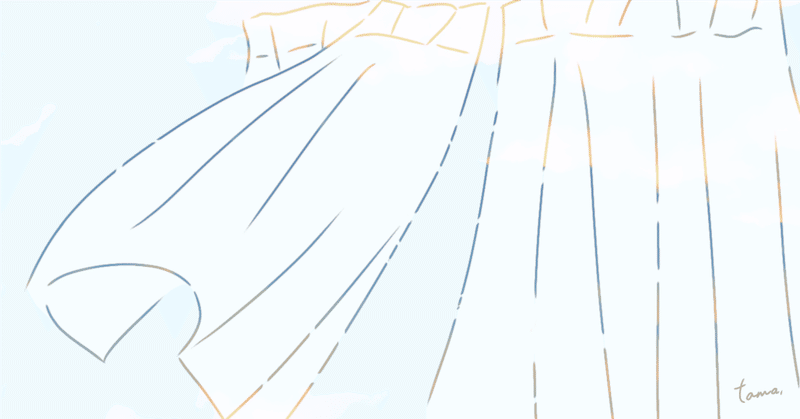
五月に吹く風 創作小説
彼女が真面目な性格だということをよく分かっていたが、そこに書かれた文字を見ると、何とも言えないもどかしい気持ちが湧いた。持ち上がりで高二の担任となり、早速進路希望調査を行った。進学先を書く欄に、昨年も私のクラスに在籍していた河合という生徒が『歌手志望』と書いて提出したのだ。
新学期の慌ただしさが落ち着いた四月末の放課後。カーテンをはためかせ、窓からグラウンドで練習する野球部の声と気持ちの良い風が教室に入ってくる。私は面談相手の河合を緊張させないよう注意しながら、向き合って座っている。彼女はシャツのボタンを一番上まで止め、リボンも正しい位置につけている。制服がきちんと整っていることは、学校と言う社会の中では模範的で、彼女は求められていることに正確に応えている。河合はそういうことができる生徒だ。
「わざわざ放課後に残ってもらったのは、進路希望調査の内容のことです。この学校は進学校だからよほどの理由がない限り、皆ここには大学名を記入するのよ。将来の夢が歌手であることを否定するつもりはないけど、進学しないで歌手を目指したいってことかな?」
私の問いかけに、河合は何も言わない。
「仕事をしながら好きなことを趣味で続けている人もいると思うの。音楽を仕事にするって難しいことだろうけど、趣味じゃなくて、河合さんは仕事にしたいの?」
俯いていた河合が真っ赤になった顔を上げる。今にも涙が零れ落ちそうだった。
「ごめんなさい。ちゃんと書いてまた明日提出し直します」
彼女はそう言うと、机の上の紙を奪うようにして、教室から出ようとした。
「責めているわけじゃないんだよ」
慌てて立ち上がりそう言ったが、彼女は困ったように笑い、頭を下げ扉を閉めた。
「最底だ」
誰もいない教室で思わずつぶやく。教師になって四年目、担任として進路指導に深く関わるのは今年が初めてだった。そんな私が彼女と面談することに乗り気でなかったのは、夢を否定し、現実を突きつける指導が嫌だったからだ。生徒の夢を応援するものが教師だという理想があった。でも、社会に少し早く出た大人が、現実的なアドバイスを子供に伝えることも必要な役割だと思う気持ちもある。
二十時半に、一人で暮らすアパートに帰宅した。仕事をしながら好きなことを趣味で続けている人もいると、偉そうに話をしたが、私自身は仕事と家の往復で夢中になれることなんてなかった。大好きな読書も捗らず、未読の本がベッドの横に積まれたままだ。私はタワーになった本の中から一冊を抜いた。これは去年買った新訳の海外の古典作品だ。中学生の頃に読んだ物語が、好きな作家の訳で生まれ変わると知り、嬉しくて発売日に手に入れた。話の大筋は覚えているから、パラパラめくり場面を選び読み直した。
気が付くと、時計の針が二十三時を指している。夢中になった高揚感と明日も仕事があるというのに、夕飯もまだであることの倦怠感を同時に感じる。子供の頃は作家になりたいと思っていた。高校生の時、初めて書いた長編で文学賞に応募したが、手ごたえはなく、大学の文学部に進学後、国語の教員になった。好きなことを趣味として続けることすら私には出来ていない。河合の切迫した表情が脳裏に焼き付いている。真面目な彼女が、学校のアンケートに自分の夢を書いた時、どんな気持ちだったのだろうか。彼女の思いが、あの短い文字にはぎゅっと込められていただろう。夢を応援するだけが教師ではないし、現実的な問題を提示することも必要だ。ただ、私はあの時彼女の気持ちを聞こうともしなかった。歌がいつから好きなのか?どんなジャンルを歌うの?親は知っているのか?具体的に何かしている?そんな風に問いかけ、対話が出来ていたなら、彼女にあんな顔をさせずに済んだのではないか。夢を追いかけることを選ばなかったとしても、河合の将来を前向きに照らすきっかけになったのかもしれない。
翌朝、職員室に河合が訪ねてきた。あの紙には、近くの国立大学の経済学部の名前が書かれてある。私が夢について問いかけると、通っている歌のレッスンやコンテストの話が彼女の口からどんどん出てきて、私が想像していたよりずっと夢を現実にするために、具体的な努力をしていた。
「この紙には書いたけど、大学進学するべきかもっと真剣に考えてみます。やりがいのある仕事をしながら、音楽を趣味にすることが悪いとは思わないけど、今はそうならないように努力をしたいと思っています」
私の目を見て、はっきりとそう語る河合を見ていると、何とも言えない気持ちが湧いてきた。ただそれは、もどかしさのようなマイナスなものではなく、窓から入る五月の風のような清々しいものだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
