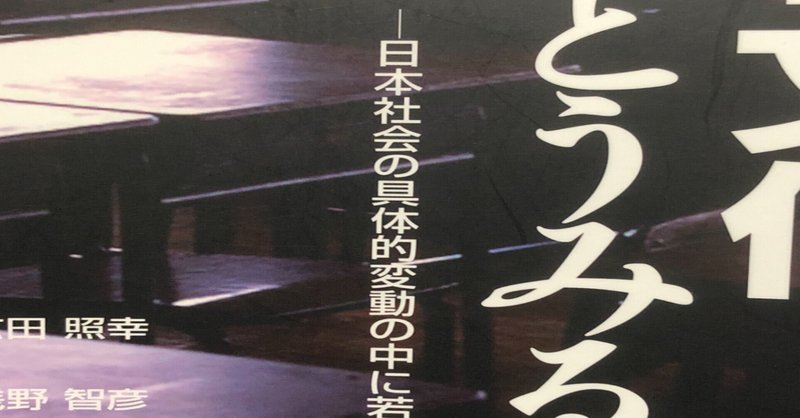
100冊読者計画003『若者文化をどうみるか? ー日本社会の具体的変動の中に若者文化を定位するー』広田照幸編著
これは大学時代に読んだ本のなかでもっとも衝撃を受けた本だ。理由は二つある。
ひとつは、自分が過ごしてきた学校や、教育や、そこで得た友達。そして学校とは別の外界や、教育とは別の趣味や、趣味空間で得た友達。家、親、地域。そういった繋がりや居場所の形成や文化には全て意味があるという強いメッセージを受けたからだ。
読んだ時期が学生だったというのも恐らく大きい。当事者意識的に読むことで、自分の人生をより俯瞰的に分析できた感覚があった。目の前のものや、通ってきたものについて考えるという癖は社会人になった今も活きているし、それが身についたのはこの本を読んでからのような気がする。
ふたつめは、オプション的要素ではあるが、本の最後に「読むべき本」「読んではいけない本」が数ページに渡ってリストアップされていたことである。
当時はなんて大胆なことをするんだろうと驚いた。
ちなみに、そのリスト通りに本を選ぶことは一度もしていない。思想的な影響を受ける気がして怖かったし、その分別ができるほど勉強していなかったからだ。
そして、この本は若者文化を分析・考察するものであり、若者達自身に向けたものではない。どちらかと言うと若者や若者文化を見つめる大人達に向けた本だ。
メッセージを受けたというのは当時の僕の勝手な感覚である。
だからこそ、社会人になった今、この本を読み直すことにした。内容を再認識できたものはもちろん、新しく思うこともある、刺激ある本だった。
✳︎✳︎✳︎
昔から言われていることだが、若者はバッシングの対象になりやすい。性差や人種やマイノリティ性や弱者性などの差別的条件が、若者という括りには(一見すると)無いからだ。
例えば、フリーターやニートや未婚は個人のやる気の問題だという扱いを受けやすい。
渋谷のハロウィンや荒れる成人式に向けられる視線はかなり冷たい。というより、理解できない独自の文化として敬遠されることが多い。
さらに、最近の傾向として、責任の個人化が強く出てきている節がある。
年金が減るから個人で貯めておく必要があるだとか、いじめやパワハラやセクハラが嫌なら転校や転職などの選択肢があるだとか、自己肯定感の向上だとか、そういった個人の心持ちや行動力で問題を乗り越えることが(しかも若者自身ではなく外の大人達から)叫ばれる傾向がある。
だが、子供や若者が抱える問題は、社会が生み出す構造的な文脈にあることを忘れてはならない。まだ働いてもないうちに老後のお金を心配したり、限られた選択肢の中でハラスメントに耐えたり、自己肯定感によって自分を奮い立たせておかねば生きていけないような社会にしたのは、一体誰の責任だと言うのだろう。
✳︎✳︎✳︎
責任の所在をはっきりさせたり、若者がまったく何も背負う必要はないと言っているわけではない。
本の内容に沿って書いてみる。
まず、大人の立場で言えば、若者文化や彼らが抱える問題をただ叩いたり全面肯定するのではなく、若者文化(消費文化)が社会にとってどういう位置を占めるのか、またそれが若者達自身にとってどういう意味を持つのかを考えるべきである。
そうすることで「多様でめまぐるしく変化する、表面的な流行や人気の向こう側に、比較的共通で安定した、若者文化と社会の関係、若者文化と個人の関係の構造を読み取ることが可能」であり、「"大人に何ができるのか/何をすべきなのか"を考える手がかりが得られる」のである。
若者の立場で言えば、学びと訴えを絶やさないことである。「個々人が、自己の利害を認識し、その社会的意味を理解して行動できることが求められてくる」のだ。
重く聞こえるかもしれないが、例えば、ある一人の訴えがSNSで広がり、時にはムーヴメントとなり、他人に現状を知ってもらえる機会になったり、それが実際の責任者に届いたり、政治的影響力のある(と期待できる)人間に届いたりするのはよく見られる光景である。
選挙に行くなどの行動は大前提だが、それ以外にも、自身を表現し訴える方法を若者は持っている。というより、若者文化そのものがカウンターカルチャーや政治的抵抗としての側面を持つこともあるのだ。その自覚を持つことは若者にとって大きな強みになるのではないだろうか。
✳︎✳︎✳︎
ひとつ思ったのは、SNSの存在にはほとんど言及がないことだ。2008年に出た本なので仕方のないことだが。
似たようなものだと、学校外で友達と行う携帯メールのやり取りが、「居場所化」的役割を担うという考察があった。
今現在の若者(若者文化)にとって、SNSは重要な「表現」や「繋がり」を確保するツールのひとつである。
チャラい格好をしたりヤンキーになったり新しいジャンルの音楽を流したりといった物理的な見えやすさではなく、大人にはまったく見えない空間で形成されるSNSという文化は、より不透明さが増したことで大人達にとっては厄介な存在となっていると思う。
小中学生に向けたSNSやインターネットの使い方の講座などは、恐らく文化が不透明な中でも大人が必死に規範やリテラシーを与えようとした結果生まれた策だと思うが、そんな講座の存在など、この時代には想像できただろうか。
このように、多元的・多層的で、流動性の高い若者文化は、これからも予想のつかないような変化をしていくだろう。
それは我々の生きる社会にとっても、若者達自身にとっても、極めて重要な資本となる。
大人になった今、それをただ否定するのでもなく、ただ肯定するのでもなく(ただの全面肯定は無視に近い)、社会へのコミットを意識させながら大切に見守っていきたい。
✳︎✳︎✳︎
去年の初め頃だったか、職場の飲み会で、その場にいた女性職員の娘に「tiktok撮ろう」と声をかけられたことがある。
正直なことを言うと、かなり戸惑った。まったく触れたことのない文化だったからだ。「tiktokを撮る」ということがどういう意味なのかもわからなかった。結局、撮らなかった。
僕自身は若者文化から卒業したつもりはなかったが、新しいコンテンツにはまったく追いついていないことを思い知らされた出来事だった。
若者文化を考えるより前に、大人の自覚を持つべきだったかもしれない。もう30歳が近いのだ。
そしてあの時、ノリノリになって一緒にtiktokを撮るべきだったと、少し後悔している。
若者文化に新しく触れ得る唯一の機会だったかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
