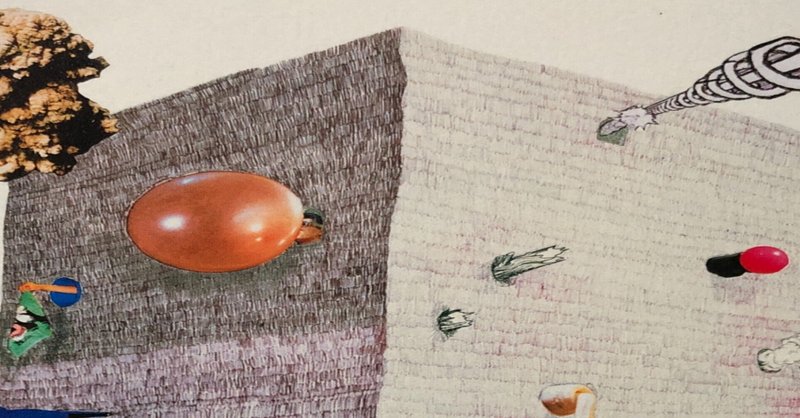
100冊読書計画011『コンビニ人間』村田沙耶香著
第155回芥川賞受賞作品。
そういえば芥川賞を獲った小説というものを読んだことがない気がするので、とりあえず買ってみた。
これがなかなか衝撃的な内容だった。話のスケールはとことん小さいのにここまで驚いてしまうのは、自分にも思いあたる何かがあったからだ。
だから、立派な賞を受賞するまでに人々の心を震わせたのだろう。
※※※
「普通とは何かを問う物語」というレビューがあった。
確かにそうでもあるのだが、僕が受けた印象は少し違う。
日常の様々な場面で、近づいたり離れたりしている合理性と人間性(或いは社会性)の狭間を、僕らは何を選択して、自分をどこに位置付けていくかを常に問われている。
趣味なんてなくても生きていけるのに趣味を探してみる。
無駄な人間関係を作らず淡々と働いていたいのにプライベートな側面も見せておく。
1人が過ごしやすいけど結婚する。
理由も不明確なまま子供を作る。
主人公は、その全てにおいて、合理性の側に自分を位置付ける人間である。
他者から見るとそれはあまりにも不気味で病的だ。だから主人公は、他者に溶け込むために少しでも人間性や社会性を身に纏おうと、静かに静かに捥がく。
そんな物語だと思う。
合理性以外に何も持たない主人公は、まるで形のない液体のような存在で、他者や社会に、自分を形作る外殻を求めている。
それがコンビニ店員という形だ。そしてコンビニ人間が出来上がった。
物語後半、彼女がコンビニを辞めると、その外殻が外れてあっという間に液体が溢れてしまう。
コンビニ店員で無くなった自分をどうしていいかわかず、ただ寝て起きるだけの、生きてるのか死んでるのかもわからないような生活。
それはまるで、合理性の末路だ。
コンビニの店員という形を失うと、合理性は拠り所がなくなる。売上をあげるためにこうすればいい、とか、人間関係を保つためにこうすればいい、とか、第一印象を良くするためにこうすればいい、とか、そんなクエスチョンとアンサーの中でしか生きられない合理性という生き物は、そこから解放されるとあっと言う間に死んでいくのだ。
もちろん合理性を手放していいというわけではない。
だが、人間性や社会性を無視していいというわけでもない。
ならどうするべきか。そんな誰もが抱える葛藤を描いた作品だった。
※※※
普通とは何かを問う、というより、異常なのは誰かを探してみろという意地悪な問いを見せつけられた気分だ。
そういった意味では好きじゃない話だった。
普通とは何か。
それは恐らく存在しない。或いは、全てが普通である、と思う。
そう思っていないと、この社会は耐えられないことばかりだ。
結婚してる人、してない人。働いてる人、働いていない人。
この作品の中では、それらをただ認めてくれるような人が1人も出てこない。
そこがまたリアルでグロテスクだ。
いろんな人がいて、僕らはただそれを認めたり、見守ったり、寄り添ったりするだけでいい。
綺麗事かもしれないが、そんな姿を我々は目指すべきなのだと最近はよく思う。
コンビニ人間も、あくまで人間なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
