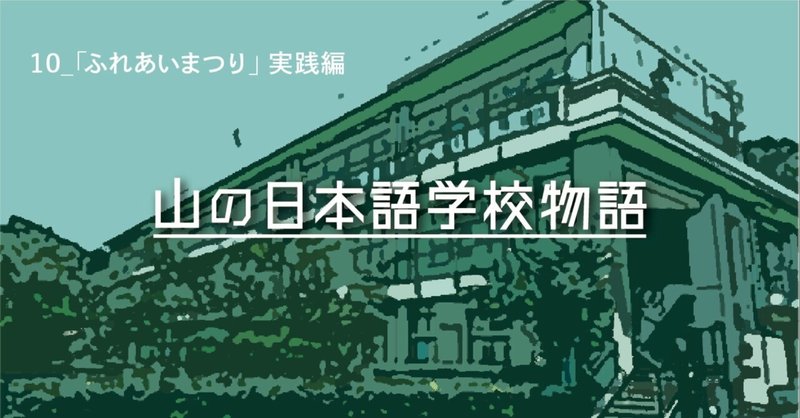
10_「ふれあいまつり」実践編 【山の日本語学校物語】
これは、とある町に開校した「山の日本語学校」(仮名)の物語です。ITエンジニアの専門日本語教育、プロジェクト型のカリキュラム、地域との連携などなど、新たな言語教育の実践とその可能性について、当時の記録をもとに綴っていきます。最後までお付き合いください。
この連載を始めるに至った経緯については、「00_はじめに」をお読みください。
前回(09)は、「準備編」として「ふれあいまつり」に出店するブースの企画、そして、「ふれあいまつり」で行うインタビュー調査の準備について書きました。日本語の学習を始めたばかりの学生たちが、2週間でこれらの準備を行ってきたわけです。今回は、この怒涛の2週間から休みなく突入した「ふれあいまつり」の実践編について描こうと思います。
「ふれあいまつり」参加の目的
2日間にわたって行われた「ふれあいまつり」は、「みどり町(仮名)」が毎年行っているもので、町内の60に近い事業者がブースを出店し、町内外から多くの人が訪れる町の一大イベントです。私たちは、このイベントに、「山の日本語学校」としてブースを出店することになっていました。イベントへの出店には、以下のような授業目的を考えていました。
- イベントを通して「みどり町」について知る
- イベント実行を通して、チームビルディングを行う
しかし、このイベントへの出店には、学校運営側の別の思惑もありました。それは、イベントを通して「山の日本語学校」を知ってもらうこと、そして、学生たちとの直接の交流を通して、地域住民の不安を払拭することです。何回か書いていますが、「山の日本語学校」の開校には、地域住民から多くの反対意見がありました。私はそれを「得体の知れないものに対する不安」と捉えていました。学生たちと直接交流する機会が増えれば増えるほど、このような不安は解消されるだろうと考えていました。
このような背景もあり、「ふれあいまつり」への出店は、学生たちが町の人と交流できる絶好の機会だと捉えていました。学生たちがこのイベントでどのような企画を立てるのかは、重要な要素であり、企画を学生に丸投げするのは、勇気がいることでした。しかし、「みどり町を知る」という目的を十分に理解していた学生たちの企画は、私の思惑以上のものでした。「準備編(09)」で書いたように、クラスが一つのイベント会社であるかのような一体感を感じることもありました。私は、学生たちをすっかり信頼し、裏方に徹することにしました。
共感していただけてうれしいです。未来の言語教育のために、何ができるかを考え、行動していきたいと思います。ありがとうございます!

