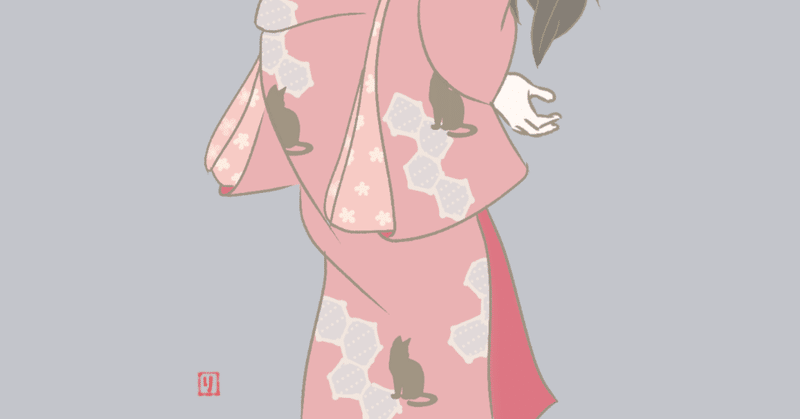
「死ぬもんか」
学生時代から慣れ親しんだ東京を離れ、故郷に錦を飾る事なく実家に戻った2000年頃、子供の頃から大好きだった叔父が亡くなった。彼が亡くなって間もなく、妻である私の叔母も後を追うように亡くなってしまった。まだ二人とも50代で、今思えば随分若かった。
母は「お金にも家族にもこんな恵まれていたのにね」とぼやいていたが、内心「人が亡くなるのに、そんな事は関係あるのだろうか」と思っていた。叔母は夫と子供が全てのような人で、昔から体が丈夫ではなかったが、叔父が亡くなって一気に健康状態が悪くなってしまった。私は仕事に趣味に遊びにと、人生がものすごく忙しい時期だった。何でもっと気にしてあげなかったのかと後悔していた。
大人しく控えめだった叔母の葬儀らしく、お通夜も葬儀もひっそりとしめやかに行われた。家族が人生のすべてのような人だったので、訪れる知人友人も多くはなく、参列者の殆どが見知った顔ばかりだった。
火葬場に家族が移動する際母から「あなた、おばあちゃんの様子を見てて」と、留守番を仰せつかった。その人は随分高齢のおばあさんで、少し前に亡くなった叔父の母親にあたる人だった。私は血の繋がりはないのだが、昔から顔なじみの人である。
たった一人の我が子を数ヶ月前に亡くし、長年世話になっていたその妻である叔母にも亡くなられて、さぞかし気落ちしているだろうと思ったが、第一声が「あんた久しぶりだわね。東京から帰って来てたんだね」と随分元気そうであった。とある市内の大地主の箱入り娘だったというその人は、昔からきちんと綺麗にお化粧をし美容院で常に髪をセットしているような人だったが、その時も90近い歳とは思えないくらいきちんとお化粧をし、髪をセットしていた。
「飲み過ぎないよう、見張ってて頂戴ね」と言われていた。皆がいる間は彼女も神妙にしていたのだが、皆がいなくなった途端、ふっと私が目を離した隙に近くにあった日本酒の小瓶の栓をひょいと開けて、勝手にコップに注いでトクトクと飲み始めた。呆気にとられている私を余所に「あんたも***高校を卒業したんでしょ、あたしもよ。あの頃は***女学校って言われててね。春になるとあの辺りは桜が咲いてすごく綺麗な名所でね」と独り言ともなんともつかないような事を話し始めた。
「あたしは本当は大学も行きたかった、でもあたしの時代の女学校は学校の先生になるか良い家のお嫁さんになるためでね、あたしは親が厳しくて職業婦人になるのもダメだって言われてたの。孫たちなんかねえ、皆せっかく大学行ったのにお嫁さん志望なんだって」つまらないわねえとフフフ、と笑った。「お嫁さんなんかつまんないわ…あんたは仕事してるの?」話しながら、どんどんお酒を注いでスルスルと飲んでいる。はい、でももうすぐ退職してイギリスの大学院に行くんです、と答えると、目を輝かせて
「良いわね、どんどん勉強なさい。今は女だって勉強して手に職ないとダメな時代よ。**ちゃん(叔母)は仕事しないで家にいて…あたしなんか婚家が嫌で嫌で…堅苦しくてねえ、飛び出しちゃった…***(叔父)には悪い事したけどね…」 と言った。私は何か言いたいような気持ちになったが、黙っていた。おばあさんは、またお酒コップに注いでゴクッと飲むと真面目な顔になって言った。
「あたしは知ってるよ、皆あたしが先に死ねば良かったのに、って思ってるんだ。息子や嫁じゃなく、あたしに先に死んで欲しかったんだよ」
藪から棒に言われて、私は戸惑ってしまった。返事のしようがなかった。若い頃たった一人の我が子を置いて婚家を出て行った人。息子が生家で居場所のない思いをする原因を作った人。田舎に似合わないエキセントリックで奔放で自分勝手な人。皆に陰口を叩かれ笑われても決して自分の生き方を変えなかった人…私はなんとなく気まずくて「そんな事はないと思いますけど」とおずおずと答えた。おばあさんは飲むのをやめずに、フフと笑って
「いいんだよ、あたしは分かってるんだから…なんだったら、皆息子や嫁が死んだのはあたしのせいだと思ってるのよ。ここはねえ、そういう土地柄なの、何十年も身に沁みてるんだよ。でもね…」
怒りを込めた口調で言った。
「あたしは死なないよ。最後まで生き抜いてやるんだ…」
さ、あんたもいいから飲みなさいよ、と私にも日本酒を勧めてきたが、私は「運転しないといけないので」と断った。火葬場にいた家族が戻ってきて、家の中が急に賑やかになった。母が「ああ、やっぱりおばあちゃん飲んじゃったのね、ダメでしょう、ちゃんと見張っててって言ったのに」とブツブツ言いながら、おばあさんからお酒を取り上げようとすると、
「いいのよ、あたしが勝手に飲んだんだから。この子はなーんにも悪くない」
と、酒を手放そうとしなかった。もう、仕方ないわねこんな日にまで…と母はぶつくさ言いながら給仕の手伝いに台所へ消えて行った。家族や隣人が次々に集まってき、私も人手が足りなそうな台所へ手伝いに向かった。振り返ると、おばあさんは喪服を着た人達の間に座って、ただ一人小さく座ってお酒を飲み続けていた。悲しそうでもなく、寂しそうでもなく、強いて言えばただ一人で何かと戦い続けるように。ただただ、ひたすらお酒を飲み続けていた。
*実際の出来事をベースにしていますが、プライバシー保護のため実在の人物との関係は脚色しています。
トップ画像:jasuさん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
