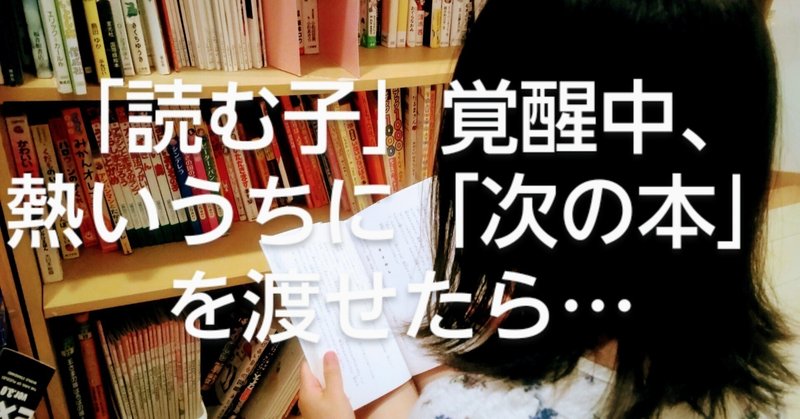
(10)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~
お手紙、つづきです。
「家にある本で、デジタル漬けになる前に『読む』習慣を」
・・・というお話をしています。
・お手紙(9)はこちらからどうぞ。
(9)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
今日は
「〝読む子〟覚醒中、熱いうちに〝次の本〟を渡せたら、そのままどんどん〝読む子〟になっていく・・・」
というお話です。
さて、「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズをひと通り読んだ長女には、本読みスイッチがオフにならないよう、間をあけずに「次の段階の本」を用意しました。
よく、「鉄は熱いうちに打て」って言いますよね!
子どもが何かを体で覚える時も、私はまさにコレだと思うんです。
「読んだらおもしろかった」という熱が冷めないうちに、「変わらずおもしろく読める本」・・・をその手に渡すこと。
ただし、「文字の大きさ(小ささ)や文章量が〝少し〟ステップアップした本」を用意することが大切かな・・・と考えていました。
ちなみにこの時期、「好きなジャンル・傾向」がはっきりしたので図書館通いはいったん卒業していました。
もちろん引き続き図書館で「次の本」を探すこともできたのですが、私は次の本は「買おう!」と決めていたのです。
さあ、次の本。本当なら子どもと一緒に選ぶのがベストではありましたが、ああでもない、こうでもない・・・という時間がもったいなく感じ、ネットの口コミなどを見て私が「これはどうかな?」という一冊を購入。
選んだのは、「科学探偵 謎野真実」というシリーズの第一巻、「科学探偵vs.学校の七不思議」(作・佐東みどり、石川北二、木滝りま、田中智章/絵・木々/朝日出版社)という一冊でした。
「科学で解けないナゾはない」が信条の天才少年・謎野真実(なぞのしんじつ)君が、仲間と一緒に不可思議な謎を解いていく物語です。
ーーこれがまた、すごくおもしろい!
長女も読むだろう・・・とある程度自信を持てたのは、数カ月かけた図書館通いがあったからなんですね。
長女の好みの傾向・好きなジャンルがわかっていたこと、
またこの「謎野真実」シリーズが「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズと同じように「事件編」と「解決編」に分かれた構成だったところに、取っ掛かりを感じたのです。
読書に限らず、子どもが「次の段階」に進む時って、
「前の段階との共通点」を確認しながら進むのがコツかな・・・
と思います。
児童書なら例えば
「同じくらいの文字の大きさ・文章量だけど、内容がちょっと難しい」とか、逆に
「似たような物語だけど、文章量が多い」とか、
「内容も文章量も同程度だけど、挿絵が少ない」とか、
・・・少しずつ成長していく仕掛けにするのが効果的ではないかと思います。
ちなみに「科学探偵 謎野真実」シリーズは、「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズに比べれば文字も小さくて文章量も多いので、
じつはどのポイントから見ても一気に2段階くらいアップした印象。
・・・なのでさすがに子どもが「絵本だ」と間違えることはなさそうでしたが、すでに「読むのは楽しい!」という感覚をつかんでいるので大丈夫だと感じたのです。
これに関しては「楽しく謎解きをする」内容と、
「事件編・解決編」に分かれている構成の共通点を信頼しました。
ーーはい、本に対しても信頼は大切です。
いずれにしても、「白い紙に黒い文字、縦書き」のこの本(謎野真実)、中身をパラパラとめくってみても、子どもから見れば、
本としての見た目は一般的な小説とほぼ変わらない印象なんですね。
ーーそれでも、これを「読める!」という段階まで一気に信頼感を高めることができたのは、それまで読んできた絵本との間に
「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズを挟んだからなのはまちがいありません。
これは、段階のなせるワザ・・・だと思います。
さぁ、どうかな長女・・・と渡してみたのですが、これが大成功。
主人公の少年たちと謎を追うのが楽しかったらしく、スイスイ読み進めることができたようでした。
ーー良かった!
挿絵もトリック(科学の解明)の図解もたくさんあって、見る楽しさも満足させてくれるこのシリーズ。当時は5刊くらいまで発行されていて、長女の「これ、おもしろいよ!」の声におされて全巻購入したのでした。
そして長女が2年生になり、当時手に入ったすべての「謎野真実」シリーズを読み終わる頃には「文章を読む」ことが習慣になり、「もうたいていの児童書は読めそうだな・・・」という感覚を私もつかんでいました。
もちろん、その間も家で「何か読んでない本、ないかな…」と思った時のために、年齢に合ったいろんなジャンルの本(物語、図鑑、クイズ、占いなどいろいろ…)を定期的に用意。
この、家に本を絶やさない…という方法については、新刊書店・古本屋・図書館の3つを大いに活用するのがいいかなと思うのですが、これについては、またあとでお話しますね。
――と、このあたりで、これ以上親としてもう頑張ることはないかな…という気もしていたのですが、私はまだイマイチ確信が持てずにいました。
いや、なんの確信でしょうか?
それは、なんと言うのかーー
「これでもうこの子は本が好きになった」
「もう『これ読んだら? あれ読んだら?』なんて言わなくても自分で選んで読むようになるだろう」ーーという確信でしょうか。
私は、子どもが本当の意味で「本好きになる」瞬間のようなものがあるとしたら、それはどういうものだろう? と、なぜだかずっと考えていたのです。何年間も。
――行動面だけでなく、心理面から知りたい。
自分でもおかしな探求だと思うのですが、それは私が「心理学と謎解きと子どもと本」に興味があるからだったのかもしれません。
そして長女が4年生の時、そのひとつの答えとも言える瞬間を私は感じたのでした。
ーーきっかけはその1年前、長女が3年生の時、私が自分の蔵書の中から「ハリー・ポッター」シリーズ(作・J.K.ローリング/訳・松岡佑子/静山社)を勧めたこと。
年齢的にもぴったりだし、自分の子どもにあの感動を味わってほしい・・・と思って勧めたのですが、結果から言えばこの時長女は1巻の第1
章あたりで読むのをやめてしまいました。
本人の言葉を借りると、「なんか主人公が親戚の家でずっといじめられてるし、知らない街の名前だし、楽しく読めなかった…」――とのことでした。辛かったみたいです。
私としてはちょっと残念でしたが、そうかそうか…と思い、無理強いせずにそのまま本棚に並べておき、そのまま1年が過ぎました。
そうしてその時から「ハリー・ポッター」は長女にとって
「家にあるけど、読んでも読まなくてもいい本」――つまり積読本になったのです。
結果的には、これが良かったと思います。
翌年、4年生になった長女はある時私に「ママ・・・私やっぱりあれもう一度読んでみる」と言って自分の手で1巻を取り出し、読み始めました。
1年間の成長が、彼女に何かをもたらしたようです。
後から本人が言っていたのですが、
「あのね、1巻の1章を読んでしまえば、2章からはもう手が止まらなくなるんだよ!」ということで・・・
そうしてその日から3カ月間、長女は1日も休む(?)ことなく、放課後や寝る前の時間、週末にハリー・ポッターを読み続け、ついには最終巻まで一気に読了。
「ハリー・ポッター」シリーズは、4巻以降の上下巻を数えると全11巻の大長編、1巻ごとにさまざまな謎が明かされ、そのすべてが緻密な伏線となる長い長~い1つの物語です。
ある日の夜、7巻下巻の最終章を読み終わり、しばらく放心したあと、
「ハリー・・・やった! やったぁ!!」
と半分泣きながらソファーでジャンプしている長女の顔を見た時、私は気づきました。
あぁ、こういうことなのかもしれないな・・・と。
「本読む子」になるということ、
それは子ども自身の心が「本は自分を楽しませてくれる」と確信すること。本との信頼関係を結ぶことなのではないでしょうか。
特に長編を読むことは、本好きの大人にとっても頭と体力をそれなりに使うもの。
それでも、読んだ先には感動がある、読書は信じるに足るもの・・・
という実感が、人を本好きにさせてくれる・・・のかもしれません。
そしてまた我が家の場合は、子どもが自分のタイミングで本を手に取ることのできる「積読本」がとても役立ちました。
お手紙(2)で、
長女は私の誘導によって本好きになり、次女は積読本によって自然なカタチで本好きになった・・・とお話したのですが、
振り返ってみると長女の場合も、私はキッカケを与えただけで最後の仕上げをしたのは積読本の存在だったのでは…と思うのです。
――もし、長女が3年生の時にハリー・ポッターを読めなかったことにガッカリして、私が本をしまったり、売ったり、借りたものなら返してしまったらどうだったでしょう?
長女はそのまま成長し、私に本を勧められたことすら忘れてしまっていたかもしれません。
家に本があることは素晴らしい。
例えその時は読むかどうかわからなかったとしても、家に本があることは、子と本の縁を結んでくれる。
――私はそう信じています。
さて、次は具体的に「字がさりげなく小さくなっていく・・・とはどういうこと?」というお話をしたいと思います。
お手紙、つづきます。
〈来年の君が読むかもしれないファンタジー 本棚の隅でその時を待つ〉
・お手紙(11)はこちらからどうぞ。
(11)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
・お手紙(1)はこちらからどうぞ。
(1)5歳頃からの積読本が「本読む子」への最短ルートでした~10年前に出会ったママさんへ~|涼原永美 (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
