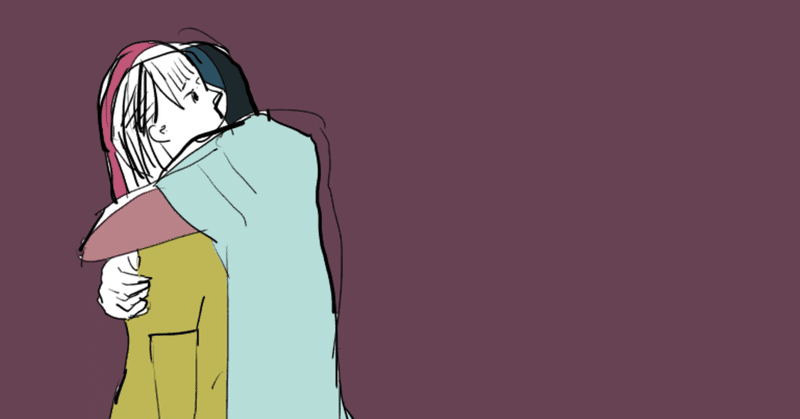
マッチングアプリで爆速恋愛した話⑨身体と心の反比例
【前回までのあらすじ】
マッチングアプリで年下の純也さんとすぐに交際成立した私。だが、クリスマスイヴの夜に不満が大爆発して、彼にすべてをぶつけてしまう。
***
純也さんはこめかみに手を当てたまま俯き、黙ったまま。ひどく落ち込んでいるようだ。ときおり「そっかー…」「うぅん…」と声を漏らす。
伝えるべきことは伝えた。あとは引きずっても仕方がない。そう思った私はどうにかこのムードを打開したかった。
「大丈夫…?」
「………。」
純也さんからは言葉が返ってこない。
「こんな短い間で、そんなに沢山かって…」
しばらくの沈黙の後に純也さんはそう言った。
そうだよ。こんなに沢山悲しかったんだよ。
「落ち込まないで…!分かって欲しいから言ったんだよ!」
わざと明るい声を出した。それでも空気の重さは1gも変わらないみたいだった。
かつて純也さんは、「不満があったら言ってほしい。改善するチャンスが欲しい。」と言った。
私が彼に全てを正直に伝えたのは、このことがあったからだ。あの時純也さんは言ったはずだ。俺を傷つけるとか考えなくていい、何も言われず急に別れ話をされる方が嫌だと。「俺はそんなに落ち込まないよ」と言って澄ましていたのに、それさえも嘘だったんだ。
俯く彼の頭頂部を見つめる今の私の瞳は、きっと非情な色を孕んでいるだろう。
しばらく奮闘してもなんら変わらない彼の落ち込みように、苛立ちが募る。
こちらの気遣いにも気付かず自分の感情を優先する。そんなところが嫌だと伝えたばかりなのに。
「ごめん。たしかに、言ってることとやってることが違ったり、気を遣えてないことがあった。」
純也さんがやっと反省らしき言葉を口にした時には既に夜も更けていて、とりあえず就寝することになった。
まるでおもちゃのように小さい、セミシングルのベッドに身体を横たえる。
大人2人が並ぶとさすがに窮屈さが際立った。
「せまーい!」
私はケタケタと笑いながら言う。まだ気まずさを孕んだ空気が流れることに耐えきれず、やけに明るく振る舞った。
しかし、その言動は裏目に出てしまったのかもしれない。純也さんが、信じられない言葉を吐いた。
「うん。狭いからさ、その解決策っていうか………くっついていい?」
正気を疑った。あぁ、この人には何も伝わらないんだ。さっきまでの落ち込みようはなんだったのか。この人は本当の意味で反省などしていない。私が精一杯伝えたことの真意も何も伝わっていない。
伸びてくる腕に捉われて、私は身体も心も硬直させる。身体が近付けば近付くほど、心が離れていく。
純也さんの寝息が首筋に当たる。規則的なその風が嫌でたまらない。頃合いを見計らって体を離すと、その分だけ純也さんの体が迫ってきて、すぐに壁に追い詰められてしまった。
結局その日は一睡もできず、朝を迎えた。
アラームが鳴り、あぁ、これでやっと起き上がる理由ができたと変な安堵を感じながらベッドから抜け出す。
寝惚け眼の純也さんにあまり眠れなかったと言うと、悲しげな表情でそっか…と言われた。
そんなやり取りも束の間、純也さんは再び眠りの中に落ちていき、結局そのまま二時間眠ったままだった。
純也さんは昼近くにやっと起き上がり、2人でご飯を食べた。
私は即席のお味噌汁に箸で波紋をつくりながら、昨日のスーパーのことを思い出していた。
「今日どうしようか。」
純也さんが今日の予定について聞いてくる。こうしてクリスマスの2日間を一緒に過ごしておきながら、実は本日25日の予定を決めていなかったのだ。
「んー…。なんか行きたいとことかある?」
自分の意見を持たない私も大概だ。純也さんが困ると知りながら、委ねるような返事しか出来ない。したい事がないのだ。彼と2人で過ごす幸せな時間が少しもイメージ出来ない。
まるで今この瞬間の空白を埋めるためのように、パソコンで今日のイベントや夕食のお店を探す。
「えくぼさん牡蠣が好きだったよね?牡蠣食べようよ。」
「うん…。」
彼の優しい提案さえも、心に響かない。それどころかご機嫌取りのように感じてしまう。そんな自分が嫌で、胸の奥に苦汁が充満したような息苦しさがあった。
牡蠣の食べられるお店をネットで見つけて予約してから、私たちはやっと家を出た。
向かったのは表参道のイルミネーションスポットだ。私は人混みが苦手で、だからおうちで過ごすことにしたはずなのに何故かここに連れられて来てしまった。
もう純也さんには諦念しかなかったが、苦手な人混みに連れていかれ、力強く手や腕に触れられるその度に逐一落胆した。
途中で写真を撮りたがるところも、自分では撮ろうとせず私の携帯で撮らせようとしてくるところも、細かい所作一つひとつが全部気になる。嫌悪の起因になる。
やっと人混みから解放され、好物の牡蠣を食べている時も、「はやく自分の家に帰りたいな」という気持ちでいっぱいだった。
結局、最初に「とりあえずで」と言ってオーダーした分だけを食べ終えると早々にお店を出て帰路を急いだ。
別れ際、純也さんはホームまで送ってくれた。うっすらと、彼の表情には寂しさが漂っていた。私はその優しさと寂しさのどちらも見ないフリをして、地下鉄に飛び乗る。
「気をつけてね。」
そう聞こえた気がしたが、その言葉を受け取って、頭で咀嚼して、言葉を返す、その単純な気力すら残っていない私は曖昧に頷くだけだ。
発車を告げる電子音が響く。
その音がいつも以上にけたたましく、耳をつんざく。
あぁ、うるさい。
ドアが閉まり、車両がゆっくりと動き出す。窓の向こうにこちらを見つめる純也さんが見えた。
お読みいただき、ありがとうございます。 あなたの中になにか響いたものがあったとき、 よければサポートお願いいたします。 大切に使わせていただきます。
