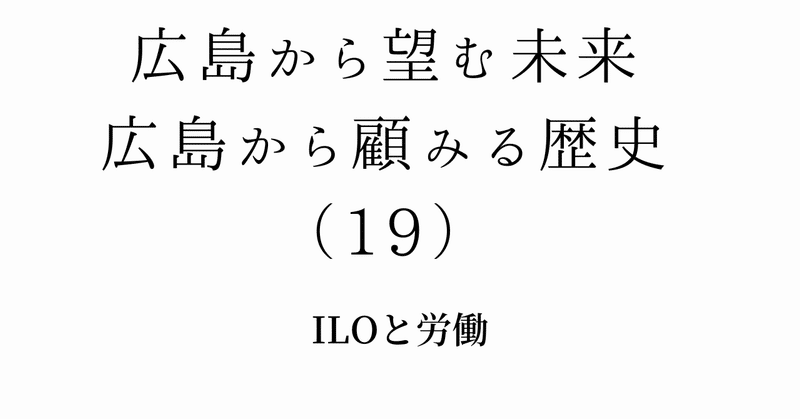
広島から望む未来、広島から顧みる歴史(19)
ILOと労働
前回ILOの設置についての問題が、東京帝国大学の経済学部設立と大きく関わっていたことを見た。そこで、このILOと労働についての問題をもう少し掘り下げて、Visionary-Essayとしてみたい。
ILOのあり方
ILOは、ベルサイユ条約第十三条でその規約が定められ、第一条で定められた国際連盟よりも先に動き出したということで、ある意味において国際連盟自体よりも先行する形で定まった世界初の国際機関だと言える。そしてそのエッセンスは、政府、雇用者、労働者の三者の代表が集まることで、問題についてそれぞれの立場から意見交換し、総会で条約を採択し、また各国政府に対して勧告を出し、その条約を批准するかどうかは各国に委ねられ、特に強制力を持つこともない、ということで、国際機関のあり方としてはかなり理想的な、非常に緩やかな合議体になっていると言える。
労働問題の難しさ
労働問題というのは、共産主義による革命待望の嵐が第一次世界大戦を引き起こしたという問題意識からすると、ベルサイユ条約に含まれても当然の、まさに問題の根源に関わる部分であると言える。これによって、革命路線からの離脱と、対話による労使間の交渉という民主的手続きが国際機関によって定められたのだと言える。理想は確かにそれで良いのだろうが、これは残念ながら、幾重にもわたって問題を引き起こしていると言わざるを得ない。
民主的手続き
まず、民主的手続きという観点で言えば、国内に民主的手続きで選ばれる議会があり、そこで法制度についての議論がなされ、各国別の法制度が民主的に形成されている、という少なくとも現在の民主主義国と呼ばれる国の間でのほぼ共通の制度・手続きが存在する。それに対して、国際機関の代表が三つのセクションに分かれ、それがそれぞれ民主的に選出されるということを想定すること自体が非常に難しい。ILOに関して言えば、縛りが緩やかなので、比較的に代表選出は問題になりにくいということはありそうだが、この代表選出の非民主性が、東京帝国大学高野教授の代表に対する異議につながり、そして結局大学を追われることになったという非常に不幸な事態につながり、それによって日本の経済学の高等教育は出発点からつまづくことになってしまったということはよく考えるべきことなのだろう。
メタ階層での民主主義実現の難しさ
この帰結は、さらに言えば、国際機関という高度に専門的な議論が展開される場において、民主主義手続きが優先されるのか、それとも専門知識が優先されるのか、という、民主主義vsエリーティズムのような妙な二分方も引き起こしかねないことを示唆する。現状の国際連合、そしてその専門機関は、ほぼ後者の考えに従い、国からの代表として、あるいは実力によってのし上がる、という、いずれにしても民主主義という手間暇かかるプロセスは省いて、ほぼ能力主義によって運営されているのだといえよう。それは、統治というものを、民主的手続きに従わせて独裁を防ぐのだ、という、近代化プロセスの常識のように行われてきたことを全く無視して、力のあるものに、国際レベルというかなりメタなポジションにおいて、権力を集中させるという、国レベルの全体主義とは比較にならないような歪んだ権力体系の下に置き、世界独裁統治システムに近いものを作り出しかねない大きなリスクを内包している。
普遍的価値の押し付けリスク
それでもまだILOのように条約の採択だけで批准は各国の自由という緩やかさがあれば、助言機関として大きな意味を持つだろう。しかしながら、いわゆる普遍的価値に近い部分については、それはどうしても押し付けに近いものになってくる。日本では、出羽守などとも揶揄されるが、「国際社会では、」というような枕詞を使い自分の意志を半ば強制的に国家や地域社会に押し付けるという行為に、国際機関がお墨付きを与えるようなことになってくると、もはや民主主義は完全に形骸化してゆく。そうなると、普遍的価値にかこつけて自分の意志を押し通すことに長けた者がどんどん権力を握り、そしてそれは民主的手続きではひっくり返しにくくなるという、超権力の事例となり、誰がどのように決めるのかも定かではない普遍的価値に支配される、非民主的権威主義の檻に社会が閉じ込められることになってゆく。そのような国際機関を一体誰が必要とするのだろうか。
ILOからの教訓
この、人類史上初の国際機関という大きな挑戦であったILOの設立から、一体どんな教訓を引き出すことができるのだろうか。まずは、当時は帝国主義全盛の時代であり、必ずしも民主主義が行き渡っていたわけでもなく、そして民主主義自体も、チャーチルが言うように、他の仕組みに比べればましな最悪の統治形態であったに過ぎず、その状況は多少ましになったとしても、いまだにたいして変わりはない、という、歴史及び現状の認識が可能であると言うことが言える。その時に、民主的な国際機関というものを、どう定義し、どう運営するのか、という大きな問題が浮かび上がる。ILOは、当時想像しうる限りの知恵を絞って、政府、使用者、労働者からそれぞれ代表を出して議論を行う、という仕組みを考えついたのだといえ、そして代表の選び方も代表団に任せることで直接には関与しないことで、それぞれの分野の自主性に基づく代表選びという、民主主義というものに対する責任を放棄することで枠組みを安定させることを優先したのだと言えそう。果たしてその在り方は依然として有効であると考えうるのか。世界最初の国際機関として、民主主義というもののあり方をトップランナーで模索し続けるのか、それとも民主主義は一旦諦め、最初の枠組内で対話を行う、という、定まった道を漸進的に切り開き、あとは専門機関としての役割に徹するのか。
労働と非民主的競争ゲーム
その問題に関してもう少し考えると、それは結局国内で収まりきらないエリーティズムの吐口を国際機関の椅子として準備しておくことで、非民主的ポスト争い椅子取り競争ゲームに少し色合いの異なった椅子を用意して、その競争に参加することに意味を見出させようとする、民主主義侵食ドライバーとして作用するのではないだろうか。それぞれの代表団に入ること自体が制約的であるとき、それは、労働というものを非民主的競争の中に見出すよう仕向けるということに、労働に関する国際機関であるILOが積極的に関与する、ということにならないのだろうか。労働の定義が非民主的であるという状態を是認するために存在する労働を司る国際機関というシュールな構図を、いったいどのように正当化しうるのだろうか。果たして、民主主義とエリーティズムを両立させうる方法はあるのだろうか。それが見つからないときに、民主主義を保留するという選択をしてでも、国際機関は維持される必要があるのだろうか。そして、条約採択や勧告にもある程度の影響力があるときに、それは非民主的意志決定を、民主政体に対して押し付ける、ということにはならないのだろうか。そして、それについて答えを見出せないまま、そのやり方を継続するということが、国際機関運営のノームとなっているときに、果たして国際機関は民主主義をどのように評価し、位置付けることになるのだろうか?それは、国際機関とはいったい何で、何のために必要なのか、という根本的な疑問を投げかけることになる問題だと言えそうだ。
組織優先のILO
ここから先は
¥ 500
誰かが読んで、評価をしてくれた、ということはとても大きな励みになります。サポート、本当にありがとうございます。
