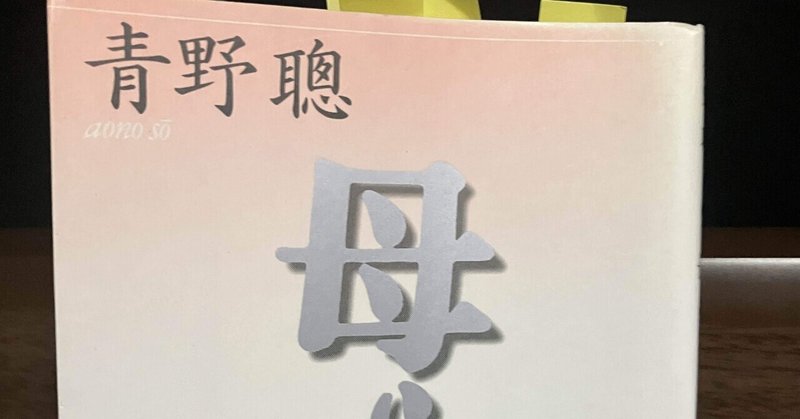
母の再生 青野聰『母よ』
江藤淳の「成熟と喪失」における「成熟」の成り立ちはあまりにも有名である。その成り立ちとは、もっとも近しい「他者」たる母からの決別――副題にある「“母”の崩壊」が成熟をもたらすというものである。ここには、ある前提がある。つまり、子と母とのあいだにどんなかたちであれ意識的な「つながり」があるという前提が。なぜなら、「つながり」がなければ喪失など起こりうるわけがないからである。
なぜ、江藤は「母」という問題に強く固執したのか?いうまでもなく、彼が幼少期に母を失っているからだ。つまり、江藤と母との「つながり」は事後的なものであったということができる。「成熟と喪失」は、幼少時に母を失った息子の憧憬の書物である。
青野聰「母よ」もまた、母への憧憬に満ちた書物であるといってよい。
青野聰は大東亜戦争末期、1943年に生まれた。父の婚外子として。年譜を引用しよう。
父青野季吉、母松井松栄の三男として(中略)生まれる。父は妻みづほと同区内の経堂に在住。
つまり、青野には二人の母がいる。実の母と、育ての母(おかあさん)とが。実の母とは青野が二歳の時に死別している。五年のブランクがあったのち、7歳のときから、疎開先から戻ってきたおかあさんに育てられる。それゆえ、青野にとっての母とはおかあさんその人であった。
が、齢を重ねるにつれて、実の母が存在を帯びはじめる。母の声をききたいと思いはじめる。彼女がどんな声をしていたのか、青野は記憶の内奥から取り出すことができないのである。そして、自分の声を母に届けたいと願う。「母よ」という呼びかけを通じて。
先に私は、本書を憧憬の書物であるといった。たしかにその通りなのだが、この作品をより深いものにしている、愛惜にも触れておきたい。青野には、母に対するギルティコンシャスがある。
母よ、人は生きているあいだに、いったいどれだけの人を殺すのでしょうか。ぼくはあなたを殺した。肺を病んだ、そうでなくてもいのちの灯が細くなっていたあなたの子宮の中で、血を吸い肉を食べ、骨を奪った。おかげであなたは残り少ない寿命のすべてを前借りしなければならなくなり、ぼくを生み落として力つきた。
母は己を生み落とした存在だ。いい換えると、子が最初に逢う他者だ。その他者を殺し、自分は生きているという感覚を青野はいだいている。この感覚が、何度も繰り返される「母よ」という呼びかけに、まるで神に許しを乞うような響きをもたらしているのだろう。
「成熟と喪失」が母の崩壊を主題とした書物ならば、「母よ」は母の再生を主題とした書物である。母との決別が成熟をもたらすという江藤の論を私は否定しない。けれども、母を再生し、包括されることによる成熟もまたあるのではないか。そんなことを私は考えたのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
